今回は「なぜ日本語の語順は欧米言語と異なるのか」について解説します。参考文献は『善の研究』(著者:西田幾多郎)などほかいろいろです。
「日本人は結論を最後まで言わないから何を言いたいのかわからない」
海外の人がこのような印象をもつということを耳にしたことがありますよね?たとえば、英語では「I play soccer with my friends yesterday」のように、主語の後に述語が来るので何をしたのかがすぐにわかります(SVO型)。しかし、日本語では「私は、きのう、友だちと、サッカーを、しました」のように、主語のあとに目的語がいくつも続いた最後に述語が来ます(SOV型)。そのため、日本語で会話をすると最後まで何が言いたいのかわからないのです。
海外ではさまざまな場面でしっかりと自分の考えを主張することが要求されます。この時、SVO型の言語では賛成・反対がすぐに明確になるため議論や討論に向いています。それが会議の効率化や生産性の向上にも貢献している要因の1つでしょう。
しかし、日本では多くの時間を場の空気を読むことやむだな説明に費やすことが多いため、それが会議の非効率化や生産性の低さにつながっている要因の1つになっているのです。 しかし、日本人は結論を遅らせることによって深い知性と共感する力を育んできたのです。海外では日本語を学んだ子どもたちにある大きな変化が表れたという研究もあるそうです。実は、日本語で大切なことは会話の効率性ではなく「思考の構造」そのものだったのです。いったい、日本語の語順と日本人の思考の構造にどのような関係があるのでしょうか?
そこで、今回は西田幾多郎の哲学をもとに日本語の特徴を考察してみたいと思います。西田幾多郎は「西田哲学」とよばれる独自の哲学体系を確立した日本を代表する哲学者です。その哲学はとても難解でありながらも「純粋経験」や「場所」などの概念を用いることで、さまざまな対立するものが矛盾しながらも統一されるという思想を体系化していきました。また、西田幾多郎は前回の動画で紹介した「禅」に傾倒して参禅体験をしていた時期があり、それが「西田哲学」の底流に善の精神が流れているといわれる所以でもあるのです(ちなみに、著書は『善の研究』であって禅の研究ではありません)。
今回の動画では難解な西田哲学をできる限りわかりやすく解説して、日本語の語順が私たち日本人の思考にどのように関わっているのかを考察しています。内容がわかりやすかったと感じた時にはぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 なぜ日本語では動詞が最後に来るのか?
日本語を学ぶ外国の人の多くが最初に戸惑うのは「語順」だといわれています。海外の多くの言語がSVO型であるのに対して日本語はSOV型だからです。また、日本語は最後に結論が来るので聞き手は最後まで相手が何を言うのかわかりません。そのため「日本語は論理的思考には向かない非効率的な言語である」ともいわれます。
しかし、日本語の語順こそが日本人の話し方や思考の構造に大きく関わっていたのです。欧米の言語が「討論」を重視するのに対して、日本語は「対話」を重視しているのです。日本人は自分の意見を述べる時に結論をすぐに明らかにするのではなく、相手の様子を伺いながら丁寧に言葉を積み重ねていきます。そして、相手の理解や共感のレベルを見極めながら最後に静かに結論を述べるのです。
そのため、日本語で会話をするときには「話し手は配慮すること」と「聞き手は待つこと」が双方に求められるのです。ちょっと前にどこかの大統領たちが会談した時こんなふうになっていたのですが、日本語では相手の背景にどのような思想や感情があるのかにも配慮する必要があるのです。だから、日本では人と人との関係を大切にする「和の信仰」が生まれてきたのでしょう。
ニーチェは『善悪の彼岸』(1886)の中で次のように述べています。「(主語概念があまり発達していない)ウラル・アルタイ言語圏の哲学者たちがインド・ゲルマン族やイスラム教徒とは異なった風に世界を眺め、異なった道を歩んでいることは多分にありうべきことであろう」
また、アメリカの言語学者エドワード・サピアとベンジャミン・ウォーフは言語が思考を規定して言語の構造が世界の認識の仕方を決定するという仮説を唱えました。(両者の名前をとってサピア=ウォーフ仮説とよばれています)
さらに、言語哲学者ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタインは「私の言語の限界が私の世界の限界である」と述べた上で「語りえぬものには沈黙しなければならない」という有名な言葉を残しています。つまり、私たちは他の言語を話す人と「世界の捉え方」が根本的にちがうということです。
SVO形式の言語では「自分の主張」がまず述べられていますよねこれは、速度のはやい直線的な思考で世界を捉えているということです。いっぽう、日本語では主語の後に「いつ」「どこで」「なにを」などの文脈が続いたあとに、ようやく最後に結論となる動詞が語られます。そのため、速度の遅い双方向(または拡散的な方向)への思考で世界を捉えているのです。
日本語を使用する時にはまず相手や周囲の状況をよく考えなければいけません。言うべきなのか言わないのか、言うならどのように言えばよいのか…このような配慮を積み重ねた先に少しずつ自分の主張を構成していくのです。つまり、SVO型の世界が「自分が見ている世界」を一方的に伝えたものであるのに対して、日本語の世界は話し手と聞き手が共同して結論にたどりつく「関係性の世界」なのです。だからこそ、日本人は「空気を読む」ということをさまざまな場面で適用できるのです。
SVO形式の言語が「競争の道具」であるのに対して日本語は「共感の架け橋」なのです。このような語順のちがいが思考のちがいを生み、文化のちがいを生んできたのです。欧米諸国が異国に対してさまざまな侵略の歴史を歩んできたのに対して、日本では和の信仰が神話の時代からすでに育まれてきていたのは驚嘆に値します。
また、日本語とは話す力ではなく聞く力を求められる言語であるとも考えられます。SVO形式の言語を使用する時にはまず自分の主張が述べられます。相手はそれに対してすぐに賛成なのか反対なのかを返す応酬型の会話となりがちです。議論や討論が発達したのもこのような言語構造の産物だといえるでしょう。
いっぽう、日本語では「わたしは」「きのう」「友だちと」「学校で」「サッカーをして」と状況をさんざん説明した後に「楽しかった」や「悲しかった」などの結論がくるのです。そのため、聞き手は途中で自分の主張をすることができない(してはいけない)のです。結論が述べられるまで待つという聞き手の姿勢が大切になるのです。
話し方が変われば人とのかかわり方にもさまざまな変化が起こります。沈黙の時間は空白ではなく相手の気持ちを受け止めたり余韻を感じたりする時間なのです。これは語らないことで語るという沈黙がいかに豊かであるかということを示しています。
「明確に言わない」「余白を残す」「相手の解釈に委ねる」―このような日本語の曖昧さこそが相手との関係を築くために必要な要素となるのです。実際に日本語を学んだ外国の人は人間関係が向上したといわれているそうです。日本語の会話では相手を尊重するという前提が共有されていなければ成立しません。「すぐに答えを出さないこと」「相手の話を遮らないこと」「言葉の背景を想像すること」日本語の語順は人と人との関係性の築き方であり社会のあり方そのものなのです。
2 西田幾多郎の哲学
欧米の価値観では自分の意図を明確に伝えられることが文明の証と考えられていました。そのため、主語と述語が即座に結びついた構造の言語になっているのです。このとき、述語は主語(主観)と目的語(客観)を分離する役目を担っています。SVO型の言語は自分と対象を明確に区別して観察したり法則を発見したりできます。
ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て万有引力の法則を完成させました。(正確にはリンゴが木から落ちるのに月が木から落ちないのはなぜかと考えたそうです)。医者が患者の症状を診察するのも同じであり、科学や医学が海外でより発展している理由の1つがここにあると考えられます。このように、見ている自分と見られている相手をはっきりと区別して、客観的に考察することができる(世界を外から見る)ところに特徴があるといえます。
これに対して、日本の哲学者である西田幾多郎は「客観的であるからこそ世界の中に自分がいることを見失ってしまう」と指摘しました。日本語では主語と述語が離れているためすぐに結論が明らかになることはありません。このとき、主語(主観)と目的語(客観)は述語で分離されていないとみることができます。そのため、日本人は世界を「外から見る」のではなく「中から感じる」―区別ではなく自分を世界の中に含めた全体のバランスや関係性を重視しているのです。西田幾多郎はこのような主語と述語の関係を「場所の論理」として展開しました。西田幾多郎の哲学について詳しく見ていきましょう
2-1 前期(善の研究)
西洋哲学では主観と客観が明確に区別されていました。「私(主観)は音楽(客観)を聴いている(I listen to music)」となります。
いっぽう、西田幾多郎は何かに没頭している状態(経験)が先にあると考えました。このような、主観と客観が区別されていない状態を「主客未分」と表現しました。音楽に没頭している「純粋経験」があって、そこから主観と客観にわかれていくのです。
純粋経験には4つの特徴があるとされています。1つ目は「主客未分」―集中・没頭の状態にあるということ、2つ目は主客未分の状態においては知識や感情・意識が未分化されているということ、3つ目はこのような集中・没頭の状態にある時こそが真の自己(実在)であるということ、4つ目は自己の内面的な要求によって人格を実現することこそが善であるということです。
西田幾多郎は「善とは人格の実現(至誠)であり、自他相忘れ主客没頭するというところに至らねばならない」と主張しています。主客合一の力をもって宇宙の統一力と一体となって人格を形成することが善なのです。そのため、個人があって経験があるのではなく、経験があってこその個人なのです。
2-2 後期(場所の論理)
西洋哲学ではあらゆるものは「有」から発生すると考えられていました(「光あれ」と神が言うところから天地創造がはじまるということです)。いっぽう、西田幾多郎は有と無はもともと「絶対無」からはじまったと考えました(古事記のはじまりは混沌であったからはじまるということです)。
絶対無とは有と無の対立や矛盾をこえた一切のものを存在させる場所―そのようなもの(絶対無)があると考えることを「場所の論理」と表現したのです。西田幾多郎は存在を「場所」という概念で捉え、その場所を絶対無の立場から考察しました。「場所」の概念とは存在するものすべてが「於いてある場所」があるとするもので、物理的な場所ではなく認識や意識、さらには絶対的な無の場所も含む概念のことです。
主語と述語の関係も「場所」という概念で捉え直され、自覚のはたらきを根拠づけることで有と無の対立をこえた絶対無の場所を明らかにしようとしたのです。自覚のはたらきとは「自己自身を無にして無限の有を含む」ものと捉えることであり、自己を無化することで無限の可能性を秘めた場所を認識できるということです。
そこから「絶対矛盾的自己合一」という概念に至りました。この世界は多数の個人の行為によって1つの世界が成立していると考えられると同時に、個人は世界に規定されることで自己になりうると考えることもできます。そのため、個人と世界は対立するようで実は根本的に同じものであると考えられるのです。このように、全ての始まりは絶対無であるとすることを「絶対矛盾的自己同一」といいます。
西田幾多郎は人間の自己意識もこの絶対無という場所に行きつくはずだと考えました。そして、過去から現在、未来へと続く私たちの意識の中でも現在こそが大切だとしました。過去と未来が絶対矛盾的・自己同一的にはたらく「現在」において集中・没頭すること―そのような純粋経験こそが新たなものを創造しうる場所になると指摘したのです。
3 ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタインの哲学
哲学体系が前期と後期に分かれて言語について考えた哲学者といえば先に紹介した天才ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタインを思い浮かべた方も多いことでしょう。ウィトゲンシュタインは数学を学ぶためにラッセルの『数学原理』を読んだことでケンブリッジ大学のラッセルのもとを訪れそのまま哲学を学ぶことになるのです。しかし、1914年に第一次世界大戦が始まると志願兵となって従軍するものの、イタリア戦線で捕虜となってしまいます。
このとき、従軍しながら執筆していた著書を友人のケインズがラッセルに届けるのですが、これがかの有名な名言の宝庫『論理哲学論考』です。『論理哲学論考』は命題とその注釈によって構成されています。その中でも最も有名な命題が「語りえぬものについては沈黙せねばならない」であり、その哲学は「語りえるものの限界を明確にしようとした」ことにあるといえます。
演繹法においては前提が真でルール(論理式)を守れば結論も真となります。この論理式はアリストテレスの三段論法によっても明晰なものとなっています。だからウィトゲンシュタインは前提についても明晰にしなければならないと考えたのです。
そこで「言語」について考えるのです。ウィトゲンシュタインは言語が世界を写し出す像であるという「写像理論」を提唱しました。そして「世界は事実の総体である、事物の総体ではない」と考えたのです。ウィトゲンシュタインのいう事態とは「様々な対象が結びついたもの」のことであり、事実とは「事態が現実にそうなっていること」を意味しています。
例えば「リンゴを食べる」というのが「事態」であり、「リンゴ」「食べる」という対象が結びついたものということです。これは現実に起きていることなので「事実」といえます。1つの事実と1つの言語は対応関係なので世界は事実が集まったものといえるのです。事実(真)であるならば結論は必ず真(世界は事実によって成立している)になります。しかし事実でない(真ではない)ならば結論が必ず真になるとはいえません。
例えば倫理(~すべき)のように世界をかえるきっかけとなるものは事実ではないのです。もちろん現実に確認することのできない神なども同様であるのでこれらのものは、真を導き出す哲学(論理学)において扱うべきではないと指摘したのです。「語りえぬもの」とは論理で真を導くことができないものという意味であり、こうしてウィトゲンシュタインはカントが人間の認識できる限界を示したように言語(哲学)の限界を明らかにした(沈黙しなければならない)のです。そして否定しようのない確定的な真理と諸問題に対する最終的解決を含んでいるとして哲学をやめて故郷で小学校の教師になるのです(その後もなんやかんやありますが詳しくはこちらの動画をご視聴ください)。
そして、後期ウィトゲンシュタイン哲学のキーワードこそ「言語ゲーム」です。前期ウィトゲンシュタインの写像理論においては、1つの事実と1つの言語が対応しておりこのような言語を「科学の言語」とよびました。しかし、科学の言語は「日常言語」から派生したものではないかと考えたのです。そのため、科学の言語を理解するためには日常言語を理解する必要があると指摘しました。そして、ウィトゲンシュタインは日常言語の中には1つの事実と1つの言語が必ずしも対応しているわけではないものがあることに気づくのです。
たとえば「雨がふる」という文があったとします。もし、日照りが続いた農家の人がこの文を言えば「雨がふる(からうれしい)」という意味になります。しかし、遠足に行く子どもがこの文を言えば「雨がふる(からかなしい)」という意味になるでしょう。このように日常言語は会話の中からその文章(「雨がふる」)だけを取り出しても、それが何を意味するのか特定することはできないのです。
そこで、ウィトゲンシュタインは言語の使用はゲームにたとえることができ、日常において言語の意味がわかれていくことを「言語ゲーム」といいました。トランプのジョーカーがゲームによって役割が変わるように、あらゆる言語は言語ゲームの中で使用されることで初めて意味がわかると考えたのです。しかし、日常言語を理解するためには言語ゲームのルールを理解する必要があり、そのためには自分もそのゲームに参加する(同じ世界に入る)必要があるとしたのです。
4 日本語の語順がもたらすもの
言語哲学者ウィトゲンシュタインも日本語の語順に着目していたといわれています。後期の著作『哲学探究』において「意味は使用にある」という命題を示すことで、言語は文法的体系ではなく、社会的実践として捉えることが可能になったと考えられます。
ウィトゲンシュタインは言語ゲームという概念の中で日常生活の中でどのように言語が使用されるのかが大切であると指摘していましたよね。ここで、日本語が「述語を最後にする」という語順で使用される意味が見えてくるのです。日本語の語順は、日本語で話す人たちがどのようにものごとを思考して、どのように他者との関係を築くかという認識の在り方とも密接に結びついているのです。
ウィトゲンシュタインは日常言語のルールを理解するために、自分もそのゲームに参加する(同じ世界に入る)必要があると指摘していましたよね。日本語で話すということが話し手にとっては論理の筋道を構成する助けとなるだけでなく、聞き手にとっても相手の見ている世界と思考過程を追体験することができるのです。
また、日本語の大きな特徴として主語が省略されることも多々あります。主語がないという空白や曖昧さを受け入れること(共通了解)ができなければ、日本語での対話(関係性の構築)をすることができないのです。西田幾多郎もまた主語がない(主客未分)状態となるような場所を重視していました。
アリストテレスの三段論法では「ソクラテスは人間である」「人間は必ず死ぬ」「ソクラテスは必ず死ぬ」となります。この時、人間という言葉が「ソクラテス」と「死ぬ」をつなぐ架け橋になっているのですが、「人間」という言葉は3つ目の文には登場しませんよね?西田幾多郎はこのような見えない(見ることはできない)けれど大切な役割をするもの―私たちの日常生活の中にも「見えないけれど大切な場」があるのではないかと考えました。
「この料理おいしいですね」という言葉を言った時のことを考えてみましょう。この言葉の本当の意味はそれが発現した「場所」によってはじめて決まるのです。家族との食事の時であれば「いっしょにいられてうれしい」という意味かもしれません。友人との食事の時であれば「話を聞いてもらえてホッとする」という意味かもしれません。同じ言葉であってもその時の関係性や状況という「場所」によって意味が変わるのです。
西田幾多郎は論理的でありながらもこの「場所」にも配慮することが大切だと考えたのです。日本語は「場所」をつくるところから始まります。日本語で「私は」「きのう」「久しぶりに」「友だちと」「思い出の」「公園で」…と語る間に、「久しぶり」という時間の感覚や「思い出の」という特別な感情。それらが幾重にも積み重なった先に「場所」ができあがるのです。そして、最後に「再会した」という結論が述べられるのですが、それは積み上げられた「場所」で起こった特別なできごとであったことが理解されるのです。
SVOで表現すると「私は再会した」と何が起こったのかを即座に伝えることはできますが、それが起こった「場所」は後からくっつけられた情報になってしまうのです。日本語は「私は」「きのう」「久しぶりに」「友だちと」「思い出の」「公園で」…と語る間に、話す人と聞く人がいっしょに同じ主客未分の「場所」を共有したり創造したりするのです。
たしかに、それは西洋的な近代思考(合理的・効率的)と比べたら非効率的ですが、それよりも日本語では「場所」を共有することを重視しているのです。近代的な西洋文明を至高のものとする思考を徹底的に破壊したのが構造主義の創始者クロード・レヴィ=ストロースです。
レヴィ=ストロースは西洋文明を中心とした歴史的なものの見方が他の文明のことを無視する偏見と傲慢な価値観の押しつけであると断じたのです。西洋的な歴史の進展は合理的・論理的に進んでいくことを是とするものであるけれど、その結果があの悲惨な戦争や地球規模の環境破壊でもあると考えられます。
それに対して未開人には西洋的な歴史というものがまず存在しません。その日その場にあるものによって毎日をすごしているのです。これを「プリコラージュ」といいます。西洋的な価値観では未開人のことを「おくれている」と捉えることになりますが、その民族にとっては生存していく上で合理的・論理的な選択をしているとも考えられます。事実その生活をしていく中では大きな戦争や環境破壊は存在していないのですから…。
いま、私たちに必要なのは「待つこと」「急がないこと」なのかもしれません。「自分ファースト」という排外主義的な傾向を強めていく世界の中で、新しい関係性を構築しているために必要なものが日本語にはあるのではないでしょうか。
まとめ
今回は「なぜ日本語の語順は欧米言語と異なるのか」について解説してきました。難解な西田幾多郎でしたがわかりやすく解説できていたでしょうか?「華やかな西洋哲学に対して日本の哲学は地味」「欧米と比べて日本はおくれている」そう思われることもあるかと思いますが日本の哲学も奥深くとても面白いのですよ。
近年、日本の禅と関わりのあるマインドフルネスがアメリカのシリコンバレーやウォールストリートで注目をあつめています。哲学の補助線を引くことができれば、日本語の語順と私たちの思考の構造にどのような関連があるかを考察することができます。
西洋の近代的な思考の結末が20世紀の世界大戦と環境破壊だとするならば21世紀は「場所の論理」を重視する西田幾多郎の哲学が意味をもつようになるはずです。自分と相手を明確に区別して自分を中心にして世界を外から見るという世界観ではなく、主客未分の絶対無から始まる新しい世界を構築していくヒントを探ってみませんか?「純粋経験」という概念をより詳しく理解することができれば、こちらの動画で解説しているように必ず幸せになることができますよ。
これからも日本の哲学について解説していくのでぜひチャンネル登録をお願いします。

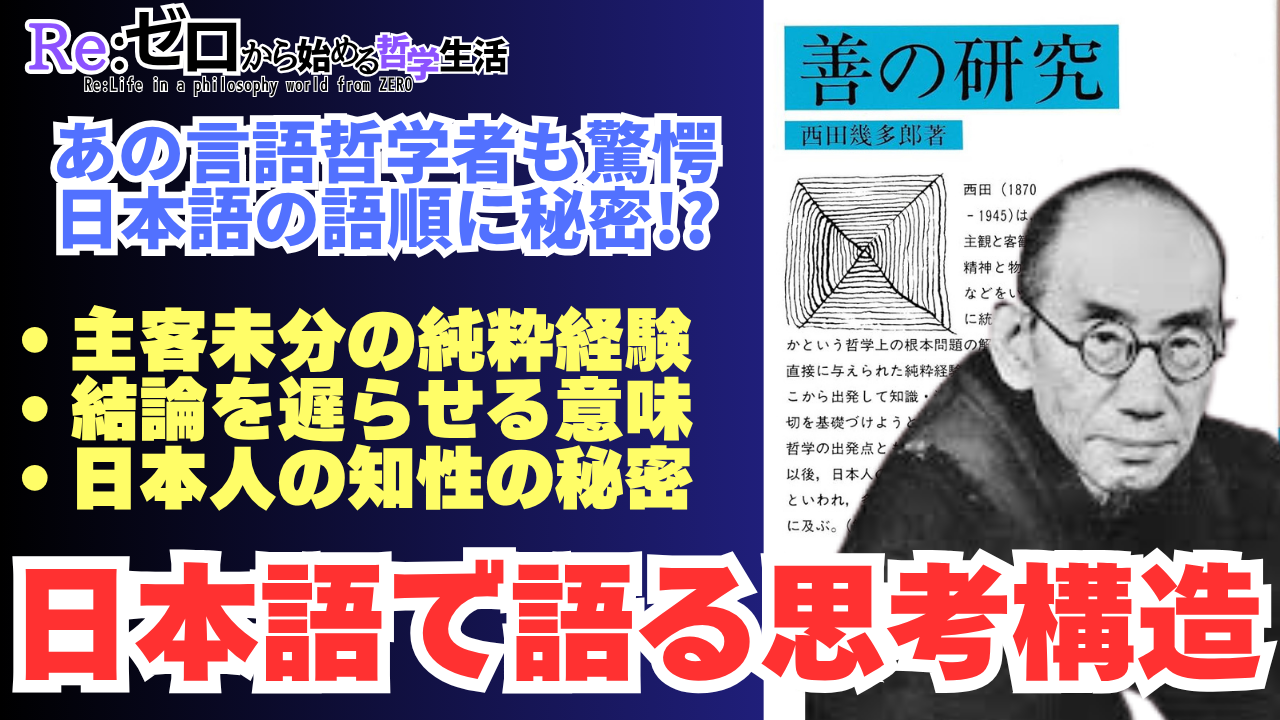
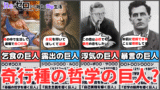

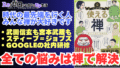
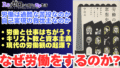
コメント