今回は「いかに天動説から地動説への転回がなされたのか」について考えていきましょう。参考文献は『チ。-地球の運動について-』(作者:うおとさん)です。
なぜ哲学や思想を学ぶ必要があるのでしょうか?前回の動画では哲学こそが常識を破壊して世界をアップデートしてきたとお伝えしました。そして数あるパラダイムシフトの中でも最も有名なのが「地動説」ではないでしょうか?紀元前のアリストテレス以来、地球こそが宇宙の中心であるという考えが常識でした。そして2世紀にエジプトのアレキサンドリアで活躍したプトレマイオスは、地球を中心とした太陽・月・惑星の運行を計算して体系づけました。これが「天動説」(プトレマイオスモデル)です。「天動説」は各地域の常識となってその後1500年間にわたる不動の定説となったのです。
この「天動説」を覆すきっかけとなったのがポーランドの天文学者コペルニクスです。コペルニクスは『天球の回転について』の中で太陽中心説―「地動説」を唱えたのです。そのため物事の見方を180度かえるような発想は「コペルニクス的転回」と表現されます。その後「地動説」はガリレオ=ガリレイが観測したことによって実証されました。そのため現在では「地動説」を誰もが当たり前のこととして理解しているのです。この「地動説」をテーマにした作品こそが「チ。-地球の運動について-」なのです。2020年から2022年までビックコミックスピリッツで連載(完結)されて2024年10月よりNHK総合でもアニメが放送されてとても話題になっています。(2022年には「手塚治虫文化賞」マンガ大賞を受賞されています)
実は地動説をテーマにした作品なのですが、作中には多くの哲学者の思想が登場します。そこで今回も「哲学の補助線」をひきながらこの作品を紹介していきたいと思います。ここで本編に入る前に1つだけお断りをさせていただきます。天動説と地動説のお話をすると「宗教と科学」の対立という印象を抱かれやすいのですが、史実的には地動説への転換はそのような単純な解釈ができるものではないようです。そもそもガリレオ裁判のような地動説に対する迫害はなかったという説もあるのです。作者の魚豊さんはそれも理解した上で「勘違い」に注目して描くことにこだわったそうです。今回の動画ではそのような点にも十分に注意しながらお伝えしていこうと思いますが、それを考慮しても世界の見方を考えるきっかけとして十分おもしろい作品だと思います。ぜひ最後までご覧になってあなたの考え方をアップデートするきっかけにしてください。
1 作品の概要
本作は第1章から第4章までの四部作という構成になっています。章ごとに別の主人公が登場しますが、前章で登場した人物も再登場することがあります。第1章(第1巻)は15世紀のP王国から物語が始まります。この国では天動説を公認するC教という宗教が中心となって、その教えに背く者は異端者として罰せられていました(P王国はポーランド、C教はキリスト教を示していると思われます)。
第1章の主人公は神童として生きてきた天才少年ラファウです。ラファウは異端者として捕まっていたフベルトから「地動説」の美しさを説かれました。そして最初は否定していたのですが少しずつ信憑性の高さと美しさに惹かれていくのです。しばらくしてフベルトは再び異端審問にかけられ死刑(火あぶりの刑)になるのですが、ラファウはフベルトに託された資料を守って天文の道へ進むことを決意するのです。しかしラファウは養父に密告されたことで異端審問官ノヴァクに逮捕されてしまいます。裁判でも地動説を信じることを堂々と宣言したラファウは拷問されることが決まります。しかし隠し持っていた毒で自殺する道を選び翌日その体は火あぶりにされるのでした。第1章のラファウの物語はここであっけなく幕を閉じることになるのです。
第2章(第2巻から第5巻)はラファウの死から10年後に始まります。偶然ラファウのペンダントを受け取り地動説の資料を発見した青年オグジーは、異端修道士バデーニと天文研究に取り組む少女ヨレンタと協力して研究を進めていきます。3人はいよいよ「地動説」を完成させるのですが同時に危機を迎えることになります。なんとヨレンタの父はラファウを逮捕した審問官ノヴァクだったのです。バデーニは拷問されるオグジーを見ることに耐えられず資料のありかを告白しました。資料は発見されてバデーニとオグジーは絞首刑になり地動説は闇の中へ…とはならず。バデーニは生前オグジーが記した手記を復元できるようにしておいたのです。またヨレンタは異端疑惑をかけられ拷問を受けるのですが逃亡することに成功します。ただし処刑されたと発表されたことでノヴァクは悲しみに暮れるようになるのです。
第3章(第6巻から第8巻)はそこからさらに25年後のことになります。金儲けを信念とする少女ドゥラカは偶然オグジーの地動説に関する手記を発見しました。しかしC教と対立する「異端解放戦線」のメンバーに本をわたすように迫られます。ドゥラカは本の内容を暗記していたので燃やすことで組織に同行する道を選ぶのです。ドゥラカは組織のボスに出会い活版印刷で本を流通させようとしていることを知ります。なんとこの組織のボスこそが第2章で異端疑惑から逃げ延びたヨレンタだったのです。
活版印刷を利用してお金儲けを考えたドゥラカはこれをレンタルする約束をしました。しかしここにも異端審問官とノヴァクが襲撃することになるのです。ヨレンタは火薬で自爆することで本の原本となるものをドゥラカたちに託したのです。その後もノヴァクたちに追われながらもドゥラカは地動説を伝えようとします。教会に追いつめられたドゥラカはノヴァクの攻撃によって負傷しながらも逃亡、そして死の間際に手記に関する伝言を伝書鳩に託すことになるのです。致命傷を受けていたノヴァクも教会で最後の瞬間を迎えようとしていました。そこでラファウの幻影と対話する中で「地動説が異端ではない」ことに気づくのです。ノヴァクは「私はこの物語の悪役だったのだ」と悟りました。そして娘ヨレンタの片腕に思い出の手袋をはめて抱きしめながら、「どうかむすめは天国へ」と祈りながら最後を迎えるのでした。
第4章(第8巻)は一転して現実のポーランド王国(1467年)から始まります。パン屋で働く聡明な青年アルベルトは親方から大学へ進学することをすすめられます。しかし幼いころの事件がきっかけで知的好奇心をもつことを悪と考えていました。ある日アルベルトはパンを教会まで届けた時に解告室で過去を話すことになりました。そして神父との対話を通して過去を乗りこえ大学へ進学することを決意するのです。朝日をあびて歩くアルベルトの耳元で一通の伝書鳩が届いたという会話が聞こえてきます。「地球の運動について」という本のタイトルが聞こえて一笑するも、「?」と考えるシーンをもって「地動説」をめぐる物語は完結することになるのです。余談として最後のページには、“アルベルト・ブゼルフスキ”はクラクフ大学に入学して後に教員として働いたこと、当時の天文学の教科書『惑星の新理論』の注釈書を書き大学で広く学びが展開されたこと、そして同大学の学生の中にその注釈書で天文を学んだコペルニクスという少年がいたことなどが記されています。
以上ざっとですが作品のあらすじを紹介してみました。最終章のアルベルトの過去エピソードには「まさかの人物」も登場します。きっと驚かれると思いますのでぜひご自身で読んでみてください。
2 作品に登場する哲学思想
『チ。』の中にはたくさんの哲学者やその思想が登場します。これらの知識や教養がある前提で本書を読むとその面白さは何倍にもなるはずです。「哲学の補助線」を引いてあらためて本書にも実際に目を通してみて下さい。
2-1 アリスタルコス(第1巻より)
ラファウがフベルトとの会話の中で知ることになるのがアリスタルコスです。アリスタルコスは紀元前3世紀頃のヘレニズム時代に活躍した天文学者です。アリスタルコスは太陽中心説を最初に唱えたとされています。そのため「古代のコペルニクス」と呼ばれることもあるそうです。
ラファウは第1巻でフベルトに「アリスタルコス」について尋ねられます。フベルトの資料はアリスタルコスの考えがもとになっていることが示唆されているのです。そして第1章の最後にラファウはノヴァクに死を恐れないのかと問われます。しかしラファウは以下の哲学者の言葉をもって返答しました。ソクラテス曰く「誰も死を味わってないのに誰もが最大の悪であるかのように決めつける」、エピクロス曰く「我々のある所に死はない、死のある所に我々はない」、セネカ曰く「生は適切に活用すれば十分に長い」
古代ギリシアの哲学者で「無知の知」で有名な哲学の祖ソクラテスも、「アテネの信じる神を信じることなく若者を堕落させた罪」で死刑判決を受けました。ソクラテスは最終章にも登場するのでそちらで詳しく解説しようと思います。
ヘレニズム時代の快楽主義の哲学者エピクロスは「隠れて生きよ」といい、感情を揺さぶられる機会をなるべく減らすことで心の平静をえることを目指しました。哲学者ルクレティウスはエピクロスの思想を詩の形式で著しました(事物の本性について)、1417年にドイツの修道院で写本が再発見されルネサンス期の思想に影響を与えました。作品内でも「ルクレティウスの詩」は重要なファクターとなっていますのでお楽しみに。
ローマ皇帝ネロの家庭教師として有名な哲学者セネカはエピクロス派と対をなすストア派の哲学者として「パンとサーカス」の時代に活躍しました。セネカは暴君ネロに仕えた経験をもとに怒りのことを悪だと批判して「この世でもっとも遠ざけるものである」と考えていました。だからこそ自分の中にある怒りと闘うことで怒りに出口を与えるなと説いたのです。
2-2 エラトステネス(第3巻より)
地球の大きさをはじめて測定した人物こそがヘレニズム時代の科学者エラトステネスです。エラトステネスの知的活動は詩学、哲学、地理学、数学、そして天文学にまで及びました。そのため様々な学問に造詣の深い人を意味する「文献学者」と呼ばれることを好みました。エラトステネスは夏至の日にアスワンの井戸の底に太陽の光が差し込むことに気づきます。そこで同じ時刻にアレクサンドリアで太陽光線と地表の垂線とのなす角度を測ったのです。この角度は地球の中心の角度と同じになるはずなので地球の外周は、井戸からアレクサンドリアまでの距離を角度(円周の50分の1)で割り返して求めました。これは約4万キロに相当するので地球の外周とほぼ等しいことが明らかになっています。
アリスタルコスは月食を利用して月の大きさを地球の約4分の1だと考えましたが、地球のサイズがわからなかったので月の大きさを計算することができなかったのです。しかしエラトステネスは地球の外周をわかっていたので計算することができたのです。その他にも、素数の判定法である「エラトステネスの篩」を発明したことでも有名です。
2-3 カール・シュミットとスピノザ(第6巻より)
第3章では「異端解放戦線」のメンバーであるシュミットという人物が登場します。「何かを理解しようとする人の知性とやらを信用していない」と考えて、シュミットは「自然主義者」を名乗り人の手でつくられたものを否定するのです。そして「神は理性の外、自然にこそ宿る」という信念をもって行動していきます。「神は自然にこそ宿る」という部分からは大陸合理論の哲学者スピノザが思い出されます。主著『エチカ』はデカルトと同じく演繹法による論理的な推論によって展開されますが、思想の制限との戦いでもあったスピノザはいつしか「最も危険な思想家」とよばれるのです。
スピノザの考える確実な真理は「全てが神の意志によって神のうちに必然的におこっている」ことを認識することでした。これを「事物を“永遠の相のもとに”観想する」といいます。つまり人も自然もすべてのものが神のあらわれであるということです。これを「神即自然」といいスピノザの思想は「汎神論」とよばれています。それまでの神のイメージは「意志をもって人間に裁きを下すような存在」でしたが、スピノザは自然や宇宙そのものを神と捉えて私たちが認識している世界というのは神のその時々における「擬態」であると考えたのです(このあたりが「危険思想家」というレッテルをはられる所以だともいえます…)。
そしてそのスピノザを批判したドイツの政治学者こそがカール・シュミットです。シュミットは全体主義国家論を提唱してナチスに理論的基礎を与えたことでも有名です。政治的なもののの本質は友と敵との対立であるとする「友敵理論」を唱えました。シュミット隊長のモチーフはこのカール・シュミットではないかなと想像しています。また、第3章ではヨーロッパの社会に大きな変革をもたらした三大発明が登場します。それが火薬、羅針盤、活版印刷(いずれも中国から伝来したもの)です。同じく中国発の「製紙法」も合わせると「四大発明」と言われることもあります。特に「活版印刷」は作中でも大きな役割を果たすようになるので注目して頂きたいです。
2-4 プラトンとアリストテレス
作中では何度もプラトンとアリストテレスの2人が登場します。古代ギリシアの哲学者プラトンはソクラテスの弟子で数々の著作を残しました。プラトンの思想は西洋哲学のあらゆる源流となったことから、20世紀イギリスの哲学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドによって「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」と称されています。
そのプラトンの弟子こそが「万学の祖」といわれるアリストテレスなのです。マケドニア出身でアレクサンダー大王の家庭教師を務めていたこともあります。プラトンが創設した学園アカデメイアに16歳で入学しますが、後にアリストテレスもアテナイ郊外にリュケイオンという学園を創設しました。そして庭園(ペリパトス)を散策しながら講義をしていたので逍遥学派といわれています。
第7巻ではシュミットがプラトン曰く「人の作る模倣は遊びのようなもので真剣に従事することではない」と言えば、ドゥラカもアリストテレス曰く「技術は自然を模倣する」と言い合うシーンが見どころです。また最終章では「タウマゼイン」という言葉が登場します。これは知的探求の原始にある「驚異」のことであり、この世の美しさに痺れる肉体のこと、そこに近づきたいと願う精神のことなのです。プラトンは著書の中で師ソクラテスを登場させて次のように語らせました。「実にその驚異(タウマゼイン)の情こそ知恵を愛し求める者の情なのだ。つまり哲学の始まりはこれよりほかにはないのだ」。またアリストテレスも著書の中で次のように述べています。「けだし、驚異することによって人間は…知恵を愛求(哲学)し始めたのである」
『アテナイの学堂』の中央に描かれている2人こそがプラトンとアリストテレスです。この2人は天を指さし「イデア」を見なさいというプラトンに対して、地に手をかざして現実をよく「観察」しなければいけないと対話しているようですよね?
2-5 資本主義と共産主義
第3章の主人公ドゥラカは移動民族の村落で暮らしていました。聡明なドゥラカはその頭脳をもって集団全体がより利益を出せる方法を考えていました。しかし村長はドゥラカの姿勢を受け入れません。なぜなら村落では皆が生活できるだけの豊かさはすでに保たれていて、利益は独占するものではなく平等に分配されるべきものとされていたからです。
これは現代でいうところの「共産主義」の発想に近いものだと思います。ところで「共産」とは「共有財産」を略した言葉だとご存じですか?ドゥラカの叔父がさりげなく使うこの言葉がそれを示唆していると考えられる場面です。しかしドゥラカは個人の自由競争によって集団全体の利益を増やせると主張します。集団で利益を分配すれば怠ける人が出てくるから功労者に報酬を与えるべきであると。そして個体差なく均一な方法で生産できる技術と商品を開発するべきであると。これはまさに「資本主義」の発想そのものですよね。
ドゥラカの叔父はそこに可能性を見出すものの反対だとドゥラカに言います。競争が加速すれば共同体は破壊され格差は拡大していくことになる。そこには弱者を救済する仕組みはなく倫理を失った自由は混沌であるからです。資本主義と共産主義の功罪がどちらもさりげなく登場するこの場面、現代の社会に置きかえて考えてみてもピンとくるところがあるのではないでしょうか?政治学や経済学も元をたどれば哲学から派生していったものであり、アダム・スミス、マルクス、ケインズ、そしてロバート・ノージックなどが有名です。過去の動画でも紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。
2-6 万物は流転する(第7巻より)
第3章の終盤でシュミットが語る言葉―「万物は流転する」(パンタレイ)、これは古代ギリシアの哲学者ヘラクレイトスが唱えたとされる言葉です。ヘラクレイトスは「自然界は常に変化している」と考えましたが、変化と闘争を万物の根源とし「火」をその象徴としたのです。
「戦争は万物の父」として戦争と平和、健康と病気など正反対に見える要素が対立によって変化が生まれ、反目しながらも全体としては調和を保っていると考えました。彼の有名な言葉に「同じ河に二度入ることはできない」というものがあり、これはものごとが絶えず変化していることを象徴する言葉といえます。ヘラクレイトスは友人がエフェソスの民衆により追放されたことに怒り、法の制定を委託した時にエフェソスの民主制を悪しきものとみて拒否しました。この時アルテミス神殿で子どもとサイコロ遊びをしていることに理由を尋ねられると「おまえたちと政治に携わるよりこの方がましだ」と答え「エフェソスのやつらなど成人はみな首をくくってしまえ」と暴言を吐いたそうです。このような厭世観と著作物のあまりの難解さから「暗い哲学者」と呼ばれました。
2-7 ソクラテス
最終章でアルベルトが大学進学をしぶる場面で親方は「アレテ―」という言葉を伝えます。「自分の得意なこと、自分にしかできないこと」がすべてのものにはあって、鳥のアレテ―は飛ぶことであり人間のアレテ―は考えることだというのです。「アレテ―」という言葉で思いうかぶのは、やはり古代ギリシアの哲学者ソクラテスです。釈迦、キリスト、孔子と並ぶ世界の四大聖人に数えられる偉大な哲学者なのです。
ソクラテスの思想には「知徳合一」というものがあります。「知」とは善悪の判断ができることであり「徳」とは人間の魂の良さのことを示しています。そして、人間の徳(アレテー)とは「魂の配慮」であると考えました。善悪の「知」を実現できれば魂は優れたものになり「徳」が実現されるということです。「ただ生きるのではなく善く生きよ」というソクラテスの言葉は知徳合一そのものです。
またソクラテスは「天才だけが知識を独占する」という当時の常識も破壊しました。そして誰であっても知識を生み出せることを産婆術という対話法によって示したのです。ソクラテスは豊富な知識をもちながらも対話する時に相手の話を聞くことに注力しました。「それはどういうことかな?」「これとこれを結びつけるとどうなるだろうか?」このように問いかけることで相手は新しいアイデアを次々と口にするようになったのです。美青年で知力や武力に優れた当時の人気アイドルでもあったアルキビアデスは、ソクラテスと対話することで知識が湧き出る快感から常に行動を共にしていたそうです。当時はプロタゴラスのようなソフィストから知識をさずけてもらうことが常識でしたが、ソクラテスは対話によって誰もが知識を生み出すことができることを示したのです。
3 3つの「チ」とは?
作品のタイトル「チ。」とは何を表しているのでしょうか?もともと魚豊さんは「知性と暴力」を描こうとしていて「地動説」がピンときたそうで、「地動説を選んだのは迫害された歴史がなかったというのが面白かった」と語っています。そして「人間は世界を勘違いするけど、そこからしか何も始まらない」としているのです。そんな前提のもとタイトルには3つの意味が込められているそうです
1つ目は「地動説」を象徴する「地」です。各章のタイトルコールは主人公が地動説と出会う場面が選ばれているのもそのためです。
2つ目は「知性」を象徴する「知」です。これはバデーニが同僚の神父と対話する場面で登場するのですが、「すでにこの世は非道徳的なことであふれている。そういう世界を変えるために何が必要だと思うか?」と問うた時に「知」というのです。
そして3つ目は「暴力」を象徴する「血」です。これはノヴァクが新人の審問官の疑問に答える場面で登場するのですが、「異端者は悪魔と結託して世界を変えようとする。それを阻止するために最も重要なもの、世界を保持するために必要なものは?」と問うた時に「血」だと言うのです。
また「チ。」についている句点そのものにも意味がこめられています。句点は地球そのもののメタファーでありタイトルにも軌道が描かれています。また句点は文の停止を意味しているものの軌道がえがかれることによって「地球が動き出す(=地動説)」というメタファーにもなっているのです。
作中で「知性と暴力」の対比を最も象徴的に描かれているのが第3章のラストです。神という絶対的な存在を信じて異端審問(=暴力)を続けてきたノヴァクがすべて自分の「勘違い」であったことを悟る時のことです。ドゥラカはノヴァクとの最後の対決の中で「これから来る金の時代」と未来を予見します。ノヴァクはそれを否定して「文明や理性の名のもとでは大虐殺がおこる」と言います。神に進むべき道を与えられなくなった人間の末路―神を失えば人は迷い続けると。しかしドゥラカはヨレンタの言葉「迷いの中に倫理がある」と返すのです。これから来る大量死の時代の責任は神ではなく人が引き受けるのだと。そこには「罪と救い」ではなく「反省と自立」があるのだと。苦しみを味わった知性はいずれ十分に迷うことのできる「知性」になる。暴走した文明に歯止めをかけて異常な技術を乗りこなせる「知性」になるのだと。個人的にはここに魚豊さんの描きたかったものがこめられているような気がします。
硬貨を捧げればパンを得られる、税を捧げれば権利を得られる、労働を捧げれば報酬を得られる、なら一体何を捧げればこの世の全てを知れる?
『チ。』の物語はこの言葉で始まりこの言葉で終わりを迎えます。ぜひその答えをこれからも一緒に探していきましょう。
4 まとめ
今回は「いかに天動説から地動説への転回がなされたのか」について考えてきました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだありますので、ぜひ本作品を手に取ってあなただけの「倫理」を見つけるきっかけにしてみてください。
「哲学は何の役にも立たない」と思われがちですが、現代社会を生き抜くためのヒントが哲学の中にはたくさんあるのです。「人間は思考することをやめてしまえば誰もがナチスのような巨悪になりうる」公共哲学の哲学者ハンナ・アーレントはこのように言いました。これからも「哲学」のおもしろさを発信していきますので、ぜひゼロから一緒に学んでいきましょう。
そしてこの動画をみてくれたあなたが「贈与」の差出人になってくれたら―そんな人が1人また1人と増えていくことでこの社会は少しずつよくなっていくはずです。この動画を作成したわたしはある意味では「差出人」の立場になりますので、それが皆さんのもとにきちんと届くかどうかはわかりません。しかしこのチャンネルを通してあなたが贈与を受け取っていたことに気づくことができる、そんな動画をこれからも制作していきたいと思います。本日の旅はここまでです、ありがとうございました。

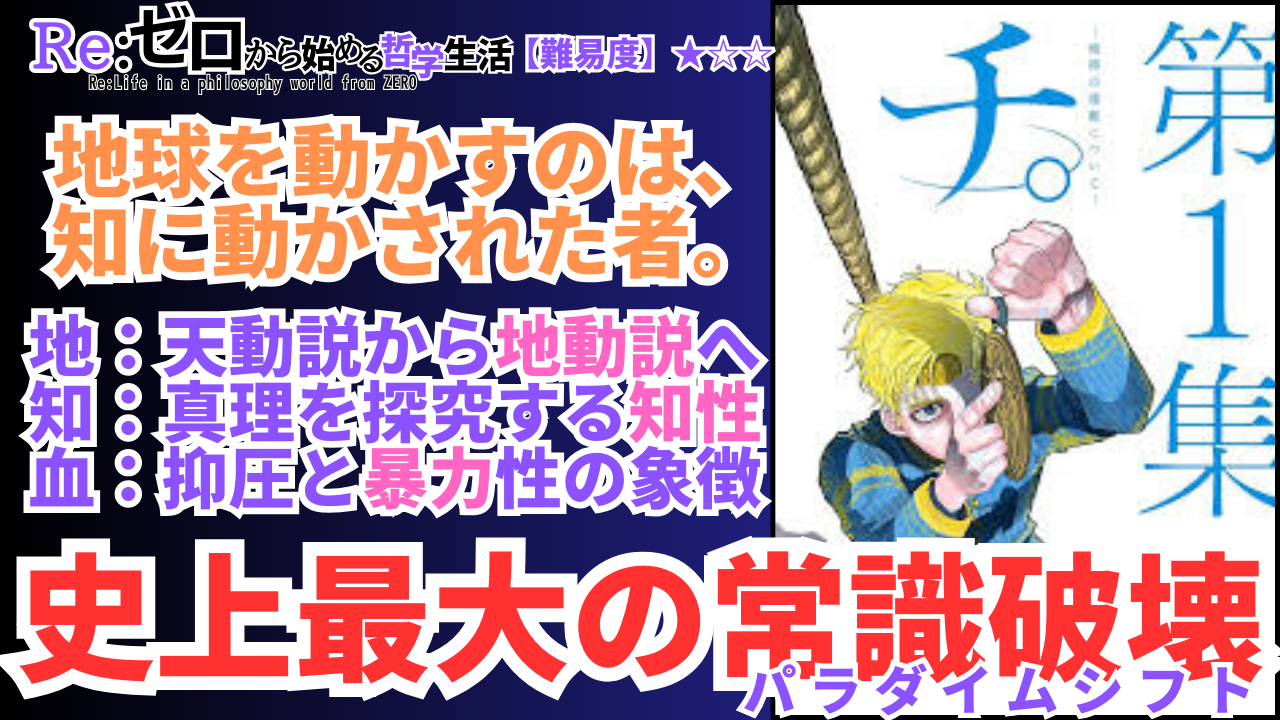


コメント