今回は「不条理と向き合い乗りこえるには?」について考えていきましょう。参考文献は『ペスト』(著者:アルベール・カミュ)と『まんがでわかるカミュ「ペスト」』(監修:小川仁志さん)です。
2020年2月27日に新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、安倍晋三首相による突然の小中学校休校宣言が全国一斉に出されました。当初は春休みまでを予定するものでしたがその期間は5月末まで延長されました。緊急事態宣言によるステイホームや不要不急の外出を自粛することを求められるなど、それまで当たり前とされていた日常は大きく変わることを余儀なくされたのです。
教育現場では学習のオンライン化への対応や部活動の大会中止など大きな影響が出ました。医療現場では医療従事者への過度な負担やワクチン対応への騒動などが問題となりました。それぞれの国がそれぞれ独自の対応をしたことも社会情勢を混乱させる要因になりました。
あれから5年、私たちはそれがなかったことであるかのように日常をすごしています。あの時どんなことが起こっていたのか?いまどんなことが起こっているのか?改めて考えてみることは、これからを生きていくためにきっと必要なことだと思います。
そこで、今回はアルベール・カミュの『ペスト』を紹介したいと思います。実存主義の哲学者でもありノーベル文学賞を受賞している作家アルベール・カミュは、不条理な運命を前に人間はいかに生き抜くべきかというテーマの作品を多く残しました。『ペスト』はカミュが戦時中のナチス占領下という状況において執筆された作品です。そこには私たちを抑圧するものに対する「反抗」を通して、私たちがどのように「自由と連帯」を獲得していけばよいのかが描かれているのです。
そこで今回も「哲学の補助線」を引きながら『ペスト』を通して、不条理な運命を乗りこえるためのヒントを探ってみたいと思います。前半では『ペスト』の概要を簡単に紹介して、後半ではカミュの哲学について解説することで『ペスト』が描いたものを考察します。この動画が面白かったと感じて頂けた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
1 『ペスト』の概要
『ペスト』の主な登場人物は以下の6人です。
物語の舞台であるオラン市で診療室を開いている医師のベルナール・リウー。本作の主人公で終盤ペストとの戦いの記録を残していたのはリウーであると明かされます。病気の妻を遠くの診療所に滞在させているのですがペストが終息した時に…。
「人は神なくして聖者になれるか」と自問している旅人のジャン・タルー。そのきっかけは判事の父が死刑判決を下す姿に失望して放浪の旅に出たことにあります。表の主人公リウーと固い友情を結び、保健隊の発起人となる裏の主人公のような存在。
オラン市のアラビア人の生活状況を取材しに来ていた新聞記者のレイモン・ランベール。スペイン内戦を経験し「正しさを貫く」ことの危険性を感じて愛に生きることを願います。恋人のいるパリにもどるためロックダウンされたオラン市を脱出しようと試みますが…。
オラン市で多くの市民から尊敬されているカトリック教会の神父パヌルー。ペストを神による愛ある罰であると解釈する説教を行うものの後にその心境が変化します。リウーたちに対して前半は反感、後半は共感をもつことになるきっかけとは…。
毎晩本を書くことに没頭しているオラン市役所の平凡な役人ジョセフ・グラン。若い頃に結婚して別れた妻への悔恨の中で毎晩小説を書くことを日課としています。保健隊が組織された時には真っ先に志願して幹事のような役割を担うことになります。
表向きは酒の代理販売業者をするグランのアパートの隣人であやしい過去をもつコタール。かつて自殺未遂を図ったがペストが蔓延する街で生き生きとするようになるその理由は…。
ほかにも、判事オトンと息子のフィリップ、医師会の有力者リシャール、オラン県知事などいますが主要6人がどのような行動をするのかにぜひ注目してください。
第1部 ペストの始まり(4月から5月)
「やがてわかったことであるが、ここにその記録をつづろうと思い立った一連の重大事件の最初の兆候ともいうべきものであったのである」(『ペスト』P9より)
194X年アルジェリアのオラン市で医師リウーはネズミの死体をいくつか発見します。やがて原因不明の熱病者が続出したことでその原因がペストであることが判明するのです。行政も医師会も世論を動揺させないために伝染病を認めようとしなかったのですが、事態をおもくみた県知事はオラン市をロックダウンすることを決断しました。外出するための個別の事情は一切考慮されることなく、突然の決定に家族や友人たちは引き離されることになりました。
第2部 ペストの広がり(5月から7月)
「そういうわけで、ペストがわが市民にもたらした最初のものは、つまり追放の状態であった」(『ペスト』P102より)
死者数は日増しに増加していくものの初期のころの人々の反応は「自分の行動制約に対する不満」が主なものでした。なぜなら、多くの市民はペストが一時的なものであると考えていたからです。
ある日、新聞記者ランベールは恋人のいるパリへ帰るためリウーに陰性証明を頼みます。リウーはそれを断るのですが「個人の幸せを考えていない」とランベールに非難されます。また、パヌルー神父は「信心深さが足りないせいでペストに見舞われた」と説教をします。人々は少しずつペストに対して未知の罪による禁固刑のような恐怖を抱くようになります。
そんな中、旅人タルーはボランティアによる保健隊を結成します。そして、リウーとタルーは神にも行政にも頼らずペストと戦うことを決意するのです。保健隊の結成を知った役人グランは真っ先に保健隊での活動を志願するのでした。そして「自分にできること」を遂行するだけと言い事務局長的な役割を担うようになります。
ランベールは密売人コタールの力をかりて街を脱出しようと試みますがうまくいきません。そして、殺人が英雄視されたスペイン戦争への参加経験からリウーたちに保健隊の活動も観念的なヒロイズムだと断じます。しかし、リウーは自分の仕事を誠実にはたしているだけだと応じるのです。そこで考えをあらためたランベールは保健隊への参加を決意するのでした。
「今度のことはヒロイズムなどという問題じゃないんです。これは誠実さの問題なんです。…ペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです」(『ペスト』P245より)
第3部 街の様子と人々の変化(8月)
「中心地区の人々は夜中に、しかもますます頻繁に、ペストの陰鬱な無感情な呼び声を窓の下に響かせる、救急車のベルをすぐ身近に聞くようになって、いよいよ自分たちの番が来たことを知るのであった。」(『ペスト』P249より)
ペストが蔓延していくと街から人々の動きが消えていくようになりました。ペストで家族を失った人が自暴自棄になって自宅に火をつけ、それを見た盗人たちが家から家具などを盗んでいく場面も描かれます。葬儀の手続きは簡素化されて死者は感染予防の観点から迅速に埋葬されていきます。ペストが長引くことで人々はある意味その生活に慣れていきます。しかし、それは感情の起伏を失った諦めの感情に支配された状態なのです。
第4部 ペストとの闘い(9月から12月)
「まことに、彼が日がな一日人々に分かち与えているものは、救済ではなく知識であった。こんなことは、もちろん、人間の職務といえるものではなかった。しかし、結局、恐怖にさらされた死者続出のこの民衆の中で、いったい誰に、人間らしい職務など遂行する余裕が残されていただろうか?」(『ペスト』P280より)
ペストとのたたかいが長引いていることで人々はどんどん疲弊していきます。しかし、コタールはこの状況にあって1人だけ満足感をえていました。なぜなら、かつて自分が経験した「いつ逮捕されるかわからない」という恐怖を、市民たちが「いつペストに感染するかわからない」という形で感じていたからです。
保健隊の活動をしながら脱出する方法を探っていたランベールにその機会が訪れました。しかし、ランベールは逡巡した末に街に残ることを決意するのです。
「自分一人が幸福になることは、恥ずべきことかもしれないんです」「僕はこれまでずっと、自分はこの町には無縁の人間だ、自分には、あなたがたはなんのかかわりもないと、そう思っていました。ところが、現に見たとおりのものを見てしまった今では、もう確かに僕はこの町の人間です、自分でもそれを望もうと望むまいと。この事件はわれわれみんなに関係のあることなんです。」(『ペスト』P307より)
10月下旬にようやく血清が届きペストにかかった判事の息子に試すことになりました。しかし、死期をおくらせただけでかえって大きな苦痛を与えてしまうことになるのでした。リウーは罪のない子が死にゆく世界など愛せないとパヌルーに神の存在を拒否するのです。パヌルー神父は再び聴衆を前にして説教を行うことになります。
しかし、前回とちがって幼い子どもの死を目の当たりにしたことで迷いが生じていました。そして、世界には、神について解釈できることとできないことがある、ペストがもたらしたことを解釈しようとせずただ学ぶべきであると言いました。だから、運命をすべて受け入れるのか、すべてを否定するしかないと説くのでした。それから数日後、パヌルー神父は突然に体調を崩して高熱を出して死んでしまいます。リウーは症状がペストのものとは一致しないことから、診断カードには「疑わしき症例」とだけ記すのでした。
11月下旬にタルーはリウーと2人きりになった折にある打ち明け話をします。もともと、タルーは自分のことをペスト患者であるという言い方をしていました。その理由は、判事である父が死刑を宣告するのを目の当たりにしたことで、社会が死刑という殺人の基に成り立っていることに気づいたからだというのです。タルーは自分が知らない間に人を殺している社会を受け入れているということがペストの中に生きていることと同じではないのかと考えたのです。
それ以来、タルーは人を死に至らしめるもの一切を拒否しようと努めてきました。ペストを振りまかない人間になるためには、強靭な意志をもつことが必要だと語るのです。そして、リウーとタルーはお互いの友情を分かち合いオランの浜辺で共に泳ぐのです。
「われわれはみんなペストの中にいるのだ、と。そこで僕は心の平和を失ってしまった。僕は現在もまだそれを捜し求めながら、すべての人々を理解しよう、誰に対しても不倶戴天の敵にはなるまいと努めているのだ。ただ、僕はこういうことだけを知っている―今後はもうペスト患者にはならないように、なすべきことをなさねばならないのだ。」(『ペスト』P375より)
クリスマスの日、グランがペストに罹患して重篤な状態に陥ります。しかし、翌日になると解熱して回復することができたのです。こうして、ペストの感染者数も少しずつ減少していくようになっていくのでした。
第5部 それぞれの結末(1月から2月)
「病疫のこの突然の退潮は思いがけないことではあったが、しかし市民たちは、そうあわてて喜ぼうとはしなかった。今日まで過ぎ去った幾月かは、彼らの解放の願いを増大させながらも、一方また用心深さというものを彼らに教え、病疫の近々における終息などますます当てにしないように習慣づけていたのである。」(『ペスト』P396より)
ペストの終焉が近づく中で人々は様々な態度をとります。慎重な姿勢を保つ人や抑圧から解放されて自分を制御できなくなる人など様々でした。しかし、希望が見えてきた頃、まさかタルーがペストに罹ってしまいました。リウーは自宅で決死の看病をしましたが、タルーは帰らぬ人となってしまうのです。リウーはとうとう「決定的な敗北」を感じることになってしまいました。
さらに、タルーの通夜の翌日、リウーは妻の死を告げる電報を受け取りました。長い間リウーは苦しみの中にいましたが、その知らせを平静な気持ちで迎えるのでした。
2月のある晴れた日、とうとうオラン市の門が開放されることになりました。ランベールはパリから恋人を迎えるのですが素直に喜ぶことができません。しかし、ペストによって愛する人を失った人々にとっては、ペストは永遠に終わりを迎えることはなかったのです。
「この記録も終わりに近づいた。もう、医師ベルナール・リウーも、自分がその作者あることを告白してもいい時であろう。」(『ペスト』P446より)
ここで本書の語り手(記録者)が実はリウーであったことが明かされます。最後の事件を報告する前に客観的な証言者の立場をとっていたことを弁明するのです。リウーが祝賀騒ぎの中で歩いていると警官隊の通行止めに阻まれてしまいました。なんと、コタールが群衆に向けて発砲騒ぎをおこしていたのです。コタールは街が正常に戻っていくのを見てまた警察に追われる恐怖を思い出していました。そして、警察がやってきたので慌てて発狂して銃の乱射事件を起こしてしまうのですが、そのまま警察に連行されていくことになるのでした。
リウーは今回の事件の記録が決定的な勝利の記録ではないことをよくわかっていました。そして、ペストは決して消滅することはなく、いつの日かまた人々に災厄をもたらす日が来ることを予告して物語を閉じるのです。
「ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類の中に眠りつつ生存することができ、…そしておそらくはいつか、人間に幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼びさまし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうことを。」(『ペスト』P446より)
2 アルベール・カミュの哲学
2-1 カミュの生涯
アルベール・カミュは1913年にフランス領アルジェリアで生まれました。カミュの人生は幼いころに戦争で家族を失い貧しさと向き合うことから始まりました。しかし、小学校で教師に恵まれ高等中学、アルジェ大学文学部へと進学していきます。この頃、重度の結核により余命を宣告されたり、学生結婚した妻に駆け落ちされたりする悲劇にも見舞われるのです。
ドイツでヒトラー政権が誕生したころ、大学を卒業したカミュは共産党へ入党しました。劇団を創設したり新聞記者になったりするものの、植民地主義を批判したことから反体制派としてアルジェリアを追放されてしまいます。ドイツ占領下のフランスを転々としながら不条理の三部作戯曲『カリギュラ』、小説『異邦人』、哲学評論『シーシュポスの神話』を執筆します。
また、非合法の新聞の編集長を務めながらレジスタンスの活動にも参加しました。『ペスト』はこのようなナチスの支配を肌で感じながら執筆された作品なのです。また、実存主義のサルトルとの交流が深まっていきました(後に論争に発展)。そして「人生には意味がないからこそ一生懸命に生きる価値がある」という不条理の哲学をカミュは独自の表現で綴っていくようになるのです。
カミュはドイツに協力的だった人々の粛清の是非に安易に賛成したことを後悔しました。そして、植民地の独立や民族解放戦争に対する政治的暴力の全てを否定したのです。しかし、この立場は主流派を拒絶するものであり、カミュは自ら表舞台から去ることになったのです。1952年にカミュ=サルトル論争の発端となる『反抗的人間』を刊行しました。旧友サルトルは政治的暴力を斥けることに対して「革命へと踏み出さないあいまいな態度である」として批判するのです。
1957年に史上2番目の若さでノーベル文学賞を受賞しますが、1960年に友人の車に乗っている時に不慮の交通事故で帰らぬ人となりました。
2-2 不条理の哲学
カミュの著作は「不条理」という概念によって特徴づけられているといえます。「不条理」とは理性をもって世界と対峙する時にあらわれる不合理性のことであり、そのような不条理な運命から目を背けずに見つめ続ける態度を「反抗」といいます。そして、人間性を脅かすものに対する反抗の態度が人々の間に連帯を生むとされました。
ちなみに、「不条理」というと難しい言葉のように感じますが、フランスでは日常的に使用される言葉であるといわれています。たとえば、不条理はフランス語でabsurde、英語でabsurdなのですがこれは「そんなアホな」「ばかげているよ」という意味なのです。
カミュの哲学は不条理というと難解でかっこいい気がしてきますが、カミュの哲学は「そんなあほな」だよと言われるとちょっと笑えてしまいますよね?人間は悲しいことや辛いことがあった時に「なぜだ?」と問いかけます。たとえ理由がわかったとしても現実を変えられるわけではないのに問うのです。なぜなら、意味や理由がわかれば苦しみに耐えられることもあるけれど、私たちは意味のない苦しみには耐えられないのかもしれないからです。
しかし、世界は、神は、もちろん何も答えてくれません。これこそが、カミュの考える「不条理」そのものだといえるのではないでしょうか。カミュはキリスト教による神への信仰や左翼的革命思想を拒否していました。そのような超越的価値に依存しないで、人間の地平に立って生の意味を探究したのです。
そして、カミュはこの不条理を「それでいい!」と受け止めることが必要であり、毎日をひたすらに生きていくことこそが幸福であるとしたのです。『シーシュポスの神話』におけるシーシュポスが永遠に岩を山頂まで運ぶ労苦を課されてもなおそれを受け止めたように、『異邦人』における主人公ムルソーが不条理な世界からはじき出されてもなお自分に正直に生き抜くことで幸福感を感じながら最後を迎えたように生きていくのです。
2-3 カミュが描いた『ペスト』とは?
カミュは『ペスト』を通して「不条理に向き合う人々の姿」を描き出したといえます。『ペスト』はナチスドイツによる占領下のヨーロッパで実際に起こっていたことへの隠喩(メタファー)だといわれています。過酷な占領下で横行した裏切りや密告、同胞同士の相互不信、刹那的な享楽への現実逃避、愛する者たちとの離別などカミュがレジスタンス活動の中で目撃した赤裸々な人間模様が『ペスト』という作品の中に大きく反映されていると考えられます。
ランベールがリウーに対して「抽象の世界に生きている」と断罪した場面がありました。新型コロナが流行した際にも、同じようなことを感じた人は多いのではないでしょうか?医療従事者に対して冷ややかな視線を送る人たちも大勢いたように思われます。しかし、『ペスト』ではリウーによる言葉「抽象と戦うためには多少抽象に似なければならない」が述べられる場面があります。1人1人の幸せという具体―感情と向き合う時間をとられるほど、それだけ効率性が悪くなり全体的なリスクが増大してしまいます。つまり、ペストとの戦いでは「人間らしさ」が最も足手まといとなってしまうのです。
これが「不条理」でなくて何といえるのでしょうか?このような状況におかれると、それを打破してくれるヒーローを望むようになります。しかし、現実においても、『ペスト』においても、それは決して現れませんでした。事態を解決したのは現場で淡々と戦い続けたリウーであり、タルーら保健隊の面々たちのようになすべきことをした人々の功績のおかげなのです。
『ペスト』でも、新型コロナでも、社会の分断が大きな問題の1つとなっていました。世界的には、自国優先主義を掲げる政治家への支持が大きくなっているように思います。私たちはもう分断を乗りこえることができないところまで来ているのでしょうか?
『ペスト』では、リウーの「誠実さ」が共感と連帯を生んでいく様子が描かれています。リウーの行動がタルーに保健隊を結成させることを決意させ、保健隊の活動を通してランベールやパヌルー神父とも共闘するようになっていきました。たしかに、不条理は容易に大きな分断を生むことにつながっていくかもしれません。しかし、分断を生むのも分断を埋めて連帯するのも私たちの行動しないなのです。
タルーのいうように、「自分がペスト患者になっていないか」と問う強い意志が必要です。ペストは「自分の目的や達成しようとしているものは正しいのだから、どんな手段でも正当化できる」と考えている人の傲慢さのことだともいえます。ペストが暗示している不条理は、またいつか私たちを必ず襲うことになるでしょう。『ペスト』を読むことを通してリウーの「誠実さ」とタルーの「共感」を少しでいいからもつことができるようにありたいと思いました。
3 まとめ
今回は「不条理と向き合い乗りこえるには?」について考えました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだありますので、ぜひ『ペスト』だけでなく『異邦人』などほかの著作も読んでみてください。
「哲学は何の役にも立たない」と思われがちですが現代社会を生き抜くためのヒントが哲学の中にはたくさんあるのです。思想家の内田樹さんは小役人グランの生き方こそがカミュにとっての理想的な市民であったのではないかと考察しています。作中でもあまりぱっとしなかったグランは保健隊の結成を知ると真っ先に志願しました。そして、ペストが終息すると何事もなかったかのように元の生活に戻っていきます。
『「紳士」にヒロイズムは要りません。過剰に意気込んだり、使命感に緊張したりすると、気長に戦い続けることができませんから。日常生活を穏やかに過ごしながらでなければ、持続した戦いを続けることはできない』(「内田樹の研究室」より抜粋)
「自分の目的や達成しようとしているものは正しいのだからどんな手段でも正当化できる」カミュはペストのことをこのように考えている人の傲慢さの象徴として描きました。私たちが気づかないうちにタルーの言う『ペスト』に罹っていないか、そして「ペストと戦う唯一の方法は誠実さ」であることを忘れないようにしたいですね。本日の旅はここまでです。ありがとうございました。

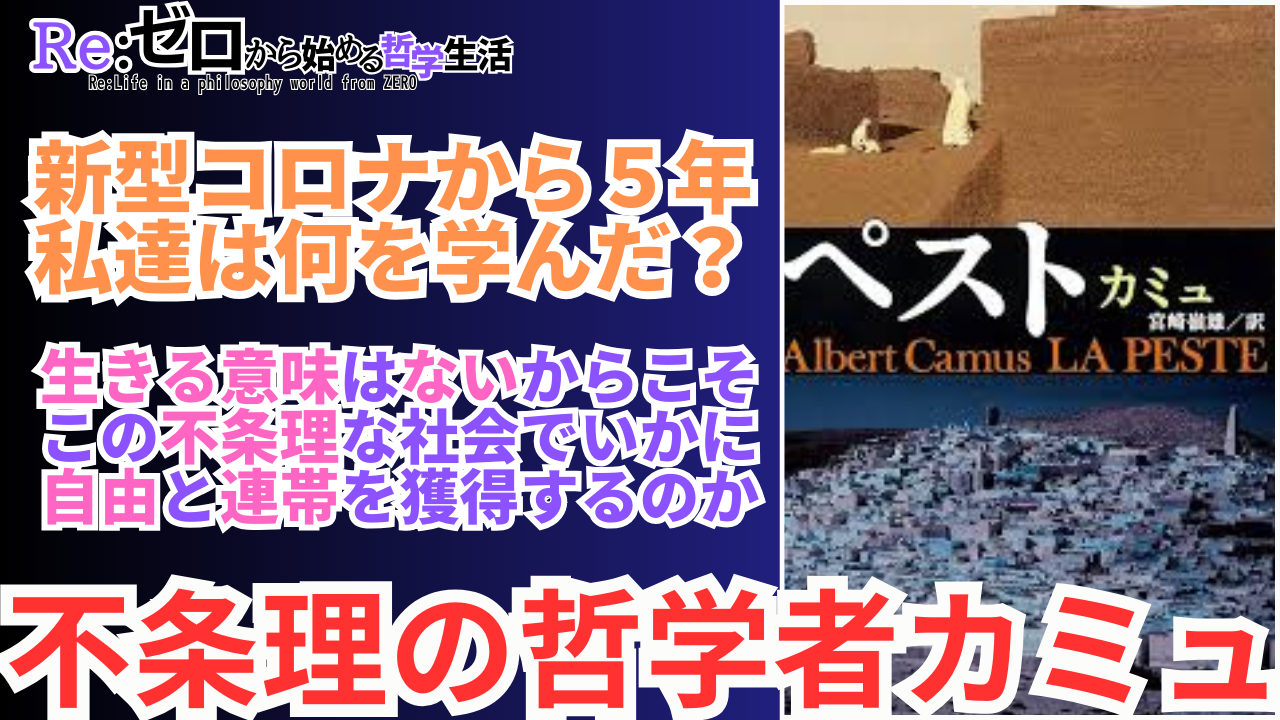

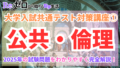
コメント