今回は「世界の成り立ちを理解するための宗教の教養」について解説したいと思います。参考文献は『世界は宗教で読み解ける』(著者:出口治明さん)です。
「宗教なんて合理的・理性的に考えれば迷信にすぎない」 こんなふうに考えている人も多いのではないかと思います。しかし、そんな人でも教会で結婚式をあげて誰かが亡くなればお寺で葬式をしたり、クリスマスのお祝いをした1週間後には神社へ初詣のお参りに行ったりもします。宗教とは関りがないと思っている人でもこのような経験があるのではないでしょうか? また、長い歴史の中で宗教は政治や経済、芸術などの文化にも大きな影響を与えてきました。「信仰」という名のもとに文化の破壊や悲劇的なできごともたくさん起こってきたのです。たとえば、今日の世界の共通ルールの多くは西洋中心に決められたものが多く、そこにはキリスト教が大きな影響を及ぼしています。キリスト教は西洋文化の根底にあり2000年の歴史と20億人の信徒をもっています。だからこそ、キリスト教をはじめとする宗教への理解は必須の教養となるのです。 紀元前1000年頃にはペルシアの地に世界最古の宗教ゾロアスター教が誕生しました。紀元前600年頃にはギリシアの地に世界最古の哲学者タレスが登場しました。つまり、まず人間のさまざまな問いに答えを出してきたのは宗教だったことがわかります。それから哲学が台頭してきて現在では科学がそのほとんどを証明できるようになりました。 では、科学が答えをだしているのであれば宗教や哲学を学ぶ必要はもうないのでしょうか?そんなことはありません、なぜなら科学もまた必ずしも万能というわけではないからです。 科学が発達した現代においても宗教はなくなるどころかむしろ発展すらしているのです。科学では説明できないことがある限り、決して宗教がなくなることはないでしょう。そのため、宗教への教養があれば世界を少し高い視座から見ることができるのです。 今回はこの動画の内容を大幅に加筆して、東洋の思想や現代社会の様々な課題との関りについても詳しく解説していきます。内容がわかりやすかったと感じた時にはぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 宗教とは何か?
人類がほかの動物たちと比べて特に秀でた身体的特徴がないにもかかわらず、この地球の覇者となれたのは「考える力」がほかのどの生物よりも秀でていたからなのです。人間は考えることで自然を征服してさまざまな文明や文化を創造してきました。その結果として幸福や不幸という概念も生み出すことになったのです。
以前の動画でポール・ゴーギャンのこの長いタイトルの絵画―『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』を紹介しました。

「世界はどうしてできたのか?」「人間はどこから来てどこへ行くのか?」この最も根源的な問いについて考えてきたのが哲学と宗教なのです。哲学者たちは世界をまるごと理解しようと思考をめぐらせました。そして、同じように宗教家たちは人間のさまざまな葛藤―生老病死などの苦しみをまるごと救おうとした人たちだったのです。
ところで、哲学も宗教も日本ではあまりなじみがない言葉のように感じると思います。その理由はどちらも明治維新によって輸入された概念に訳語がつけられたからなのです。宗教は英語で「religion」なのですがラテン語「 religio」から派生したといわれています。「re」は再びという意味の接頭語で「 ligare」は結びつけるという意味の言葉です。つまり「神と人とを再び結びつける」というような意味なのではないかと思われます。
この神という概念が生まれたのは約12000年前のドメスティケーションの時代―いわゆる狩猟・採集社会から定住・農耕社会への転換期だとされているそうですが、それ以来どうやら私たち人間の脳はあまり進化していないようなのです。人間は定住を始めたことがきっかけで世界を支配するようになっていくのです。地球上の全て―植物を支配する農耕、動物を支配する牧畜、そして金属を支配する冶金、これらを支配した人間はいよいよこの世界を動かす原理をも支配しようとしたのです。
「太陽を動かしているのは誰か?」「誰が我々の生死を決めているのか?」そのような自然界のルールを定めているもの―それこそが「神」であると考えたのです。このような中で「時間」に対する概念も大きな役割を果たしてきたと考えられます。
紀元前1000年頃に誕生したとされる世界最古の宗教であるゾロアスター教では、「最後の審判」という過去から未来に向かい直線的に流れる時間の概念を生み出しました。ここには「始まり」と「終わり」があるという点が重要なポイントになります。なぜなら、まず神様が世界を創造した後にいろいろあるものの最後には終わりを迎える―このようなストーリーがあるからこそ宗教における「救済」の考え方が形成されたのです。
特にセム的一神教(ユダヤ教・キリスト教・イスラム教)では唯一神を信仰することで現世の苦しみに耐える力と心の平安をもえることができるのです。
これに対して、東洋の思想では「輪廻転生」という円環する時間の概念が誕生しました。自然界の周期的な変化をもとに暦が発明されたことにその起源があると考えられます。暦もまた時間を管理するという点で自然界のルールを支配しようとした1つの形態です。円環する時間の中から「自分とか、ないから」という思想が生まれました。そして、輪廻の苦しみから逃れるために解脱という救済を示す思想が誕生するのです。
「自然の円環する時間」と「人生の直線的な時間」という2つの時間の概念は、宗教の発展に大きな影響を与え、現代に至る世界観を形成する重要な要素なのです。
2 ユダヤ教とアメリカの政治
2023年に起きたパレスチナとイスラエルの衝突は世界中に大きな衝撃を与えました。これに対して世界中からイスラエルの攻撃を非難する声があがるいっぽう、アメリカ(と同盟国の日本)はイスラエルを支持するスタンスをとっているのです。
パレスチナの問題を正しく理解して、アメリカの政策を読み解くためにはユダヤ教に関する理解が必要になるのです。
ユダヤ教はもともとユダヤ民族の民族宗教でもある一神教の宗教です。信者数は約1500万人で聖典はヘブライ語聖書タナハ(旧約聖書)であり、ユダヤ教を信じる人々のことをユダヤ人(自称イスラエル人で他称ヘブライ人)とよびます。
紀元前13世紀頃にエジプトで苦難の生活を強いられていたイスラエルの民は預言者モーセに率いられてエジプトを脱出します(出エジプト)。そして、紀元前11世紀頃にイスラエルの地にヘブライ王国を建国したといわれています。ソロモン王とダビデ王の時代に最盛期となりエルサレムにヤハウェ神殿を建造しました。その後に北のイスラエル王国と南のユダ王国に分離するのですが、前722年にイスラエル王国はアッシリアに滅ぼされてしまいます。
前586年にユダ王国は新バビロニアに滅ぼされヤハウェ神殿も破壊されてしまいます。新バビロニアの王ネブカドネザル2世による住民連行事件が有名な「バビロン捕囚」で、住民のヘブライ人はそのまま約50年の捕囚生活をバビロンで送ることになったのです。その後アケメネス朝ペルシアが新バビロニアを滅ぼしてヘブライ人は解放されるのですが、ヘブライ人は司祭階級を除いてほとんどエルサレムに還らなかったようです。当時のバビロンは世界随一の都といわれていましたので、50年後のヘブライ人の子孫がわざわざ知らない田舎の土地へ行くかと言われても…(東京で生まれた人が遠い先祖が地方の山村にいるからって帰りませんよね?)
エルサレムに帰郷した司祭階級の人たちはユダヤ教のヤハウェ神殿を再建しましたが、このままではユダヤの民族は消滅してしまうのではないかと考えました。そこで、民族のアイデンティティを確立するために「旧約聖書」を整備するのです。旧約聖書ではユダヤの民は苦しい時代を生きているがもともと神に選ばれた民族である、だから最後は救世主があらわれて救ってくれるという選民思想を説いたのです。ちなみに、救世主はヘブライ語でメシアといいギリシア語ではクリストス(キリスト)です。
旧約聖書はユダヤ教においてタナハといわれます。この中には創世記から順番に歴史的に物語が語られていますが、実は多くのねつ造もふくんでいるとされています。たとえば、アダムが土からつくられたという話はシュメール人の神話をもとに、ノアの方舟はメソポタミアの大洪水、エデンの園はメソポタミアの地名をもとに。もちろん、先に紹介した最後の審判はゾロアスター教をもとにされています。
そんな旧約聖書は世界中に離散(ディアスポラ)しているユダヤ民族のアイデンティティを確かなものとすること以外にも大きな理由があって制作されました。それがユダヤ民族にもアケメネス朝に負けない歴史があることをアピールするためです。(日本も中国に負けない歴史があることをアピールするために記紀を編纂しましたよね)。
ユダヤ教では神が与えた立法やモーセの十戒を遵守することで私たちは神に選ばれるという選民思想が根底にあります。ユダヤ人たちは中世の時代から長きにわたって迫害され続けてきました。ローマ帝国によってキリスト教が公認されるとユダヤ人はイエス・キリストを十字架にかけた罪人であるというレッテルをはられました。また、十字軍の遠征においてアラブ人と同様にユダヤ人も異教徒とみなされたことやキリスト教で禁止されていた利子を認めるユダヤ人を金の亡者とも揶揄されたのです。19世紀には反ユダヤ主義の流行からロシアを中心とするポグロムやフランス将校がスパイ容疑をかけられたドレフュス事件なども起こりました。
このような時代の流れの中でユダヤ人たちはやがてユダヤ人の国家を建設しようという、いわゆるシオニズム運動(シオンとはパレスチナの古名)が始まるのです。パレスチナの地は当時オスマン帝国が支配していたのですが、オスマン帝国を弱体化させるためにイギリスは1917年に「バルフォア宣言」を出してパレスチナの地にユダヤ人の国家を建設することを約束したのです。ところが、イギリスは1915年に「フサイン=マクマホン協定」をアラブ人と、1916年に「サイクス=ピコ協定」を仏露と結んでいたのです(悪名高い三枚舌外交)。
第二次大戦後の1948年にユダヤ人は約束どおりイスラエルを建国するのですが、もともとこの地にいたアラブ人たちはパレスチナ難民となってしまうのです。そして、イスラエル建国に反発したアラブ諸国との間に4度の中東戦争が起こりました。イスラエルには「独立戦争」であり、アラブ諸国には大災害(ナクバ)だとされています。
1993年に結ばれたオスロ合意は両者の問題を解決する糸口になると考えられました。この合意はアメリカのクリントン大統領の立ち合いのもと、イスラエルのラビン首相とパレスチナ解放機構のアラファト議長によって調停されました。しかし、1995年にイスラエルの右翼過激派によってラビン首相は暗殺されてしまいます。翌1996年に右派政党のネタニヤフ首相が就任すると和平交渉は停滞してしまいました。
パレスチナ側でも共存を目指すファタハと武力闘争を志すハマスの対立が大きくなります。2006年にはハマス側がガザ地区からファタハを追放する出来事も起こりました。その間にイスラエルはどんどん入植地を拡大させていき巨大な壁を建造しました。その結果、2023年にハマスがイスラエルを攻撃して人質をとる事件が勃発したのです。イスラエルは報復として「戦争状態」と声明を出して大規模な爆撃を行い、両者の戦闘は2025年現在に至るまで継続しているのです。
なぜ、日本の同盟国アメリカはイスラエルを支持する姿勢をとっているのでしょうか?その背景にはイスラエルを支持するキリスト教徒には神の祝福があるという宗教的な信念が関係しているからなのです。トランプ大統領の支持基盤でもあるキリスト教の宗派の1つである「福音派」では、同性婚への反対など保守的な態度をもち大統領選挙を左右する力をもっています。
また、アメリカはイスラエルに次いでユダヤ人が多い国でもあります。イスラエル系のロビー団体はアメリカの中東政策に対しても大きな影響をもっていて、豊富な資金をもとに共和党だけでなく民主党からも大きな支持を集めているのです。そのため、トランプ大統領だけでなく民主党のバイデンやカマラ・ハリスも「イスラエルは正当な自衛権を行使している」というスタンスをとっているのです。
2025年5月、ハマス指導者を殺害したというニュースが報道されました。これまで何度も停戦協定を行ってきたもののうまくいかなかった両者の問題が、この先どのようになるのかを注視していかなければいけないと思います。
3 キリスト教と資本主義
ダニエル・デフォーの著書『ロビンソン・クルーソー』を読んだことがあるでしょうか?18世紀に出版された本書は当時のヨーロッパの時代精神を反映したものとなっています。主人公クルーソーの行動や思想にはプロテスタンティズムの影響が大きいと考えられます。
たとえば、無人島に漂着した時には規則正しい生活を送り勤勉に働くのです。クルーソーは聖書を読んだことで神の意志を自らの生活に反映させようとすらするのです。また、無人島を開拓して文明を築いていこうとする姿からは、当時の植民地主義や帝国主義的な精神を象徴しているとも解釈できるようです。原住民の黒人フライデーを文明化しようとする姿勢には当時のヨーロッパ中心主義的な世界観が色濃く反映されているようにも思えます。
このように、『ロビンソン・クルーソー』にはプロテスタンティズムの倫理感や、資本主義の精神とヨーロッパ中心の植民地主義という特徴が現れていると考えられます。
このプロテスタントとはキリスト教における宗派の1つです。プロテスタンティズムと資本主義の関係を理解するためにはキリスト教の起源と発展と歴史を正しく知るところから始める必要があるのです。
キリスト教はイエスを救世主として信仰する世界最大の宗教です。信者数は20億人以上(世界人口の約30%)で聖典は旧約聖書と新約聖書です。旧約聖書とは「Old Testament」であり、新約聖書とは「New Testament」の翻訳です。キリスト教ではイエス以前の預言者と神との契約のことを旧約(旧い約束)とよび、イエスの言葉や奇跡を弟子がまとめたもの(新しい神との契約)を新約とよんでいるのです。つまり、もともとの起源はユダヤ教にもあるといえる一神教の1つなのです。
イエスはユダヤ教の上層部に蔓延していた堕落を批判する活動をしていたようです。いわゆる、ユダヤ教における宗教改革ともいえる運動だったと考えられます。しかし、ユダヤ教の司祭たちはイエスの活動が教義を脅かすものだと不信感を募らせて、ローマ総督ピラトにローマへの反逆を企てていると密告したのです。そして、民衆たちも十字架の刑を要求したことからピラトはイエスを処刑したのです。
イエスの死後はその教えを弟子の12使徒が中心となってエルサレムで布教していました。しかし、イエスの教えを最も体系的に発展させたのはパウロだと言われています。パウロはイエスの弟子ではなくローマ市民権をもつユダヤ人でした。もともとはイエスの教えを迫害するパリサイ派のユダヤ教徒だったのです。しかし、パウロはイエスの死から数年後にダマスカスへ向かう途中で天からまぶしい光が降り注いだことがきっかけで落馬して失明してしまいました。この時に天上から主イエスの声が聞こえて回心したといわれているのです。
そして、エルサレムに向かいますがイエスを迫害していたので追い出されてしまいます。そのため、アナトリア半島やエーゲ海の周辺都市にいるユダヤ人に布教活動をしたのです。この時パウロがエルサレムから距離のあるローマ帝国の辺境で布教したことが、後にキリスト教が世界宗教に発展する契機となっていったのは運命の悪戯といえそうです。
パウロはイエスの教えを以下のように布教したといわれています。―神が天地を創造して人間はエデンの園で楽しく暮らしていたけど、神の教えを破って禁断の知恵の実を食べたことで原罪を背負うことになってしまったのだ。そのためイエスは全人類の原罪を贖うために十字架で磔刑にされたのであり、イエスこそが人類の救世主メシア(キリスト)である。
パウロの書簡は後に新約聖書の正式文書に位置づけられていきます。ローマで布教活動をしていた初期キリスト教団は庶民に人気のあった地元の宗教―ミトラス教とイシス教からアイデアを拝借しているのです。ミトラス教では冬至にお祝いをする文化があるのでイエスの誕生日も冬至の頃にしました。これがクリスマスの起源であり正式に12月25日に決まったのは4世紀の頃です。
また、イシス教ではイシスが子どもを抱く像があるので、そこからイエスを抱く聖母マリア像をつくったのです。このような布教活動の末にイエスの教えは少しずつローマ帝国の中でも広がりました。そこで、イエスの教えを新たに文書にしようとしたことで新約聖書がまとめられるのです。新約聖書は27の文書の集合体としてまとめられるのですが、正式にキリスト教に認められるのは4世紀の終わり頃だったようです。27文書は4つの福音書と使徒言行録、そしてパウロなどによる21の書簡と黙示録で構成されています。福音とは良い知らせのことで英語ではゴスペル、ギリシア語ではエヴァンゲリオンです(あの有名な哲学アニメもキリスト教からアイデアを頂戴しているということですね)。
福音書はイエスの言行を4人の書記者(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)が纏めたものです。また、使徒言行録はペテロやパウロなどの伝道の記録のことであり、黙示録はキリストの再来と地上の王国の滅亡を啓示する内容となっています。
マタイ福音書にはイエスの誕生について以下のような記述があります。ベツレヘムで大工をしていたイエスの父ヨゼフには許嫁のマリアがいましたが、まだ愛を交わしたことがないのに妊娠していることに気づくのです。そのため、マリアと別れることを決意するのですが夢の中に神の使者があれわれて「マリアを妊娠させたのは神の精霊であるので生まれた子にイエスと名付けなさい。イエスは人類の罪を救うために生まれてくるのだ」とお告げしたのです。
しかし、アレクサンドリア教会のアリウス司祭はこの伝説を次のように解釈しました。神は唯一の存在であるのでイエスは神そのものではなく神のつくった人の子である、と。もちろん、イエスの神性を否定するものではないのですが神ではないということです。
当時の教会では「イエスは神の子」とされていたのでアリウスを破門することにしたのです。しかし「イエスは人の子」というアリウスの主張はわかりやすいので、さまざまな地域に広く伝承されていくことになるのです。
3世紀になると、ユーラシア大陸の大規模な寒冷化によって諸部族が次々にローマ帝国に侵入するようになりました。そこで、皇帝ディオクレティアヌスは広大なローマ帝国を4つの地域に分割―いわゆる四分割統治(テトラルキア)をしましたがそれも長くは続きませんでした。その後コンスタンティヌス大帝によってローマ帝国は再統一されるのですが、その過程で313年に「ミラノ勅令」が発令されることになったのです。これは帝国内での信教の自由を認めるものでここにキリスト教の弾圧はおわるのです。
コンスタンティヌス大帝はキリスト教の教義をめぐる討議をする公会議を開催しました。場所はニカイア(現トルコのイズニク)で325年に第1回の会議が開催されました。この会議のテーマは「イエスは神の子なのか人の子なのか」ということでした。「イエスは神の子」とした論客はアレクサンドリア教会のアタナシウス司祭です。アタナシウスは「神とイエスが異質なものであったら信仰は成立しないので。父なる神と子なるイエスは同質であることからイエスは神の子である」と考えました。そして「マリアを身ごもらせたのは神の位格をもつ精霊であるのでイエスは神の位格をもっている」と主張したのです。ここに「父なる神と子なるイエスと精霊の3つの位格はすべて一体の神である」とする「三位一体説」が誕生してこれがニカイア信条として正式な教義となっていくのです(父と子と精霊の名において…というやつですね)。
その後テオドシウス帝がコンスタンティノープル公会議で三位一体説を正当な教義として、392年にキリスト教をローマ帝国の正式な国教と定めました。これによってギリシアの神々への信仰も禁止されたことから古代オリンピックも中止となったのです。
中世ではキリスト教のカトリック教会があらゆる分野で大きな影響力をもっていました。中でもエジプトのアレクサンドリア教会、シリアのアンティオキア教会、エルサレム教会、コンスタンティノープル教会、そしてローマ教会の5つは五大本山といわれました。エジプト、シリア、エルサレムの3つはイスラム勢力の影響によって衰退していくのですが、コンスタンティノープル教会とローマ教会は激しく対立していくようになります。そして、1054年に長い対立の果てに大シスマ(東西教会の大分裂)が起こりました。これがローマ=カトリック教会とギリシア正教会に分離することにつながっていくのです。
ローマ教会は中世ヨーロッパ社会に大きな影響力を行使するようになりました。1077年には「カノッサの屈辱」とよばれるローマ皇帝を破門する事件が起こります。また、1095年にはクレルモン公会議において「十字軍」への呼びかけが行われました。この後200年に及ぶ遠征はイスラム教との間に大きな禍根を残して失敗に終わるのです。
それだけでなく、武力で異教徒を排斥する思想はイベリア半島の「レコンキスタ」や新大陸アメリカにおけるイエズス会による侵略という名の布教運動につながるのです。十字軍の失敗や教会の腐敗をきっかけに起きた宗教改革は、16世紀にドイツの修道士マルティン・ルターによって始まりを告げられました。1517年、ルターはゲッティンベルグ城の教会に95ヶ条の論題を掲示しました。
また、フランスではジャン・カルヴァンも独自の改革運動を展開しました。その結果、プロテスタントとよばれる新しい宗派が形成されていくことになったのです。このカルヴァンが主張した「予定説」こそが資本主義の発展につながっていくのです。予定説とは「救済は神によってあらかじめ決められている」という考え方のことです。あらかじめ決まっているならどのように生きてもいいように思えますが、プロテスタントでは選ばれた者であることを証明するために勤勉に働こうとするのです(ロビンソン・クルーソーの行動はまさにこの予定説にもとづいているといえます)。
カルヴァンの教えでは世俗的な成功は神の恵みであると解釈されています。つまり、仕事で成功して富を築くことは神に選ばれた証明になるということなのです。また、カルヴァンは時間を無駄にすることが罪であると考えていました。これは、効率的な時間の使い方や労働管理の大切さにつながっていくものでもあります。
ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーは、著書の中でカルヴァンの予定説が勤勉な労働を肯定して経済活動を評価する価値観を形成することでのちの資本主義の発展を支える精神の基礎になったと主張しているのです。(『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』)
宗教改革に対抗する形でローマ教会からはイエズス会が結成されました。創設者はイグナチオ・デ・ロヨラや日本に来たフランシスコ・ザビエルたちです。同時期にヨーロッパではアメリカ大陸への進出が本格化するようになります。コンキスタドール(征服者)のスペイン人はアステカ帝国やインカ帝国を滅ぼしました。スペインやポルトガルを中心とした侵略によって植民地となった新大陸やアジアでイエズス会の宣教師たちは先住民や現地の人々を改宗させる運動を展開したのです。
現在のキリスト教は大きく分けて以上の3つの宗派に分類されています。カトリックはラテン諸国(フランス、イタリア、スペイン、南米など)を中心に、プロテスタントはゲルマン諸国(アメリカ、イギリス、ドイツ、北欧など)を中心に、そして正教会はスラブ諸国(ロシアや東欧など)を中心に信仰されています。
ローマ教皇を選出する選挙「コンクラーベ」が2025年の春に大きな話題となりました。(コンクラーベについてはこちらの動画をご視聴ください)
たしかに、キリスト教の中でカトリックの信徒は最も多く強大な組織が形成されています。しかし、全体から見れば1つの宗派にすぎないということもできるのです。キリスト教と一口に言ってもさまざまな宗派が存在していて政治的な背景にどの宗派が影響を及ぼしているのかを見極めなければならないのです。
4 イスラム教とユースバルジ
イスラム原理主義をキーワードにしたニュースがよく報道されるようになりました。イスラム教はテロ組織と変わらない危険な思想であると思う方も少なくありません。しかし、原理主義やテロ組織が台頭する背景には「ユースバルジ」の問題があるのです。
ユースバルジとは「人口構成において若年層が突出して高い状態」を示す言葉です(超高齢化社会の日本にとってはうらやましい部分でもあるのですが…)。ユースバルジは急激な人口増加によって発生すると考えられています。乳幼児の死亡率が低下して出生率も高い状態が続くと若年層が急増することになります。たしかに、国の活力となるという意味ではポジティブな要因となるのですが、経済システムや労働市場が若年層を吸収できなければ失業率の上昇につながります。安定した職業をもつことができずいずれその不満は爆発することで大きな社会的事件につながってしまうのです。
歴史的にも「義和団事件」「十字軍」「フランス革命」「1960年代の学生運動」などがユースバルジの問題を背景にした事件だと考えられています。この不満の受け皿となっているのが過激なイスラム原理主義組織の存在なのです。イスラム国などのテロ組織は若者たちに居場所や目的を与える存在となっているのです。
ユースバルジの問題を解決するためには経済発展と雇用創出が不可欠だといえます。若者が希望をもって社会や政治に建設的に参加できるチャンスを提供することも必要です。実はイスラム教とはもともと平和と共生を説く宗教なのです。イスラム教に対する正しい理解をするところから始めることが必要だと思います。
イスラム教はムハンマドが布教した唯一神アッラーを信仰する一神教の宗教です。成立は6世紀ですが信者数は約18億人(世界第2位)でさらなる増加が見込まれています。聖典はクルアーンでイスラム教の信徒のことをムスリムとよびます。
イスラム教の聖典はクルアーンとハディースです。クルアーンには「詠唱すべきもの」という意味があります。ムハンマドが神から託された言葉で構成されていて、ムハンマドの死後650年に完成したとされています。ハディースはムハンマドの言行(スンナ)を記録したものです。
ムハンマドは570年頃にアラビア半島の交易都市マッカで生まれたといわれています。商人としての生活を送りながらもヒラー山の洞窟にこもって瞑想するようになりました。40歳のころムハンマドのもとに天使ガブリエルがあらわれて「詠め」と言うのです。ムハンマドは読み書きができませんでしたが心の声を聞きなさい。そして、聞いたことを声に出して歌うように詠みなさいと告げるのです。「詠む」とは詠唱する―つまり声に出して読む、歌うことを意味しています。
ムハンマドは夢中で詠唱するうちに瞑想から目覚めて妻のハディージャに伝えました。最後の預言者ムハンマドと最初の信仰者(ムスリム)が誕生した瞬間です。ムハンマドは普通の生活をしながらクルアーンを伝える日々を送っていました。しかし、当時のアラビア半島では多神教が信仰されていたので迫害されたことから、622年にムハンマドと信者はマッカを離れて西のマディーナで布教を始めました。これがヒジュラ(聖遷)とよばれるイスラム歴の元年になるのです。
マディーナでは信者が増えたことからムハンマドはこの地の支配者―市長であり軍の司令官でありイスラム教の教祖になっていくのです。やがてムハンマドはマッカの軍勢と戦い勝利して630年にマッカに帰還しました。この時カーバ神殿にあった多神教の像は破壊しましたが、カーバ神殿そのものはイスラム教の大切なモスクとして残したのです。マッカはもともと交易都市でありカーバ神殿では定期的に祭典が開かれていました。商人たちはさまざまな思いを詩の形式で詠唱していたといわれています。イスラム教の聖典がクルアーンとなったのはきっとこの行事が影響したと考えられます。そのため、現在でもクルアーンは声に出して詠唱することが原則となっているのです。
イスラム教はユダヤ教やキリスト教と同じくYHWHを唯一神とする一神教です。ただし、イスラム教では唯一神YHWHをアッラーとよんでいます。また、イスラム教にはキリスト教や仏教にみられる聖職者(司祭や僧侶)がいません。そのため寄付をする必要がなく必要な時には誰かが兼業をしながら儀式を進行するのです。
イスラム教の信仰の中心は六信五行(6つのことを信じて5つの行動をすること)です。六信とは神・天使・啓典・預言者・来世・定命を信じることです。神はYHWH(アッラー)であり天使はムハンマドに預言を託したガブリエルのこと、啓展はクルアーンであり預言者はもちろんムハンマドのことです。そして、来世とは天国と地獄の存在を信じることであり定名は予定説のようなもの―人間が救われるのか滅びるのかはあらかじめ神が決めているということです。
五行とは信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼の5つの行動をすることです。信仰告白とは「アッラーが唯一神でありムハンマドが最後の預言者です」と宣言すること、礼拝は1日に5回マッカのカーバ神殿がある方向を向いて礼拝すること、喜捨はお金があるなら貧しい人たちにめぐみなさいという教えのことです。断食(ラマダン)はイスラム歴の9月に日の出から日没まで食事をとらないことであり、巡礼は一生の中で一度はマッカのカーバ神殿を訪れましょうということです。
イスラム教といえば「スンナ派」と「シーア派」という言葉を聞いたことがありますよね。スンナとはクルアーンやハディースに記されているムハンマドの言行のことです。そのため、スンナ派とはムハンマドの言行を大切にしましょうという派閥のことです。いっぽう、シーアとは「アリーの派閥」のことを意味しています。そのためシーア派は日本語だとアリーの派閥派閥になってしまうのでおかしいのですが、いつのまにかこのような言い方が定着してしまったものと思われます。
イスラム教徒の中ではスンナ派が圧倒的に多数(約80~90%)であり、イランやイラクを中心とする一部の地域でシーア派が信仰されています。ムハンマドの死後にイスラム教の指導者は3人の戦友たちに順次継承されていきました。カリフ(ムハンマドの代理)と呼ばれ順調に継承されてイスラム帝国も拡大していきます。
ところが、4代カリフにアリーが選ばれた時に大きな問題が起こってしまったのです。3代カリフのウスマーンが暗殺されたことで真相究明を求める声があがったのです。アリーのカリフ就任に異議を唱えたのがシリア総督の立場だったムアーウィアでした。そしてムアーウィアとの間に大きな争いが起こりひとまず和議が申し入れられたのですが、過激派が「ムアーウィアの反乱もそれを許したアリーも堕落している」と激怒したのです。そして、双方に暗殺者を送るのですがアリーだけが暗殺されてしまうのです。
アリーの長男ハサンはムアーウィアに帝国の統治を任せて自分は身を引くことにしました。そして661年にムアーウィアがシリアのダマスカスに遷都してウマイヤ朝を興すのです。しかし、アリーの次男フサインのもとに東からアリーを信じる使者が訪れて、新しいイスラム帝国をつくるさそいを受けることになるのです。680年にフサインは50名ほどの一族を引き連れてメソポタミアに向かうのですが、ウマイヤ朝から軍隊が派遣されてカルバラーの戦いで命を落としてしまうのです。アリーとフサイン一族はムハンマドの血統を正式に継承しているのだから、ムスリムの宗教的指導者の立場を与えるべきと考える宗派をシーア・アリーというのです。
実はアリーはムハンマドの娘と結婚をしており、次男のフサインはササン朝の王女を妻にしていました。つまり、フサインの子どもはイスラム教の創始者とペルシア王朝の血をひいているのです。ペルシアの人々にとってはとても誇らしいことであるので、アリーの一族の長をイマーム(指導者)とよぶようにしたのです。そのため、ペルシア(イラン)では現在に至るまでシーア派の勢力が優勢であり、宗教と政治の実権をシーア派の最大派閥(十二イマーム派)が握っているのです。
スンナ派とシーア派の争いというのはイスラム教の指導者が多数に選ばれたカリフなのか、フサインの血を引くイマームなのかとする対立のことなのです。(キリスト教のように教義をめぐる悲惨な争いというわけではありません)。ちなみに、カルバラーの戦いがあった日のことをシーア派では「アーシューラ―」といいシーア派の男性は惨殺されたフサインの殉教命日として自分の体をムチなどで叩いて泣き叫びながら行進して祈りを捧げるのです。
現在イランの政治体制は民主主義的な側面をもっているように見ることもできますが、最高指導者といわれる国家の最高権力者は宗教指導者の中から選ばれています。大統領や国会議員は選挙で選出されますが、最高指導者はそれを覆すこともできるのです。現最高指導者アーヤットラー・ハメネイ師は1989年からその地位に君臨しています。1979年のイラン革命によってパフラヴィ―朝による王政が打倒されてからは、イスラム法学者の政治力が強まるいっぽう民衆の評価はあまり高くないようです。欧米諸国との関係悪化による経済制裁などによって経済はボロボロ、宗教規範による日常生活の閉塞感は革命以前より厳しくなったことに原因があるようです。「古代ペルシア帝国の栄光」を回顧して王政を望む声も少なくないようです。
中東地域では冷戦後も欧米諸国やロシアの思惑に振り回されているという側面もあります。1990年の湾岸戦争ではアメリカを中心とする多国籍軍がイラクに侵攻しました。これが、2001年のアメリカ同時多発テロ事件の発生につながっていきます。アメリカはテロとの戦争や大量破壊兵器を理由にアフガニスタンやイラクに侵攻しました。結局、大量破壊兵器は見つからず米軍の撤退によって中東地域はさらに混乱しました。
歴史を振り返ればユダヤ教の章でも解説したサイクス=ピコ協定などによって連合王国とフランスの都合で中東地域が分割されたことがされた過去があります。そして、2011年に始まった「アラブの春」とよばれる民主化運動の時には、またも連合王国とフランスがリビアへの軍事介入を主導したのです。ロシアはシリアのアサド政権を支援して直接的な軍事介入も行っていました。冷戦時代からロシアとシリアは同盟関係にあり中東への影響力を高める狙いがあるのです。(ただし、2024年にサド政権は崩壊しました)。
中東地域の民族的・宗教的な対立や経済・貧困問題には大国の関与が影響しているのです。近年、イスラム教は中東だけではなくアジアで勢力を拡大している傾向にあります。世界最大のムスリム人口の国はインドネシアでほとんどがスンナ派のイスラム教徒です。インド、パキスタン、バングラデシュにも1億人以上のイスラム教徒がいるとされます。インドネシアやマレーシアでは穏健なイスラム教の解釈が主流であるものの、パキスタンやアフガニスタンでは保守的な解釈が強くなっているようです。アジアにおけるイスラム教の影響力を今後も注視する必要があるといえそうです。
5 ヒンドゥー教とインド・パキスタン問題
近年、インドのナレンドラ・モディ首相が率いるインド人民党がヒンドゥー・ナショナリズムを掲げて政権を運営しています。インドの全人口のうち約8割にあたる10億人がヒンドゥー教徒といわれていますが、2019年にイスラム教徒を排除するような市民権法案が可決されて問題となりました。
実はインドにおけるヒンドゥー教とイスラム教の対立には長く複雑な歴史があるのです。紀元前500年頃、インドでは聖典ヴェーダをもとにしたバラモン教が主流でした。バラモン教には社会を4つの階層に分けるカースト制度があったのですが、やがてクシャトリヤ出身のブッダやマハーヴィーラのような思想家が登場するのです。ブッダは仏教、マハーヴィーラはジャイナ教の創始者とされています。
仏教ではカースト制度を否定して個人の悟りを重視する教えを説いて広がっていきます。そのため、バラモン教は土着の信仰と結びつき大衆的なヒンドゥー教へと発展するのです。
「ヒンドゥー教」とはもともと他称として用いられるインド在来の信仰を示す言葉でした。「インダス川の向こう側の人々」を指す地理的な呼称だったのですが、19世紀にヒンドゥーをナショナル・アイデンティティとして自称するようになるのです。
7世紀になるとインドにもイスラム教の影響が広がり始めます。ウマイヤ朝に始まるイスラム王朝には異教徒と協力関係を築く王朝もあれば、寺院を破壊したり略奪したりする王朝も存在しました。そして、13世紀のデリー・スルタン朝がインド仏教の最後の拠点を破壊したことで、インドにおける仏教は事実上なくなりイスラム教とヒンドゥー教の二大勢力が残るのです。
16世紀からインドを支配していたムガル帝国に対して次第に連合王国が影響を強めます。連合王国は得意の分割統治政策(ディバイド&ルール)によって、ヒンドゥー教とイスラム教の対立を利用しながら支配を強化していくのです。つまり、インドにおける両者の対立はこのときの連合王国に原因があるといえます。(エルサレム問題もそうですが、連合王国こそが世界の諸問題の根源ですね…)
第二次大戦後の独立運動では両者の対立はさらに表面化されていくことになりました。マハトマ・ガンディーはヒンドゥー教の非暴力の教えを政治運動に取り入れましたが、インドからパキスタンが分離独立する時には大きな宗教対立が起こって大惨事となります。現在もインドとパキスタンは犬猿の仲でカシミール地方をめぐって紛争が続いています。このような背景を理解した上でモディ首相のナショナリズム政策を見てみると、イスラム教徒への差別的な法律が出されていることからインド社会の分断を招いています。日本ではモディ首相が唱える「世界最大の民主主義国家」という標語をよく報道しますが、このような宗教的な差別に対しても目を向けなければいけないといえるでしょう。
ヒンドゥー教の特徴の1つは多様で身近な神々を崇拝する信仰にあります。特にヴィシュヌ神とシヴァ神はヴェーダのころからブラフマンと合わせて三大神格として崇敬されてきました。ブラフマンは世界の根本原理をあらわす抽象的な神格であったのに対して、ヴィシュヌ神とシヴァ神は日常生活に密接にかかわる存在として崇拝されたのです。日本では七福神のうち大黒天がシヴァ神から派生した神格であると考えられています。
ヒンドゥー教では「アヴァターラ(=化身)」の概念を発展させた点でも重要です。これは神がさまざまな姿になって地上にあらわれるという考え方のことです。そして、さまざまな神々の物語が『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』のような叙事詩となって描かれ親しまれていくのです。このように、ヒンドゥー教は大多数の下層民に対して広がっていくことになりました。簡単でわかりやすいヒンドゥー教に対して仏教の教義はややこしく思われてしまいます。そのため、仏教は都市部の知識人や富豪たちの間で広がっていくことになるのです。しかし、先に述べたように、イスラム王朝によって豪華な仏教の寺院は破壊されていきます。
いっぽう、庶民が集まるようなヒンドゥー教の小さな寺院はそれぞれの地域に少しずつ根差していったからこそ残存することができました。仏教にとってはなんともいえない結末だといえるかもしれませんね。
6 仏教と東南アジア
仏教は発祥地であるインドからはほぼ消滅してしまいましたが、代わりに東南アジアや東アジアに伝播して発展していくことになりました。タイやミャンマーでは仏教が社会に深く根づき僧侶が精神的な支柱になっています。2021年のミャンマー軍事クーデターによってアウン・サン・スー・チー国家顧問とウィン・ミン大統領が拘束された時には、仏教僧侶たちが反軍政デモと平和的な抗議活動を通して人権の尊重を訴えました。
いっぽう、「仏教ナショナリズム」とよばれる思想も存在して、少数民族や他宗教に対する反感の原因にもなっています。特にロヒンギャ(ラカイン州に住むベンガル系イスラム教徒の少数民族)問題に関して、ロヒンギャの人々は、独自の言語や文化を持ち長年ミャンマーで暮らしてきましたが、ミャンマー政府からは「不法移民」と見なされ差別や迫害を受けてきたのです。
7 儒教と中国共産党
中国共産党は中国を統治するために儒教の要素を取り入れていると考えられます。共産主義(マルクス主義)といえば無神論なのですが、中国政府は共産党の管理下において現在5つの宗教―仏教、道教、イスラム教、カトリックとプロテスタントを公式に認めているようです。中国政府に認可を受けていない宗教団体やチベット仏教には規制や弾圧が続いています。
いっぽう、儒教に対しては比較的に寛容な姿勢をとっているようなのです。なぜなら、中国は社会主義なのに市場経済によって世界第2位の経済大国となりましたが、このとき、儒教を宗教というより哲学として扱うことで急速な経済発展にともなう社会の変化や価値観の多様化に対応するために利用したのです。儒教は社会を支配するために都合がよい理論だったのです(徳川家康も朱子学を導入することによって江戸幕府260年の礎に利用しました)。
現代の中国では建前では共産主義ながらも実態は儒教によって支配された社会といえます。
8 世界の宗教勢力図の展望
アメリカの調査機関が示した宗教勢力図における2050年の予測では世界の宗教人口に大きな変化が見込まれています。
キリスト教では2050年までに約29億人に増加すると見込まれていますが世界人口に占める割合は約30%程度と今と変わらない数字となっています。しかし、地理的分布には大きな変化があるとされています。2050年にはサハラ以南のアフリカがキリスト教徒の最大の集中地域となる見込みです。しかし、ヨーロッパのキリスト教徒の割合は約25%から16%まで減少するようです。また、アメリカでは無宗教者や他宗教者の増加によって大きな増加は見込めないようです。このような変化はヨーロッパよりもアフリカの方が重要視される可能性を示唆しています。ローマ教会の枢機卿にはアフリカやラテンアメリカの出身者が増加してきており、映画『コンクラーベ』の中でもアフリカ出身の枢機卿が有力候補になっていました。
イスラム教では2050年までに約28億人に達すると予測されています。世界人口に占める割合も約30%に上昇してキリスト教と同規模になるとされています。地理的分布としてはアジア地域が約53%に減少するものの、アフリカでは16%から24%まで増加するとされているのです。また、ヨーロッパにおいても約6%から10%へとほぼ倍増されるとされています。これには、移民の影響も大きいとされているようです。21世紀に最も勢力を伸ばすとされるイスラム教の動向を注視しなければいけません。
ヒンドゥー教では2050年までに約14億人まで増加すると予測されています。これは世界人口の人口増加と同じペースで進むことから、2050年でも世界人口の約15%を占めるでしょう。ただし、地理的分布としては北米でわずかに増加いていくものと思われます。大手テック企業にインド系が多いことも関係しているのではないでしょうか?
仏教では2050年までにやや増加した後に減少して現在と変わらない水準に戻るでしょう。ただし、世界人口に占める割合は7%から5%に減少するものと思われます。近年、北米やヨーロッパでは瞑想やマインドフルネスが流行していますが、これは必ずしも仏教徒としてのアイデンティティを必要とせずに広がっているようです。そのため、仏教の影響力は統計的な数字よりも大きいのではないかと言われています。
ユダヤ教では2050年までに約1600万人に微増しますが世界人口に占める割合は現在と変わらず0.2%のままだと思われます。イスラエルにおける割合は世界人口の約50%であることは変わらないものの他の地域では減少傾向に進んでいくようです。ユダヤ教の教えでは『旧約聖書』にあるように「産めよ、増やせよ」なのでイスラエルにおける出生率は先進国の中でも例外的な高さを保つとみられます。しかし、ほかの地域ではユダヤ教から無宗教などへの改宗が進んでおり、若年層では「ユダや教徒ではなくユダヤ系」という認識をもつ傾向に向かっているようです。ユダヤ教徒の相対的な減少は各地域におけるユダヤ系組織の活動にも影響がでるかもしれません。
9 まとめ
今回の動画は「世界の成り立ちを理解するための宗教の教養」について解説してきました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだたくさんありますので、ぜひ本書を手に取ってより詳しく学んで頂けたらと思います。
2050年における日本の宗教について述べると仏教徒の人口は全人口の約36%から25%まで減少するものとみられています。そして、無宗教者の割合は増加傾向にあるようです。もともと、日本では特定の宗教に属さないと認識する傾向にあるのですが、それが今後も強まっていくものと思われます。ただし、移民の増加によってこれまで少数だったイスラム教徒などが増加するでしょう。そのため、多様化する社会においては宗教のリテラシーがますます重要になるはずです。このように、それぞれの宗教の共通点と相違点や歴史的な背景を知ることで、これまで知らなかった世界の見方が大きく変わることもあったのではないかと思います。
宗教の知見をもとに「哲学の補助線」を引いて世界を眺めることができるといいですね。

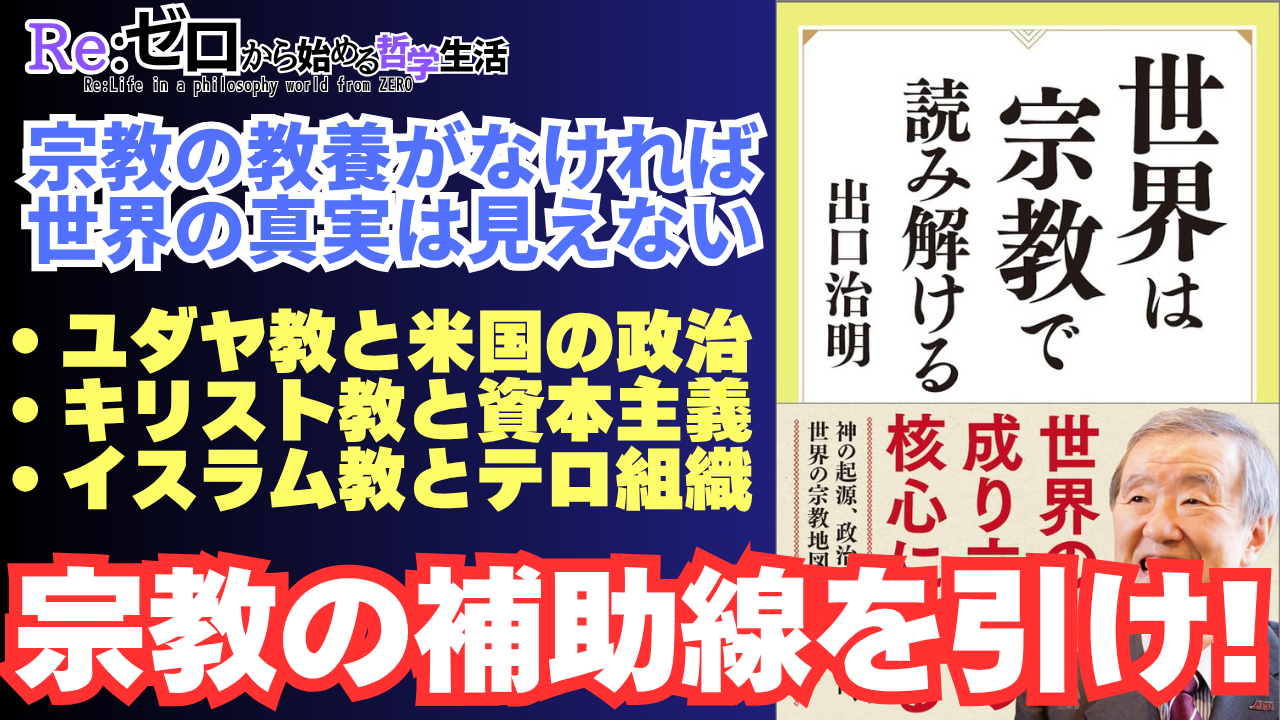
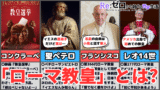
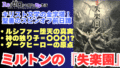

コメント