今回はRe:ゼロから始める哲学生活「やっぱり幸福な人生は無理」について解説します。参考文献は『なぜヒトだけが幸せになれないのか』(著者:小林武彦さん)です。
本書は『生物はなぜ死ぬのか』『なぜヒトだけが老いるのか』と合わせて累計25万部を超える生物学講義のベストセラーシリーズ最新刊です。
すみませんが、前言撤回します!
前回の動画でアリストテレスの哲学から「幸福になる方法」を解説したのですが…やっぱり私たちは幸せになることはできないことがわかってしまいました!なぜヒトだけが幸せになることができないのでしょうか?その理由は生物学において扱われている「遺伝子」にあったのです!
アリストテレスが分類した学問体系の中の1つにも「自然学」がありましたよね。アリストテレスはイルカが哺乳類であることを看破した生物学者でもありました。そこから1800年代くらいまでの生物学は分類学的な仕事が中心だったようです。NHK朝ドラ「らんまん」のモデルとなった牧野富太郎さんのようなイメージです。しかし、その後に遺伝の法則が発見されると遺伝情報の実態が染色体やDNAであること、DNAの二重らせん構造やDNAの配列まで解読されるようになったのです。
そんな生物学の視点から私たちの「幸せ」を定義した時に出てくる答えが「死からの距離が保たれている状態」だと著者の小林さんは述べています。この定義をもとに私たちの幸せを妨げている原因を考えてみたときに見えてきたもの―それこそが「遺伝子」だったのです。
繰り返される戦争や地球規模の気候変動、格差や少子化の問題を抱える日本の社会、新しいテクノロジーとしてのAIの登場など今わたしたちは大きな試練に直面しています。こんな時代だからこそ「ヒトとは何か」「ヒトの幸せとは何か」を考える必要があるのです。
哲学の中でも重要なキーワード「幸福」「生死」「人生」―これらの問題を新たに「生物学」の視点から考えてみたいと思います。後半では本書の内容に「哲学の補助線」を引きながら解説もしているのでご期待ください。内容がわかりやすかったらぜひ高評価&チャンネル登録をよろしくお願いします。
1 ヒトの幸せとは何か?
著者の小林さんはあらゆる生物にとって共通の生物学的な「幸せ」とは何かといえばズバリ生きていること(死からの距離を保つことができている状態)と述べています。生物にとって生きるモチベーションとなっているのは「生存本能」と「生殖本能」であり、これらは、「個」としての生き残りのために「生存本能」があって「種」としての生き残りのために「生殖本能」があると考えることができます。これらがあるから生物は「死からの距離」を保つ(幸せになろう)としているのであり、結果的に個として生き残り子孫を残してきた種だけが現在まで存在しているのです。
たしかに、現代は太古の昔と比べたら獣におそわれることもなく医療も発達しているのですぐに死んでしまうほど危険な世界を生きているわけではありません。しかし、肉体的(物理的)な死とは別に精神的な死との距離はどうでしょうか?明日への希望がもてなかったり埋まらない格差に絶望したりする中で日本では約2万人をこえる人たちが自ら死を選んでいる状況なのです。ヒトは「社会的な動物」であるがゆえに社会の中でしか生きていくことができません。つまり、社会の中で孤立したり孤独になったりすると生きていくことができないのです。(社会的な生き物であるアリやハチは1匹で飼うと数日で死んでしまうそうです)
そもそも、(動物の1つの種としての)ヒトとはどんな生き物なのでしょうか?ヒトは約700万年前にチンパンジーと共通する祖先から分かれたきたといわれています。分かれたきっかけは気候変動などの影響によって森から出る必要があったからです。サバンナに出たことで森の中には存在しなかったさまざまな危険に遭遇したはずです。その過酷な状況を生き延びることができた集団がヒトになったのだといわれています。
このとき「直立二足歩行」と「社会性」が重要な要素となったと考えられます。二足歩行によって両手を自由に使えるようになったり脳の肥大化を可能にしたりしました。これが脳(知能)の発達に大きな影響を与えたことで社会性が発達することになるのです。こうして生き残った種族が私たちの直系の祖先になる「ホモ・サピエンス」です。
約20万年前にアフリカで誕生して装飾品をつくったり絵を描いたり何でもしていました。そして、約4万年前に日本列島に到達して狩猟採集の生活を送っていたのですが、約1万3000年前の縄文時代に農耕が始まり、弥生時代には農耕定住の生活を送りました。
その後、ヒトは進化の過程で技術的には石器から土器、火の利用、狩猟具や農機具、移動のための乗り物、医薬品、精密機器、通信機器、そして人工知能を開発するのです。また、文化的には言語やコミュニティの形成、音楽や絵画などの芸術、食の多様化や国家の形成などを次々に成し遂げていくのです。これらの技術や文化のほとんどの部分は、700万年の中のわずか1万年―定住農耕の生活を営むようになってからの出来事であるところがポイントです。つまり、ヒトとは定住前の集団で移動する身軽な「冒険家」から、定住後の家や都市を作りそこにものを貯めこむ「建築家」へと変化した生き物なのです。
さて、このような進化をしてきたヒトですが、身体的には圧倒的に不利な生き物です。走るのも泳ぐのも速くはなくて、病気への耐性も高くはありません。しかし、だからこそ、集団の結束力やテクノロジーを駆使することで生き残ってきました。ヒトは腕力よりも集団で協力する協調性やものを作る技術力によって生存してきたのです。このような社会性が生存のために重要な要素であるため、「協力」することができなければ(仲間はずれにされて)生きていくことはできません。そのため、「正義」「公平」「利他」などの精神が必要不可欠となっていったのです。正義がない人(卑怯なことをする)や公平でない人(ずるばかりする)、自分勝手で集団に貢献しない人は孤立して仲間外れになっていったことでしょう。ヒトは進化の過程で協力するために必要な力を遺伝子に刻み込んでいったのです(同時に不正義や不公平を嫌う感情も遺伝子に刻まれていきました)。
現代の哲学でも重要なキーワードになっているこれらの概念や価値観は結果的に生きる残るために必要な要素だった―生物学的にこのような価値観をもつ者だけが生き残ることができたといえるのです。さらに、ヒトは集団の中での自分の評価を気にするようにもなっていきます。集団への貢献度が高ければ当然その分け前は高くなるものであり、現代でも基本的には貢献度が高い人の方が分け前(給料)は高くなるはずですよね。ヒトにとって集団の中での評価の高まりは、その集団から追い出されにくくなることで死からの距離を遠ざけること(=幸せ)につながったと考えられるのです。つまり、ヒトにある大きな特徴でもある比べる力(よりよいものを志向する気持ち)は幸せになるために遺伝子に刻まれた重要な手段だったといえるのです。ところが、この「比べる力」こそが現代の私たちを幸せから遠ざける要因でもあるのです。
2 なぜヒトは幸せになれないのか?
2-1 遺伝子のミスマッチ
ヒトは700万年かけて小さな集団の中で助け合うことで進化してきました。現代の私たちもこのような進化の過程で淘汰されてきた遺伝子をもって生きているのです。しかし、今から約1万年前に私たちの世界に「格差」が誕生しました。私たちの祖先は700万年のうち699万年は狩猟採集の移動生活を送っていました。しかし、約1万年前に狩猟採集から農耕牧畜の定住生活へ大きく変化していくのです。
この生活様式の変革によって財産を所有することができるようになりました。それまでは、移動をするので財産をもつ必要がなく集団で全てを消費しておしまいでした。そのため、この時期の遺跡を調査しても大きな争いの形跡はほとんどないようなのです。しかし、定住生活が始まったことで「格差」が生まれお互いに争いが始まっていくのです。
ここに、私たちが幸せになれない原因があると考えられるのです。著者の小林さんはこれをYKK(弥生格差革命)とよんでいます…。私たちは700万年かけて幸せな生活を送る行動パターンを遺伝子に刻んできました。小さな集団の中で協力することで生き延びる(=幸せになる)ことができたのです。ところが、わずか1万年前に生まれた格差社会にはこれをうまく適応できないのです。遺伝子が新しい環境に適応していくためには数万年単位の時間がかかるといわれており、狩猟採集に適応した遺伝子で農耕定住の格差社会に適応することがそもそも難しいのです。
たとえば、私たちは誰でも「自慢」をしたい気持ちを遺伝子的にもっています。なぜなら、狩猟採集の時代に大きな獲物をしとめたことを自慢することは、集団の中で喜びを分かち合うための感情につながるので遺伝子に残っていきました。獲物をとれば集団から承認をえることができると同時に集団全体も食料をえられます。この時代の自慢は集団の中で相互に幸せを感じ合うための大切な感情だったのです。
しかし、現代社会で自慢をするとどうなるか…想像がつきますよね?その原因は自慢をした後に集団で喜びを共有するところが抜け落ちているからなのです。なぜなら、定住農耕の時代にはコミュニティが巨大化・希薄化していったことで、集団のための貢献度によって承認や分け前が決まるわけではなくなってしまったからです。
現代でも社会の維持に必要なエッセンシャルワーカーの収入は決して高いとはいえません。いっぽう、世の中には何らかの偶然や幸運によって裕福になっている人が多くいます。前者は社会に貢献しているのに不遇な状況であることに不幸を感じていますし、後者は承認や尊敬されることもなく嫉妬や強奪の対象となることに不幸を感じています。
私たちは狩猟採集の時代にはコミュニティの中でうまくやれば「幸せ」になれたのに、定住農耕の時代に財産(と格差)が生まれたことで「幸せ」になりにくくなりました。700万年かけて刻んできた遺伝子と現代社会の生活様式がミスマッチを起こしているから、私たちはこの世界でなかなか幸せになることができないのです。
2-2 現代社会の生活様式とテクノロジーの功罪
都市部の生活では遺伝子とのミスマッチがより顕著にあらわれることになるでしょう。集団の希薄化は人間関係の希薄化(孤立)につながり、集団への貢献度が正しく評価されない(孤独な)生活は遺伝子的に幸せとはいえません。狩猟採集(歩くこと)に適している肉体的にも座りっぱなしの生活は大きな負荷となります。その結果、腰痛や消化不良、視力や筋力の低下などさまざまな影響が肉体に生じています。
さらに、死に方にも変化が生じているそうです。狩猟採集の時代は動き回るので循環器系のトラブルでぽっくりいくことがよくありました。しかし、現代社会は動かないため心臓への負担が減ったことでそれ以外の臓器の衰え―いわゆる「病気」によって死ぬ割合が多くなってきているのです。現代社会には700万年かけて遺伝子が遠ざけてきた2つの天敵―「孤独」と「病気」が蔓延しているといえるのです。
また、私たちに備わるほかの動物がもたない能力の1つに「比べる」というものがあります。「よりおいしいものを食べたい」「よりよいものを作りたい」この気持ちが強いからこそ私たちはここまで進化することができたのです。狩猟採集の時代では、集団内の自分の立ち位置を他のメンバーと比べる必要がありました。自分が集団にどれだけ貢献しているのかを他のメンバーと比べることができなければ、気づいた時には集団から外されてしまう可能性があるからです。
ところが、現代社会ではこれが負の側面につながってしまうのです。SNSではそれが顕著になっているような気がしますよね。目の届く小さな集団を形成することで適応してきたのに、見えない巨大なネット世界の中で孤立を感じる現代社会に適応するのは相当困難なのです。
さらに、「テクノロジー」もまた同じように考えることができます。よりよいものを作りたいという創造性があるからこそヒトの社会は発展してきました。新しいテクノロジーを開発した人はその使い方を間違えることはないから問題ないのです。(トンカチを発明した人は必ずクギを打つことに使うはずなので)。しかし、トンカチだけを手にした人はそれをクギのためだけに使うとは限りません。よりよい方法に使うこともありますが、最悪の使い方をすることもきっとあるでしょう。(第二次世界大戦で使用されたあの兵器もまさに同じように考えることができます…)
現代のインターネットも私たちの生活を大きく便利にしたテクノロジーであるいっぽう、コミュニティの希薄化・巨大化をもたらす要因にもなってしまっています。現代社会はお互いの顔を見ることのできない巨大なインターネット世界の中で大人も子どもも朝から晩まで座り続ける生活が肉体的・精神的なストレスを与え、仮想空間の中で疑似承認をえることでしか満足できない社会となっているのです。
さいごに、AIについても考えなければいけないでしょう。著者の小林さんは人類の滅亡を防ぐ方法は2つあると言っています。1つは昔のような暮らしにもどること、もう1つは科学技術に頼ることだそうです。しかし、前者で80億人の人口を支えることはほぼ不可能でしょう。そのため、AIなどの科学技術を上手く使って幸せに暮らせる未来を創る必要があります。ただし、どこまでいってもAIはアルゴリズムであり道具でしかありません。AIに何かを聞いて「よくわからないけどAIはこう言っているよ」では無責任ですよね。
700万年前に私たちの祖先は森からサバンナに出てその環境に適応していきました。そして、サバンナから平野へ移動した後にいよいよ現代の私たちは、この現実の世界から仮想現実のネット世界へ出ていこうとしているのかもしれません。車がなかった時代と比べて現代の私たちは歩く機能を失っていると言われています。AIがなかった時代と比べて未来の私たちは考える機能を失っているのかもしれません。「考える」ことで環境に適応して地球の覇者にまだ昇りつめたヒトが、「考える」ことを放棄してしまえばいつか淘汰される運命を避けることはできないのです。
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』byポール・ゴーギャン
「世界はどうしてできたのか?」「人間はどこから来てどこへ行くのか?」今こそ哲学の補助線を引いて真剣に「考え」なければいけないのではないでしょうか?
3 ヒトは幸せになれるのか?
「遺伝子と環境の不適合」こそが私たちを幸せから遠ざける大きな原因となっていました。狩猟採集の時代であれば、チャンスは平等にあって貢献度が正しく評価されていました。不正などの悪事は憎まれ喜びや悲しみもみんなで共有する信頼できるコミュニティ―そこで安心して子育てや老後を送れるように遺伝子はカスタマイズされてきたのです。
しかし、農耕定住によって格差が生じたことで私たちは不公平感に苛まれ、不特定多数の顔が見えない世間からの評価や孤独と不安におびえながら暮らしています。遺伝子に刻まれた行動原理や思考パターンは数万年かけなければ変わらないため、やはり遺伝子にあった(集団の中で助け合う)生活が幸せになる絶対条件なのです。
もしかしたら、いま求められているのは1人1人が生き生きとすることのできる狩猟採集の時代のような小さなコミュニティを形成することなのかもしれません。そのためには、テクノロジーを上手く利用することが必要になるでしょう。テクノロジーを上手く利用することができれば、遺伝子にマッチした現代社会を再構築することができるかもしれません。
50年周期で訪れているという生命科学の大革命において、次に起こることは「脳の情報処理に関わる機能の解明」ではないかと考えられています。情報過多な現代社会において膨大な情報をヒトの脳が理解できるよう簡略化する理論―難しいことを簡単に説明してくれる親切なAIの開発が期待されているのです。
また、本書では東南アジアの先住民であるプナン族の生活についても述べられています。プナン族の生活を見ていて一番「幸せ」だと思えることは格差がないことだそうです。限られた天然資源を誰かが独占すればコミュニティを維持することはできません。そのため、生活の不安や将来の心配、孤独や疑似承認などの負の要素は1つもないのです。もしかしたら、マルクスはこのような社会を夢見て共産主義を唱えたのかもしれませんね(共産主義などのいろいろな主義について解説しているこちらの動画もご覧ください)。
歴史を振り返れば完全な共産主義を実現することは難しいのかもしれませんが、ある程度は共同所有をするという「公共の精神」を取り戻すことは必要だといえそうです。そのためには、地域のコミュニティなどに所属する方がよいと思えることが大切です。格差が大きすぎると裕福な人は個人で完結させることができるので共有を拒みます。
とはいえ、格差が0でも成長を目指す意欲も失い公共財もなくなってしまうでしょう。このような個人主義に偏りすぎないで発展することのできるバランス感覚は、教育の力によって醸成されるところが大きいといえるでしょう。ヒトも生態系の一部としてあらゆる生き物たちとつながっているのです。公共的な精神を子どもの頃から身につけようとすること、地球という限られた環境の中で1人勝ちをしようとしないこと、隣人が不幸なのに自分だけが幸せになることはできないことを再認識する必要があります。
格差を小さくすることはなかなか難しいかもしれませんが、公共のために働く方々(エッセンシャルワーカー)への敬意をもつことはできると思います。著者はこのような共同体としての公共の精神さえもつことができれば、コミュニティの中で自然に助け合いの輪を広げられるのではないかと述べています。まさに、自分が受けた恩恵を次の人に返す「恩送り」の精神を取り戻すのです(恩送りを贈与という概念で解説しているこちらの動画もぜひご視聴ください)
また、科学技術の進歩によってみんなが恩恵を受けることができるのであれば、ある程度の経済的な格差は許容されるべきであると著者は述べています。ただし、知識や技術などを誰かが独占・固定化することは避けなければいけません。このような考え方はジョン・ロールズの「正義論」にも出てくるものでした。ロールズは「無知のヴェール」という思考実験において2つの原理を導き出しました。第一原理「平等な自由と権利」―これは私たちが他の人の自由を奪わない範囲で、基本的な自由を平等に持つべきであるという考え方です。第二原理「機械平等・格差」―これは公正な機会均等という条件の下で最も不利な人々の利益が最大化される場合において不平等は認められるという考え方です。つまり自分が社会的な弱者である可能性もあるため弱肉強食でもいいとは言えませんが、最低限の生活は保証されるべきであると考える以上それを恵まれた人(格差や不平等)に頼ることは問題ないということになるのです(正義について考えるのにぴったりのこちらの動画もぜひご視聴ください)。
著者は狩猟採集の時代の2つの「幸せ」のエッセンスを再現する提案を行っています。1つは安心して暮らせる新しいコミュニティの構築、もう1つは格差なく誰もがゼロベースから成長できる環境の2つです。本書では最後にある架空の事例をもとにその可能性について述べられています。ぜひ、ご自身でその内容を読んで「幸せ」の形をあらためて考えてみてください。
4 まとめ
今回はRe:ゼロから始める哲学生活「やっぱり幸福な人生は無理」について解説しました。動画の中では解説できなかったこともたくさんありますので、ぜひ本書を手に取ってさらに詳しく学んでみてください。
「テクノロジー」を創造しようとする衝動は遺伝子に刻まれているので変えられません。しかし、「テクノロジー」の正しい使い方は遺伝子に刻まれているわけではないのです。トンカチ程度なら人類を滅亡させるほどの脅威はないかもしれませんが、インターネットやAIは真剣に考えないと本当に人類を滅ぼす可能性をもっています。そんな時代だからこそテクノロジーを上手に使うための「倫理」が求められているのです。
哲学者アリストテレスはあらゆる学問を体系化したことから「万学の祖」といわれています。「論理学」「倫理学」「自然学」「形而上学」などあらゆることに関心をもっていたのです。ところが、アリストテレスの哲学は何かといわれてもそれにあたるものはないのです。それはアリストテレスにとって哲学が「知的探求の過程と結果そのもの」だったからです。
「哲学は何の役にも立たない」「哲学は難しそうで興味がもてない」
そんなふうに思われる方が多いのかもしれませんが、哲学は本書のように「そもそも」を真剣に考えること自体を楽しむものなのです。アリストテレスは学園リュケイオンを開設して歩廊を散歩しながら講義していたことからアリストテレスの学派はペリパトス派(逍遥学派)と呼ばれていたそうです。ぜひ、あなただけのお気に入りの歩廊(ペリパトス)を散歩しながら、「哲学の補助線」を引くことで新しい世界の扉を開いてみてください。
Every wall is a door, and you have the key.
(全ての壁は扉であり、そのカギはあなたの手の中にある)ラルフ・ワルド・エマーソン

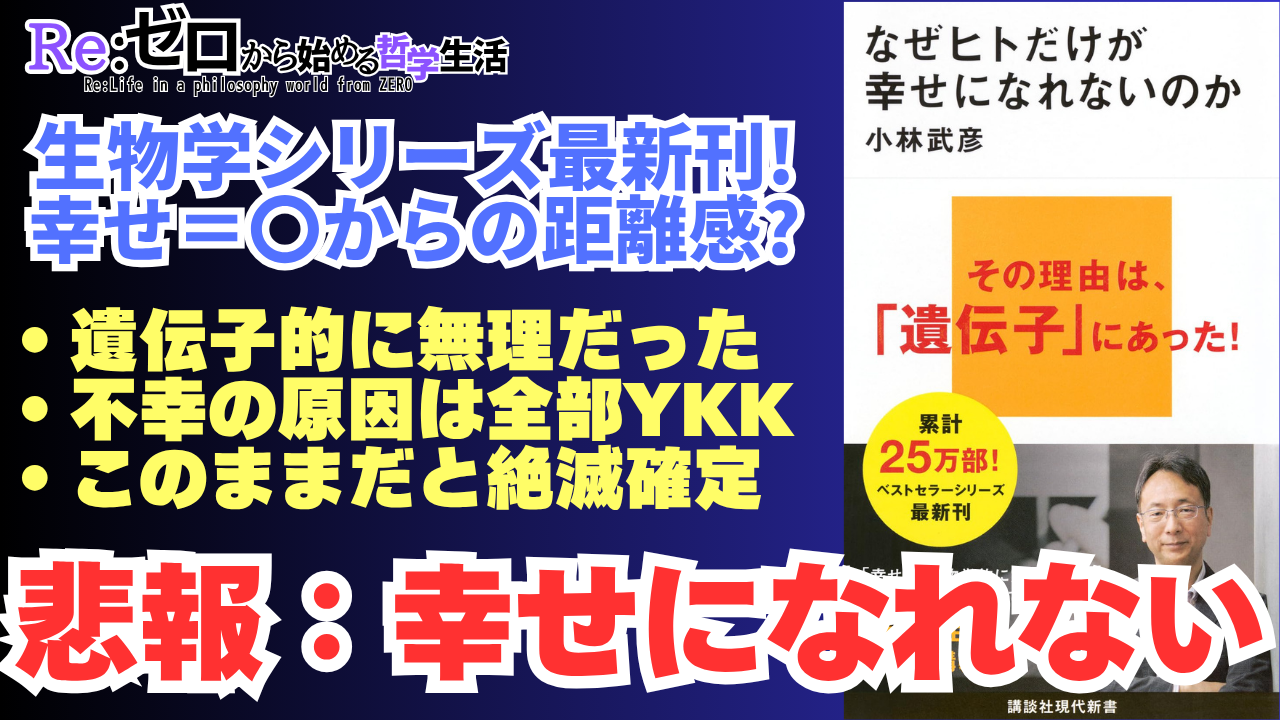
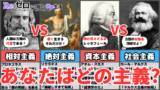

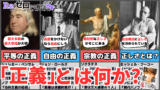

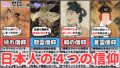
コメント