今回は「人生のモヤモヤを全て解決する禅の教え」について解説します。参考文献は『使える禅-暮らしに役立つ基礎知識-』(著者:枡野俊明さん)です。
近年シリコンバレーやウォールストリートでマインドフルネスが注目されています。Googleではマインドフルネスの講習を毎年数千人が受講していると話題にもなりました。なぜ、マインドフルネスがこんなにも流行となっているのでしょうか?
マインドフルネスとは「今この瞬間の体験に意識を向け、評価や判断をせずありのままを受け入れる心の状態」のことです。瞑想などを通して集中力や内省力を高めストレスを軽減する効果が期待されています。
このマインドフルネスは、もともと東洋哲学である仏教の用語を翻訳したものであり、道元を祖とする曹洞宗の基本理念を採用した精神療法の1つが端緒となっているのです。曹洞宗は達磨大師を開祖とする禅宗の一派であり、道元が日本に伝えたひたすらに坐禅をすることで悟りの境地に至ることを目指す宗派です。
AppleのCEOだったスティーブ・ジョブズは禅に傾倒していたことでも有名です。 そんな禅は日本で鎌倉時代に伝わりそれから間もなく戦乱の世に広まっていくのですが、「今この瞬間こそが大切」と説くその教えは戦う武士たちに広く受け入れられました。禅には鎌倉幕府の北条時頼・時宗の親子、室町幕府の足利尊氏、戦国時代の武田信玄、そして江戸時代の剣豪である柳生宗矩や宮本武蔵など名だたる偉人が師事してきたのです。
現代では科学の発達によって脳波やホルモン分泌の測定が可能になったことから医学的にも禅の有効性が実証され始めてきているようなのです。禅から宗教色を除いた精神療法的な部分がマインドフルネスとして流行しているのです。
そこで、今回は「禅とは何か?」「禅の思想とは?」について詳しく解説していきます。後半では私たちが日常の中でそれと知らずに使っている禅語についても紹介しています。禅を知ることができれば、きっとあらゆる悩みから解放されて、今に集中して最高のパフォーマンスを発揮することができるようになることでしょう。内容がわかりやすかったと感じた時にはぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 禅とは何か?
禅はインドの仏教に中国の思想が加わって誕生した「禅宗」における独自の思想のことです。仏教はインドで釈迦によって始まりその教えは弟子へと継承されていきました。その28代目にあたる達磨大師が6世紀に中国へ渡って教えを広めたことから、両国の思想が反映された「禅宗」が誕生したのです。達磨大師は仏教の理論より坐禅の実践を重視したことから「禅宗」の開祖とされるのです。
達磨大師はもともと南インドの香至国の王子として生まれたといわれています。そこで見出されて修業に励んだ後に中国にわたることになるのですが、このときの中国の皇帝(武帝)との禅問答はあまりに有名な爆笑案件です。
皇帝「私は寺をいっぱい建てたから御利益いっぱいあるよね?」
達磨「ない!」
皇帝「仏教でいちばん大切なことって何ですか?」
達磨「そんなものは、ない!」
皇帝「それではあなたは誰なのですか?」
達磨「知らん!」
なんと達磨大師は反抗期の中学生が親に言うようなセリフを皇帝にしてしまったのです。せっかく仏教を中国に広める大チャンスだったのにそれを自らぶち壊すまさに暴挙…そのまま山奥の少林寺にこもって壁に向かって9年間も坐禅を続けたとされています。
その後、禅宗の教えは弟子たちに引き継がれていくのですが、五祖(弘忍)の時代に神秀と慧能という2人の逸材が登場しました。そして、神秀による北宗禅と慧能による南宗禅に分かれていきます。しかし、北宗禅は衰えていったことで南宗禅が残り現在まで続いていくことになるのです。
唐の時代にはさらに二系統に分かれていき、最終的に五家七宗に分かれました。このうち、鎌倉時代に栄西が臨済宗を、道元が曹洞宗を日本に伝えました。栄西は北条政子に迎えられて寿福寺を開山したり京都に建仁寺を開いたりしました。その後も武家政権と強く結びつくことで主な寺院は官寺となっていき、幕府や朝廷が定めた寺院の格付けである「五山十刹」制度によって選定されていきました。主な寺院には京都五山の南禅寺や建仁寺、鎌倉五山の建長寺や円覚寺などがあります。
「臨済宗」では、坐禅の最中に師が公案(禅問答となる問題)を出す看話禅が有名です。アニメ「一休さん」のモデルとなったのも臨済宗の一休宗純という型破りな僧侶でした。
いっぽう、道元は権力と結びついたりほかの宗派と兼ねたりすることを強く戒めました。そして、深山幽谷の地(福井県)に永平寺を開いて正しい教えを伝授しようとしたのです。「曹洞宗」では、厳しい修業を行いひたすら壁に向かって坐禅をすることを重視します。坐禅には黙照禅(坐ることそのものに全身全霊を傾けること)と只管打坐(悟りを求めて坐るのではなく坐る姿が仏の姿であると捉える)の2つがあります。
江戸時代になると、明の時代の臨済宗として黄檗宗が隠元隆琦によって伝えられました。京都の宇治に満福寺を開いて明朝様式の建築や煎茶などの文化が大きな影響を与えました。こうして、現在の日本には「臨済宗」「曹洞宗」「黄檗宗」の3つが残っているのです。
2 禅の思想
禅の思想の最大の特徴は「禅即行動」―つまり、身体での実践を重視しているということです。学問のように頭で考えるのではなく、身体を通して自分で体得することが大切なのです。
禅では、誰でも仏になる資質(仏性)をもっていると考えられています。仏性とは一点の曇りもない本来の自己のことであり、厳しい修業を重ねて煩悩や執着などから解放されることで到達できる境地のことです。
達磨の没後、宋の時代になって禅の思想を簡潔に表現したものが「達磨の四聖句」―「不立文字」「教外別伝」「直指人心」「見性成仏」です。「不立文字」とは大切な真理は言葉や文字で伝えることはできないので、自らの体験を重視してひたすら坐禅を実践する必要があるということです。「教外別伝」とは経典ではなく体験を土台に師から弟子へ直接に伝えるということです。「直指人心」とは自己を見つめて仏性に気づくということであり、「見性成仏」とはその仏性を自覚して悟りを開くということです。
そのため、禅では身体に意識を向けるところから始まります。修業の中心は「坐禅」であり、その基本は「調身」「調息」「調心」とされています。姿勢を整えることで呼吸が深まり、五感が研ぎ澄まされていくようになるのです。その結果、煩悩や執着から解放されて心が落ち着くというわけです。
坐禅の時には「今この瞬間」「自分のこと」にだけ集中することが大切です。他人の言動や過去の後悔、不確定な未来に対する不安などに振り回されてはいけません。「主人公」という言葉はもともと禅語の1つなのですが、これは「何にもとらわれない自由な自分」という意味なのです。さまざまなストレスを抱える現代人にとって「主人公」として自分を見失うことなく、真っ直ぐに生きていくためのヒントが禅にはたくさん詰まっています。ふとした瞬間に坐禅をしたり禅の思想を凝縮した言葉(禅語)を眺めたりしてみてください。
3 禅の修行
釈迦は菩提樹の下で7日間の坐禅修業によって悟りに至ったといわれています。また、達磨は少林寺で壁に向かって9年間も座り続けていたとされています。禅の修行の第一歩は、まず坐禅をすることから始まります。
坐禅の基本はやはり「調身」「調息」「調心」の3つです。体の軸を立てて背筋を伸ばすことで身体の軸を意識するようにしましょう。眼は半眼で約1m先の前方を見ながら視線を床に落とします。足を反対側の太ももにのせて首や肩の力をぬいてゆったりと坐るようにしましょう。組んだ足の上で手のひらを重ねて親指をつけて手を組むようにします。臍下の丹田に意識を集中して息を深く吐き切り鼻からゆっくり息を吸うようにするのです。
坐禅の最中には思考しないことを心がけましょう。さまざまな煩悩が浮かんでくることは仕方ないのですが、次から次へと流していくことが大切になります。やがて、何も考えない心地よい時間が流れていることに気づくようになっていきます。
坐禅の流れは、まず坐る場所に合掌をしてから足を組むようにします。左右にゆれながらバランスをとってお尻と両膝で身体を支えて上体を伸ばしましょう。手を組んだら半眼になって呼吸を整えていきます。鼻呼吸をゆっくり続けながら無心で坐ることを心がけるようにしましょう。身体を整えることで心も同時に整っていくことを体験することができるはずです。さまざまなストレスや不安要素など(実体がないもの)があったとしても、坐禅によってそれらを流してしまうことができれば執着からも解放されるのです。
また、禅では坐禅だけでなく日常のすべてが修業であるという考え方をしています。写経や読経はもちろん、食事や掃除、移動までもが悟りへ通じる修業なのです。「一に掃除、二に信心」という言葉があるように、掃除は信心を上回るほど重要な修業だと考えられています。
また、動物性食品を使わないいわゆる精進料理を食べることも大切な修業の1つです。食材の本来の味を最大限に引き出して旬の野菜などでていねいに作られているため、高たんぱく低カロリーでありながら味わい深く消化もよい健康食品となっています。精進料理の基本的な考え方は道元が老僧から聞いた食の修業に関する典座(食事係)には料理の際に「喜心」「老心」「大心」の3つの心が大切とされています。
「喜心」とは料理をもてなす喜びや感謝をすること
「老心」とは相手を思って心をこめること
「大心」とは仏の大きな心をもって集中することという意味です
食事も修業である典座がいかに重要な役割なのかがわかる教えだといえます。禅寺では食事も決まった作法があって「五観の偈」という経文を唱えてから頂くのです。一には、功の多少を計り彼の来処を量る(この食事ができるまでの多くの人々のはたらきに感謝します)。二には、己が徳行の全欠を忖って供に応ず(自分がこの尊い食事をいただくに値するのかを省みます)。三には、心を防ぎ過を離るることは貪等を宗とす(心を正しく保ち過ちを持たないためにいただきます)。四には、正に良薬を事とするは形枯を療ぜんが為なり(良薬としてこの食事を健康な身心を養うためにいただきます)。五には、成道の為の故に今此の食を受く(仏道修行を実践するために有り難くこの食事をいただきます)。みなさんもぜひ、「五観の偈」を唱えてから食事をいただいてみてください。
4 禅の言葉
禅語とは禅宗の僧侶たちによって語られてきた言葉であり、悟りの境地を表した言葉や悟りに至るための心構えなどが短い言葉に凝縮されています。誰もが聞いたことがあるあの言葉もそのルーツが禅語にあったと知ったら驚くでしょう。
「禅即行動」
禅では何よりも体験すること、実践することを重視しています。やらない理由やできない言い訳をすることには何の意味もありません。たとえ失敗したり間違えたりしたとしても、それが大事な経験となって次の行動につながっていきます。まずは行動することが大切であり、行動が習慣となっていくのです(と、アリストテレスも言っていましたよね?)。
「淡交」
荘子の言葉である「君子の交わりは淡きこと水の如し」が由来となった言葉です。徳が高い人物は水のようにさらっと付き合うという意味であり、相手との適度な距離感をもつことの大切さを教えてくれます。
「明珠在掌」
明珠とは明るく輝く宝石のことであり、在掌とは手の中にあるという意味です。誰もが周りのことばかり気にしたり比べたりしてしまうものですが、自分には人にはない貴重な魅力がすでにあることを気づかせてくれる言葉です。
「天上天下唯我独尊」
釈迦が生まれてすぐに発したといわれている言葉です。天上天下とは広い宇宙のことであり、唯我独尊とは私たち1人1人の尊い命のことを意味しています。自己中心的な王様というイメージで誤解されているのですが、この広い宇宙に私たち1人1人が尊い命をもって生まれてきたという意味なのです。誰もが使命を果たすべく生まれてきて、誰もが唯一無二の役割をもっているのです。
「以心伝心」
心を以て心に伝える、言葉や文字を使わず心と心とを通じ合わせるという意味です。禅では「教外別伝」の通り師が弟子の心に直接伝えるようにしていきます。相手の表面的なことに捉われずお互いに理解しようとする気持ちや、相手への尊敬の念があってこそ心と心を通わせることができるようになるでしょう。
「一期一会」
「一期」とは人間の一生であり、「一会」とはたった1度だけの出会いを示しています。もともとは茶席での心得を表す言葉だったのですが、現代ではより広い意味で「一生にたった一度の大切な出会い」のように使われています。たとえ茶会で何度でもお茶を点てることがあったとしても、今日という日の茶会はたった1度きりなのだから心を尽くしてもてなすという意味です。
「滅却心頭火自涼」
織田信長によって武田家が滅ぼされたときに武田信玄が学んだ快川禅師の恵林寺も焼き討ちにされるのですが、その禅師が火に焼かれながら最後に伝えた言葉として広まった有名な言葉です。「心頭滅却」とは、こだわりや執着心に振り回されない状態を意味します。この境地に至れば雑音は消え炎の熱すらもありのままに受け入れられるということです。どんなに厳しい境地に陥ったとしても無心になって立ち向かうことを教えてくれます。
「単刀直入」
禅ではものごとの核心(本質)をしっかり捉えることを重視しています。単刀とは一振りの刀のことであり、直入はまっすぐに切り込むことを意味しています。あれこれ考えて本題を避けたり回りくどい言い方ではぐらかしたりするのではなく、ズバッと核心を突くように伝えることが大切だということです。
「行雲流水」
空に浮かぶ雲は気ままに行き、水は捉われることも留まることもなく流れるという意味。修業僧を「雲水」とよぶのは、自由な心でいなければならないというこの言葉が語源です。わたしたちも、何かに執着したりとどまったりすることなく、自由気ままにのびのびと進み続けていくことの大切さを教えてくれる言葉です。
「知足安分」
知足とは足るを知るということ、安分とは自分が置かれた境遇に満足するということです。富や名声などあれこれほしいと高望みばかりしていると心は落ち着きません。欲望に限りはなく常に満たされない心で不安にいるのではなく、自分の境遇を自分に見合ったものであると捉えれば穏やかな心でいることができるのです。
「日々是好日」
中国(唐末期)の禅師の言葉で「毎日毎日が好い日」という意味です。生きていれば人間関係や仕事のことで悩んだり落ち込んだりすることがあると思います。しかし、そのような気持ちは損得勘定や優劣というものさしに執着した生き方なのです。そのような執着を捨ててありのままにその日にしか経験できなかったこととして、毎日を積極的に生き切ることが大切だと考えましょう。どんな日であっても、毎日を「好日」にすることができるかどうかはあなた次第です。
まとめ
今回は「すべてのモヤモヤを解決する禅の教え」を解説しました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだたくさんありますので、ぜひ本書を手に取ってより詳しく学んで頂けたらと思います。
西洋哲学はとても難解ではあるものの、理解ができないものではありません。しかし、東洋哲学は、そもそも理解をすることが不可能なものなのです。なぜなら、西洋哲学が真理を目指して「階段」を上るように少しずつ発展しくのに対して、東洋哲学はいきなり「真理に到達した(悟った)」というところから始まります!そして、後世の人はそれをさまざまな解釈で伝えていくという「ピラミッド」型なのです。禅もその1つであり実践することでしか真理(悟り)に到達することはできないのです。
曹洞宗を伝えた道元は修業時代に師が「心身脱落」と一喝するのを見て悟ったそうです。身も心もあらゆる執着から解き放たれすべてを捨て去った先にこそ真理があったのです。だからこそ「只管打坐」―ひたすらに坐禅に取り組むことが悟りに至る道だと考えたのです。
仕事のストレスや人間関係の不安など…そんなものはそもそも実体のないものです。禅を通して「今この瞬間」「自分がやるべきこと」に集中するようにしてみましょう。まずは「調身」「調息」「調心」から始めてみることです。東洋哲学に興味をもった方はぜひこちらの動画もご視聴ください。達磨禅師についても相当おもしろい紹介のされ方をしているのでおすすめです。

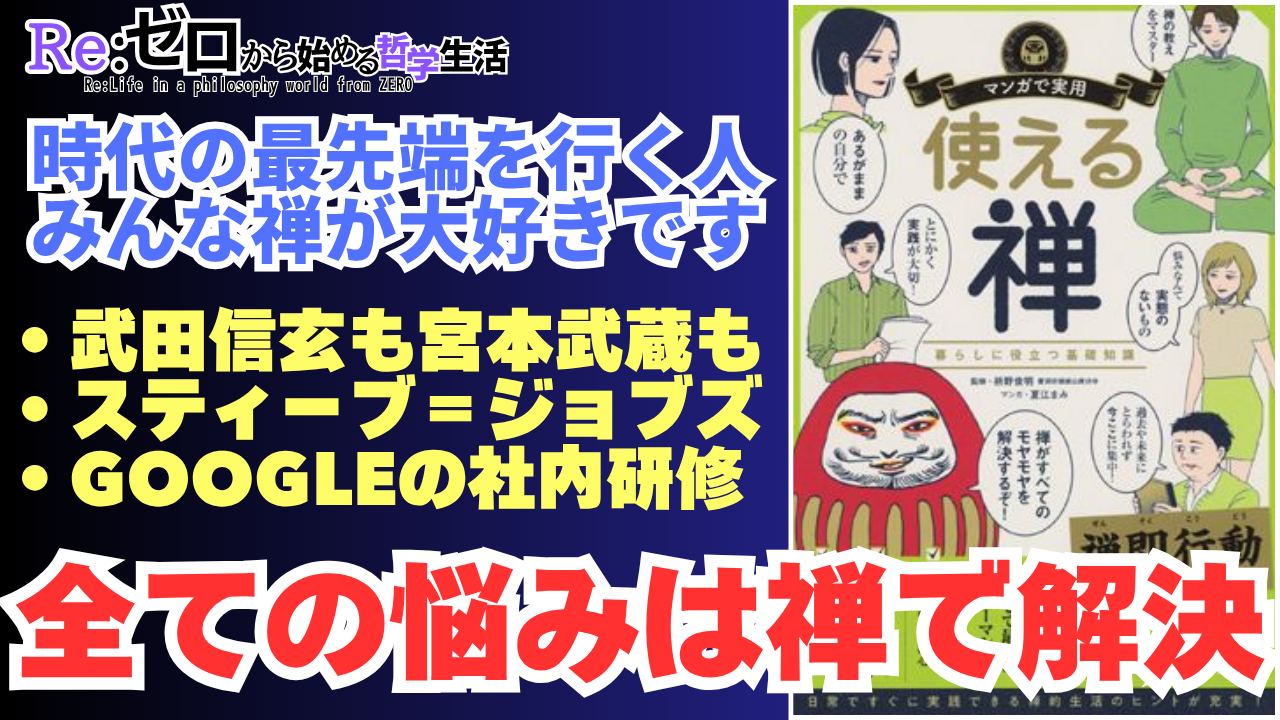
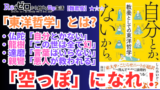
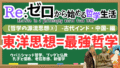
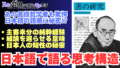
コメント