今回は「世界史の諸悪の根源ってあの国じゃない?」について解説したいと思います。参考文献は『教科書では教えてくれない世界史』(著者:土井昭)です。
著者の土井さんは予備校講師でありながら、「世界史解体新書」というYoutubeチャンネルを運営されている方です。 これまで、哲学や宗教の補助線を引きながら世界の真実の姿を眺めてきました。そこで、ふと思ったことがあります…「世界史の中の諸悪の根源って全部イギリスじゃない?」 イギリスの正式名称は「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」です。イギリスとはイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4か国による連合国(UK:United Kingdom)なのです。(そのため、連合王国と表記した方がよいのですが面倒なので今回はイギリスにします)。 みなさんはそんなイギリスに対してどんなイメージをもっているでしょうか?かつて世界の5分の1を支配して栄光ある孤立を推進した大英帝国の輝かしい歴史、ロイヤルファミリーやマナーハウスをはじめとする古き良き伝統と共にロックやファッションなどの文化においては時代の最先端を走る新しさが共存する国、マナーやエチケットを重視するおだやかな国民性と紳士の国。そんなふうに思っていた時期が、わたしにもありました… しかし、その本当の姿は学校や会社に1人はいるただの「こじらせ野郎」だったのです。パレスチナ問題、インド-パキスタン問題、ミャンマーのロヒンギャ問題などなど…これらは昔から現在に至るまで解決の糸口さえ見えない複雑な問題なのですが、そのほとんどにイギリスの関与があると知ったらみなさんは驚くでしょうか? イギリスは世界史の中で目的のためなら手段を選ばない陰謀や傲慢な行動をとったことでネット界隈でしばしばブリカスとよばれているのを目にした方もいるかと思います。 今回はイギリスの歴史と諸国との関係をわかりやすく解説していきます。動画の後半では「イギリス病」から考える日本の現状についても解説しています。ぜひ、動画を最後までご覧になってイギリスがブリカスかどうかを判断してみてください。内容がわかりやすかったと感じた時にはぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 イギリスの歴史
イギリス全体の国土は約24万㎢で日本の3分の2ほどの大きさです。人口は約6900万人なので日本の約半数ほどだといえます。イングランドはグレートブリテン島の中心に位置する政治経済の中心といえる国です。首都ロンドンはイギリスの首都でもあるのでここがイギリスの中心となる国といえます。人口は約5300万人なのでイギリス人のほとんどがイングランド人なのです。
イギリス王室で有名なバッキンガム宮殿やウェストミンスター寺院などがあり、そのほかの観光名所にはビッグベンやストーンヘンジなどもあります。また、シェイクスピアやビートルズなどの著名な文化人も多数輩出されています。さらに、サッカーやラグビー、テニスなどのメジャースポーツ発祥の地としても有名です。
スコットランドはグレートブリテン島の北部にある人口約550万人の国です。首都エディンバラは『ハリーポッター』の原作者の出身であることから、物語の舞台としても有名で街中の至る所にハリーポッターの世界観があふれています。
ウェールズはグレートブリテン島の西部にある人口約300万人の国です。「山の国」といわれる通り南北を貫く巨大な山脈があり国土の4分の1が国立公園です。ヨーロッパで面積あたりの城の数が最も多く城の数だけ戦争があったことを示しています。
北アイルランドはアイルランド島の北東部にあたる人口約190万人の国です。もともと同じ1つの国だったのですが独立して現在もアイルランドと国境を接しています。分裂後は北アイルランドだけがイギリスの一部になっているということです。
もともと、グレートブリテン島にはケルト人が生活をしていたといわれています。しかし、BC55年にローマ皇帝ユリウス・カエサルのガリア征服が始まり、紀元43年頃からローマ帝国によって本格的な支配が始まるのです(属州ブリタニア)。現在のロンドンの起源はこの時期のローマ帝国が建設した商業の中心地―「沼地の砦」を意味するロンディニウムというテムズ川沿いの交易都市にあるのです。
その後400年頃にゲルマン人の大移動が起こってローマの支配が終わるのですが、それからゲルマン人の一派であるアングロサクソン人によってグレートブリテン島に7つの王国が作られるのです。この時代の有名な逸話にチョコレートで有名な「ゴディバ夫人」の物語があります。圧政をする領主の夫に対して情け深い夫人が減税を求めたところ、「裸で馬にまたがって街を横断しろ」と言われるのですが見事にこれを達成するのです。この時、街の人たちは夫人に恩義を感じて誰もその姿を見ようとしなかったのですが、トムという男だけがこれを覗き見していたという伝説が残っています。これが、覗き見をする人の代名詞であるピーピング・トムの由来となったようです。
幾度の戦争の末に800年頃には1つにまとまりイングランドが誕生したようです。しかし、北欧からのヴァイキングによる侵略や、フランスからのノルマン公国による征服(ノルマンコンクエスト)などが続いていきます。これが後にフランスとの百年戦争(1337年~1453年)につながっていくのです。
ウェールズはグレートブリテン島へのゲルマン人などによる侵略でもともとの先住民たちが西部に追いやられて誕生した国です。スコットランドも同じように北部に追いやられた先住民たちの国なのですが、10世紀にヴァイキングに侵略されていたという歴史をもちます。そのため、スコットランドはグレートブリテン島の先住民だけでなく、ヴァイキングとアイルランド人たちによって原型がつくられ独自の文化が発展しました。アイルランドはケルト人と先住民によって独自の文化を形成していました。スコットランドと同じようにヴァイキングに侵略された歴史をもつのですが、ヴァイキングは港を整備して操船の技術を伝授するなど様々な貢献もしたようです。そこから北部が北アイルランドとして独立するようになるのです。こうして、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドが形成されたのです。
しかし、1272年にイングランドがウェールズを侵略しました。この時、イングランドの侵略を阻止した実在するアーサー王を元にしているのが、あの「アーサー王伝説」だといわれています。イングランドはウェールズを併合することに成功して、戦士王エドワード1世は長男を「プリンス・オブ・ウェールズ」に任命しました。ちなみに、プリンス・オブ・ウェールズは現在のイギリス皇太子に与えられる称号であり、第二次世界大戦で日本軍が沈めたイギリス戦艦の名前もプリンス・オブ・ウェールズでした。
ウェールズを併合したイングランドは次にスコットランドを併合しようとします。1292年にイングランドの介入によって新しいスコットランドの国王が就任するのですが、その結果スコットランドはイングランドに臣従することを求められるのです。それからお互いに小さな争いを繰り返していくのですが、約300年後イングランドに国王の継承者がいなくなってしまったことがきっかけで両国は互いの独立を認めながらも同じ人が国王となる「同君連合」を築くのです。そして、1707年に両国は1つにまとまり「グレートブリテン王国」が誕生したのです(しかし、実際にはイングランドによるスコットランドの併合でした)。
アイルランド併合のきっかけは1541年にイングランド王ヘンリー8世がアイルランド国王であることをアイルランド議会に承認させたことに始まります。ヘンリー8世は「離婚したい」で有名なプロテスタントの英国国教会をつくった国王です。北アイルランドにはこのプロテスタントの信者が多くいたことから1603年にイングランドは北アイルランドを植民地にしてしまいます。1789年カトリック信者への不当な扱いに反発が高まっていたアイルランドでは、独立戦争やフランス革命にも影響を受けたことで独立するための反乱が起こるのです。この反乱は鎮圧されてしまうのですがグレートブリテン王国はアイルランドを併合して「グレートブリテン王国及びアイルランド連合王国」を成立させました。
ところが、1918年にアイルランドが再び独立を宣言したことによって翌年にイギリス・アイルランド戦争が勃発することになるのです。その結果、アイルランドは南北に分割されてプロテスタントの多かった北部だけが連合王国に残ることになりました。そして、カトリックの多かった南部はアイルランドとして独立することになるのです。こうして、1922年に「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」となるのです。
現在のイギリスは連合王国ではあるものの政治・経済ではイングランドが優位な状況です。そのため、イングランド以外の国では独立運動が実施されています。(ただし、経済面での不安要素が大きいことから実現はしていません)。
2 イギリスが関与してきた国際問題
2-1 パレスチナ問題
2023年に起きたパレスチナとイスラエルの衝突は世界中に大きな衝撃を与えました。これに対して世界中からイスラエルの攻撃を非難する声があがるいっぽう、アメリカ(と同盟国の日本)はイスラエルを支持するスタンスをとっているのです。パレスチナの問題を正しく理解して、アメリカの政策を読み解くためにはユダヤ教に関する理解が必要になるのです。
ユダヤ人たちは中世の時代から長きにわたって迫害され続けてきました。ローマ帝国によってキリスト教が公認されるとユダヤ人はイエス・キリストを十字架にかけた罪人であるというレッテルをはられました。また、十字軍の遠征においてアラブ人と同様にユダヤ人も異教徒とみなされたことやキリスト教で禁止されていた利子を認めるユダヤ人を金の亡者とも揶揄されたのです。19世紀には反ユダヤ主義の流行からロシアを中心とするポグロムやフランス将校がスパイ容疑をかけられたドレフュス事件なども起こりました。このような時代の流れの中でユダヤ人たちはやがてユダヤ人の国家を建設しようといういわゆるシオニズム運動(シオンとはパレスチナの古名)が始まるのです。
パレスチナの地は当時オスマン帝国が支配していたのですが、オスマン帝国を弱体化させるためにイギリスは1917年に「バルフォア宣言」を出してパレスチナの地にユダヤ人の国家を建設することを約束したのです。ところが、イギリスは1915年に「フサイン=マクマホン協定」をアラブ人と1916年に「サイクス=ピコ協定」を仏露と結んでいたのです(悪名高い三枚舌外交)。第二次大戦後の1948年にユダヤ人は約束どおりイスラエルを建国するのですが、もともとこの地にいたアラブ人たちはパレスチナ難民となってしまうのです。そして、イスラエル建国に反発したアラブ諸国との間に4度の中東戦争が起こりました。イスラエルには「独立戦争」であり、アラブ諸国には大災害(ナクバ)だとされています。
1993年に結ばれたオスロ合意は両者の問題を解決する糸口になると考えられました。この合意はアメリカのクリントン大統領の立ち合いのもと、イスラエルのラビン首相とパレスチナ解放機構のアラファト議長によって調停されました。しかし、1995年にイスラエルの右翼過激派によってラビン首相は暗殺されてしまいます。翌1996年に右派政党のネタニヤフ首相が就任すると和平交渉は停滞してしまいました。
パレスチナ側でも共存を目指すファタハと武力闘争を志すハマスの対立が大きくなります。2006年にはハマス側がガザ地区からファタハを追放する出来事も起こりました。その間にイスラエルはどんどん入植地を拡大させていき巨大な壁を建造しました。その結果、2023年にハマスがイスラエルを攻撃して人質をとる事件が勃発したのです。イスラエルは報復として「戦争状態」と声明を出して大規模な爆撃を行い、両者の戦闘は2025年現在に至るまで継続しているのです。
2025年5月、ハマス指導者を殺害したというニュースが報道されました。これまで何度も停戦協定を行ってきたもののうまくいかなかった両者の問題がこの先どのようになるのかを注視していかなければいけないと思います。
2-2 インド-パキスタン問題
インドとパキスタンは国境を接する隣国でありかつては1つの国でした。しかし、第二次世界大戦後にインドからパキスタンが分離独立する時には、大きな宗教対立が起こって大惨事となりその後も幾度となく戦火を交えています。現在もインドとパキスタンは犬猿の仲でカシミール地方をめぐって紛争が続いています。そのため、両者の関係が第三次世界大戦の引き金になるかもしれないといわれています。
なぜなら、インドとパキスタンはお互いに核兵器を保有しているからです。問題の起源はイギリスがインドを植民地にするため進出したところから始まります。イギリスはインドを植民地化したときに宗教の対立を利用した分割統治を行いました。つまり、インド国民の不満をイギリスではなく同じ国のちがう民族に向けさせたのです。
当時のインドはムガル帝国のもと最大にして最後のイスラム帝国が統治していました。そのため、イギリスは多数派であるヒンドゥー教徒を優遇するようにしたのです。さらに、有名無実化していたカースト制度を復活させて対立を煽るようにしました。その後、1947年に戦争で疲弊したイギリスはインドの統治権を手放すことになります。このとき、インドの指導者ガンディーは「ひとつのインド」としての独立を望むのですが、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の間にはすでに埋めることのできない溝ができていました。イスラム教徒たちはイスラム教徒のみの国家として独立することを望んでいたのです。そのため、両者はそれぞれ別々にヒンドゥー教徒の多いインドとイスラム教徒の多い東西パキスタンとして独立したのです。
この時、インドにいたイスラム教徒とパキスタンにいたヒンドゥー教徒は迫害されることをおそれて大移動することを余儀なくされてしまいました。その数1000万人以上とされており、その過程で略奪や強制改宗などのさまざまな非道が行われてしまったのです。
さらに、この時どちらの国として独立するのかを決められなかった場所―それが現在も問題となっているカシミール地方なのです。カシミール地方ではそこの住民の多くがイスラム教徒であったのに対してヒンドゥー教徒の王がインドへの所属を表明するというねじれ構造ができてしまいました。そのため、イスラム教徒の住民たちがインドへの併合に対して反発する中でインドとパキスタンの両軍がカシミール地方を舞台に激突することになりました。
1950年代の後半に中国とソ連の関係が悪化したことも両者の関係に影響を及ぼしました。ソ連がインドを支援して中国がパキスタンを支援したことから、両者の争いはソ連と中国の代理戦争の様相を呈するようになっていきます。これが現在まで続くインドと中国の関係悪化の原因でもあるのです。
1970年には東パキスタンに大規模なサイクロンが発生して甚大な被害が出ます。このとき、西パキスタンが支援しなかったことで東パキスタンは独立を望みました。インドは東パキスタンの独立を支援したことで西パキスタンと全面戦争に突入するのです。これに勝利したインドはカシミール地方における優位性をえることになり、東パキスタンはバングラデシュ(ベンガル人の国)として独立することになったのです。
ちなみに、第二次世界大戦中インドのベンガル地方で大飢饉が発生したときにイギリスでは英雄とされている首相ウィンストン・チャーチルは「野蛮な地域に住む汚らわしい人間」「ウサギのように繁殖するだろう」とインドの人たちのことを蔑み頑なに食糧支援をしなかったといわれています。また、インドの指導者マハトマ・ガンディーに対しても「半裸の聖者を気取った弁護士」という開いた口が塞がらない呼び方をしました。現在に至るまで両国は幾度となく武力衝突を繰り返してきています。イギリスも問題の解決に協力はしてきたものの手に負えなくなってしまったので、それからはカシミール問題に対して無言を貫く紳士のふるまいをするようになりました。
2-3 ミャンマーのロヒンギャ問題
ロヒンギャとはミャンマー西部ラカイン州に住むベンガル系の少数民族のことです。ミャンマーは、公用語がミャンマー語で9割が仏教徒の国なのですが、ロヒンギャはミャンマーに住んでいるもののロヒンギャ語を話すイスラム教徒なのです。もともと200万人ほどが住んでいたようですが現在は80万人ほどといわれています。
ロヒンギャの人々は、独自の言語や文化を持ち長年ミャンマーで暮らしてきましたが、政府からは「不法移民」と見なされ国籍を与えられず差別や迫害を受けてきたのです。ミャンマー政府は移民であることを受け入れれば国籍を与えるとしているのですが、ロヒンギャはこれを拒否しているようなのです。
ちなみに、隣国のバングラディッシュはベンガル人が中心でイスラム教を信仰する国です。つまり、バングラデシュと宗教や言語を同じにする人たちがミャンマーにいるのです。そのため、ミャンマーはロヒンギャに対してバングラデシュに帰るべきだと考えています。しかし、バングラデシュはこれを拒否しているのです。ロヒンギャが過去に何度も難民として流入してきた時に混乱が生じたことがあるからです。
このような対立の原因もやはりイギリスだったのです。イギリスがインドを植民地化したときに、ミャンマーも植民地にしていました。イギリスはやはり分割統治をするのですがミャンマーでは少数民族を優遇したのです。もともといたイスラム教徒に加えて隣のベンガル地方(現バングラデシュ)からもイスラム教徒を連れてきていたと言われています。これらのイスラム教徒たちがロヒンギャの起源であるといわれているのですが、そうなるとミャンマーはイギリスが関与したロヒンギャに支配されていたことになります。
第二次世界大戦中には日本軍が侵攻してきてイギリス軍と戦闘を行うのですが、日本はミャンマー軍と共に、イギリス軍はイスラム教徒たちと共に戦うことになりました。ということは、ミャンマー人はロヒンギャの人たちと争っていたということになります。そのため、第二次世界大戦後にミャンマーが独立をしたときには、植民地支配以前から住んでいる人の子孫にミャンマー人としての国籍が与えられました。歴史的にはイギリスの保護を受けたロヒンギャの方が優位にいたことへの反感もあってベンガル地方から来たイスラム教徒には国籍が与えられなかったのです。
ミャンマーにとっては、歴史的にもロヒンギャに対してよい感情をもつことはできません。イギリスの庇護の元で支配された過去があり言語も宗教も見た目もちがう民族のことを「同じ国の仲間である」と言われてもなかなか素直に受け入れることは難しいでしょう。現在イギリスはミャンマーやロヒンギャに対する支援について無言を貫いています…。
3 イギリスとその他の国々の関係
まず、イギリスと最も仲が悪いとされている国と言えばまちがいなくアイルランドです。17世紀に清教徒革命の指導者オリバー・クロムウェルがアイルランドを侵略しました。そこでは悲惨な虐殺があったといわれそのまま植民地にされてしまうのです。
イギリスは自国で農業ができないのでアイルランドを穀倉地帯にしようと考えました。アイルランドは厳しいノルマを課されて輸出用の小麦を生産することになったことで、アイルランドではジャガイモを主食としなければいけなったのです。しかし、19世紀にジャガイモの病気が発生して生産することができなくなりました。このとき、大量の小麦はあるのにジャガイモだけ生産することができないため、アイルランドでは多くの餓死者が出たとされています(有名なジャガイモ飢饉)。
また、フランスやロシアもイギリスを嫌いな国として有名です。フランスとは中世の王位継承と領土をめぐる100年戦争にはじまり、ヨーロッパの数々の戦争やインド、アメリカ大陸におけるさまざまな戦争を重ねています。負け惜しみではないと思いますが、フランス人はイギリスの料理をバカにしていますよね。
ロシアとは帝国主義時代の覇権を争うグレートゲームによる対立がありました。当時の海軍最強国であるイギリスと陸軍最強国であるロシアは、ユーラシア大陸の至る所で覇権をめぐって争うことになったのです。ちなみに、英語で奴隷のことをスレイブといいますがその語源はスラヴのようです。ロシアの人たちはスラヴ系の民族とされていますが、この地域の民族は古代や中世において奴隷にされることが多かったのです。そのため、奴隷のことをスラヴにちなんでスレイブというようになったそうなのです。
現在のウクライナ戦争でイギリスがやたらウクライナを支援したり、日露戦争の時にわざわざ日英同盟を結んだりする理由もなんとなくわかりますね。
中国もイギリスに対して嫌悪感を抱いている国の1つといえます。当時(清朝時代)のイギリスは産業革命によって過酷な労働が社会問題となっていたので中国から大量のお茶を輸入して労働者を酷使していたのです。しかし、これでは貿易赤字となってしまうので植民地にしていたインドからアヘンを中国に大量に売るようにしたのです。そのため、中国はアヘン中毒者が蔓延するようになってしまいました(しかも、イギリスは中国が拒否しても密貿易までして売りつけていたようです…)。
これがアヘン戦争につながってそのまま清は欧米諸国に侵略されることになるのです。中国はアヘン戦争の南京条約によって香港島をイギリスに割譲されただけでなく、アロー戦争の北京条約で九龍半島を割譲されそのまま新界を租借されることになるのです。これが現在まで続く中国の「一国二制度」の始まりなのです。1997年にイギリスは中国の求めに応じて香港全体を返還することに決めました。このとき、一国二制度の維持や香港人による統治が約束されたのですが、中国共産党はそんなこともお構いなしに徐々に中国化政策を進めているのです。
南アフリカの人種隔離政策アパルトヘイトもイギリスのせいだといえる制度です。もともと、南アフリカを支配していたのはオランダでした(それもどうかと思いますが)。南アフリカにいるオランダ系の移民をブール人とよぶのですが、イギリスが植民地化しようとしたときに起こったのが南アフリカ戦争(ブール戦争)です。
もうピンときた方もいるかと思いますが、イギリスが南アフリカを統治するために考えられたのがアパルトヘイトなのです。身分差別をつくることでイギリス人とブール人(白人)は協力して南アフリカの現地の人たち(黒人)を支配しようと考えたのです。
これに反発したのがネルソン・マンデラです。1964年に国家反逆罪で終身刑を受けるのですが1990年に釈放されると、アパルトヘイトを撤廃して大統領となって民主的な南アフリカを実現していったのです。
オーストラリアを植民地化した時にはヨーロッパでもよくある狩りをしました。ただし、ただの狩りではなく現地の人を対象にしたアボリジニー狩りをしたのです。イギリス人は狩りに成功した証として壁にコレクションして並べたとまでいわれています。それだけでなく、核実験をアボリジニー居住区で行ったこともあるのです。
アメリカ大陸に渡ったピルグリムファーザーズもイギリスのプロテスタントたちでした。そして、西部開拓を行いながらアメリカ大陸をイギリスの植民地にしていくのです。アメリカの先住民ネイティブアメリカンとの戦いでは細菌兵器を使用しました。現地には存在しないウイルスのため免疫のない先住民たちは天然痘のウイルスがついた毛布を配布によって病気になってしまったのです。アメリカを植民地化することでイギリスは大規模なプランテーションをつくりました。ここに、アフリカから大量の奴隷を連行してきて黒人たちに強制労働をさせたのです。これが、現在も続くアメリカにおける黒人差別の問題につながっていくのです。
4 「イギリス病」と日本の失われた30年
イギリスは第二次世界大戦によって戦勝国になったものの国土も精神もボロボロになってしまったのです。そのため、大英帝国とよばれて世界の5分の1を支配していた世界最強の国の実態はさまざまな民族紛争や民族差別の原因をつくった諸悪の根源であった―戦後のイギリスではこのような自虐史観の教育を行うようになっていたのです。その結果、イギリスは「イギリス病」に罹ってしまうのです。
イギリスの戦後経済は不振になり国民は自信を失っていくようになるのです。「イギリスは悪い民族なのだ…」「イギリスは世界に対して謝罪と賠償をするべきだ…」このように、どん底にまで落ちたイギリスを立て直したのがあのさっちゃんです。
鉄の女ことマーガレット・サッチャーは自虐史観をやめて愛国教育を推進しました。サッチャーはイギリスを賛美するだけではなく正しい事実を伝えるようにしました。たしかに、植民地化して奴隷貿易をしたけどそれはイギリスだけではない、むしろイギリスは奴隷貿易を最初にやめた国でもあるということインドを支配したけどインドに鉄道などのインフラも整備して開発もしたこと。このように、事実をきちんと併記するようにしていったのです。その結果、イギリス人たちは民族としての誇りを取り戻して立ち直っていったのです。
これを聞いて現在の日本も同じような状況にあると思いませんでしたか?私たちの多くは学校で「日本はアジアの国々を侵略した」と教えられ、どこかの国が「謝罪と賠償をしろ」と言ってくるのでしなければいけないと思っています。安倍総理は戦後70年の時に(募集を募っただけと言った安倍総理のことは相当に怪しいと思いますけど)それでも、せっかく戦後70年談話において「ここで終わりにする」と言ったのにそれをこの人がまたのこのこ出てきて80年談話とか余計なことを言わないか心配です…。
「失われた30年」といわれてしばらくたつのですがこのままだと気がついた時には失われた50年どころか100年にまでなりそうな予感です。まずは、自虐史観をやめるところから失われた時間を取り戻すことが始まるかもしれません。
7 まとめ
今回の動画は「世界史の諸悪の根源ってあの国じゃない?」について解説してきました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだたくさんありますのでぜひ本書を手に取ってより詳しく学んで頂けたらと思います。
現在に至るまで解決の糸口が見えない宗教・民族問題の数々にはまちがいなく連合王国の関与が関係しています。このように、連合王国の歴史的な背景を知ることで、これまで知らなかった世界の見方が大きく変わることもあったのではないかと思います。これからも「哲学・宗教の補助線」を引いて世界を眺めることができるといいですね。


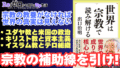
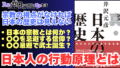
コメント