今回は「哲学者は労働をどのように考えてきたのか」について解説したいと思います。参考文献は『労働の思想史』(著者:中山元さん)です。
なぜ、私たちは「労働」をしなければいけないのでしょうか?日本国憲法の第27条には「勤労の義務」が明記されていますが、働かないからと処罰されることもなければ働くことを強制されているわけでもありません。これは、働くことによって自立して社会に貢献してくださいというような意味であり、あくまで「倫理的」な規定であるということなのです。
では、遺産や配当などの不労所得で生活している人は非難されるできなのでしょうか?納税の義務さえ守ればよく、労働を義務化するのはいきすぎであるとも言われています。そもそも、この条文は旧ソ連のスターリン憲法に倣って考えられたものであり、国民すべてを労働者にするという社会主義的な思想であると批判されることもあるのです。
いっぽう、「世界は誰かの仕事でできている」というテレビのCMが流れていたように、誰かの仕事でつくられた世界で生活するのだから世界づくりには自分も参加した方がよい、仕事は自分の能力を発揮したり生きがいを見つけたりするためにするものである、このような考え方のもとで労働することに意味を見出すことも間違ってはいないでしょう。
いったい、「働く」ことにはどんな意味や目的があるのでしょうか?現代の私たちにとって「労働」は生活の一部であるどころか、そのほとんど全てを構成しているといっても過言ではない状況になっていますよね。だからこそ、「働く」ことについてあらためて考えることが必要だといえるのです。
そこで、今回は「働く」ことに対して「哲学の補助線」を引いて考えてみましょう。原始の時代から現代に至るまで多くの哲学者たちが「働く」ことを考えてきました。その中で時代ごとに「働く」ことの意味は大きく変わってきたことに気づけると思います。いつもより気合を入れてつくったのでボリューム感5割増の内容になっています。わかりやすかったと感じた時にはぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 なぜ私たちは働くのか?
現代の私たちは「働く」ことにほとんどの時間を費やしています。そのため、働かなければ生きていけないと多くの人が考えていることでしょう。たしかに、生計の維持という点からも働くことは必須の条件だといえます。しかし、働くことの意味はそれだけではなくほかにもあります。
たとえば、働くことによって、社会を構成したり他者とつながったりすることもできます。また、働くことによって自己実現をしたり喜びや満足をえたりすることもできます。このように、働くことには、生計の維持、つながり、喜びという3つの側面が考えられます。
哲学者ハンナ・アーレントは労働を意味する言葉には2つの系列があると指摘しました。1つは「労働」という言葉であり、もう1つは「仕事」という言葉の2つです。どちらかといえば、「労働」には苦労しながら働くという否定的な意味が強く、「仕事」には工夫しながら働くという肯定的な意味が強く含まれているように思えます。
古代ギリシアでは労働はポノス、仕事はエルゴンという言葉で表現されていたようです。労働(ポノス)には働くことの苦痛という意味が強く、仕事(エルゴン)には働くことによって生まれる成果に重点を置く意味が強く含まれます。古代ギリシアの叙事詩人ヘシオドスは『仕事と日』の中で労働と仕事を考察しています。たとえば、プロメテウスがゼウスの命令に反して人間に火を与えたことからゼウスは人間に罰(労働と死)が与えられたとされています。ヘシオドスは人間を苦しめるものとして「苦しい労働」をあげているのです。
いっぽう、女神エリスは人間に働こうとする気持ちを植えつけたとされています。人間たちは自分の手で仕事をすることによってその成果物の卓越さを他者に示したのです。このように、古代ギリシアではすでに苦しい肉体的な「労働」とやりがいのある「仕事」という2つの側面がはっきりと認識されていたのです。
近代になって、ジョン・ロックは2つの概念のちがいを「身体の労働と手の仕事」という言葉によって表現しました。働くには、自分の身体を使う厳しい労働と手や頭を使い才能を発揮する仕事があるのです。ただし、私たちは嫌な労働でも生計の維持や他者とのつながりをもつことができます。つまり、労働と仕事は働くという営みの中で分けられながらも密接に関連しているのです。
ハンナ・アーレントは「労働」と「仕事」のほかに「活動」という概念も提唱して人間の行動の全体をこれら3つの概念によって考察しました。「労働」とは人間が自分の生命を維持するために必要とする苦しい営みを示しています。そのため、労働は個人の生活(食事や掃除)を支えた後には何も残さないものだといえます。「仕事」とは自分の能力を発揮して社会のために何かを残そうとする営みを示しています。世界には、仕事によってさまざまな作品や道具が残されていくのです。そのため、仕事は個人的な才能を発揮するという意味では「個人的」ではあるものの、世界に成果物を残すという意味では半ば「公的」な性格を帯びていると考えられます。
「活動」とは公的な場において自分の思想などを発揮しようとする営みを示しています。そのため、個人的な生活の維持というものだけではなく、共同体の活動に参画するという意味で「公的」な性格を帯びるものだと考えられます。思想や行動のような「活動」の後には目に見える成果物のようなものは残りませんが、ハンナ・アーレントはこれを労働や仕事とは明確に異なる次元の行為として捉えたのです。
古代ギリシアのポリスでは個人が家庭において生活を維持するために労働をしていました。これは家において行われるものであるため公的な世界からは隔絶されたものでした。いっぽう、「仕事」は共同体(ポリス)のために行われるものであることから、公的な性格を帯びてはいるものの公的な「活動」とは別の種類のものとされていました。なぜなら、これは主に職人による手仕事であったことから、共同体のための発言をすることは認められていなかったのです(身分的にも仕事をしている人は自由人としての権利をもたず排除されることが多かった)。
ソクラテスの友人アリスタルコスは親族が多く経済的に苦しいときでも「異国の人間を奴隷として買ってさせるもの」として仕事をさせることを忌避しました。自分の親族は自由な身分であり仕事は自由な人間がやるべきではないと信じていたのです。
アリストテレスも職人たちには自由人にふさわしい徳が欠如していると考えていました。「労働」や「仕事」に対して「活動」は公的な自由の領域で行われるものであって、ポリスの自由民だけが自由を享受しながら公的な活動に従事していたのです。自由とは支配されないということでありながら、支配する必要性もないということです。そのため、生計の維持や何かの成果物を世界に残すものでもなく無償で行われました。
しかし、現代では公的な自由な営み(活動)であっても重要な職業になっていると、マックス・ウェーバーは『職業人としての政治』の中で指摘しています。現代の政治は「政治を職業とする真の人間たち」によって担われている活動なのです。
以上のことから、現代における「働く」という営みは、ハンナ・アーレントの分類―「労働」「仕事」「活動」ではうまく整理できなくなっていることがうかがえます。私たちは「労働」や「仕事」のような生活を支える個人的な営みを通していたとしても、他者や社会とのつながりをえたり社会的な評価をえたりするようになっているのです。私たちは働くという営みを通して個人的な生活を支えるための労働をすると同時に、仕事をすることで世界に何かを残したりつながりをえたりもしているのです。つまり、現代では労働と仕事の両方の営みの中で自己実現を達成することができるのです。
2 石器時代の労働
ジャン=ジャック・ルソーは『人間不平等起源論』の中で原初の時代の人間が他者との関係をもたず木の実を食べるだけのような「自然人」としての生き方を描きました。それは遊びのようなもので苦しい労働でもなければ何かを残す仕事でもありませんでした。
石器時代の人間がどのような生活を営んでいたのかを知るヒントをアフリカのカラハリ砂漠に住むブッシュマンに見ることができます。ブッシュマンはいくつかの核家族を中心とした集団生活をしていて、男は狩猟と道具の製作、女は採集と料理のような労働の分業が成立しているのです。このとき、ブッシュマンの労働と生活は最低限の必要性を満たすものにとどまります。なぜなら、それ以上の労働は無意味なだけでなく生きるための妨げになるからです。獲りすぎた獲物は腐るだけであり、過剰な食物はキャンプを移動する時の邪魔になります。
労働で獲たものをすぐに消費して余剰を貯蓄しないという生活様式は国家や社会の形成とはあきらかに疎遠なシステムであると考えられます。つまり、国家という制度が生計の満足を超える生産を提供することを強いているのです。新石器時代を迎える頃には、人類は定住と農耕によって食料を貯蓄するようになりました。植物を支配する農業と家畜を支配する牧畜、金属を支配する冶金や宗教の誕生―それが、都市生活や集団的な労働の組織化、技術と文明の発展をもたらすことになるのです。
狩猟や採集が中心の労働は菜園や田畑での栽培や家畜の世話などに変わっていきました。河川の近くに誕生した文明が形成される過程では道具の開発や治水工事も行われました。そのため、貯蓄をするための農業や治水工事などの労働を強いられることになるのです。国家の誕生によって余剰作物が集められ、それを保管するための倉庫が建造されました。そして、穀物の量を記録するための文字が発明されるようになって文字をあやつる官僚的な組織の中から神官などの権力者(王)が登場するのです。そのため、この時代にはピラミッド建造のような奴隷としての労働の搾取が行われました。また、他国と戦争をするための徴兵としての労働も多かったのではないかと考えられます。
このように、国家の誕生によって労働は個人が生存するために行うものではなく、国家のために奉仕する(搾取される)という苦しい労働観へと変化していったのです。このような労働制度は、以後ローマ帝国からヨーロッパの絶対王政にいたるまで人類の歴史の中で労働の過酷さを物語るものとして残っていくことになるのです。
3 古代の労働
文明の誕生は労働の否定的な側面を強めることになったと考えられるいっぽう、近代至る労働の歴史は労働の肯定的な側面を見出していくかの歴史でもあるといえます。メソポタミアやエジプトのような古代文明における人間は農業や労役、徴兵などの労働をひたすらに搾取される存在であったと考えられます。
しかし、古代ギリシアにおけるポリスではちがった労働観が生成されていました。古代ギリシアにおいて、働くという営みには「労働」と「仕事」の2つの側面が存在して、そこには肯定的な側面と否定的な側面がそれぞれに含まれていたと考えられます。
これに対して、アリストテレスは行為の対象との関係という観点から、行為の営みを「制作」「実践」「観想」という三種類に分類をしました。「制作」と「実践」は自然の産物のような偶然性を備えるものを対象とする行為です。「制作」の営みには自然に働きかけて何かを生み出すという点で労働や仕事が該当します。「実践」の営みには何かを生み出すわけではないものの、他者に働きかけるという点で政治活動や裁判のような活動が該当します。
いっぽう、「観想」は自然法則のような必然性を備えるものを対象とする行為です。星空を観測する天文学をはじめとするさまざまな学問(真理の探究)がこれにあたります。アリストテレスはハンナ・アーレントが示した「労働」と「仕事」を「制作」、「活動」を「実践」に置いて、さらに「観想」というものを想定しました。
そのうえで、奴隷や職人は「制作」に従事して自由な市民は「実践」に従事するか「観想」に従事することになると考えたのです。古代ギリシアでは「労働に従事する奴隷と仕事に従事する職人」「活動に従事する政治家」そして「観想に従事する哲学者」という3種類の人間像が成立していたのです(もちろん、労働は卑しいものであり観想がもっとも望ましい営みであったとされていた)。
このような階級構造はその後の社会でも同じように継承されていくことになりました。西洋社会における第一身分(聖職者)、第二身分(王族や戦士)、第三身分(農民)など。近代になって、ようやく人間のすべての活動は仕事としてみられるようになっていきます。畑を耕す労働は農民の仕事、工場で作業をする労働は労働者の仕事、政治活動は政治家の仕事、思索にふけるのは学者の仕事としてみられるようになります。そして、それぞれの仕事によって生計の維持や自己実現をしていくことになるのです。
4 中世の労働
中世ヨーロッパの社会を支配していたのはまちがいなくキリスト教でした。ヘブライズムの思想の出発点は『旧約聖書』であり、そこではアダムとイブ以来「労働は神によって与えられた罰」として描かれていました。
ところが、中世キリスト教の社会では奇妙な逆転現象が起こっていきました。最上位の観想に従事するべき聖職者たちが最下位の労働に従事するようになるのです。そのきっかけとなったのが、修道院という制度でした。
初期の修道院では労働を含む素朴な信仰生活が営まれていたそうです。もちろん、スコラ哲学をはじめとする知識の伝達は宗教者としての修道士が中心でした。同時に、テンプル騎士団や聖ヨハネ騎士団のような戦士としての存在も兼ねていたのです。つまり、この制度の中で修道士たちは聖職者であり戦士であり、また農民でもあったのです。
このような中で、労働に精神的な意味が付与されたということが重要な意味をもちます。修道士にとって必要のない労働に従事することは、服従の精神を示すことだったのです。また、労働によって魂を清めることが救済の道に必要な過程だとされていったのです。そのため、修道院での労働は精神的なものでありその成果を求めるものではないことから、仕事が巧みであることを誇るような修道士は罰せられていたほどなのです。
修道士の労働は労働の肯定的な側面を再発見するだけなく様々な利点を生み出しました。労働によって経済的に自立できたこと、規則的で規律ある生活様式をもたらしたこと、そして労働の成果が公平に分配されたことで平等の精神を培ったことなどがあげられる。それは、福祉国家の原型のようなものであったと考えられます。
その後、十字軍が行われる中で中世の社会は大きな発展を遂げていくことになります。農業生産力の向上、商業と貨幣経済の発展、そして都市が活力をもつようになるのです。そして、7つの大罪に代表されるような卑しい職業に従事する労働であっても、「労働にもとづく職業は正当である」という考え方をされるように変化していきました。労働そのものに価値が認められるようになったことの証だと考えられます。
中世の修道院における労働は本来の意図とはちがう逆説的な現象を発生させました。もともと魂の救済のために行っていた苦しい労働によって望まない富がもたらされました。しかし、富の蓄積は教会の世俗化と堕落のきっかけにもなっていきました。禁欲的に労働に勤しむほどその目的を忘れるほどの富という副産物を生み出す―このような皮肉が近代になって資本主義のエートスを生み出すことになっていくのです。
5 近代の労働
中世では労働の意味が苦痛で避けられるものから価値あるものへと変容していきました。しかし、近代における資本主義的な市民社会が誕生するためには、さらに大きな3つの変革を必要としたのです。1つ目は宗教的な側面―マルティン・ルターとジャン・カルヴァンによる宗教改革です。2つ目は経済学的な側面―アダム・スミスによる労働価値説という経済学的な理論です。3つ目は哲学的な側面―トマス・ホッブズやゲオルグ・ヘーゲルによる哲学的な考察です。そして、これらの3つの側面を統合するようなかたちで登場したのがカール・マルクスです。それぞれ、簡単にですが紹介していきたいと思います。
5-1 資本主義的な市民社会の誕生と労働
1つ目の宗教的な側面での変革において、マルティン・ルターは教会が富を蓄積して堕落していることを批判しました。プロテスタントの信徒たちは教会による救済ではなく禁欲的で合理的な生活を心がけ、与えられた仕事を使命とみなしてひたすら神に仕えることを目指したのです。
まず、ルターは「召命」という言葉を天職としての職業を示すものとして使いました。そのため、世俗的な職業に従事しながら義務を果たすことが評価されることになるのです。
次に、カルヴァンは恩寵という「予定説」を提唱しました。職業の貴賤や貢献に関わらず救われるかどうかはあらかじめ決まっているということから、信徒たちは救われるという確信をえるため勤勉に労働することを推奨されたのです。
やがて、労働することそのものが道徳的な価値と結びついていくことになります。労働は信徒にとって倫理的な義務で、労働しないものは怠惰な者であるとされていきます。このようなプロテスタンティズム精神が資本主義を支える重要な精神となっていくのです。
資本主義の労働者はそれまでとは異なるそれにふさわしい労働者になる必要があります。このような労働する主体への構築は身体と精神という2つの側面から考えられます。身体の側面では、農業から工場労働にふさわしい身体の構築をするということ、精神の側面では、工場労働にふさわしい価値観を構築することを目指したのです。資本主義における工場労働では、分業体制で規則正しい効率的な作業が求められます。そのため、労働者の身体的には規律と訓練が要求されるようになっていったのです。
20世紀の哲学者ミッシェル・フーコーは『監獄の誕生』の中で「規律・訓練は服従させられ訓練される身体を、従順な身体を作り出す」と指摘しました。これを実現させるために、閉鎖空間による管理、配置と監視、そして時間的な配置(時間割)などのさまざまな方法が考え出されていった。
このように、労働者の身体は機械化されていくことになるのですが同時に人間には心があるため精神の側面からも資本主義の価値観が求められていくのです。規則を教えそれを遵守させること、規則に違反した際には厳しい罰が課せられること、そして、試験でランク付けを行うことによって労働者は「規格化」されていくのです。現代の学校や工場にも、その思想は根強く残っていることに気づかなければいけませんね。
以上のことから、労働が神聖視されて行く過程で労働者は規格化されていき、資本主義が近代の市民社会を支える経済的な原理、生活様式となっていくことのです。
2つ目の経済学的な側面での変革において、アダム・スミスは資本主義の論理を読み取り、近代経済学を確立していきました。それ以前の重商・重農主義では、労働が生み出す価値があまり認められていませんでした。
アダム・スミスは産業分野に関わらず商品の価値が労働によって決まることを示しました。まず、社会が成立するためには、人間の労働と余剰物の交換による分業が必要となります。これは、プラトンが『国家』の中で国家が生じる理由について「1人1人では自給自足できず多くのものが不足するから」と語っているのと同じです。そして、誰もが労働と交換をするような商業社会では「見えざる手」に導かれて、自分の利益を追求する方がそう意図する場合よりも社会の利益を高めると考えたのです。
ただし、労働は価値を生み出すが全ての労働がそうではないとアダム・スミスは考えました。そのちがいは、生産的な労働(価値を生み出す工場労働など)と非生産的な労働(価値を生み出さない家事労働など)という概念で捉えられました。
アダム・スミスは原材料を加工する労働によって価値が作られると考えていたので政治家や軍人、聖職者、医者、学者、芸術家なども価値を生まない労働者と見なされました。(ちなみに、全ての商品の価値の源泉が労働にあると指摘したのが後述するマルクスです)。
以上のことから、アダム・スミスをはじめとする近代経済学は労働と労働者の存在に対して近代の市民社会と資本主義にふさわしい地位と資格を与えることに貢献したのです。
3つ目の哲学的な側面での変革において、多くの哲学者が労働の意味を問い直しました。アリストテレス以来、人間には自然に社会を構成しようとするような人間性があって人間はそのような最高善を目指す道徳的な存在であると考えられてきました。しかし、先に見たように近代の市民社会においては、人間はひたすら自分の欲望を追求する孤立した存在であると考えられるようになりました。
このような人間観の先駆けとなったのは、トマス・ホッブズです。著書『リヴァイアサン』の中で、人間は自然状態において「万人の万人による闘争」―自らの欲望のために他者のものを奪ってもよいとされる戦争状態にあったと指摘しました。そして、このような状態を終結させるためには「社会契約」をするしかないと考えました。ホッブズは人間が道徳的によい社会を作り出そうと考えていたのではなく、欲望の実現(労働の果実)を守るための法を定めるための必然であったと考えたのです。
これに対して、ジョン・ロックは「所有が労働から生まれる」という考え方を提示しました。ロックは身体の所有権(自分の身体は自分だけのもの)という考えのもと、身体の労働によって獲得されたものに対して所有権が発生すると指摘しました。ホッブズは労働の成果を保護するために国家や法が必要とされると考えましたが、ロックは既に獲得している所有を保護するために国家や法が必要とされると考えたのです。2人の国家を設立する目的は同じであっても、ロックは労働の概念を提起することによって所有権を確立することに貢献しました。つまり、労働こそが社会を形成する可能性を生み出す営みであると規定されたのです。
また、ジャン=ジャック・ルソーは労働が不平等をもたらしと指摘したうえで、財産をもつことで所有権を無視する者に対抗するために国家や法を樹立したと考えました。その結果、自然の自由を破壊して、財産と不平等を定めた法が永久のものになるのです。ルソーは、労働が生み出した不平等が法(社会)を作り出すことになったので人間の自由を破壊したこのような社会を改革するために社会契約を必要としたのです。
いっぽう、ドイツではイマヌエル・カントが人間の尊厳という観点から労働を考察しました。カントも労働が生きるために必須であると同時に辛く過酷なものであると考えていました。しかし、この辛く過酷な経験をすることで人間は進歩できると考えたのです。カントは辛い労働を自らの意志で理性を陶冶する手段として強要することによって、人格的な存在としての尊厳をもつことにつながるとみなしていました。労働は「人間を陶冶」するための重要な手段であり、人間がその歴史を推進していくためにも不可欠なものであると考えたのです。
そして、カントの思想を批判的に継承したのがゲオルグ・ヘーゲルです。ヘーゲルは労働の問題を根源的に考えるために自己意識をもつ過程について思索します。(これを説明するとめちゃくちゃ長くなるのでだいぶカットしますが…)
ヘーゲルは自己意識が他者と出会った時に相手に対等なものとして承認されることを要求すると考えました。(「え?」と思ってもいいから納得してください!)。ここで、互いに承認を求める闘争が発生して、どちらかが屈服した時には自立した意識が主となり隷属した意識は奴となるのです。これが有名なヘーゲルの弁証法で、自己意識はこれによってさらなる存在へとなるのです。
承認された自己意識としての主は奴に対して労働を強いることができます。その結果、奴は自然に直接はたらきかけて労働することになり、主は自然との間に間接的な関係をもつようになります。奴にとってのこの労働はたしかに強いられたものではあるものの、そもそも人間には「制作する動物(ホモ・ファベル)」という定義があります。
人間は労働する(自然に働きかける)ことによって動物とは異なる人間たりえるのです。すると、労働を強いられた奴は労働(自然にはたらきかけること)で人間らしくなるのです。これもまた奴による自然との間に発生した弁証法であり、それは主との間にも発生します。たしかに、主によって奴は労働を強いられることになりますが、自然との弁証法の間に自立した奴はこの段階で主との関係を逆転させるようになるのです。なぜなら、主は奴の労働に依存することで結果的に奴に隷属することになるからです。
ヘーゲルは、このような労働の弁証法によって労働に自然をかえる働きだけでなく人間のそのものを変える働きがあることを示しました。労働することによって人間は人間らしさと人間性をもつことができるということです。こうして、ヘーゲルは労働を否定的なものから肯定的なものとして捉え直したのです。
5-2 マルクスの思想とさまざまな労働観
ヘーゲルの思想を直接的に受け継いだのがマルクスの盟友フリードリヒ・エンゲルスです。エンゲルスは人間が手を使い自然に働きかけて生産することで人間になったと考えました。手で道具を使い頭で考えることで文化や社会が形成されていったのは労働のおかげであり、人間とほかの動物を分ける本質的な区分を生み出すものもまた労働であると指摘しました。
そして、カール・マルクスもまた同じように労働こそが人間と動物を分けると考えたのです。ところが、19世紀は資本主義の原初的な負の側面が表出する時代でもあったことから、現実の労働はプロテスタントが掲げるような聖なるものとは全く異なる状態だったのです。労働はもはや自己実現の場ではなく、資本家による搾取の対象となっていました。
そこで、マルクスはヘーゲルの「外化」(道具は人間の理性がものになったもの)をもとに「疎外」という概念を生み出し労働における否定的な側面(4重の疎外)を考察しました。1つ目は生産物からの疎外(自分がつくったものを資本家に奪われること)です。2つ目は生産行為からの疎外(労働時間を資本家に奪われること)です。3つ目は人間の本質的な活動からの疎外(生活のためのただの手段になること)です。4つ目は人間的本質からの疎外(仲間ではなく競争相手としての他者になること)です。
マルクスはこのように疎外された労働者のことをプロレタリアートと呼びました。そして、資本主義的な生産様式の根幹たる私有財産を否定して、新しい世界秩序の再構築を求めて「万国の労働者よ、団結せよ」と言ったのです。
共産主義革命とは労働を疎外させるものとしての装置にしている国家を廃絶して、まったく異なる新しい協同社会をつくりあげることを目的とするものでした。そして、分業が廃止された共産主義社会おける労働は自発的な手と臨機応変な精神、喜びに満ちた心で自分の仕事をこなすアソシエーション労働になると指摘したのです。「共産主義はこわい」というイメージをもつ方も多いかもしれませんが、マルクスの資本論をぜひあらためて再読してみるのも面白いかもしれませんよ。
さて、マルクスは社会がブルジョワジーとプロレタリアートで対立していると言いました。しかし、マルクスの疎外とは異なる考えを展開したことでマルクスとエンゲルスから楽観的な「空想的社会主義者」といわれた思想家たちがいました。それが、サン=シモン、フーリエ、オーウェンの3人です。
サン=シモンの著作には後代の社会主義者たちの思想が萌芽として含まれるとされました。オーウェンの実験はあまりにユートピア的でありその多くは失敗に終わったものの、協同組合の構想はマルクスの理想とするアソシエーション労働に共通するとされました。フーリエは労働することが快楽となる共同体(ファランジュ)を構想しました。3人の思想が楽観的で空想的かどうか、本書を手にとってぜひ考えてみてください。
また、労働は喜びであり救世主であると語ったのは哲学者ヨセフ・ディーツゲンです。ディーツゲンは社会主義が1つの宗教であり、労働が自然を克服するための手段(労働こそが救世主)であると主張しました。労働が宗教的な救済の対象となるかどうかはわかりませんが、たしかに労働しないのであれば何をするの?という問いが新たに生まれそうな気がします。
ほかに、ドイツの哲学者マックス・シェーラーは労働の喜びをいくつも列挙しました。自分の能力の向上、心地よい身体の疲労感、さまざまな満足感、共同する喜びなどです。
このような労働を賛歌する哲学とは対照的に労働からの解放を主張する哲学も登場します。マルクスの娘婿ポール・ラファルグは労働ではなく「怠惰の喜び」を唱えました。ラファルグは労働を賛美するのはブルジョワジーであって、身体を酷使するプロレタリアートはそんな労働賛歌に騙されてはいけないと訴えました。そして、1日3時間ほど働いて残りの自由時間で人間らしい生活を送るべきだとしました。働く権利など悲惨になる権利であり、怠惰になる権利こそ芸術と高貴な美徳の母なのです。三大幸福論のバートランド・ラッセルも同じようなこと(1日4時間)を主張しました。
また、現実に工場で働くことでその過酷さを体験した哲学者がシモーヌ・ヴェーユです。ヴェーユは労働によって友愛の絆が生まれることを認めつつも、工場労働がいかに働く人々の人間性を押しつぶすものであるのかを主張しました。ただし、ヴェーユの言うように全て工場労働が過酷なものであるとも限りません。ヴェーユが働いていた時期はフレデリック・テーラーが主導したシステム―テーラー方式が最盛期となっていた時期であったことと無関係ではないでしょう。
テーラー方式は効率的であることを最優先した結果、労働者からあらゆる自発性と仕事への生きがいや誇りを奪うものになっていたのです。このテーラー方式を採用して大量生産のシステムを確立したのがアメリカで自動車王と呼ばれたヘンリー・フォードです。
フォードはライン方式を導入したフォーディズムによる自動車の生産方式を確立しました。フォーディズムではテーラー方式のように作業を分解して円滑に作業させただけでなく、当時としては異例ともいえるような高い賃金を労働者に支払うことにしたのです。フォード社の労働者はそれまで購入できなかった自動車を購入できるようになり、それが自動車の市場を爆発的に拡大することにも貢献しました。アメリカ的な生活様式は世界の注目を集め、憧れを生むことにもつながりました。これがアメリカの軍事的な覇権を支える文化的な背景となっていったと考えられます。
しかし、やがてフォーディズムは大きなインフレと景気の後退を招くことになります。そんな中、労働者の自発性を奪うという欠陥を是正した新モデルが日本で採用されます。1980年代のトヨタ方式は労働者の自発性を高めることで生産性を向上させたのです。また、スウェーデンのセル生産方式も高い離職率を抑えることに貢献しました。このように、テーラー方式のように労働意欲を削るような労働方式では生産性を高めることができないことが明らかになっていくのです。
近代の労働観がどのような変遷をとげてきたのか理解できたでしょうか?あまりに長く難解なところもあったかと思うので、ぜひ繰り返し確認してみてください。
6 現代の労働
現代の労働について、まずは「家事労働」について考えてみたいと思います。かつて、生活の自立を目指すために女性が家庭の仕事をするのはごく一般的なことでした。しかし、フェミニズムでは、女性の家事労働に対しても賃金の支払いを要求しました。なぜなら、資本主義の社会では、商品の生産をする労働だけが仕事になっていたからです。賃金が支払われる労働だけが仕事であって、自立的な活動は無価値とされてしまうのです。
このような、賃金の支払われない労働を「シャドウワーク」という概念で表現したのがオーストリアの文明批評家イヴァン・イリイチです。イリイチはシャドウワークと対になる賃金が支払われない労働として、「ヴァナーキュラー」(家庭でのみ使用される)という概念を用いました。かつて行われていたようなヴァナーキュラーな仕事であればそもそも労働とは考えられず、賃金を要求するシャドウワークの登場は資本主義が到来したことと無関係ではないのです。つまり、近代における労働観の変化の帰結がフェミニズムの誕生だったとも考えられます。
また、労働を「肉体労働」「精神労働」だけでなく「感情労働」に分類して考えたのがアメリカのフェミニスト社会学者アーリー・ラッセル・ホックシールドです。肉体労働はものを運ぶ仕事など、精神労働は経理などのデスクワーク、そして感情労働には航空機の客室乗務員などが想定されています。肉体労働や精神労働を笑顔で行わなければいけないわけではありませんが、感情労働(客室乗務員)では笑顔でいることも仕事の1つであるといえるのです。そのため、感情労働では自己の感情を否定したりごまかしたりすることを求められます。その結果が、これだけ多くの精神疾患を生み出す原因となっているのかもしれません。
ほかに、「依存労働」という概念を提起したのはエヴァ・フェダー・キティです。依存の問題は身体的・精神的にある種の能力を欠く幼児や高齢者など、自律して生きていけない人が他者の労働に依存しなければならないという点にあります。そこには生活できないから他者の労働に依存するという支配関係だけでなく、生計を維持するためにこの労働に依存するという支配関係の問題が隠れています。また、依存労働には、特有の道徳的な問題も含まれていることから目を背けてはいけません。一度だけの善意の援助を行うことはそれほど難しくないとしても、それが毎日のことであれば相手の要請を受けることも拒むこともストレスとなるのです。広義の依存労働は感情労働でもあるという点を忘れてはいけません(その最悪のケースの1つが日本でも起きたあの事件だといえるかもしれません…)。
最後に、AIの発展が現代の労働にどのような影響を及ぼすのかについて考えてみましょう。AIの誕生によって数年後には多くの仕事が人間の手を必要としなくなるとされています。ロボットの第一の利用分野には、人間の肉体労働を代替するものが考えられます。第一世代の工場の生産ラインや第二世代のセンサー機能があるロボットだけではなく、第三世代の人間が作業できない環境(海底や宇宙)で活動するロボットが開発されています。また、ドローンによる点検や配送、Amazonの倉庫内などにある自動フォークリフト、ガンダムのような人間の機能を拡張するロボットなどがあげられるでしょう。
第二の利用分野には、人間の精神労働を代替するものが考えられます。チェスや将棋のAIはすでに人間の能力を上回っているとされ、銀行のコールセンターや医療の診断にもAIの判定が導入されていくようになるでしょう。
第三の利用分野には、人間の感情労働を代替するものが考えられます。高齢者の養護施設では話し相手となるロボットが成果をあげているといわれています。
いっぽう、AIが活用されることで多くの仕事が人間の手を離れることも危惧されています。AIが代替できるような単純作業に携わる人たちから次第に仕事が奪われていくのです。そのため、AIに判断させるにはコストがかかりすぎる煩雑な仕事として「ブルシットジョブ」という概念を提唱したのが人類学者デヴィット・グレーバーです。
自動化の後に残る非人間的なブルシットジョブには次の5つがあると言われています。1つ目は上司や顧客の機嫌をとるためだけの「取り巻き」、2つ目は他人を脅したり欺いたりする「脅し屋」、3つ目は発生したバグや欠陥を修正せずに取り繕うだけの「尻ぬぐい」、4つ目はやっていないことをやっていると主張する「書類穴埋め人」、5つ目はブルシットジョブそのものを作り出す仕事をする「中間管理職」。どれも自動化することはできないもの、すなわち人間の感情に関わるばかりですよね?私たちはAIを利用した先に訪れる未来について目をつぶるわけにはいかないのです。
7 まとめ
今回の動画は「哲学者は労働をどのように考えてきたのか」について解説してきました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだたくさんありますので、ぜひ本書を手に取って詳しく読んでみてください。
人間はただ生計を維持するためだけに労働をするのではなく労働という営みを通して新たな技術と新たな自己を作り出してきました。このような技術の発展について、人類は歴史上3度の技術革命を経験しています。新石器時代の農業革命、近代の産業革命、そして現代の情報革命です。農業革命は豊かな社会と文明をつくり、産業革命は人間の生活は大きく向上させました。情報革命によるAIの誕生は人間の可能性を超越するものとなるかもしれません。
いっぽう、労働という視点から見たらこれらの革命は多くの問題も引き起こしてきました。農業革命による定住は階級的な不平等を生み、労働の成果が国家に搾取されたのです。また、産業革命によって機械が人間を使うような事態がもたらされました。そして、情報革命によっていよいよ人間は機械に仕事を奪われるようになるのです。
「働くとはどういうことか?」をあらためて考える必要性に気づいてもらえたと思います。今回は人類の誕生から現代に至る系譜の中で「労働とは何か?」について考えてきました。いまの自分の労働観が必ずしも当たり前のものではなく、どのような歴史的な文脈の中で培われてきたものなのかを知ることができましたか?
「哲学は役に立たない」「哲学は何も生み出さない」と思われるかもしれませんが、さまざまな哲学者たちの議論を知ることがきっと労働を考えるきっかけになったはずです。情報革命が私たちの労働にどのような影響を及ぼすのかはまだまだ未知数です。ぜひ、これからも「哲学の補助線」を引いて「労働」について考え続けてみてください。(個人的にはラファルグの「怠惰の喜び」が実現してほしいと思うのですが…)
ぜひ、皆さんの感想をコメント欄で教えてください。

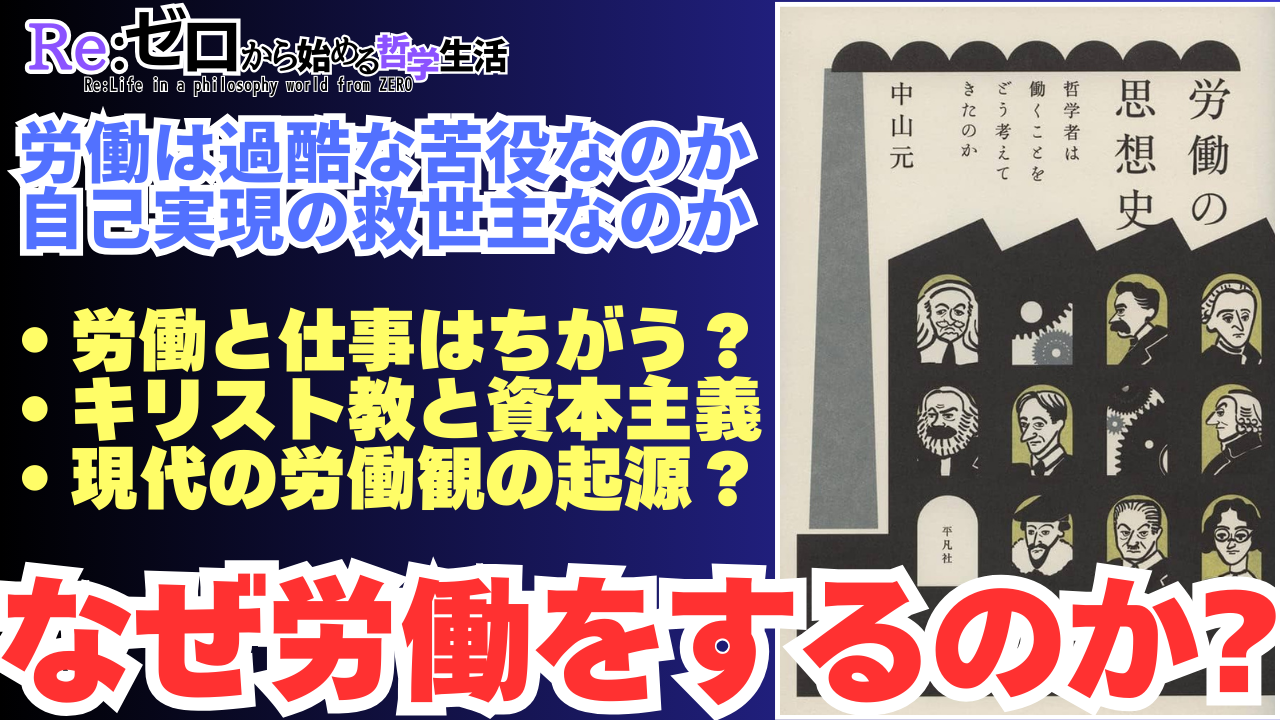
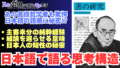
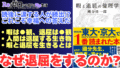
コメント