今回は「哲学を学びたいけどはじめの一歩が踏み出せない」人のためのものです。ステップに応じて5つの参考文献を紹介したいと思いますのでご期待ください。
最近、哲学がいろいろな場面で注目されていることをご存じですか?哲学は答えの出ない問題を延々と考えているだけで、実生活やビジネスには何の役にも立たないと思っている人も多いのではないでしょうか?しかし、欧米のビジネス界では哲学者が大手企業のコンサルをすることも多く、Googleやアップルでは専属の哲学者をフルタイムで雇用しているそうです。
なぜ、哲学や思想を学ぶ必要があるのでしょうか?それは固定観念を破るための方法を知ることができるからです。固定観念とはその時代の人にとってあまりに常識的なものとなっているので、それを疑いもせず正しいと信じている人には何が固定観念なのかも自覚できないのです。だからこそ哲学や思想を学ぶことで何が固定観念なのか?を見つけることができます。そして、固定観念を見破る方法とそれを解決するための新しい方法を提示できるのです。
『暇と退屈の倫理学』の著者である國分功一郎さんは劇作家ブレヒトの言葉「英雄がいない時代は不幸だが、英雄を求める時代はもっと不幸だ」に対して「哲学のない時代は不幸だが、哲学を必要とする時代はもっと不幸だ」と述べています。哲学が必要とされるこの時代に哲学の教養を欠いては幸福になることなどできないのです。
話題となった『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』においても、VUCAの時代ではこれまでのような論理だけにもとづいた思考ではなく直感的に「真・善・美」を判断することができる哲学の素養が求められるとされています。
また、フランスでは高校3年生が哲学を必修科目として学んでいて哲学がそれまで学んできた知識の内容をより深く理解するための教養とされているのです。そして、民主主義の社会において理性によってものごとを考えて、自分の考えを発表したり行動したりすることのできる「市民」を育てようとしているのです。
日本では2022年から新学習指導要領のもと高校生でも「公共」という科目が新設されて、2025年には大学入試共通テストで「公共・倫理」として出題されるようになりました。これからは、哲学こそが私たちにとって必須の教養になるということなのです。
しかし、哲学を学びたいけど何から始めればいいのかわからない…このように思っている人も多いのではないでしょうか?そこで、今回は「哲学を学びたい」と考えている人に5つのステップを紹介します。この5つのステップを順番に踏むことで誰でも哲学の基礎を身につけることができます。
まず、1つ目と2つ目のステップでは「哲学の面白さ」を感じてほしいと思います。哲学のことを全く知らなくても、とにかく「哲学って面白い!」と感じてほしいのです。3つ目のステップでは、哲学の全体像をつかんでほしいと思います。およそ2500年にも及ぶ哲学の歴史の全体像をつかむことで哲学がどのように誕生して、どのように発展してきたのか、そして、哲学がこれからどのように必要とされていくのかを理解できるようになります。全体像を理解することができれば、興味のある時代や推し哲を見つけることもできますよ。4つ目のステップでは、哲学の実用性を知ってほしいと思います。哲学はそれぞれの時代において常に決定的な役割を果たしてきました。哲学こそが時代を動かしてきたといっても過言ではありません。ここまで来れば、もう「哲学は何の役にも立たない」とは口が裂けても言えないでしょう。最後に、5つ目のステップでは、「哲学の補助線」を引けるようになってほしいと思います。哲学の教養があれば、それまで気づけなかったことにも自然と目を向けることができるようになります。
このチャンネルでは、それを「哲学の補助線を引く」と表現しています。哲学の教養を身につけて補助線を引くことができるようになると、こんなにも世界を見え方が変わるのか!ということを実感して頂けると思います。
古代ギリシアのソクラテスは「哲学の目的はよりよく生きることである」と言いました。ものごとの本質がわかるようになれば、正しい判断ができるようになるということです。ぜひ、新年度を迎える今こそ、哲学を学ぶためのはじめの一歩を踏み出してください。
ちなみに、それぞれのステップでは参考となる本も紹介しています。読書をする時間がないという人には、Amazonオーディブルがおすすめです。
1 『その悩み、哲学者がすでに答えをだしています』
まずは、何より「哲学って面白い」ということを感じるところから始めてほしいと思います。そこで、絶対におすすめできるのが『その悩み、哲学者がすでに答えをだしています』です。内容はさまざまな悩みについて哲学者が答えるというものです。実は、私もこの本を読んだことがきっかけで哲学の世界に入ることになったのです。
今から約3200年前のエジプトで書かれたパピルスには実在したある人物の人生が詳細に記述されていました。書記という仕事に就くために勉強したことや17通の愛の詩を送ったこと、そして、書記となって墓作り職人の監督をした時に部下の出勤簿を管理したことなどです。しかし、そこには「誕生日だから休む」「二日酔いだから休む」という欠勤理由から、口うるさい上司に対して「上司にはさからわない」「ためになることもある」のような部下である自分に言い聞かせているような苦悶の言葉が残されていたのです。おかげで不真面目な部下と口うるさい上司の板挟みにあい不眠に悩まされていたようです。
紀元前に生きていた人々も現代人である私たちも、人間はいつの時代であっても同じような悩みをもっていたことがわかります。このような悩みに真っ向から挑み、思考することのみによってその解決の糸口を見出してきたのが偉大な哲学者たちなのです。
「やりたいことがあるが、行動に移す勇気がない」という悩みには大陸合理論の哲学者ルネ・デカルトが答えを出してくれます。
「自分のルックスに自信がない」という悩みには実存主義の哲学者ジャン=ポール・サルトルが答えを出してくれます。
「パートナーとケンカが絶えない」という悩みにはドイツ観念論の哲学者ゲオルグ・W・F・ヘーゲルが答えを出してくれます。
本書に登場する哲学者たちはいずれも超がつくほどの有名人ばかりです。もちろん、哲学者に関する予備知識などは全く必要なく楽しむことができる内容です。誰にとっても共感できるさまざまな悩みに対して「そんな考えがあるんだ」「そうか、こう考えればいいんだ」と思うことができますよ。哲学を始めるための最初の一冊はこれで決まりといえるほど面白いのでぜひおすすめです。読書をする時間がない場合は本書を参考文献にしたこれらの動画をぜひご視聴ください。
2 『自分とか、ないから』
『その悩み、哲学者がすでに答えをだしています』には、西洋の哲学者が多く登場します。しかし、「東洋哲学だって面白い」ということも実感してほしいと思います。そこで、絶対におすすめできるのが『自分とか、ないから』です。2024年に出版されてこれまでに10万部をこえるベストセラーになっている本です。
著者のしんめいPさんは東大に合格して就職・結婚したもののその後「職」「家」「嫁」を失って実家でひきこもる生活をしていたそうです。そして、いろいろな書籍を読み漁った末の最後に辿りついたのが「東洋哲学」でした。「東洋哲学」のいいところは「どう生きればいいのか」をテーマにしているところです。つまり、きちんと「答え」が用意されているということです。
哲学には「答え」はないと考える方も多いかと思いますが「東洋哲学」にはあるのです。本書では東洋哲学を代表する7人の哲学者について紹介されています。
「教室のはしっこで窓の外を見つめているタイプ」のブッダ
「クラスメイトや先生をどんどん論破する面倒なやつタイプ」の龍樹
「そもそも教室にいないで校庭で草と同化しているタイプ」の老子と
「学校に一度も来たことがない不登校タイプ」の荘子
「無言で壁に向かって座り続けるタイプ」の達磨
「テストでわざと0点を取り続けて退学になるタイプ」の親鸞
これだけ聞けばとんでもない陰キャばかりで「東洋哲学って大丈夫?」と心配になりますが、「クラスの中心にいる人気者のタイプ」の空海も登場するのでご安心ください。インドでは、ブッダが「自分なんてない」、龍樹が「この世はフィクション」と言いました。中国では、老子と荘子が「ありのままが最強」、達磨が「言葉はいらねぇ」と言いました。日本では、親鸞が「ダメな奴ほど救われる」、空海が「欲があってもいい」と言いました。
いずれも、「え、どういうこと?」と思われるものばかりですよね。しかし、著者のしんめいPさんは、東洋哲学に出会ったことがきっかけで、全てを失って家に引きこもるという虚無感から脱出することができたのです。哲学書なのに圧倒的に読みやすく気づいたら声を出して笑ってしまうほど面白い一冊です。読書をする時間がない場合は本書の解説をしているこちらの動画をぜひご視聴ください。
3 『史上最強の哲学入門』
この2つをクリアすることができれば、哲学の面白さにふれることはできたと思います。そこで、3つ目のステップでは、哲学の全体像をつかんでほしいと思います。おすすめの本は『史上最強の哲学入門』『史上最強の哲学入門-東洋編-』です。
なぜ、表紙があの有名な哲学書「グラップラー刃牙」風のイラストなのかといえば、著者の飲茶さんがこれまでの哲学入門書に足りなかったものこそが「バキ」分(強い論を求めて知を戦わせた男たちの情熱の物語)であると考えたからです。つまり、哲学とは絶対的真理への到達を目指した哲学者による知の極限バトルなのです。
「哲学者入場!」というかけ声のもとユニークな二つ名によって哲学者が紹介されます。
・国家は王のもの、邪魔する奴はリヴァイアサンで殴るだけ!ホッブズ!
・実存だったらこの人を外せない、超A級反逆児キルケゴール!
・ダメ人間が帰ってきた、お尻を出した子一等賞!ルソー!
・神殺しは生きていた!超人ニーチェ!という具合に…(わくわくしてきたでしょ?)
ところで、『史上最強の哲学入門』には西洋哲学編と東洋哲学編があるのですが、実はこの2つは全く異なるものであるといえます。西洋哲学はとても難解ではあるものの、理解ができないものではありません。しかし、東洋哲学は、そもそも理解をすることが不可能なものなのです。なぜなら、西洋哲学が真理を目指して「階段」を上るように少しずつ発展しくのに対して、東洋哲学はいきなり「真理に到達した(悟った)」というところから始まります!そして、後世の人はそれをさまざまな解釈で伝えていくという「ピラミッド」型なのです。
ちなみに、著者の飲茶さんは哲学とは「考えるのって楽しい!」が知れる学問だと言います。そして、哲学の定義として①フィロソフィー(知を愛する)②メタフィジックス(考えることで物質の新しい法則や本質に気づく)③新しい概念(言葉)を創り出す活動、の3つを紹介されています。哲学を学ぶことで新しい生き方や価値観をもつことができるようになるということです。
YouTubeでも多くの方が取り上げているほど面白い哲学を学ぶための最強の1冊です。でも、これに関しては絶対にオーディブルで聞くことをおすすめします。読み手の方の声と内容があまりにマッチしすぎているので爆笑せずに聞くのは不可能です。
4 『世界をアップデートする方法』
哲学の面白さを知り、哲学の全体像を理解できた後は哲学の実用性を知って頂きたいです。そこで、おすすめの本が『世界をアップデートする方法』です。哲学と聞くと何の役にも立たないと思われることもあると思いますが、この本を読めばいつの時代も哲学こそが世界を動かしてきたことがわかるはずです。
ソクラテスは「産婆術」という対話法によって誰もが思考を深める手法を確立しました。ソクラテスが破壊した当時の常識は「天才だけが知識を独占する」ということでした。そして誰であっても知識を生み出せることを産婆術という対話法によって示したのです。
また、ソクラテスが「対話」によって知識を創造したのに対してアリストテレスは「観察」によって新しい知識を増やしていく方法を明確にしました。博物学、倫理学、政治学、論理学、心理学などあらゆる学問を体系化したことから「万学の祖」と称えられ1000年後には天動説を打ち砕くきっかけにもなっています。
近代では、デカルトが全てを疑い思考を再構築することで教会の呪縛を解き放ちました。これまで絶対とされたキリスト教の教えが宗教改革によって大きく揺らいでいた時代です。そんな時代にデカルトはものごとを理性によって合理的に考えることを提案したのです。そして、あらゆるものを疑ったとしても疑えないものがあることを見つけたのです。それが疑っている自分の存在があることだけは疑えないということです。これが哲学界で最も有名な命題「我思う、故に我あり(コギト・エルゴ・スム)」です。
また、ルソーは民主主義というアイデアによって権力者が支配する世界を一変させました。この時代のヨーロッパでは権力者が統治する「絶対王政」が当たり前とされていました。そのような時代にルソーは1人1人の国民の意志が統合されることによって、その国家の方針が決まるという民主主義を構想したのです。今日、私たちが民主主義の社会で生活できるのはまぎれもなくルソーのおかげなのです(もちろん、社会主義を提唱したマルクスもいるのでそれはそれなのですが…)
このように、哲学者たちがいかに世界をアップデートしてきたのかを知ることで哲学の有用性がしっかり理解できるはずです。おすすめは「キリスト教の常識を破壊した究極のエロ本『デカメロン』」の部分です。読書をする時間がない場合は本書の解説をしているこれらの動画をぜひご視聴ください。
5 哲学の補助線
4つのステップをクリアできれば、既に哲学の基礎を十分にマスターできているはずです。そこで、最後に「哲学の補助線」を引けるようになってほしいと思います。哲学の教養を身につけて「哲学の補助線」を引くことができるようになると、世界を見え方がそれまでと全くちがうものになることを実感して頂けると思います。実際に、以下のマンガや小説を読んでみることでそれがわかるかと思います。
5-1 『チ。-地球の運動について-』
まずは、簡単なものとして『チ。-地球の運動について-』がおすすめです。
紀元前アリストテレス以来、地球が宇宙の中心である(天動説)という考え方が常識でした。「天動説」は各地域の常識となってその後1500年間にわたる不動の定説だったのです。しかし、天動説を覆し「地動説」を提唱したのがポーランドの天文学者コペルニクスです。その後「地動説」はガリレオ=ガリレイが観測したことによって実証されました。そのため、現在では「地動説」を誰もが当たり前のこととして理解しているのです。
この「地動説」をテーマにした作品こそが『チ。-地球の運動について-』なのです。2020年から2022年までビックコミックスピリッツで連載(完結)されて、2024年10月よりNHK総合でもアニメが放送されて今とても話題になっています。(2022年には「手塚治虫文化賞」マンガ大賞を受賞されています)。
『チ。』は地動説がテーマの作品なのですが、作中には多くの哲学者の思想が登場します。第1章のラファウ編では、「死」について考える場面が描写されています。ソクラテス曰く「誰も死を味わってないのに誰もが最大の悪であるかのように決めつける」エピクロス曰く「我々のある所に死はない、死のある所に我々はない」セネカ曰く「生は適切に活用すれば十分に長い」のように3人の哲学者が引用されます。
第3章のドゥラカ編では、「資本主義と共産主義」について考える場面が描写されます。政治学や経済学も元をたどれば哲学から派生していったものであり、アダム・スミス、マルクス、ケインズ、そしてロバート・ノージックなどが有名です。資本主義と共産主義の功罪がどちらもさりげなく登場するこの場面も「哲学の補助線」を引いて考えることができるようになると、現代の社会に置きかえてピンとくるところがあるのではないでしょうか?
また、異端解放戦線のメンバーであるシュミットという人物も出てきます。シュミットは「自然主義者」を名乗り人の手でつくられたものを否定するのですが、〈シュミット〉と〈自然主義者〉と聞けば、ドイツの政治学者カール・シュミットとデカルトと同じ大陸合理論の哲学者バールーフ・デ・スピノザです。登場人物のモチーフがわかると物語をより多面的に理解することができるようになります。
そして、『チ。』の中では何度もプラトンとアリストテレスが対比して登場します。ラファエロの名作『アテナイの学堂』の中心にいる2人の哲学者こそがプラトンとアリストテレスなのです。
さらに、最終章では「タウマゼイン」という言葉が登場します。これは知的探求の原始にある「驚異」のことであり、この世の美しさに痺れる肉体のこと、そこに近づきたいと願う精神のことです。真理の探究において最も重要なことは自分の直感と世界の絶美を信じることです。「タウマゼイン」こそが人類を真理の探究へと導いてきたといっても過言ではありません。『チ。』は地動説をめぐる人間たちの「タウマゼイン」を軸にした壮大な物語なのです。
5-2 『ペスト』
次に、アルベール・カミュの『ペスト』にもチャレンジしてみてほしいと思います。
2020年2月27日に新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため安倍晋三首相による突然の小中学校休校宣言が全国一斉に出されました。緊急事態宣言によるステイホームや不要不急の外出を自粛することを求められるなど、それまで当たり前とされていた日常は大きく変わることを余儀なくされたのです。教育現場では学習のオンライン化への対応や部活動の大会中止など大きな影響が出ました。医療現場では医療従事者への過度な負担やワクチン対応への騒動などが問題となりました。それぞれの国がそれぞれ独自の対応をしたことも社会情勢を混乱させる要因になりました。
あれから5年、私たちはそれがなかったことであるかのように日常をすごしています。あの時どんなことが起こっていたのか?いまどんなことが起こっているのか?「哲学の補助線」を引くことで少し高い視座からあの出来事の本質を捉えられるでしょう。
『ペスト』は第二次世界大戦中のヨーロッパでアルベール・カミュによって執筆されました。実存主義の哲学者でもありノーベル文学賞を受賞している作家アルベール・カミュは不条理な運命を前に人間はいかに生き抜くべきかというテーマの作品を多く残しました。『ペスト』はカミュが戦時中のナチス占領下という状況において執筆された作品であり、そこで実際に起こっていたことへの隠喩(メタファー)だといわれています。
『ペスト』には私たちを抑圧するものに対する「反抗」を通して私たちがどのように「自由と連帯」を獲得していけばよいのかが描かれているのです。100ほど前に書かれた作品にもかかわらずそこで描かれていることは、新型コロナの影響によって日常を奪われた私たちの姿と酷似するものばかりでした(実際に当時は『ペスト』を手に取って読む人が多かったようです)。
ロックダウンされた都市から脱出しようとする新聞記者はそれを拒む医師に「個人の幸せを考えていない」「抽象の世界にいる」と断罪します。また、教会の神父は「信心深さが足りないせいでペストに見舞われた」と説教します。自分には関係ないと勝手な行動をする者やパニックになって自暴自棄になる者など現実にも同じような現象が起きていたことに何度もはっとさせられることでしょう。
ペスト、新型コロナ、自然災害、ナチスなどの暴力…
「不条理」はまたいつか(すでに?)、私たちのことをおそう日が来ることでしょう。その時、自分にできることは何かという想像力を『ペスト』を読んで高めておいてください。難解な内容ですので、まずは本書の解説をしているこちらの動画をぜひご視聴ください。
5-3 『パンとサーカス』
最後に、長編小説『パンとサーカス』にチャレンジしてみるのはどうでしょうか?
タイトルにもある「パンとサーカス」とは古代ローマの独裁者がローマ市民にパン(食料)とサーカス(見世物)を提供することで、ローマ市民を満足させて政治的無関心にしたという逸話がもとになったものです。このような市民の批判精神を曇らせて問題を市民の意識から隠蔽する独裁者の政治手法を「パンとサーカス」と表現して現在では愚民政策の比喩として用いられているのです。
なぜ、これが本書のタイトルに選ばれたのでしょうか?それは、まさに現在の日本がこのような状況に置かれているからにほかなりません。作中で中国諜報機関のスパイであるミュートという人物が次のように言います。「日本が集団的自衛権を行使できるようになったからといって米国は何もする気はなく、リゾート気分で日本に駐留して費用を日本に負担させてさらに増額を要求するだけです」「有事の際は日本を守ると曖昧にリップサービスをするだけで、アメリカは何1つ具体的な戦略を示してこなかった」
日米関係におけるこの見立てを、ただの小説の妄想だとあなたは断言できるでしょうか?本書の中には哲学のエッセンスがふんだんに盛り込まれています。「哲学の補助線」を引いて読むことができれば作品の解像度はうんと上がることでしょう。
物語の概要を簡単に紹介すると、高校時代2人で秘密サークル「コントラ・ムンディ」を作った御影寵児と火箱空也。寵児は米国留学を経て中央情報局(CIA)エージェントとなって帰国、空也は父の知人の人材派遣会社で働く中で大物フィクサーから「世直し」を提案されます。
政府要人の暗殺をきっかけに事件の解明を求められる寵児でしたが、その矢先、ドローンによる国会議事堂や横田基地への自爆攻撃が行われてしまいます。テロリストの首謀者として追われる身となった空也。大物フィクサーと自分の上司が裏で通じていたことに気づく寵児。ありえないと思われていた政権交代が起こるものの命を狙われることになった空也と寵児。日本を舞台にした壮大な物語は、どのような結末を迎えることになるのでしょうか?
「私の暴走にどうかお付き合いください」
著者の島田雅彦さんはこのように言いますが、これをただの妄想だと一蹴するのか。これこそが真実であると感じるのかはあなた次第です。登場人物はのべ50人以上で500ページにも及ぶ長編にもかかわらず、読み始めたら手を止めることなく最後まで一気に読まずにはいられない本作ですのでオーディブルと合わせて本書の解説をしているこちらの動画をぜひご視聴ください。

6 哲学の世界へ
ここまで、5つのステップを紹介してきました。これから先は、あなたの興味に応じてさらに深くまで哲学の世界を探検してみてください。本チャンネルでは、大きく「ビジネス」と「悩み」に分けて哲学を紹介しています。「哲学×ビジネス」では、哲学とビジネスの関係を掘り下げた内容が多いです。
たとえば、「論理的思考」(ロジカルシンキング)をご存じでしょうか?ロジカルシンキングは、もともと哲学の思考方法からヒントをえているものなのです。一般的なルールや法則にものごとを当てはめて結論を導き出す「演繹法」、複数の事実から一般論等のルールや法則を導き出す「帰納法」、対立する2つの物事を組み合わせることでより良い結論を導き出す「弁証法」などです。詳しくはぜひこちらの動画をご視聴ください。
いっぽう、近年そのロジカルシンキングよりも重視されているのが直感なのです。なぜならVUCAの時代においてはこれまでのような論理だけにもとづいた経営ではなく直感的に「真・善・美」を判断することができる哲学の素養が求められるのです。ドイツ観念論のイマヌエル・カントは、理性と感性の問題について『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』という著書をのこしましたが、これら3つの著書こそがそのまま「真・善・美」について考察したものとなっているのです。それを解説した本が『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』です。
「哲学×悩み」では、哲学を実生活に役立てるという内容が多いです。『その悩み、すでに哲学者が答えを出しています』のほかにも、ひぐちまりさんの『人間関係×哲学思考-頭のモヤモヤを32人の哲学者が答えていく-』や小川仁志さんの『哲学を知ったら生きやすくなった』『運を哲学する』などがあります。
また、2025年からは「大学入試共通テスト」講座も定期的に配信する予定です。受験生にとって定期テストや入試に役立つことはもちろん、哲学をビジネスや日常生活にも活かせる一般教養として学べる内容にしたいと思います。(実際に哲学を好きに学んでいただけで共通テストで80点は取れるようになりました)哲学を学んでいきたいという方はぜひこのチャンネルの動画を見て頂ければと思います。
7 まとめ
今回の動画は「哲学を学びたいけどはじめの一歩が踏み出せない」をテーマにしました。この5つのステップは実際に自分が哲学を学んできた足取りそのものでもあるので、まさに本当の「ゼロから始める哲学生活」だと言っても過言ではありません。
「不正解は無意味を意味しない」
「地動説が異端かどうかは時の権力者の裁量によって変わる」
「迷いの中に倫理がある」
これは『チ。』の中に出てくる大好きな言葉なのですが、作中には「この世は非道徳的なことで溢れている。そんな世界を変えるために何が必要か?」と問うたバデーニが「知」と答える場面があります。
これまで、正しさを主張するため暴力によって罪なき人々の血が流れてきました。大航海時代の植民地支配、アメリカ大陸の制服、ナチスによるホロコーストなどなど。いずれも「絶対に正しい」とされていることを盲信した結果が引き起こした悲劇です。私たちは「絶対的正義」を掲げた時に恐ろしいほど残虐なことを可能にしてしまうのです。
しかし、人類は「知性」によってそれを乗りこえることを忘れませんでした。古代ギリシアでは考えることのみで物質の最小単位が原子であること、また、地球がういていることや丸い形をしていることをもつきとめたのです。
中世では民主主義という思想によって絶対王政の常識を破壊することも達成しました。苦しみを味わった知性はいずれ十分に迷うことのできる知性―暴走した文明に歯止めをかけて異常な技術を乗りこなせる知性になります。私たちは何が正しいのかわからないからこそ「迷う」ことが大切なのです。私たちは「迷う」ことでしか倫理を見つけることはできないのです。だからこそ、その答えをこれからも一緒に探していきましょう。
本日の旅はここまでです、ありがとうございました。




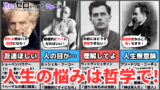
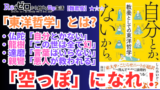




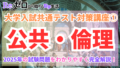
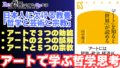
コメント