今回は「Re:ゼロから始める哲学生活」源流思想③東洋思想の哲学編を解説します。参考文献は『哲学と宗教全史』(著者:出口治明さん)です。
ポール・ゴーギャンのこの長いタイトルの絵画―『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』をご存じでしょうか?「世界はどうしてできたのか?」「人間はどこから来てどこへ行くのか?」この最も根源的な問いについて考えてきたのが哲学と宗教なのです。
哲学という言葉の起源は「philosophy(愛知)」のことであり、「知(sophy)を愛する(philo)」という意味です。これを明治時代に西周が「賢哲を愛し希求する」という意味で希哲学―すなわち「哲らかにすることを希む学問」になったとされているようです。 つまり、哲学を一言で表すならば「真理を探究する知的営み」ということになります。
「そもそも正義とは何か?」のように「そもそも」を哲かにする学問が哲学なのです。 最近、この哲学の中でも東洋哲学がいろいろな場面で注目されていることをご存じですか?実生活やビジネスには何の役にも立たないと思っている人もいるかもしれませんが、Googleやアップルでは専属の哲学者をフルタイムで雇用しているそうです。
また、東洋哲学のエッセンスでもある坐禅や瞑想をもとにしたマインドフルネスがシリコンバレーやウォールストリートで流行しているのです。東洋哲学のいいところは「どう生きればいいのか」をテーマにしているところです。そして、きちんと答えが用意されているのです。哲学には答えがないと考えているかもしれませんが、東洋哲学にはあるのです。東洋哲学はとにかく楽になるための哲学なのです。
『暇と退屈の倫理学』の著者である國分功一郎さんは劇作家ブレヒトの言葉「英雄がいない時代は不幸だが、英雄を求める時代はもっと不幸だ」に対して、「哲学のない時代は不幸だが、哲学を必要とする時代はもっと不幸だ」と述べています。哲学が必要とされるこの時代に哲学の教養を欠いては幸福になることなどできないのです。 そこで、このシリーズでは「古代から現代までの哲学」を全て解説していく予定です。今回は西洋哲学の原点でもある古代ギリシア(ヘブライズム)の哲学を紹介します。哲学を継続して学ぶことができますのでぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 東洋哲学の源流思想
1-1 ブッダ以前の古代インド思想 -解説編-
インドといえば仏教発祥の地ですが実は現在のインドで仏教徒の割合は多くありません。13世紀のころにはインドにおける仏教はほぼ消滅していたともいわれています。代わりに現在のインドで信徒が多い宗教が「ヒンドゥー教」です。古代インドのバラモン教にもともとの土着信仰が融合して形成されたといわれています。
紀元前15世紀ごろ、イラン北部からアーリア人がインドに侵入してきて、先住民族を支配する中で独自の信仰体系を形成していきました。これは祭祀階級バラモンを頂点とする「カースト制」という階級制度を基盤にしています。バラモンはこの宗教で特権的な存在となっていて、聖典『ヴェーダ』に示される秘儀や神々の声を聴くことができる存在とされていました。
1950年に制定された憲法でこのカースト制は明確に禁じられたのですが現存しています。なぜなら、インド思想の重要な要素として「輪廻転生」という考え方があるからです。輪廻転生とは永遠に生と死がくりかえされるという考え方です。これは単に同じ人生をくりかえすというわけではなく、前世の行い(業=カルマ)によって来世の生まれが決定されるのです。そのため、善い行いをすれば高い身分に生まれることができるいっぽう、悪い行いをすれば低い身分(あるいは動物)に生まれることもあるのです。インドの人にとってカーストがなくならない1つの原因はこのような思想にあるのです。
このような、輪廻転生の運命から逃れ幸福に至る方法として考えられたのが「解脱」です。世界最古の哲学といわれヴェーダの最後に位置づけられた「ウパニシャッド哲学」では、ヨーガなどの修業によって「梵我一如」を悟ることができれば解脱できるとされています。「梵(ブラフマン)」とは宇宙の根本原理で神々をふくむ森羅万象の全てだとされています。「我(アートマン)」とは自我の本体のことでかんたんに言えば魂のようなものです。つまり、「梵我一如」とは宇宙と自我は究極的に同一であるということなのです。
バラモンたちは『ヴェーダ』の権威を絶対化して真理を独占していたのですが、紀元前6世紀ごろから商工業が発達してクシャトリヤやヴァイシャの地位が向上しました。そのため、バラモンの宗教的な権威もだんだんと低下していってしまったのです。そして、『ヴェーダ』の宗教的な権威を公然と否定する自由思想家が登場するのです。それが、ヴァルダマーナやゴータマ・シッダールタたちです。
ヴァルダマーナはジャイナ教の開祖として「マハーヴィーラ」とも尊称されています。ヴァルダマーナはカースト制を批判して徹底的な不殺生(アヒンサー)と無所有などを根本教義とする厳しい苦行による解脱を説きました。ほかにも、真理認識の不可能性を説いた懐疑論者のサンジャヤ・ベーラッティプッタ、自由意志を否定した宿命論的自然論者のマッカリ・ゴーサーラ、道徳否定論者のプーラナ・カッサパ、唯物論と快楽論を説いたアジタ・ケーサカンバラ、七要素集合説(四元素+苦楽命の7つの要素)を説いたパクダ・カッチャーヤナ。このブッダを除く6人の自由思想家たちは「六師外道」と総称されています。
また、修業として現在の健康法でもある「ヨーガ」があげられていましたが、もともとは呼吸を整えて瞑想しながら精神を統一するという宗教的な修業方法でした。アーリア人が侵入する以前からインドで行われていたとされていて、後にバラモン教だけでなくジャイナ教や仏教にも取り入れられていきました。坐禅の原型とされていてブッダはこれによって悟りを開いたとされていることから、仏教の中でも禅宗では特に重視されているものなのです。
2-1 ブッダの教え -解説編-
シャカ族の王子ゴータマ・シッダールタが創始したのが仏教です。仏教とは仏になる(成仏する)ための教えのことなのです。そして、仏(仏陀)とは、「悟りを開いたもの」という意味です。つまり、ユダヤ教やキリスト教のように絶対的な神による救いを求めるのではなく、仏教は修業をして仏になる(真理を悟る)ことが究極の目標となるのです。
ブッダは王族として物質的に何ひとつ不自由のない暮らしに虚しさを覚えたことで、29歳で地位と妻子を捨てて出家することで修行者(沙門)になることを選んだのです。そして、6年間の修業の末に成仏(解脱)して80歳で入滅するまで教えを説きました。
ブッダの教えの核心はあらゆるものごとが相互に依存しているということです。このような、何ごとにも原因があって引き起こされると考えることを「縁起説」といいます。たとえば、努力をした(原因)ので大学に合格した(結果)のような因果関係のことです。しかし、大学に不合格だった(結果)時には自分の怠慢(原因)を反省するのではなく、ほかのところに原因を求めてしまうことが往々にしてよくあります。そのため、ブッダは人間の苦悩の根本原因が縁起に対する無知(無明)だと気づいたのです。「人は必ず死ぬ」という根本的な真理と向き合うことができなくなってしまうときに、不老不死のような無理な欲望を抱いてしまうことこそが苦悩の原因となるのです。
煩悩、我執、渇愛の3つはいずれもこのような欲望をあらわす典型的なものといえます。ブッダは悟りに至るためには四諦と八正道が必要であると説きました。四諦とは諦めるという意味ではなく明らかにされたこと―つまり、「真理」ということです。ブッダが悟りを開いた後に行った最初の説法(初転法輪)で説いたのがこの4つの真理です。
「苦諦」…人生は苦しみであるという真理
「集諦」…苦しみの原因は煩悩を抱えてしまうからであるという真理
「滅諦」…苦しみの原因を滅ぼせば涅槃に至れるという真理
「道諦」…そのための正しい道(八正道)によって苦しみの原因を滅ぼせるという真理
正しい修業では「中道」―快楽と苦行の両極端を避けることが大切だとされています。(アリストテレスの過少と過剰を避ける中庸と同じですね)。当時のインドではジャイナ教のように厳しい苦行をすることが大切と考えられていました。ブッダも同じようにしたのですがそれでは悟りを開くことができなかったことから、無益な苦行を明確に批判しているところが仏教とジャイナ教のちがいでもあります。
ブッダは出家者(仏門に入る者)とは別に在家信者(ふつうの人)向けの教えも説きました。それが仏法僧の三宝へ帰依することと五戒を守るという三帰五戒です。仏法(仏の教え)やお坊さんに帰依(信じて頼りにする=信仰)して、殺人、窃盗、みだらな行い、詐欺、そして飲酒をしないようにするということです。
ブッダの教えは膨大な経典にまとめられているのですべてを網羅するのは大変です。そこで、ブッダの教えを簡単にまとめたものが「四法印」です。
「一切皆苦」…人生のあらゆるものは苦しみである
「諸行無常」…あらゆるものは変化・消滅をする
「諸法無我」…永遠不変の実体は存在しない
「涅槃寂静」…煩悩を克服した悟りの世界は安らかである
「法(ダルマ)」とは真理という意味であり四諦と同じく4つの真理を示しています。「一切皆苦」は四諦の苦諦と同じ苦しみがあるということ、「諸行無常」は平家物語の冒頭句でもありこの世の全ては変化して消えるということ、「諸法無我」はウパニシャッド哲学における「我(アートマン)」をも否定するのです。これは「私」という存在の否定ではなく自我が実体であるということを否定しているのです。
無常と無我は縁起を別の言い方で表したものでもあることから「無常無我」こそが仏教の核心的思想であるともいえるのです。ブッダの教えを貫く根本精神は苦悩する一切衆生を救おうとする慈悲の心なのです。
ブッダの入滅後、ブッダの弟子たちの間で教えの解釈をめぐって混乱が起こりました。なぜなら、ブッダは生前に何も書き残さなかったからです(ソクラテスと同じ…)。そこで、弟子たちはブッダの教えを経典にまとめるための会議(仏典結集)を開催しました。その結果、「経・律・論」の三蔵とよばれる仏典がまとめられたのですが、その過程で立場のちがいが表面化するようになってしまったのです。
ブッダが説いた戒律を固辞しようとする保守的な「上座部仏教」と教えを柔軟に解釈しようとした「大乗仏教」とに分裂してさらに細かく分かれていきます。教団分裂後の仏教を「部派仏教」とよび、前者の流れから「上座部仏教」、後者の流れから「大乗仏教」が形成されていくのです。
上座部仏教では自己の悟り(自利行)を重視するため戒律遵守や出家主義の側面が強いです。阿羅漢(修業の完成者)を理想として主に南方に伝播していきました(南伝仏教)。大乗仏教では衆生救済(多利行)を重視するためブッダの慈悲の精神を尊重しました。菩薩(衆生済度を目指す修行者)を理想として主に日本や中国に伝播しました(北伝仏教)。上座部仏教は「小乗仏教」ともよばれることがありますが、これは大乗仏教に対してという意味合いのある蔑称となっているので気をつけましょう。
そもそも、「乗」には悟りの道に至るための乗り物という意味があるのです。大乗仏教ではすべての生きとし生けるものが仏性(成仏の才能)をもっているとする「一切衆生悉有物証」(『涅槃経』)を根本思想としています。大乗仏教では大きな乗り物で悟りの世界へ行こうという平等主義の教えが説かれるのです。
いっぽう、上座部仏教ではひたすら自分の悟りを目指す側面があることから、大乗仏教から見ると独善的(一人用の乗り物)と映っていたのです。仏が「悟りをえた者」であるのに対して菩薩は「成仏を目指す修行者」という意味でした。のちに、大乗仏教では「苦悩する衆生を救済する修行者」という意味になっていきます。そのため、菩薩はそもそも仏ではありませんが、大乗仏教では有力な菩薩はそれ自体が信仰の対象となって仏像などもつくられたのです。(ブッダの次に成仏したとされる「弥勒菩薩」や「観音菩薩」「阿弥陀如来」など)。菩薩を目指すものがなすべきことは「六波羅蜜」とよばれ、布施、持戒、忍辱、精進、禅定、般若の6つがあります。
大乗仏教は数百年かけて『般若経』や『法華経』などの大乗仏教経典を編纂していきました。中でも大乗仏教の理論化に最も貢献したのがナーガルージュナ(龍樹)です。
龍樹は「空の思想」を大成して『般若心経』を理論化したといわれています。実は現代物理学では物質が粒子であると同時に波動でもあると説明しているのです。つまり、物質とはいわゆる「モノ」と言えるのかどうかわからなくなってきたのです。龍樹の空の思想もこの考え方と同じようなものであり、それが『般若心経』の「色即是空 空即是色」(ものごとは空である)ということです。万物を存在しているとも、していないとも言えないものとして相対的に把握するのです。
龍樹のほかにはヴァスバンドゥ(世親)の「唯識思想」も覚えておきましょう。これは私たちが世界で出会うあらゆるものや現象が心の現れであるとする考え方です。心の外の世界などというものはいっさい存在せず、心の奥底にある「アーラヤ識」によって生み出される迷妄にすぎないということなのです。そのため、瞑想(ヨーガ)によって心のあり方を整えれば迷妄も消え去るということです。
3-1 古代中国の思想(儒家) -解説編-
中国思想のはじまりは紀元前の春秋・戦国時代までさかのぼることになります。周王朝が衰退して社会が混乱を極める時代の中で人間や社会のあり方についての指針を示すために登場した思想家たちが諸子百家です。古代ギリシアで自然哲学者たちが、古代インドでブッダが登場した時代と重なることから、20世紀のドイツの哲学者カール・ヤスパースはこの時代を「枢軸の時代」とよびました。
諸子百家を代表する孔子を始祖とする思想家たちのことを「儒家」とよびました。孔子の言行録である『論語』や弟子の思想書『孟子』などで体系化された学問が儒教です。儒学はほぼ同じ意味ですが、こちらは孔子によって始まった学問体系全般のことです。
儒教は孔子より前から中国で重視されていた敬天思想や葬祭などの礼法を大切にする倫理思想・政治思想を示しています。儒教では五経(『詩経』『書経』『易経』『春秋』『礼記』)が根本経典となっていますが、孔子より後には四書(『論語』『孟子』『大学』『中庸』)も根本経典となりました。
孔子は周王朝の封建制を理想の政治として世の中の乱れの原因を礼法の廃れにあると考えてその復興を目指していました。君主と諸侯が血縁関係で結ばれて国全体が和合していた古き良き時代を求めたのです。
孔子の思想の特徴は「仁」と「礼」であらわすことができます。仁とは親愛の情―つまり親しい者への愛が大切だと考えるのです。そして、愛や孝悌こそが仁の基本だと説きました。愛とは自分を偽らないという「忠」と他人を思いやる「如」のことであり、「孝」とは父母によく仕えることであり「悌」とは兄によく仕えることを意味します。つまり、仁とはまごころから他者を配慮することであり、家族を何より大切にするべきであるということなのです。儒家では社会の秩序を整えるために目上の人への敬意をとても大切にしていたのです。
このような内面的なよい心が仁であるならば、目に見える形で実践することが礼なのです。誰かに感謝する時はお礼として頭を下げるものであり、それができない人のことは無礼者とよぶのはここに起源があるのです。孔子は「己に克ちて礼に復るを仁と為す」―つまり、欲望を抑えて礼を実践することが仁である(克己復礼)と述べています。内面的な「仁」と目に見える形であらわれる「礼」の実践は表裏一体の関係なのです。
孔子は理想の社会のあり方として「徳治主義」を唱えました。徳ある君主が政治を行えば人民にもその徳が波及するという考え方のことです。君主は率先して道徳を身につけなければいけないのであり、世の中が乱れているとすればそれは君主の「不徳の致すところ」なのです。
孔子の死後、儒家は仁と礼のどちらを重視するのかによってわかれていくことになります。仁を重視する立場の最大の思想家が孟子、礼を重視する立場の最大の思想家が荀子です。孟子は「人間は生まれつきだれもが善の素質をもっている」と考えました(性善説)。もちろん、素質なのでだれもが善を実現できるわけではありません。そこで、善の素質を四端の心(惻隠、羞悪、辞譲、是非)とよんで修養によって伸ばしていけば仁義礼智という四徳が身につけられると説いたのです。
また、孔子の教えをさらに細かく展開して人間関係に求められる徳を5つに整理しました。父子の「親」、君臣の「義」、夫婦の「別」、長幼の「序」、朋友の「信」です。この中で唯一対等な関係であるのが朋友の「信」です。
孟子の政治思想は孔子の徳治主義をさらに具体的に展開したものとなっています。まず、為政者は武力で天下統一を目指す「覇者」(覇王政治)ではなく、民衆を大切にして徳で天下統一を目指す「王者」(王道政治)であるべきだとしました。王道政治は「天命」(天による命令)にもとづいておこなわれるものであり、君主は天命にかなった人物(=天子)でなければならないと説いたのです。もし、君主が徳を失えば天命にかなった人物に交代させる必要が出てきます。これが「易姓革命」(天命が革まり、王朝の姓が易わる)の思想です。
いっぽう、荀子は「人間は生まれつき悪の性質をもっている」と考えました(性悪説)。そのため、正しい生き方をするには教育によって矯正しなければいけないとしたのです。荀子は人間が欲望や安易な選択に流されやすいことを熟知していたので、社会の秩序を保つためには聖人のつくったルール(=礼)を守るしかないと考えたのです。これが「礼治主義」であり、その教えは弟子の韓非子による「法治主義」に影響するのです。
4-1 古代中国の思想(そのほかの諸子百家) -解説編-
儒学以外の諸子百家では老子と荘子が大成した道家の思想(老荘思想)が重要です。儒家が厳しく自己を律する教えであるのに対して、道家はあわてずさわがず悠然と生きることを目指す教えといえます(ありのままに)。
中国では科挙に合格して立身出世をすることが尊いとされる価値観があるいっぽうで、都市から離れた山奥で気の向くまま仙人のように生きる暮らしへの憧れもあるのです。その究極の境地が老荘思想なのです。
老子は儒家の人為的な道徳を批判して自然と一体化することを説きました。「大道廃れて仁義あり(おおいなる道がすたれたから仁義が生まれた)、知恵出でて大偽あり(知恵が生まれたから大きな虚偽が生まれた)、六親和せずして孝慈あり(家族が不和になったから孝慈が尊ばれるようになった)、国家昏乱して忠臣あり(国家が乱れたから忠臣が尊ばれているにすぎない)」
このように、儒家が大切にする「仁義」「知恵」「孝慈」「忠臣」などは、本当の「道」が失われてしまったから生まれたものにすぎないと指摘しているのです。(生活習慣病が増加した社会で健康食品がもてはやされているようなもので本末転倒…)
老子の説く「道」とは聖人のつくった規範ではなく万物を育む根源的な自然そのものです。自然の世界には善悪などなくすべて必然的な法則(=道)があるだけなのです。そして、老子は道に従わず小賢しい知恵や人為的な価値基準に従って不自然な行為をすることを批判して「無為自然」に生きることを説いたのです。無為とは何もしないということではなく、不自然なことをしないというような意味です。「これこそが道だ!」と名付けてしまうようなものはそもそも本当の道ではないのです。
老子にとって理想の生き方は「上善は水のごとし」の言葉に示されています。水はつねに低い方に向かって流れ誰にでもめぐみをもたらすものです。つまり、人間にとって望ましい生き方は謙虚に誰とも争わないあり方ということです。
老子は儒家ほどではないものの政治思想も残しています。それが「小国寡民」です。大国よりも小さくても自給自足できる程度のつつましい国が理想だということです。老子と荘子の大きな違いは政治のあり方について語っているかどうかという点にあります。
老子の後に登場した荘子は道家を大成させた人物であり相対主義的な世界観を示しました。荘子は人間がもっている善悪や美醜、是非や貴賤などの価値観は、すべて人間が人為的に用意したものにすぎない(万物斉同)と指摘したのです。
「胡蝶の夢」というエピソードでは蝶になった夢から目醒めた荘子が「自分が蝶になった夢を見たのか、蝶が荘子になっている夢を見ているのか」と考えます。これは夢と現実の区別など無意味なことであるのだから、あるがままの世界をあるがままに生きればよいという意味なのです。そのため、人間の知恵など有限なのだから何ごとも決めつけるべきではないと言います。「無用の用」といって一見するとムダに思えることも実は有用なこともあり、自然の中に無駄なものや無用なものなど一切ないということを説いているのです。
荘子の唱える万物斉同を認識した理想の人間像を「真人」とよびます。あらゆる区別を超越した自由な存在で自然の理と一体化した逍遥遊の境地に至るのです。このような、道家の老荘思想をもとに中国の伝統的な民間信仰(神仙思想など)が加わって形成された宗教を道教とよぶのです。中国では、儒教や仏教とともに道教が三大宗教として位置づけられています。
儒家と道家のほかには墨家の墨子が重要人物です。墨子はもともと儒学を学んでいたとされています。しかし、儒家の仁が親しい者に限られる愛(別愛)であることを批判して、万人を隔たりなく愛するべきであるとする兼愛の思想を提唱しました。キリスト教と似ているのですが、墨家の兼愛は自己犠牲を説いているわけではありません。皆を愛することでお互いの利益が実現する(交利)という相互扶助の側面があるのです。
また、侵略戦争を否定する「非攻」の思想も提唱しました。ただし、自衛のための戦争は肯定しており、墨家は専守防衛における軍事のスペシャリストだったといわれています。墨子は「1人を殺すのは犯罪なのに戦争で大量殺戮をするのも許されない」と述べました。
荀子の弟子で法律と刑罰によって社会秩序を維持するべきと考えたのが法家の韓非子です。人間の善を実現することは不可能であるとして信賞必罰によってコントロールするのです。法家の思想を取り入れた秦が乱世に終止符を打ち中国に統一王朝を実現させるのです。
それから約1000年後の宋の時代に「新儒学」と総称される2つの潮流が誕生します。それが宋の時代に朱子が創始した「朱子学」と明の時代に王陽明が創始した「陽明学」です。孔孟の教えは人の生き方や世のあり方を説く現実的な訓戒のようなものでしたが、1000年の時を重ねる中で新儒学では自然現象から人間の道徳までを包括的に説明する壮大な哲学理論へと発展したのです。
朱子(朱熹)は宇宙の全てが物質的な様子である「気」と非物質的な原理としての「理」から成り立っていると考えました(理気二元論)。これを人間の心に当てはめると、人間の本来の心(本然の性)は孟子の言うように善です。しかし、現実には肉体(気)をもつのでどうしても欲望に曇ることになります(気質の性)。このように、朱子は心の乱れ(情)を気に由来するものと考えて、善の心(性)こそが理であるとして「性即理」という立場を唱えたのです。
情(気質の性)を清めて性(本然の性)へと復初するためには心を静めて修養する居敬と万物の理をわがものにするという窮理が必要になります。居敬窮理によってあるべき心の状態に復することを目指すのが朱子学であるといえます。このように自分の心を整えることができれば家族も国家も安泰になる―修身・斉家・治国・平天下と朱子は説いたのです。
王陽明は朱子学を学んだ末に心を性と情に分けて考えるのではなく、心をまるごと肯定してそこに理が宿るという「心即理」という立場を唱えました。朱子が万物のあらゆるところに理が宿ると考えたのに対して、王陽明は心の中にのみ宿るものである理を完成させることを目指すべきだと考えたのです。そのためには、生まれつきもっている正しい心(良知)を磨く必要があります。
この時、朱子学のように書物を読むだけでなく実践することが不可欠だと指摘したのです。王陽明は実践することによって良知(=善)が実現することを致良知といいました。陽明学では知ることと行うことはいずれも心のはたらきであり表裏一体の関係なのです。これを「知行合一」といいます。
儒教で重視される四書五経の中で『大学』と『中庸』はもともと『礼記』の一篇でしたが、朱子が別に取り出して『論語』『孟子』と並べて四書と位置づけたとされています。
まとめ
今回は「大学入試共通テスト講座⑤源流思想-古代中国の哲学編-」を解説しました。東洋哲学の原点にして史上最強の哲学の基礎をマスターできましたか?
「哲学は何の役にも立たない」「哲学は難しそうで興味がもてない」そんなふうに思われるかもしれませんが哲学って実はとても面白いんですよ。
このチャンネルでは哲学の面白さを発信していますのでぜひ受験勉強のためだけと思わず、学生や社会人の方にも楽しみながら哲学のことを学んでほしいと思います。
これまで正しさをめぐる暴力によって数えきれない罪なき人々の血が流れてきました。大航海時代の植民地支配、アメリカ大陸の制服、ナチスによるホロコーストなどなど。いずれも「絶対に正しい」とされていることを盲信した結果が引き起こした悲劇です。私たちは「絶対的正義」を掲げた時に恐ろしいほど残虐なことを可能にしてしまうのです。
ポピュリズム全盛ともいえる現代社会もまた倫理なき世界へと逆行している気がします。こんな時代だからこそ「倫理」が必要であり「哲学」が求められているのです。「私たちは迷うことでしか倫理を見つけることはできない」(『チ。』より)ぜひその答えをこれからも一緒に探していきましょう

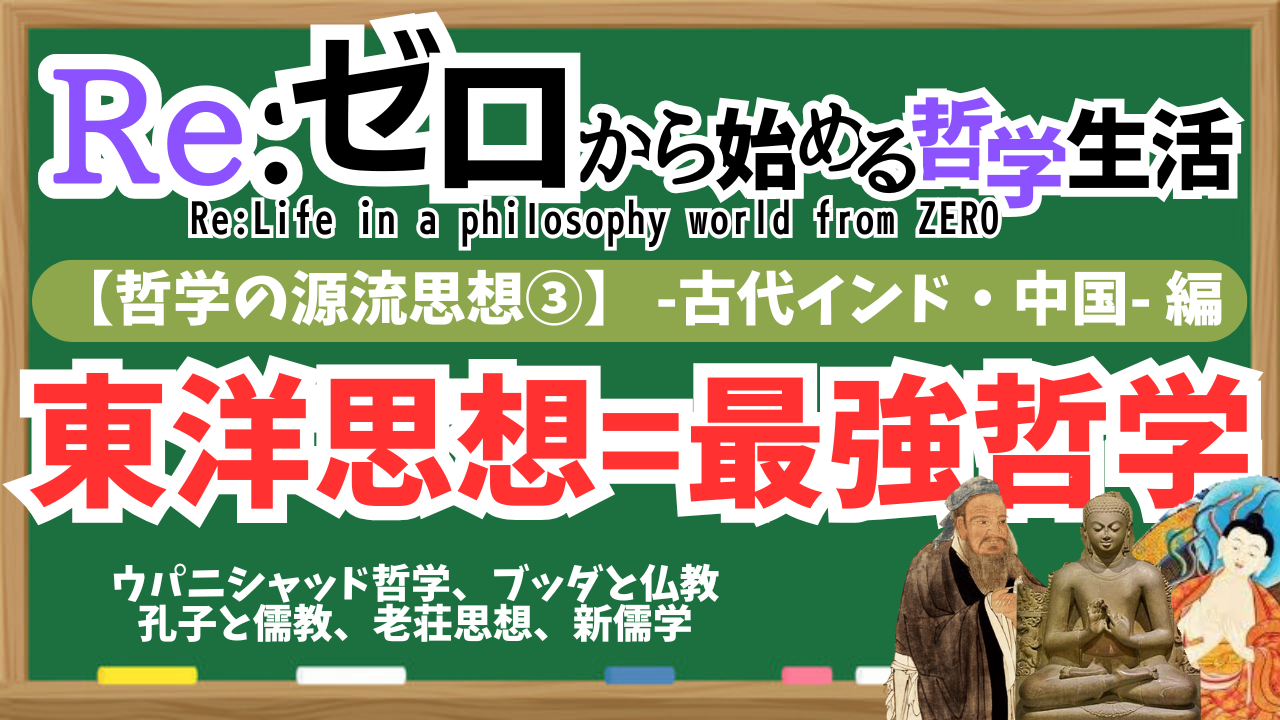

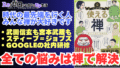
コメント