今回の動画では「大学入試共通テスト2025を完全解説」していきます。正解だけでなくその他の選択肢や関連する語句についても詳細に解説していますので、同類の問題ができた時に対応できるようになっています。
2022年度の高校生からは新学習指導要領による教育課程がスタートしました。そのため2025年の大学入試共通テストでは教科・科目に大幅な変更点があります。
たとえば、これまでの「現代社会」の代わりに「公共」が必修として新設されています。その結果2025年のテストからは「倫理」だけの科目はなくなり、「公共・倫理」という科目を選択することが必要になりました。新学習指導要領における「考察する力」を問うように作成された問題へと対応するためには下記の3つの力が必要になるでしょう。
①前提となる知識 ②主題に基づき、知識を組み合わせて判断する力 ③資料を素早く読み解く力
それを踏まえた上で「公共・倫理」の問題を解説していくと、2022年に示された試作問題と同様に問題構成は大問6つで設問数は全部で33問でした。第1問と第2問は公共分野でそれぞれ「男女共同参画社会」「公共空間の形成」が主題です。第3問から第6問は倫理分野でそれぞれ「源流思想・芸術」「日本の思想」「認知バイアス」そして「戦争と平和」が主題です。配点は「公共」で25点、「倫理」で75点となっています。
全体の概要として、第1問は男女共同参画社会に関する探究活動を題材にした問題でした。男女平等とアイヌ問題についての法整備や平等主義の分類についての知識と読解力が問われる問題となっています。
第2問は公共空間の持続形成に必要なことという題材の探究活動を素材にした問題でした。ユルゲン・ハーバーマスとハンナ・アーレントについての知識や帰納法についての理解と読解力が問われる問題となっています。
第3問は「推し」と芸術というテーマについての会話文をもとに源流思想と西洋近現代思想から広く出題されました。古代ギリシアの哲学者たち、各時代の宗教、科学革命とルネサンスなどセンター試験時代のようなオーソドックスなものが多かった印象です。
第4問は外来思想と日本思想の関わりというテーマの会話文をもとに、神仏習合やさまざまな哲学者・思想家たちについての問題が出題されました。
第5問は認知バイアスを中心とする会話文で心理学関連の問題ではいずれも知識ではなく思考力を求める形式でした。
第6問は戦争と平和についての会話文を題材にして現代ヒューマニズムや人間の安全保障、フランクルの思想などが出題されました。それでは早速2025年の問題にチャレンジしてみましょう。問題文をじっくり考えたいときは動画を止めることをおすすめします。大学入試共通テスト講座を定期的に配信していくのでぜひチャンネル登録をお願いします。
第1問 公共分野
問1では、「男女平等に関する法的状況」について問われています。問題文には「日本国憲法14条」「女性差別撤廃条約を批准」とあります。日本国憲法14条は「法の下の平等」について、また、1985年に女性差別撤廃条約の批准に向けて男女雇用機会均等法を制定しています。「両性の本質的平等」は日本国憲法24条であり、「男女共同参画社会基本法」は1999年に公布・施行されていますので正解は選択肢②「法の下の平等」「男女雇用機会均等法」です。
問4では、「平等主義の分類」と「アイヌ問題」について問われています。問題文には「個人や属性に関わらず全ての人を同じように扱う」「クォータ制のような制度を新たに導入」「アイヌ民族に対する差別」とあります。法律や制度などにおける取り扱いの平等のことを「形式的平等」、現実の格差をなくそうとする平等のことを「実質的平等」といいます。形式的平等は「機会の平等」、実質的平等は「結果の平等」と解釈することができます。また、「アイヌ施策推進法」はアイヌ民族を支援するため2019年に制定されています。「アイヌ文化振興法」はアイヌの人々の誇りを尊重する社会を目的とした法律で1999年に制定されていることから正解は選択肢③となります。
第2問 公共分野
問1では公共空間について問われています。問題文には「コミュニケーション的行為の理論」「対等な立場で自由に意見を交わす」「『人間の条件』の活動」などとあります。『コミュニケーション的行為の理論』の著者はユルゲン・ハーバーマスであり、公共性の形成に必要なものは「対話的理性」であると主張しました。また、『人間の条件』の著者はハンナ・アーレントであり、人間の営みを「労働」「仕事」「活動」の3つに分類しました。選択肢にある「他者危害原理」は功利主義のJ・S・ミルであるので正解は選択肢⑤です。
問3では帰納法による推論について問われています。帰納法とは、一般的なルールや法則にものごとを当てはめて結論を導き出す思考法です。イギリス経験論の祖フランシス・ベーコンによって提唱されました。問題文の発言Ⅰ「これらの事実が何度もあったことから…経験則が導き出せる」と発言Ⅲ「これらの経験を基にして…哲学対話の方針につながった」は帰納的推論です。発言Ⅱ「義務がある」という前提から「対話のルール」を演繹的に導き出しているため正解は選択肢⑤となります。
問4では公共空間の持続的形成について問われています。問題文アには「全ての参加者はオンライン会議に出席」とあるのでこれは「非対面的関りのみ」です。問題文イには「料理教室で講師に味見をしてもらう」とあるのでこれは「対面的関りのみ」です。問題文ウには「外出できなかった人がインターネットで参加」とあるのでこれは「対面的関りに非対面的関りが加わった」と考えられます。そのため、正解は選択肢②となります。
公共の問題は、哲学に関する基本的な知識に加えて資料の正確な読み取りと一般常識があればそこまで難しくはないと思います。
第3問 倫理分野(源流思想など)
問1では古代ギリシア思想の美について問われています。選択肢①のヘシオドスは古代ギリシアの叙事詩人で『神統記』において神々の誕生系譜とウラノス、クロノス、ゼウスによる三代の政権交代劇を描いたので不正解。選択肢②のデモクリトスは物質の最小単位が原子であると考えた古代ギリシアの哲学者、数的比例の美を考えたのは古代ギリシアの数学者ピタゴラスなので不正解。選択肢③のソクラテスは無知の知を基に対話によって絶対真理を見つけようとした哲学者、ソフィストとよばれた相対主義の代表的な哲学者はプロタゴラスなので不正解。そのため、正解は選択肢④のプラトンです。プラトンはイデア論を提唱して、イデアに憧れ慕うことをエロースといいました。エロースはさまざまな美を求めますが、やがて美そのもの(美のイデア)を求めるのです。
問2では宗教と芸術の関係について問われています。選択肢①のバビロン捕囚とはユダ王国の首都エルサレムが新バビロニアのネブカドネザル王によって征服されて住民のヘブライ人が連行された事件のことです。これを契機としてユダヤの民はユダヤ人としての民族意識を高めて、ユダヤ教という宗教の体系をつくりあげたといわれています。ただし、ユダヤ教では偶像崇拝は禁止されているので不正解です。選択肢③の涅槃図は仏教の開祖である釈迦が亡くなった様子を描いた絵画なので不正解、選択肢④の磔刑図は十字架に架けられたイエスの姿が描かれた絵画ですが人類の現在が購われた様ではないので不正解。そのため、正解は選択肢②です。ユダヤ教徒同じくイスラム教でも偶像崇拝は禁止されていますが、神の像の代わりにメッカのカーバ神殿の方角を示すミフラーブというくぼみがあります。
問3ではアウグスティヌスの思想について問われています。アウグスティヌスはパウロや新プラトン主義に影響を受けて、教会を絶対的な存在と定め「神の恩寵による救い」の理論を展開しました。そのため、キリスト教カトリック教会における「最大の教父」とよばれています。資料によれば「作られた美だけを追い求めるのは罠」とあるので、正解は選択肢③です。
問4では中国思想について問われています。選択肢アには「人の本性は善」とあるので性善説の孟子、選択肢イには「どの価値も相対的なもの」とあるので万物斉同の荘子、選択肢ウには「仁を表現するものが礼」とあるので儒教の孔子、選択肢エには「家族主義的な考えを批判」とあるので墨家の墨子。墨子は孔子の仁礼の思想を家族に偏ったものであると批判して兼愛を提唱しました。以上のことから、正解は選択肢①となります。
問5では大乗仏教の思想について問われています。選択肢アは「一切のものは実体をもたない空」などとあるので正解。選択肢イは「出家した菩薩が送る生活を理想化」の部分が不正解、維摩経は世俗の生活の中で仏教の真理を実現するさまを描いたものとされています。選択肢ウは「無著と世親は心がつくりだした表象にすぎない」などとあるので正解。2人は兄弟であり唯識思想の実質的な創始者といわれています。選択肢エは「すべての衆生が仏になる(一切衆生)」は涅槃経なので不正解。以上のことから、正解は選択肢②となります。
問6では近代の芸術について問われています。問題文には「天文対話」「自然科学」「人間の目に映る世界の中に美」などとあります。『天文対話』の著者はガリレオ=ガリレイで観測をすることで地動説を実証しました。コペルニクスの著書は『天球の回転について』です。また、近代の科学者が因果法則の発見に努めていました。四原因説は古代ギリシアのアリストテレスの思想などです。そして、ルネサンス期の学問や芸術は神ではなく人間を中心とするあり方を探究しました。プロテスタンティズムとはカトリックから分離したプロテスタント各派の思想のことです。ルターとカルヴァンによる宗教改革がそのきっかけとなりました。以上のことから、正解は選択肢④です。
問7ではベンヤミンの資料をもとに芸術作品と複製技術について問われています。ヴァルター・ベンヤミンは「アウラ」を提唱したフランクフルト学派の哲学者です。資料には「一回限りの作品に代わり同一の作品を大量に出現させる」「現代の大衆運動と密接に結びついている」などと書かれています。選択肢①は「1回限りの作品と同等のアウラを与える」が不正解、選択肢②は「歴史的、社会的文脈から切り離すことなく」が不正解、選択肢④は「唯一無二性という価値を無力化せず」が不正解、そのため、正解は選択肢③となります。
問9ではこれまでの会話をもとにこれまでの学習内容について問われています。場面2では老子の思想について語られている部分がヒントになります。場面3では現代アートについて語られている部分がヒントになります。また、近代の思想家の芸術に関する考えについては問題文キのマルクスの記述が正解です。社会主義を提唱したカール・マルクスは社会の下部構造(生産活動)が上部構造(芸術などの精神的な活動)を規定すると主張しました。問題文オのウェーバーはプロテスタンティズムが資本主義に与えた影響を説きました。問題文カのニーチェはキリスト教的道徳が弱者のルサンチマンを生み出したと言いました。以上のことから、正解は選択肢⑥となります。
第4問 倫理分野(日本の哲学)
問1では日本における古代の宗教観について問われています。選択肢②は「仏と神の関係は固定された」が不正解、選択肢③は「神道と陽明学」が不正解、おそらく陽明学ではなく朱子学かな(多分)?選択肢④は「死後の霊魂の存在を否定」が不正解、復古神道とは「儒教や仏教などの影響を受ける以前の日本民族固有の精神に立ち返ろう。以上のことから、正解は選択肢①となります。
問2では親鸞の思想について問われています。親鸞は「善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」の悪人正機を提唱しました。これは、善人ですら往生できるのだから悪人はなおさら往生できるという意味です。つまり、全ての衆生を救う阿弥陀仏に帰依しれば本願によって救われるということです。選択肢①は「自力の行」、選択肢③は「他者に救いの手」、選択肢④は「それ以外」が不正解。そのため、正解は選択肢②となります。
問5では日本の思想について問われています。問題文には「雑居」「皮相の上滑り「キリスト教を接いだもの」などとあります。加藤周一は近代化に伴う急速な西洋化に端を発する日本文化のありよう―日本文化の雑種性を論じた文明評論家です。丸山真男は日本の思想をさまざまな思想が雑居しているにすぎないと批判しました。夏目漱石は日本の文明開化を内発的なものではなく外発的開花にすぎないと批判しました。三宅雪嶺は伝統文化を否定する西洋化政策を批判して、実現して、人類社会は進歩していくという「国粋主義」を提唱しました。新渡戸稲造は国際連盟事務次長として働き『武士道』を著した教育者です。「太平洋のかけ橋になりたい」と米国留学をするなど日本で最初の国際人とされています。内村鑑三は日本独自のいわゆる無教会主義を提唱した日本のキリスト教思想家です。武士道の精神の土台にキリスト教の真理を実現する接ぎ木のキリスト教を主張しました。以上のことから、正解は選択肢⑤となります。
第5問 倫理分野(認知バイアス)
問3ではクリティカルシンキングについて問われています。クリティカルシンキングとは、客観的な視点で物事や問題を分析して、本質を見極めて合理的な判断をする思考法(批判的思考)のことです。ソクラテスは「無知の知」のもとで自分が何を知らないのかを知るべきであると考えました。これは反省的に自分の認知そのものを対象とするメタ認知と捉えることができます。ミルは「他者危害」の原則のもとで自由について論じた功利主義の哲学者です。これは他者の視点に立ってものごとを捉えることであると考えることができます。デカルトは「演繹法」によって確実な真理から結論を導き出すことを重視しました。これはいくつかの前提から論理的に結論を導く思考方法であると考えることができます。そのため、正解(不適切なもの)は選択肢④となります。
デューイは「道具主義」を提唱したアメリカのプラグマティズムの哲学者です。これは日常の問題を解決する道具として知性を使うという立場なのでヒューリスティック―つまり、問題をすばやく解決するための直感的な判断)を否定するわけではありません。
第6問 倫理分野(戦争と平和)
問1では非暴力的な問題解決をした人物について問われています。選択肢②のロマン・ロランは反ファシズムをかかげて戦争反対を主張しましたが、『永遠平和のために』はカントの著作なので不正解です。選択肢③のガンディーは「非暴力」をかかげたインド独立の父といわれる政治指導者ですが「アタラクシア」はヘレニズム時代のエピクロス派の思想なので不正解です。選択肢④のキング牧師は黒人差別の解消を求めた公民権運動の指導者ですが「生命への畏敬」は密林の聖者アルベルト・シュバイツァーの言葉なので不正解です。「I have a dream」や「愛なき力は暴力、力なき愛は無力」などの言葉が有名です。そのため、正解は選択肢①です。トルストイは『戦争と平和』を著したロシアの作家です。名門貴族に生まれたもののヒューマニズムの観点から農民の側に立って戦いました。
問2ではフーコーの思想について問われています。ミッシェル・フーコーはフランスのポスト構造主義の哲学者です。人間の思考は見えない権力構造によって規定されていると主張しました。そのため、正解は「日常生活の中に権力構造が潜む」とある選択肢③です。
問3では安全保障の概念について問われています。資料では安全保障の概念を国家に限定する狭義のものとして捉えることを批判しています。また、すべての人を対等な同胞とみなす態度はコスモポリタン思想と同じといえます。コスモポリタン思想は古代ギリシアのストア派の哲学によるものです。以上のことから、正解は選択肢⑦となります。
まとめ
今回は「大学入試共通テスト2025にチャレンジ」について紹介しました。全ての問題は紹介できませんでしたのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。
「迷いの中に倫理がある」
これは『チ。』の中に出てくる大好きな言葉なのですが、作中には「この世は非道徳的なことで溢れている。そんな世界を変えるために何が必要か?」と問うたバデーニが「知」と答える場面があります。これまで、正しさを主張するため暴力によって罪なき人々の血が流れてきました。
大航海時代の植民地支配、アメリカ大陸の制服、ナチスによるホロコーストなどなど。いずれも「絶対に正しい」とされていることを盲信した結果が引き起こした悲劇です。私たちは「絶対的正義」を掲げた時に恐ろしいほど残虐なことを可能にしてしまうのです。
哲学は何の役にも立たないと思われがちですが、「公共・倫理」には、よりよい社会を実現することを考える問題が出題されていました。これからの時代を生きる私たちには哲学の教養がまちがいなく必要なのです。苦しみを味わった知性はいずれ十分に迷うことのできる知性―暴走した文明に歯止めをかけて異常な技術を乗りこなせる知性になります。私たちは何が正しいのかわからないからこそ「迷う」ことが大切なのです。私たちは「迷う」ことでしか倫理を見つけることはできないのです。ぜひその答えをこれからも一緒に探していきましょう。本日の旅はここまでです。ありがとうございました。

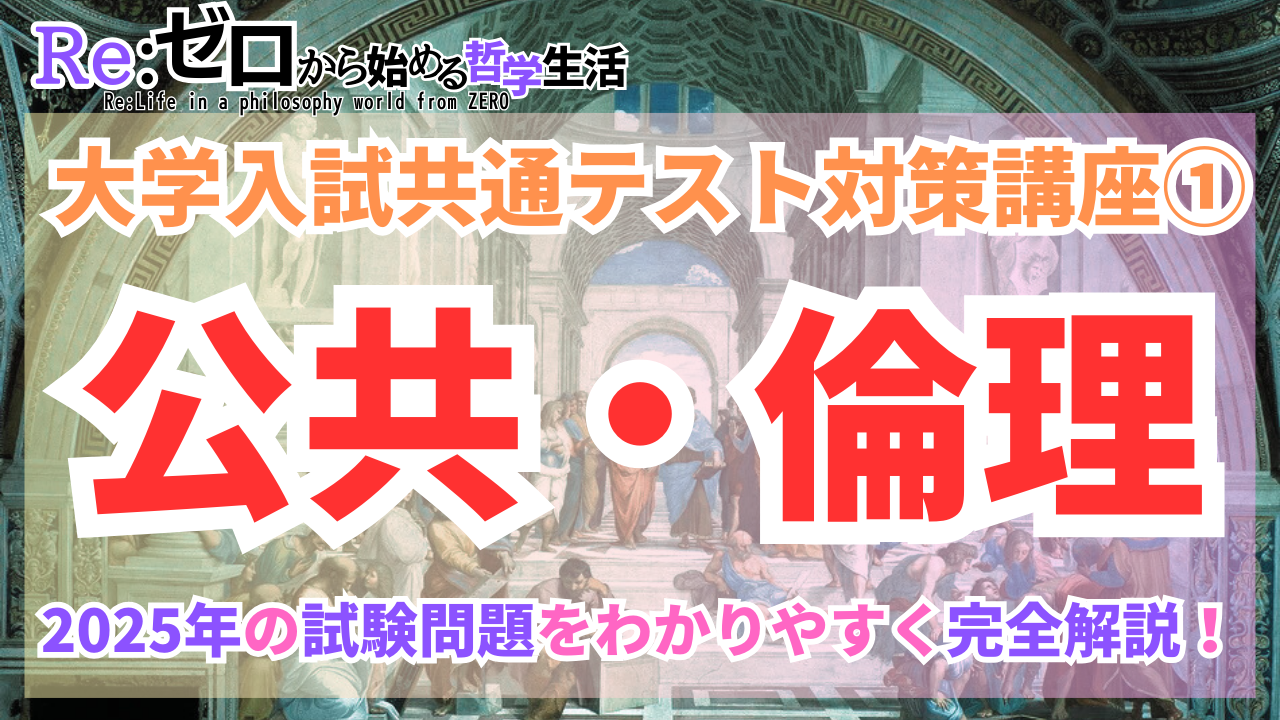

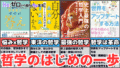
コメント