今回は「自己啓発の源流-アドラー心理学の教え-」について解説したいと思います。参考文献は『嫌われる勇気』(著者:岸見一郎さん・古賀史健さん)です。
精神分析学といえばフロイトやユングを思い浮かべる人が多いと思います。しかし、この2人に加えて知られざる第三の巨頭が心理学の世界にはいたのです。それがオーストリア出身の精神分析学者アルフレッド・アドラーです。
アドラーはもともとフロイトが主宰する協会に所属していたのですが、学説上の対立から袂を分かちアドラー心理学と呼ばれる独自の個人心理学を提唱しました。アドラー心理学は堅苦しい学問ではなく人間理解の到達点として受け入れられています。しかし、時代を百年も先行したとされるその思想にはまだ時代が追いついていないのです。つまり、誤解はかんたんであっても、理解はむずかしい思想だということです。もし、このアドラー心理学を正しく理解できれば誰もが今日から幸せになれるはずです。
「嫌われる勇気」は2013年に出版され2014年にはビジネス書ランキングの2位に、そして2015年には堂々の1位を獲得した大ベストセラーです。2025年現在の世界累計発行部数は1350万部を突破しているそうです。
本書は、迷える青年がアドラー心理学の哲人のもとを訪れて、人生の幸福を見つけていくというストーリーとなっているのでとても読みやすい内容です。忙しくて読書をする時間がないという方はぜひAmazonのaudibleをご利用ください。概要欄にaudibleの登録ができるリンクを用意してあるのでチェックしてみてください。アドラー心理学はこれまでのあなたの常識をきっと破壊してくれることでしょう。(ただし、あまりに衝撃的な内容なので信じられないことも多いかと思いますが…)
1 変わらないのは変わらないと決心しているからだ
あなたは「全ての人が変わることができる」と言われて納得できますか?誰もがそうありたいと願いつつも、現実には難しいように感じるのではないでしょうか。もし、過去にトラウマとなる原因があった場合はなかなか一歩を踏み出せないものです。しかし、アドラーは「過去の原因が現在の結果を規定する(原因論)」を否定します。
たとえば、過去にいやなこと(どんな原因)があったとしても、必ずしも現在が同じ結果(たとえば不登校)になるわけではないからです。(これでは決定論のように過去が未来を確定させるので動かせないことになってしまう)。
アドラーは「過去の原因」ではなく「現在の目的」を考えることが大切だといいます。ひきこもりであれば「不安だから外に出ない」のではなく、「外に出たくないから不安になっている」ということです。つまり、外に出たくないという目的のために不安という手段を用意しているのです。アドラー心理学ではこのような考え方を原因論に対して「目的論」といいます。
そして、アドラーはこの中で明確に「トラウマ」を否定しているのです!なぜなら、いかなる経験もそれ自体では成功の原因や失敗の原因にはならないからです。私たちは経験によるショック(トラウマとされるもの)に苦しむのではなく、「経験に与える意味」によって自らを決定しているだけなのです。ひきこもりであれば、ひきこもることで多少の不満はあるものの、自分の目的にかなった行動をとることはできていると考えるのです。
もちろん、なかなか受け入れがたい考え方だということはわかりますが、人間が変われる存在だとすればおのずと原因論ではなく目的論に立脚するしかないのです。あなたはほかの誰かとして生まれ変わることはできませんのであなたのままでいいのです。しかし、このままのあなたでいいかというとそれはちがうといえます。もしも、今のあなたが幸せを実感できないでいるならばこのままでいいはずがありません。目的論の立場でいえば、不幸なあなたは「自らが不幸であること」を選んだからなのです。
アドラー心理学では人生における思考や行動の傾向のことをライフスタイルとよびますが、「不幸なあなた」はあなたが自らの手でそのライフスタイルを選んだということです。だんだん悲しみを通り越して怒りがわいてくるのもわかりますが、ライフスタイルが先天的なものではなく選んだものであるならばそこに希望―すなわち、再び選び直すことができるという可能性を見つけることができまるはずです。
もちろん、「自分で選んだライフスタイルだから選び直せ」と言われても難しいですよね。しかし、アドラーはあなたが不幸なあなたでいることを変われないでいるのは、自らに対して「変わらないという決心」をしているからであるというのです。なぜなら、多少の不満はあったとしても今のライフスタイルの方が楽だと思うからです。
もし、新しいライフスタイルを選んだらより不安な人生を送ることになるかもしれません。だからこそ、ライフスタイルを変えるためには「勇気」が試されるのです。ここに、アドラー心理学が「勇気の心理学」であるとされる理由があります。変われないという人には「幸せになる勇気」が足りていないのです。不幸なあなたにできることは、まず今のライフスタイルをやめると決心することです。
「もし~だったら」という可能性の中に生きていてはいつまでも変わることができません。なぜなら、変わらない自分への言い訳として「~になれたら」と言っているだけなのです。そうではなく、世界や自分への意味づけ(ライフスタイル)を変えれば、世界とのかかわり方や自らの行動までもが変わらざるをえなくなるはずなのです。だからこそ、あなたはライフスタイルを選び直せばいいだけなのです。
これは決してあなたの人生が不幸であったのは自分が悪いのだと断罪しているのではなく、これまでがどうであったとしてもこれからの人生には全く関係ないと言っているのです!
2 全ての悩みは対人関係
アドラーは「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」と言いました。原理的に無理なのですが、宇宙の中でただひとりで生きることができれば―この世界から対人関係がなくなってしまえばあらゆる悩みが消えるということです。
そんな孤独には耐えられないと思うかもしれませんが、そもそも孤独という概念すらなくなるはずなのです(もちろん言葉や論理もなくなります)。しかし、無人島に1人でいたとしても、部屋に1人でいたとしても、孤独を感じるのはどこかにいる「誰か」を感じるから孤独になるのです。だからこそ、すべての悩みは対人関係の悩みということなのです。
たとえば、あなたはほかの誰かと比べて劣等感を感じたことがありますか?アドラーは劣等感という言葉を現在のような文脈でつかった最初の人といわれていますが、もともと劣等感とは自らへの価値判断(自分には価値がないとか)に関わる言葉でした。身長が低い、体型が肥満型、容姿が気に入らないなど…このような劣等感を抱くことはよくあることだと思います。
しかし、問題はそれ自体が「客観的な劣等性」を意味するものなのではなく、そこに自分がどのような意味づけをしたのかという「主観的な劣等感」にあるのです。つまり、他者との比較(対人関係)において自分が感じているにすぎないのであって、比較する相手がいなければそもそもそんなものを感じることはないということです。私たちを苦しめている劣等感とは「客観的な事実」ではなく「主観的な解釈」なのです。
アドラーは劣等感を悪いことだとは言っていません。もともと人間には無力な状態から脱したいという普遍的な欲求―理想の状態に近づきたいという「優越性の追求」の感情が備わっているのです。しかし、理想を達成できない自分のことを劣っているとつい思ってしまうものです。これが劣等感なのですが、それをきっかけに前進しようとできれば問題ありません(試合でレギュラーになれないからもっと練習をしよう、のように)。
いっぽう、劣等感を何かの言い訳に使っている状態を「劣等コンプレックス」といいます。(身長が低いからレギュラーになれない、足がおそいからレギュラーになれない、のように)。アドラーはこのような論理のことを「見せかけの因果律」であるとして、なんの因果関係もないところに重大な因果関係があるように説明することと言っています。なぜ、そんなことをするのかといえばライフスタイルを変える勇気がないからなのです。
たとえば、「学歴が低いから成功できない」と言う劣等コンプレックスは、「学歴さえ高ければ成功できる」ということになりますよね。これは、そうすることで自分あるいは周囲に向かって自分の有能さを暗示しているのです。このような「本当のわたしは優秀なのだ」という偽りの優越感に浸ることを、「劣等コンプレックス」に対して「優越コンプレックス」とアドラーは言います。実はこれら2つは言葉の意味では正反対なのですがつながっているのです。
大切なのは、アドラーが優越性の追求をもつことや劣等感を抱くことは問題なくても、劣等コンプレックスや優越コンプレックスをもつことが問題だと言っているところです。そもそも、優越性の追求とは自らの足を一歩ふみ出す意思のことであって、他者と比較して上を目指そうとする競争の意思ではありません。そして、健全な劣等感は他者との比較において感じるものではなく、「理想の自分」との比較から生まれるものだということです。
まずは、私たちは他者との間にさまざまなちがいがあることを受け入れる必要があります。そのうえで「われわれは同じではないけれど対等である」と考えてみるのです。これをなかなか受け入れることができない理由は対人関係の軸に競争があるからです。競争の先には勝者と敗者があって、その延長線上にコンプレックスが生まれるのです。その結果、他者のこと(あるいはこの世界のこと)を敵であると見なすようになります。対人関係の軸に競争があるから他者の幸福が私の敗けであるかのように感じるのです。だからこそ、敵でなく仲間であると思うことができれば世界の見え方は大きく変わります。
アドラーは他者のことを仲間ではなく敵であると思ってしまう原因は、「人生のタスク」から逃げているせいだと指摘しています。アドラーの考える人生のタスクは行動面と心理面に分けられるのですが、行動面では「自立すること」と「社会と調和して暮らせること」の2つ、心理面では「わたしには能力がある」と「人々はわたしの仲間である」という意識です。
そして、アドラーは長い人生の過程で生まれる対人関係(人生のタスク)のことを「仕事のタスク」「交友のタスク」「愛のタスク」の3つに分けました。これらは対人関係の距離と深さが問題になることなのですが、これらは社会の中で生きている以上は直面せざるをえない対人関係を表しています。
仕事のタスクは他者との協力なくして成立する仕事がないことからもわかりやすいです。これは、仕事によってのみ結ばれる関係なので距離も深さもハードルは低くなります。この段階でつまずいてしまった人がニートやひきこもりと言われる人たちなのです。
交友のタスクは仕事をはなれたさらに広い意味での人間関係ということになります。仕事によって強制されることはないので踏み出すのも深めるのも難しい関係といえます。
愛のタスクは恋愛関係や家族(親子)との関係のことであり最も難しい人間関係です。3つの中で最も距離が近くて関係も深いものとなるからです。
アドラーはさまざまな口実を見つけてこれら人生のタスクを回避しようとすることを、「人生の嘘」と呼びました。アドラー心理学は「所有の心理学」(原因論)ではなく「使用の心理学」(目的論)です。「何が与えられたかではなく、与えられたものをどう使うか」ということです。大切なのは善悪や道徳ではなく、どこまでいっても「勇気」の問題ということなのです。
3 自由とは嫌われる勇気をもつことである
アドラー心理学では「他者からの承認欲求」を否定しています。なぜなら、私たちは「他者の期待を満たすために生きているわけではない」からです。他者からの承認を求め、評価を気にしてばかりいるのは他者の人生を生きることなのです。大切なことは「課題の分離」という考え方を知ることです。
私たちは自分の課題と他者の課題を分離しなければいけないのです。そのうえで、他者の課題には一切ふみ込まないようにしなければいけません。あらゆる人間関係は「他者の課題に土足でふみ込むこと」から始まるのです。
では、それが誰の課題であるのかを見分けるにはどうすればいいのでしょうか?それは「選択によってもたらされる結末を最終的に引き受けるのは誰か」と考えるのです。子どもが勉強しないことや引きこもって出てこないことを解決するのかどうか―これらは原則としてあなた(親)ではなく本人が解決する課題なのです。あなたにできることは自分の信じる最善の道を選ぶことであって、その選択について他者がどのような評価を下すのかは他者の課題になるのです。つまり、自分のことを相手がどのように思ったとしてもそれは相手の課題なのです。
あらゆる悩みが対人関係にあるのは課題の分離ができていないことに原因があります。まずは、「これは誰の課題なのか」を考えて課題の分離をすることが大切です。そして、他者の課題には決して介入しないこと、同時に自分の課題には誰ひとりとして介入させないようにすることにするのです。これができたときにはじめて、私たちは対人関係の悩みから自由になることができます。
アドラー心理学にはどうしても常識へのアンチテーゼという側面があります。さまざまな常識(原因論、トラウマ、承認欲求)を否定して、目的論の立場からすべての悩みが対人関係にあると考えて課題の分離をする―こんなことは頭でわかっていたとしてもなかなかできることではありません。
そもそも、承認欲求を求めてしまうのは「嫌われたくないから」であると考えられます。もちろん、わざわざ嫌われたい人などいないのは当たり前です。しかし、みんなから嫌われないようにするには常に他者の顔色を伺う必要があります。このような生き方は相手だけではなく自分に対しても嘘をつく生き方にほかなりません。
イマヌエル・カントは他者から嫌われたくないと思うような本能的な欲望のことを「傾向性」(本能や衝動のおもむくままに生きること)と言いました。そのうえで、カントは傾向性のおもむくままに生きることが自由なのではなく、坂道を上るように傾向性にあらがいながら生きることが自由であると言いました。すべての悩みは対人関係である以上、その悩みから解放されることこそ自由といえます。だからこそ、自由とは「嫌われる勇気をもつこと」なのです。
もちろん、これはわざわざ嫌われるような生き方をしろと言っているのではありません。そうではなく、嫌われることを恐れるなということなのです。「あらゆる人から好かれる人生」が自由で幸福な人生なのではありません。「誰かに嫌われている人生」であっても自分がどうあるかを貫くことができる人生―それこそが自由で幸福な人生なのです。
「嫌われたくない」と思うことは自分の課題であり自分が選ぶことができますが、「自分のことを嫌う」のは相手の課題であってそこに介入することはできないのです。「〇〇があったから関係が悪くなった」と考えるのは原因論であって、「関係をよくしたくない」という目的のために過去の何かを用意しているだけなのです。
まずは自分が変わることから始めなければいけません。自分が変わったとしても変わるのは自分だけであって相手がどう思うかは関係ないのです。
4 対人関係のゴールは共同体感覚
前の章でお話をしたように、他者のことを敵ではなく仲間としてみることができれば、そこに自分の居場所を見つけてきっと共同体のために貢献しようと思えるはずです。これを「共同体感覚」といいます。「課題の分離」をすることが対人関係のスタートだとするならば、対人関係のゴールは「共同体感覚」をもてるようにすることです。
共同体とは家族や学校だけに限らず国家や人類などを包括したすべてのものであり、時間軸では過去から未来、そして動植物をも含むものだとアドラーは述べています。共同体感覚は言いかえれば「社会への関心」ということになるのですが、その最小の単位は「わたしとあなた」のふたりの関係になります。
そして、これを起点に「自己への執着」から「他者への関心」に切り替える必要があります。自己執着(自己中心的な)人物といえば暴君や和を乱す人が思いつきますが、実は課題の分離ができず承認欲求にとらわれている人もまた自己中心的な人なのです。なぜなら、「わたしが他者からどう見られているのか」にしか興味がない生き方―「わたし」のことしか頭にないという点で自己中心的なライフスタイルだといえるのです。
「わたし」とは人生の主役でありながらも世界の中心にいるわけではありません。あくまで、共同体のメンバーであり全体の一部であるのです。自己中心的な人は自分が世界の中心にいると思いこんでいて、他者は「わたしのために何かをしれくれる人」でしかありません。
しかし、当然ながら他者は「わたし」の期待を満たすために生きているわけではありません。そのため、自己中心的な人は「わたし」の期待に応えてくれない他者を敵とみなす―結果的にそれが重なっていく中で大切な仲間(共同体感覚)を失うことになるのです。
あなたは「世界」という言葉を聞いてどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか?自己中心的な人が見ている世界は「世界地図」のようなものだと考えられます。実はヨーロッパの世界地図は中心にヨーロッパが描かれていているのですが、ヨーロッパの人が日本で売られている世界地図を見たら違和感を抱くことになるでしょう。自分が世界の中心にいると思いこんでいる人は世界をこのように見ているのです。
しかし、もし世界のことを「地球儀」のように考えてみるとどうなると思いますか?地球儀であればヨーロッパでもアジアでも、すべての場所を中心に見ることができます。世界の中心ではなく「共同体の一部」というのはこのように世界を見ることなのです。
私たちは誰もが「ここにいてもいいんだ」という所属の安心感を求めています。そのためには、人生のタスクに向き合うことで共同体にコミットしなければなりません。世界の中心にいて他者のことを「わたしのために何かをしてくれる人」と思うのではなく、世界の一部として他者に対して「わたしは何をすることができるか」と考えるのです。
では、課題の分離をして共同体感覚をもつためにどうすればいいのでしょうか?課題の分離をしてお互いに協調することができる関係をもつためには、「縦の関係」ではなく「横の関係」という概念をもつ必要があります。アドラー心理学では褒めることも叱ることも、相手を操作しようとする「縦の関係」になるとして否定されているのです。そして、同じではないけれど対等であるという「横の関係」にすることを求めるのです。
そもそも、劣等感とは「縦の関係」の中から生じてくる意識なのです。誰もが対等であるという「横の関係」の中では劣等感を感じることなどありませんよね。「縦の関係」として相手を褒めたり叱ったりして操作するのではなく、「横の関係」ではその代わりに相手を「勇気づける」ようにするのです。
なぜなら、人は褒められることによって、「自分には能力がないのだ」という信念を形成してしまうからです。信じられないかもしれませんが、アドラー心理学では褒めるという行為を「能力のある人が能力のない人に下す評価」としているのです。なぜなら、褒められようとするのは他者の価値観に合わせて生きることと同じだからです。
「横の関係」では、褒めるのではなく「ありがとう」と感謝を伝えることや「うれしい」という喜びや「助かりました」というお礼の言葉を伝えるようにします。なぜなら、私たちは感謝されることで自分が他者に貢献できたと知ることができるのです。そして、他者に貢献する(自分には価値がある)と思えた時に初めて勇気をもてるのです。
アドラー心理学では共同体に貢献できていると自ら思えた時に自分の価値を実感できます。評価するのではなく、勇気づける(貢献できたと思えるようにする)ことが大切なのです。もちろん、これは他者の役に立てなければ価値がないというわけではありません。他者のことを「行為」のレベル(何をしたか)で見ればそうなってしまうかもしれませんが、「存在」のレベル(ただそこにいてくれること)を見ればどうなるでしょうか。
まずは他者との間にひとつでもいいから「横の関係」をあなたが築くようにするのです。これは誰とでも友達のように振る舞えばいいということではなくて、意識の上では対等であると思うようにすることが何よりも大切なことなのです。
5 誰でも今この瞬間から幸せになれる
アドラー心理学では自己への執着から他者への関心をもつようにすることで、共同体感覚がもてるようになるというお話をしてきました。そのときに必要になることが「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」なのです。
「自己受容」と似た言葉に自己肯定というものがありますが、これはまったくちがいます。まず、「自己受容」とは自己肯定のように「わたしはできる」と思うのではなく、できない自分であってもありのままの自分のことを受け入れるようにするということです。「本当の自分は100点を取れるはずだ」と言い聞かせるのが自己肯定であるのに対して、「60点だったけど100点を取るにはどうすればいいかな」と考えるのが自己受容です。
つぎに、「他者信頼」とは他者を信じるときにいっさいの条件をつけないということです。もちろん、無条件に相手を信じれば裏切られるだけだと誰もが思うはずです。しかし、裏切るか裏切らないかを決めるのは相手であって自分ではないのです(課題の分離)。アドラー心理学では「それは無理だろう…」と思うことが何度も出てきますが、課題の分離がきちんとできれば世界は驚くほどにシンプルに考えることができるのです。
「他者信頼」のことを宗教や道徳として無条件に信じることが大切だと考えるのではなく、「横の関係」を築いていくための手段であると考えるようにしてみてください。結局は信頼することを恐れていたら誰ともよりよい人間関係を築くことなどできません。自己受容することも、他者信頼することも、結局は「勇気」の話だということなのです。ありのままの自分を受け入れ、他者を信頼することができた時に、あなたにとって他者は仲間であることに気づくことができるはずです。
そして、他者が仲間であると思うことができれば、自分の所属する共同体に居場所を見つけ、そこに貢献しようと思うことができるのです。これが仲間に対して何かしたいと思う「他者貢献」なのです。もちろん、「他者貢献」とは「わたし」を捨てて相手に尽くすという自己犠牲ではなく、「わたし」の価値を実感するためにこそなされるべきもののことです。私たちは「わたしは誰かの役に立っている」という実感をもつことができて、ようやく自分の価値も受け入れることができるようになります。
ここに、アドラーが人間を理解することは容易ではなく、これが全ての心理学の中で実践することがもっとも困難であると述べた所以があります。ユダヤ教の教えの中に次のような話があるそうです。
「10人の人がいたときに、そのうちの1人は必ず批判する」
「しかし、そのうち2人は受け入れる親友になれて、残りの7人はどちらでもない」
大切なのはあなたを批判する1人に注目をするのか、あなたのことを受け入れてくれる2人に注目するのかで世界の判断が変わります。どうでもいい一部のことにだけ焦点を当てて世界全体を評価してはいけないのです。
はじめに「すべての悩みは対人関係である」と言いましたが、裏を返せば私たちの幸福もまた対人関係の中にあるはずだと考えることができます。そして、アドラーは「貢献感こそが幸福である」と定義したのです。つまり、「私は誰かの役に立てている」という主観的な感覚を持てればいいだけなのです。
「特別な存在」である必要などどこにもありません(それは承認欲求の罠です)。アドラー心理学では「普通であることの勇気」こそが大切であるとされています。もちろん、普通であるとは無能であるという意味ではありません。人生を登山のように考えるのではなく、「いま、ここ」という連続する刹那と捉えるのです。なぜなら、登頂することが人生の目標(そこから人生が始まる)になってしまうと、人生のほとんどの時間はその途上でありそれは仮の人生でしかなくなってしまいます。その場合、登頂できなかったとしたらあなたの人生は何だったと言えるのでしょうか?
人生とは、いまこの瞬間をダンスするように生きる連続する刹那であると考えてください。何かを目標に努力をして結果的にそこにたどりつくことができなかったとしても、「いま、ここ」という瞬間が充実していればそれで十分だということです。人生はいつもシンプルであり、つねに完結しているのです。
人生における最大の嘘とは、まさに「いま、ここ」を真剣に生きないということです。過去や未来に囚われ「いま、ここ」から目を背ける生き方こそ人生における最大の嘘です。過去も未来もないのであれば、決めるのは昨日でも明日でもない「いま、ここ」なのです。
アドラーは「一般的な人生の意味はない」と答えています。理不尽な出来事によって命を落とした人に対して人生の意味など語れるはずもありません。しかし、アドラーは「人生の意味はあなたが自分自身に与えるものだ」とも言っています。あなたの人生に意味を与えられるのは、ほかならぬあなただけなのです。
もし、あなたがアドラー心理学における幸福や自由を選ぼうとした時に道に迷ったら、「他者貢献」という導きの星を掲げるようにしてください。他者に貢献するという導きの星さえ見失わなければ迷うことは何もありません。たとえ、誰かに嫌われたとしても関係なく自由に生きてかまわないのですから。
「いま、ここ」で「嫌われる勇気」をもつのです!
6 まとめ
今回の動画は「自己啓発の源流-アドラー心理学の教え-」について解説してきました。本書の中では最後に「わたしの力は計り知れないほど大きい」と語られています。これは、「わたし」が変われば世界だって変わるということであり、世界とは誰かが変えてくれるのではなく、「わたし」によってしか変わらないのです。
「誰かが始めなければならない。ほかの人が協力的でないとしてもあなたには関係ない。あなたが始めるべきだ。ほかの人が協力的であるかどうかなど考えることなく。」
ぜひ、あなたの頭上に「他者貢献」という導きの星を掲げて勇気を出してみてください。そして、過去や未来を見ることなく刹那としての「いま、ここ」を生きてください。この動画を見て頂いたことで、あなたはすでにその第一歩を歩み始めています。ぜひ、実際に本書を手に取ってさらに詳しくアドラー心理学を学んでみてください。
そして、人生のタスク―「自立すること」と「社会と調和して暮らせること」「私には能力がある」と「人々は私の仲間である」という意識を大切にしてみてください。「課題の分離」をすることで対人関係のスタートを切ることができて、「共同体感覚」という対人関係のゴールにたどりつけることを願っています。

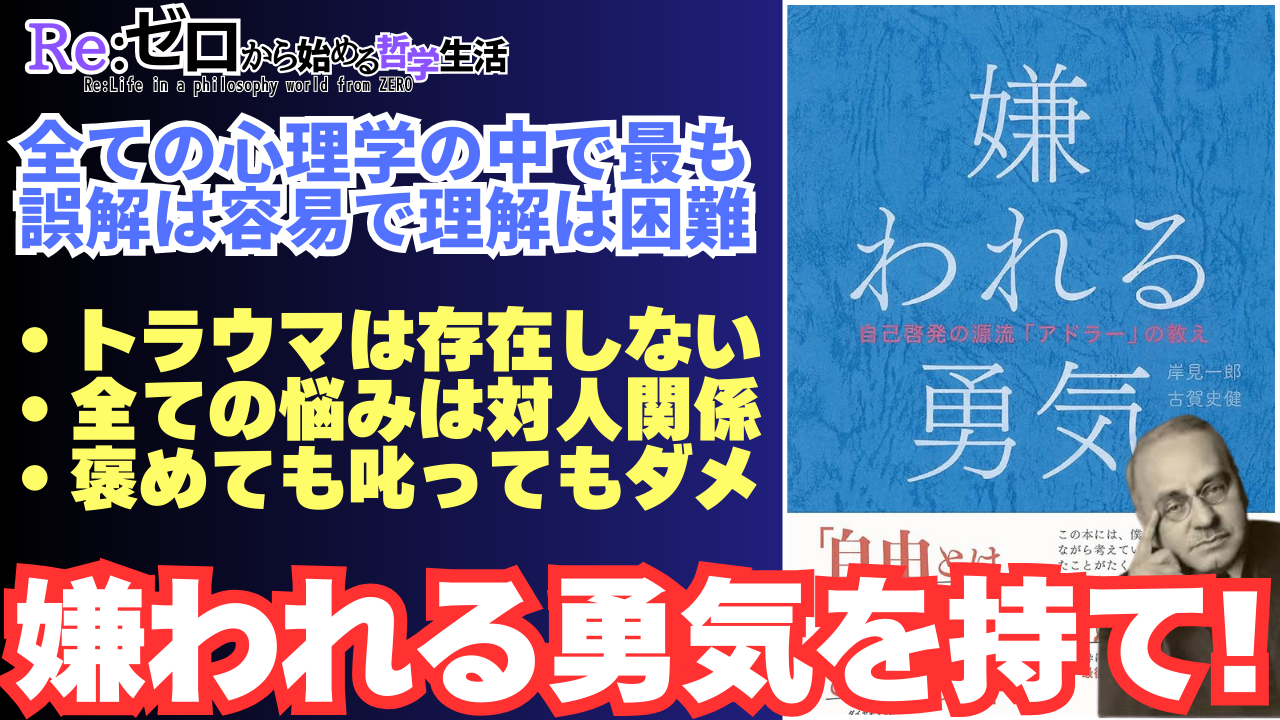
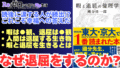
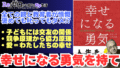
コメント