今回は「宗教の補助線をもとに見る日本人の歴史と信仰」について解説したいと思います。参考文献は『真・日本の歴史』(著者:井沢元彦さん)です。
実は日本には地理的に特殊な条件に恵まれた国であることから、世界史の常識には当てはまらない日本だけの特別な宗教・信仰が存在するのです。しかし、私たちは日本人がもっている宗教観をほとんど理解しないまま大人になります。前回の動画で日本人がもつ宗教の1つが「穢れ忌避」信仰であることをお話しました。
持統天皇が藤原京を建造するまでは都を次々に移転していたのですが、その理由は天皇が死ぬことで発生する穢れ(死穢)に原因があったのです。また、穢れを忌避する信仰があったので天皇は武力を放棄するのですが、その結果として私的な武装集団である武士が誕生することになっていったのです。
このように、日本の歴史は日本人がもつ宗教の視点を知らなければ理解できないのです。日本の歴史教育が正しさを教えずただ暗記するだけのつまらないものになっている理由は「宗教」という視点の欠如(と歴史学会の傲慢さ)に原因があったと著者は述べています。
少し前に「宗教」がわかれば世界が見えるという動画を出しましたが、日本人の行動原理や歴史の特殊性もまた「宗教」という視点がなければ見えないのです。まさに、「哲学の補助線」「宗教の補助線」を引くことが大切なのです。
私たちが無意識にとっている行動原理がどのような信仰によるものなのか?学校や教科書では学べない日本の歴史と日本人の真実の姿が見えてくるはずです。今回は「穢れ」の他に示されていた残りの3つ―「怨霊」「和」「言霊」の信仰について詳しく解説しています。
『逆説の日本史』の著者が描き出す傲慢な歴史学会の闇と正しい日本の歴史観。ぜひ、動画を最後まで見て頂き「宗教の補助線」をひいて歴史を眺めてみてください。内容がわかりやすかったと感じた時にはぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 怨霊鎮魂
前の動画で紹介したように、日本では「穢れ」こそが諸悪の根源であるとされていました。日本は天皇を中心とする神の国であるにも関わらず悪いことも起きるのはなぜか?そのような問いについて整合性を持たせるために考えられたのが「穢れ」だったようです。だからこそ「穢れ」を避けることを大切にする信仰があったのですが、たとえ神であっても「死」の穢れからはのがれることはできません(イザナミの神話)。
「穢れ」は禊(清らかな水で流すこと)によって祓うことができるのですが、天皇の死という大きすぎる穢れは祓うことができませんでした(だからこそ、天皇が代わるごとに首都を移転していたのです)。もう1つ、禊では祓うことのできない大きすぎる穢れがこの章で紹介する「怨霊」なのです。怨霊は怨念を抱いたまま亡くなった人の死穢から発生する穢れのことであり、殺されたり恨みをもって死んだりするなど不幸な死に方をすれば、その怨念は強力な穢れとなってさまざまな禍をもたらすと考えられたのです。
そのため、怨霊が生じてしまった場合には「鎮魂」をするようにしてきたのです。日本で最初の怨霊は神話に登場する「オオクニヌシ」ではないかと著者は述べています。神話ではオオクニヌシはアマテラスの孫に国を譲ったことにされていますが、真実はオオクニヌシの一族は戦争によって敗れたのではないかと考えられているようです。
オオクニヌシが怨霊となって禍をもたらすのではないかとされたことから、オオクニヌシが国を譲ったという美談にして神として出雲大社に祀るようにしたのです。出雲大社の神殿は天皇の御所や東大寺の大仏殿よりも巨大な神殿だったといわれています。古代においてその国で最も大きな建築物は国王の宮殿か国教の神殿というのが常識でした。
常識に反することをするのには理由があるはずなのです。征服者が敗者のために国で一番の巨大な建築物に祀るなんて普通では考えられません。だからこそ、日本の宗教―怨霊鎮魂の信仰という理由しかありえないのです。日本におけるぶっちぎりで最強の怨霊といえば崇徳上皇(最も気の毒な天皇)です。崇徳天皇は鳥羽天皇の子どもとされるのですが、実は祖父の白河法皇が鳥羽天皇の妻に手を出して産ませた子どもだったのです。
そんな悲劇の出生秘話をもつ崇徳天皇なのですが、上皇になってからも自分の子どもを天皇にすることを後白河天皇に阻まれてしまいます。その結果、朝廷内が崇徳派と後白河派に分かれて武士団による代理戦争が起こるのです。これが有名な「保元の乱」です。この戦乱は後白河天皇が平清盛と源義朝を味方につけたことで勝利しました。そのため、崇徳上皇は出家して許しを請うのですが讃岐に流罪となってしまったのです。
崇徳院は軟禁生活の中でも仏教に帰依して写経に務め、五部大乗経の写本を完成させて朝廷に差し出し、寺に納めるようにお願いしました。ところが、後白河天皇は呪詛が込められているのではないかと疑って送り返すのです。これに激怒した崇徳院は自らの血で「この経典を魔道に回向する」と書き込み、天皇家を没落させてそれ以外の者をこの国の王にすると呪いの言葉に残しました。それから崇徳院は崩御するまで爪や髭を伸ばし続け天皇家を呪ったといわれています。
その後の歴史はみなさんも知っている通り、平治の乱に勝利した平清盛が朝廷の権力を掌握するようになりました。さらに、その平家を滅ぼした源頼朝が鎌倉に武家政権を開き、やがて執権となった北条義時が後鳥羽上皇を流罪にすることになるのです。これを見た人々は「崇徳上皇の呪いが成就したのだ」と思ったことでしょう。室町時代に書かれた『太平記』では崇徳上皇は怨霊の首座として登場しています。
近代以前の日本では「崇徳上皇こそが最強の怨霊」というのは人々の常識だったのです。しかし、日本では穢れを避ける(禊によって祓う)信仰があったことから、悪いことは水に流して忘れてしまうということがあるあるだったのです。
崇徳上皇が最強の怨霊とされた証拠として明治への改元の時の記録を見てみましょう。明治天皇は江戸幕府から政権を返上された際に改元よりも先に鎮魂の儀式を行ったのです。穢れは禊によって祓うことができますが怨霊には鎮魂をすることが必要とされていました。具体的には怨霊を霊験あらたかな神として祀るようにするということです。
たとえば、菅原道真は天神様として北野天満宮や太宰府天満宮に祀られています。また、怨霊にならないようにあらかじめ鎮魂の意味を込めた諡がおくられていました。諡とは天皇の死後に業績などに応じておくられる呼び名のことです。この諡に「徳」の字をおくられている天皇を思い返してみてほしいのです。
思いつくのは壇ノ浦の戦いでわずか8歳にして入水することになった「安徳天皇」です。しかし、8歳の天皇に本当に徳などあったといえるのでしょうか?ほかにも、誰も看取る人がいない中で孤独に死んだ「孝徳天皇」、宇佐八幡宮神託事件で銅鏡との不貞を疑われた「聖徳天皇」などがあげられます。
ピンときたかと思いますが、徳の字がある天皇はみんな不幸な死に方をしているのです。不幸な死に方をしているから怨霊にならないように「徳」のある人だったと鎮魂したのです。ただし、後鳥羽上皇の時からはされなくなってしまうのです。後鳥羽上皇はもともと「顕徳」だったのですが効力がなかったのか後鳥羽に改められました。これ以降、徳の字をおくる鎮魂方法は行われなくなっていくのです。
神として祀ることや諡に徳の字をおくること以外にもさまざまな方法で鎮魂がされました。著者は源氏物語や平家物語などの文学や能楽までもが鎮魂の産物だったと述べています。源氏物語を書いたのは権力者として君臨した藤原道長の娘に仕えた紫式部です。藤原氏が頂点にいるにも関わらず「源氏」が主人公の物語を書くなどありえるでしょうか?物語では源氏のライバルを右大臣家としているのですがどう考えてもこれは藤原氏です。つまり、現実には源氏を左遷した藤原氏が勝つのですが、敗れた源氏が怨霊にならないようにと鎮魂の意味から書かれた物語だと考えられるのです。
平家物語は史実と同じように源氏が平家を滅ぼす内容になっていますが、平家は滅ぼされてしまったけどすばらしい一族であったと称える内容にもなっています。これを琵琶法師による語り物として文字を読むことのできない一般の人々が聞いたのです。琵琶法師の語る物語に当時の人々はきっと心を動かされたことでしょう。ただし、「耳なし芳一」というお話があるように怨霊を語ることには大きな危険が伴います。(穢れがふれることによっても伝わるため避けられてきたのと同じ理屈です)
だからこその「法師」だったのですが、ここから演劇の誕生までには時間がかかりました。それを解決したのが世阿弥の「能面をつければ大丈夫だよ」作戦だったのです。世阿弥は能面に怨霊を憑依させることで演者が怨霊を演じることを可能にしたのです。歌舞伎は素人が簡単にまねできるものではありませんが能は比較的だれでも演じられます(能が素人でも楽しめるカラオケであるといわれる所以です)。
豊臣秀吉は能楽師に「明智うち」という演目を考案させて自ら演じてみせたとされています。徳川家康は能楽を将軍家の式学(儀式に用いられる芸能)に採用しています。このような流れの中で日本における識字率の向上という副産物も生まれていくのです。「怨霊」信仰を知ることでこれまで見えなかった歴史の真実が見えてくるのです。
2 和の信仰
日本は「和」を重んじる国である、ということには多くの人が納得してくれるはずです。では、なぜ日本では「和」を重んじられているのでしょうか?ここにも、日本だけの特別な「宗教」の補助線を引くことで見えてくることがあるのです。
和とは「穏やか、仲がいい、調和している」というような状態のことです。日本人は「和を保つ」ことを重視して「和を乱す」ことを嫌う傾向にあるのですが、このような精神のはじまりは聖徳太子の十七条憲法に起源を見つけることができます。十七条憲法の第一条には「和を以て尊しとする」となっています。そして、第二条には「仏教の教えを守ること」、第三条には「天皇の命令に従うこと」と書かれています。また、第十七条には「独断で決めてはいけないから論議しなさい」と書かれているのです。
何かを伝えたい時には「はじめ」と「おわり」に大切なことを述べることが多いので、仏教の教えや天皇の命令よりも「和」を大切にすることを重視していることがわかります。聖徳太子は推古天皇の摂政として仏教の教えを中心とした政治を行っていました。古代の常識では最高権力者の命令や神(宗教)の教えこそが意思決定の最優先事項でした。にもかかわらず、時の権力者である聖徳太子は「和」が大切であると言ったのです。しかも、その内容は「話し合えば全てうまくいく」という意味不明な論理でした。
このように、明らかに説明のできない不合理な行動をとる理由は「宗教」しかありません。聖徳太子は「話し合い(=和)」という宗教を信仰していたのです。聖徳太子はものごとを話し合いで解決すればその内容は正しいものであり、話し合いで解決すれば必ず成功すると考えていたということなのです(話し合い絶対主義)。
しかし、逆もまた真なりで、聖徳太子はものごとを話し合い以外の方法で解決することは、絶対に間違っていると考えていたということにもなります。話し合うとは複数で決めることなので、その反対は1人が独断で決めることです。7世紀に制定されたこの教えを21世紀になった現代でも私たちは信仰しているのです。
たとえば、稟議書のようなものがあるのはそれだけ「独断」が嫌われている証です。民主主義とは多数決のことであり本来は多数の意志が即座に反映される制度のことです。しかし、日本では民主主義のことを「みんなで決める」制度だと思っているのです。さらに、その決定には「和」がなされていなければいけないと思いこんでいるから厄介です。みんなでラーメン屋に行こうとしているのに1人だけうどん屋に行ってはだめなのです。みんなで(反対者を根絶するまで)話し合えばうまくいくと考えられているということです。聖徳太子がこんな不合理なことを考えたのはそれが当時の常識だったからだと思われます。
話し合い絶対主義の起源は先に紹介したオオクニヌシの国譲り神話に由来されるのです。神話では国を譲るように迫られたオオクニヌシが息子に相談する場面が描かれています。まず、コトシロヌシはそんなことはダメだといって海に飛び込んだとされています。つぎに、タケミナカタは武力で解決しようとするのですが敗北したとされています。その結果、オオクニヌシは国を譲ることを決断したということなのですが、ポイントはオオクニヌシが国を譲るかどうかを「独断」で決めていないということです。つまり、合意がえられない決定は怨霊を生み出すと考えられていたことが推察されます。
大和朝廷は、話し合いをすることによってこの国は誕生したのだ―建国の神話を書くときにこのように美談として正当化したということです。アマテラスは直後に「ここは私の子孫が治める国だと確定した」と宣言しているのです。これは三大神勅の1つである「天壌無窮の神勅」とよばれるものであり、話し合いによって決まったことならば怨念が発生しないので正当性が認められる―このような社会認識が建国の神話を考える時には常識になっていたと考えられるのです。
前章の「怨霊」信仰も今回の「和」の信仰もそのルーツは同じ国譲りの神話にありました。「日本は同調圧力が強い」「日本は話し合いをすることが目的になっている」このように感じていた方も多いかと思いますが、その原因は日本人が信仰する「宗教」という視点を通すことではじめて見えてくるのです。
3 言霊の信仰
「穢れ忌避」の信仰から「怨霊」と「和」の信仰が派生してきましたが、あと1つ日本人にとって重要な信仰に「言霊」信仰があります。言霊とは、「言葉には発した通りのことが実現する」という力があると考えることです。言葉には霊が宿っていると考えられていたので、その霊の力によって発した言葉の通りのことが実現するとされていたのです。
日本人は無意識のうちに「言霊」信仰に縛られていることにほとんど気づいていません。1970年代頃からマスメディアなどで「差別後追放キャンペーン」が展開されてきました。「めくら」や「びっこ」などの言葉を差別的だからという理由でやめようという運動です。何が問題なのかというと、文化や芸術の分野にまでその影響が及んでいったことなのです。
なぜ、こんなことが起こってしまうのでしょうか?それは言霊信仰に縛られた結果、差別語をなくせば差別がなくなると信じているからです。「いじめ」という言葉を使わなければいじめがなくなるでしょうか?言葉をなくせばその実体もなくなるというのは言霊の世界の中だけの話なのです。にもかかわらず、結婚式での「切れる」や受験生への「落ちる」などは禁句とされています。ほかにも、戦時中に退却を「転進」、敗戦を「終戦」と表現したことも同じです。
そんな言霊信仰のルーツは『万葉集』を開くことで理解することができます。そのはじめの歌は、雄略天皇が若菜を摘んでいる娘の名を尋ねるという内容なのです。「君の名は」という映画がありましたが実はこれ、万葉集の時代のプロポーズなのです。この時代には女性が名前を公に明かしてはならないという風習が常識となっていて、青春ドラマのように夕日に向かって名前を叫ぶなんて絶対にしてはいけなかったのです。古代において権力者の名前は最高軍事機密であることがほとんどでした。なぜなら、当時は呪いの力を信じていたので名前を知られてはいけなかったのです。
このように考えると、邪馬台国の女王「卑弥呼」の名前も実名ではないことがわかります。「卑弥呼」は中国の『魏志倭人伝』に登場する女王の名前として登場するものです。つまり、外国の記録に記された呼び名だったのです。だとすれば、邪馬台国とはヤマト国であり卑弥呼が女王の称号だったと考えられます。もとは「日皇女(巫女)」だったものに中国お得意の卑しい字を当てた表現にされたのです。
このように考えると、歴史の新しい側面が見えてくるのではないでしょうか?言霊信仰の世界では合理的な判断をすればするほど糾弾されてしまうことになります。戦時下の日本で、戦況を正しく理解して勝機はないと言えば非国民と罵られ、「日本は必ず勝てる」と言い続けた愚かな指導者たちが賞賛された理由がまさにこれです。
原子力発電所の説明会で「人間のつくるものなので事故はありえる」と言うべきですよね。同時に「だからこそ、このように危機管理をしています」と答えることが誠実な対応です。しかし、こんなことを言って避難訓練などしようものなら、「事故が起こるということなのか!」と非難されて正しい行動がとれないのと同じです。あれだけの大惨事を起こした戦争や震災を経験したにも関わらず何も変わらない現状―これを解決するためには「日本には言霊の信仰がある」ことを理解するしかありません。日本人の多くは無意識に言霊に縛られているので合理的な判断を妨げられているのです。
このように、言霊には危機管理や政治という場面でマイナスの影響を与えてしまいます。しかし、和歌の前では平等であるという素晴らしい側面もまたもっているのも事実です。日本では古くから天皇御所において「歌会始」という伝統行事が行われてきました。歌会は『万葉集』を見れば奈良時代には始まっていたことがわかります。年の初めに開催される歌会始は遅くとも鎌倉時代には始まっていたという記録もあります。『万葉集』には天皇から庶民に至るまであらゆる秀作が身分に関わらず集められています。歴史に残る詩集や歌集はいくつもありますが、それらは権力者や偉人の作品集なのです。万葉集のような歌集は世界中のどこにもなく、世界に誇れる素晴らしい文化といえます。まさに、「和歌の前の平等」が日本には存在するのです。
これも「誰の言葉であっても言葉には霊力が宿る」と考える言霊信仰のおかげなのです。言霊信仰の良い面と悪い面をどちらも正しく理解することができるように、日本の歴史教育のあり方を再考しなければいけないのではないでしょうか?
4 まとめ
今回の動画は「宗教の補助線をもとに見る日本人の歴史と信仰」について解説してきました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだたくさんありますので、ぜひ本書を手に取ってより詳しく学んで頂けたらと思います。
日本の歴史教育には「建国の神話」が全く教えられていないという問題点があります。(そもそも、これが問題点だと思っていない人がほとんどだと思います)。「神話は事実ではない」「創作であり非科学的だ」のような批判もあることでしょう。しかし、日本神話を禁じた張本人であるアメリカは『聖書』をきちんと教えているのです。日本が「聖書を学ばせるのはよくない」と言えば受け入れて中止してくれるでしょうか?
ポール・ゴーギャンのこの長いタイトルの絵画―『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』をご存じでしょうか?「世界はどうしてできたのか?」「人間はどこから来てどこへ行くのか?」この最も根源的な問いについて考えてきたのが哲学と宗教なのです。哲学と宗教の教養をもつことできっとあなたの人生はよりよいものになっていくでしょう。
今回の動画で日本人の行動原理には特別な宗教観があるとわかっていただけたと思います。ぜひ、これからも「宗教の補助線」を引いて歴史を眺めてみてください 『逆説の日本史』シリーズは正しい歴史を知るためにもぜひ読んでほしいおすすめ本です。


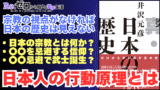
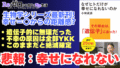
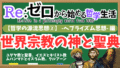
コメント