今回は「Re:ゼロから始める哲学生活」近代思想①ルネサンスと宗教改革編を解説します。参考文献は『哲学と宗教全史』(著者:出口治明さん)です。
忙しくて読書をする時間がないという方はぜひAmazonのaudibleをご利用ください。
ポール・ゴーギャンのこの長いタイトルの絵画―『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』をご存じでしょうか?「世界はどうしてできたのか?」「人間はどこから来てどこへ行くのか?」この最も根源的な問いについて考えてきたのが哲学と宗教なのです。
哲学者たちは世界をまるごと理解しようと思考をめぐらせてきました。そして、同じように宗教家たちは人間のさまざまな悩みや葛藤―生老病死などの苦しみをまるごと救おうとした人たちだったのです。しかし、現在では科学がそのほとんどを証明できるようになってしまいました。では、科学が答えをだしているのであれば哲学や宗教を学ぶ必要はないのでしょうか?
そんなことはありません、なぜなら科学もまた必ずしも万能というわけではないからです。科学が発達した現代においても、哲学はビジネス界をはじめいろいろな場面で注目を集め、宗教はなくなるどころかむしろますます発展しているとされているのです。科学では説明できないことがある限り、決して哲学や宗教がなくなることはないでしょう。そのため、哲学や宗教の教養があれば世界を少し高い視座から見ることができるのです。
『暇と退屈の倫理学』の著者である國分功一郎さんは劇作家ブレヒトの言葉「英雄がいない時代は不幸だが、英雄を求める時代はもっと不幸だ」に対して、「哲学のない時代は不幸だが、哲学を必要とする時代はもっと不幸だ」と述べています。哲学が必要とされるこの時代に哲学の教養を欠いては幸福になることなどできないのです。
そこで、このシリーズでは「古代から現代までの哲学」を全て解説していく予定です。今回は近代思想の原点となる3つの運動―ルネサンス、宗教改革、そして科学革命についてわかりやすく解説します。中世から近代へと至る過程でルネサンスと宗教改革がどのような経緯で展開され、近代科学がどのように発展してきたのかを解説しますのでぜひ最後までご視聴ください。
1 ルネサンス期の思想
ヨーロッパの中世は、キリスト教による神を中心とした価値観が社会を支配していました。中でもエジプトのアレクサンドリア教会、シリアのアンティオキア教会、エルサレム教会、コンスタンティノープル教会、そしてローマ教会の5つは五大本山といわれました。
エジプト、シリア、エルサレムの3つはイスラム勢力の影響によって衰退していくのですが、コンスタンティノープル教会とローマ教会は激しく対立していくようになります。そして、1054年に長い対立の果てに大シスマ(東西教会の大分裂)が起こりました。これがローマ=カトリック教会とギリシア正教会に分離することにつながっていくのです。
カトリック教会はこの時期のヨーロッパ社会に大きな影響力を行使するようになりました。1077年には「カノッサの屈辱」とよばれるローマ皇帝を破門する事件が起こります。また、1095年にはクレルモン公会議において「十字軍」への呼びかけが行われました。この後200年に及ぶ遠征はイスラム教との間に大きな禍根を残して失敗に終わるのです。
十字軍の失敗はカトリック教会の宗教的権威を大きく失墜させることになりました。同時に、十字軍によってイスラム世界に伝わって研究されていた古代ギリシアやローマの古典文化が再発見されて逆輸入されることにもなりました。これがルネサンスの運動へと発展していくきっかけになるのです。
ルネサンスとはフランス語で「再生」や「復興」を意味する文化運動なのですが、「神中心主義」から「人間中心主義」への転換運動だったと考えることができるのです。中世では絶対的な神の権威と比べたら人間は小さな存在であるとされていたのに対して、ギリシアやローマの古典文化ではありのままの人間が肯定・賛美されていたのです。
ミケランジェロのダビデ像は人間の力強さや美しさの象徴とされる有名な作品の1つです。そして、ルネサンス期の絵画の特徴といえば「遠近法」です。遠近法は遠くのものを小さく、近くのものを大きく描く技法のことですが、これは「人間の視点」から捉えられた世界像を表しているのです。(中世の絵画がのっぺりしているのは全体を把握する「神の視点」が捉えた世界像)
本チャンネルのモチーフである遠近法の極地ともいえる作品「アテナイの学堂」を描いたラファエロ・サンティもこの時代の有名な芸術家の1人です。「アテナイの学堂」についてはこちらの記事をご視聴ください。
古典の教養を身につけて人間性の解放を目指した人々のことを「人文主義者」とよび、人文主義(ヒューマニズム)の思想はルネサンスの時代に重なるように登場しました。人文主義者はあらゆる方面から真理と美を探究して人間を理解しようとしたのです。その代表的な人物が万能の天才であり遠近法の完成者レオナルド・ダ・ヴィンチです。
初期の人文主義者には『神曲』の著者であるダンテ・アリギエーリがいます。ダンテは神の言語であるラテン語ではなくトスカーナの方言で『神曲』を執筆したのですが、これが後にイタリア語に発展していくことになるのです。地獄と煉獄と天国をダンテがめぐるという壮大な物語についての解説はこちらの動画にて。
ほかにも、『叙情詩集』で恋愛を賛美したペトラルカやダンテの理解者でもある『デカメロン』のジョバンニ・ボッカッチョなどがいます。カボチャのメロンでおなじみボッカッチョの『デカメロン』は中学の歴史教科書にも掲載されているのですがその内容はまさに「エロ本」です。ボッカッチョは僧侶の堕落ぶりを「エロ本」という形で描き出すことにしたのです。
この時期の有名な思想家にはピコ・デラ・ミランドラやマキャベリ、エラスムスがいます。ミランドラは人間の尊厳の根拠が自由意志にあると主張しました。前回の動画のアウグスティヌスは自由意志による善を否定していたのですが、人間の価値は運や家系ではなく意志と責任によって行為した結果で決まると考えたのです。(努力をして成功することは素晴らしいけど宝くじにあたった大富豪は偉くない!)
近代政治学の祖マキャベリは『君主論』によって宗教(道徳)と政治を分離しました。政治の本質は道徳ではなく力にあると喝破して、「獅子の獰猛さと狐の狡猾さ」をもつ君主こそが理想的な君主であると考えたのです(善良であっても優柔不断な君主では外敵から国を守ることはできない!)。たとえ不道徳な手段でも断固たる決断力で国益を守る君主でなければいけないのです。マキャベリは道徳や善意で世の中を変えることはできないと見抜いていたということです。
エラスムスはルネサンス期における最大の人文主義者とよばれています。エラスムスはギリシア語原典の『新約聖書』を校訂して出版しました。これによって、宗教上の真理がカトリック教会だけの独占物ではなくなりました。「エラスムスが産んだ卵をルターが孵した」といわれるように、誰もが『聖書』をという考えはルターの万人司祭主義を先取りするものだったといえます。
また、『愚神礼賛』によってカトリック教会の腐敗と堕落を徹底的に批判しました。愚かな女神が自画自賛するという体裁で教会を含めた人間社会の愚かさを風刺したのです(当然カトリック教会は激怒して禁書に指定…)。エラスムスはカトリック教会を批判しても教会を離れることはありませんでした。エラスムスの親友で『ユートピア』を著したトマス・モアもこの時代の人物です。
人文主義者とは別に箴言による人間への省察を行った思想家をモラリストといいます。ユグノー戦争に心を痛めたモンテーニュは『エセ―(随想録)』の中で宗教的な「寛容の精神」の重要性を強調しました。モンテーニュは世の中の人々が不当な自説に固執することを問題として、ソクラテスの無知の知に倣って「ク・セ・ジュ(私は何を知るか)」と主張しました。(同じく「寛容」について述べたヴォルテールはもう少し後の時代に登場します)
もうひとり、早熟の天才パスカルは著書『パンセ』の中で「人間は悲惨さと偉大さの両方をあわせもつ中間者だ」と述べました。たしかに、人間は無力であり苦しい時にはすぐに逃げ出してしまう弱い存在だとしても、そのような事実を反省することができる存在であることもまた事実だといえます。そして、最も有名なあの格言「人間は考える葦である」と言ったのです。超訳としては「人間は葦のように弱いが考えることができるという点で強い」でしょうか。人間の弱さや思考することの崇高さを一言で表した名言中の名言といえる言葉です。
ただし、パスカルは「想像力は敵である」とも指摘しています。ものごとを過少に評価したり過大に評価したりするのは想像力のデメリットです。パスカルが考える力を尊重しながらもその限界を示していることも覚えておいてください。さっきまで「考える“足”」と思っていた人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
2 宗教改革
十字軍の失敗というカトリック教会の権威失墜と堕落の極みは、イタリアのルネサンス運動に続いてヨーロッパ北部での宗教改革へと発展していきました。
1517年にローマ教皇レオ10世がサン=ピエトロ大聖堂を改築するために、贖宥状(免罪符)を販売したことがそのきっかけとなりました。これに対して、ドイツの神学者マルティン・ルターは、ヴィッテンベルグ城の教会に「95ヶ条の論題」を貼りだしました。その結果、ルターは教会を破門されることになるのですが、これに同調してカトリックに抗議した人たちはプロテスタントとよばれるようになります。フランスでは「ユグノー」、イギリスでは「ピューリタン(清教徒)」とよばれました。
1620年にメイフラワー号でアメリカ大陸に渡った102人の清教徒たちのことを「巡礼始祖」(ピルグリムファーザーズ)ともいいます。
ルターの主張の核心は「人は内面的な信仰のみで救われる」という信仰義認説です。これは、かつてパウロが説いたものと同じなのですが、教会による贖宥状の購入という行為ではなく信仰こそが大切であることを示したのです。その信仰の拠り所となるものこそが『聖書』です(聖書中心主義)。
当時の『聖書』はラテン語で書かれていたのでほとんどの民衆は読めませんでした。そこで、ルターはこれをドイツ語に翻訳して誰もが信仰の世界に入れるようにしたのです(これによって、聖職者の宗教的特権はますます否定されることになりました)。
そして、神の前ではすべての信者が平等であり、だれもが神と直接につながっていると考えられるようになりました(万人司祭主義)。そのため、プロテスタントの教会では神父ではなく牧師が礼拝を司っているのです。
また、ルターは世の中の職業はすべて神による召命であるという職業召命観も示しました。いっぽう、ジャン・カルヴァンは主著『キリスト教綱要』の中で「予定説」を強調しました。予定説とは、救われる者は「予め決定」しているという考え方のことです。
予め救われるかどうかが決まっているなら何をしてもいいのではないかと思いますよね?カルヴァンは信仰に生き禁欲的な生活を送り続けることで確信をもてると主張したのです。さらに、ルターが主張した職業召命観をカルヴァンはとくに強調しました。職業は召命(神に与えられた使命)なのでそこに貴賤はなく天職であるということです。そのため、職業活動の結果として豊かになることは信仰心の証であると肯定したのです。
19世紀の社会学者マックス・ウェーバーは著書の中で勤勉と貯蓄という利潤追求が宗教的に正当化されたことによって資本主義の発展につながったと主張しています。
18世紀に出版されたダニエル・デフォーの著書『ロビンソン・クルーソー』もまた当時のヨーロッパにおける時代精神を強く反映した作品となっています。主人公クルーソーの行動や思想にはプロテスタンティズムの影響が大きいと考えられます。
たとえば、クルーソーが無人島に漂着した時には規則正しい生活を送り勤勉に働きます。その理由は聖書を読んだことで神の意志を自らの生活に反映させようとしているのです。また、無人島を開拓して文明を築いていこうとする姿からは当時の植民地主義や帝国主義的な精神を象徴しているとも解釈できるようです。原住民の黒人フライデーを文明化しようとする姿勢には当時のヨーロッパ中心主義的な世界観が色濃く反映されているようにも思えます。
このように、『ロビンソン・クルーソー』にはプロテスタンティズムの倫理感や、資本主義の精神とヨーロッパ中心の植民地主義という特徴が現れていると考えられます。
宗教改革は神の絶対性を強調する思想運動であると同時に教会という外的権威に頼るのではなく内面的信仰への道を開拓した運動でもありました。つまり、宗教改革もまた、ルネサンスと同様に自律的に思考するという近代自我を生み出すきっかけとなっていたと考えることができるのです。
3 科学革命
中世ヨーロッパでは自然が固有の目的を実現するように秩序付けられているとする思想―「目的論的自然観」が主流となっていました。神学者トマス・アクィナスはアリストテレスの哲学を応用することで森羅万象が神の意志(目的)であるとキリスト教にとって都合のいい説明をしていました。
しかし、物理学や天文学が発展したことによって神の意志ではなく自然の法則(因果関係)を明らかにしようとするようになっていきました。これを目的論的自然観に対して「機械論的自然観」といいます。
この時代の大きな変化といえば「天動説」から「地動説」への転換です。地動説を最初に唱えたのは紀元前3世紀のアリスタルコスだといわれています。ヘレニズム時代の天文学者で「古代のコペルニクス」と呼ばれることもあるそうです。
しかし、2世紀にエジプトのアレクサンドリアで活躍した天文学者プトレマイオスが、地球を中心とした太陽・月・惑星の運行を計算したことで天動説を体系づけました。そして、神の創造した地球こそが宇宙の中心であるという考えが常識とされてきたのです。
しかし、ニコラウス・コペルニクスは『天体の回転について』の中で地動説を提唱しました。ここから物事の見方を180度かえるような発想は「コペルニクス的転回」と表現されます。
また、ジョルダーノ・ブルーノは地動説と宇宙の無限性を主張しました。古代の科学文献ヘルメス文書を読み物質が原子(アトム)の集合体であると考えて、あらゆる存在がアトムの離合集散で生成分解されるという無限の宇宙観を想定したのです。ブルーノの説は自然観察にもとづいたものではありませんでしたが、常識に捉われることなく近代以降の宇宙観を直感的に先取りしたといえるものでした。
ただし、コペルニクスとブルーノは司祭と修道士という立場であったことから、キリスト教を否定するつもりはなかったと考えられています。コペルニクスは神が創造した宇宙を最も簡潔に説明できる理論を求めた結果として(この時は完全な円運動としての)地動説にたどり着いたとされています。
その後、ヨハネス・ケプラーが観測データをもとに地動説を支持して、有名な楕円軌道の法則を含む「ケプラーの法則」を発表することになるのです。そして、ガリレオ・ガリレイもまた天体望遠鏡による観察の結果を主著『天文対話』にまとめることで地動説を支持したのです。
地動説をめぐる騒動の中で教会はコペルニクスの書物を禁書にして、1600年にはブルーノを異端審問にかけて宗教裁判によって火刑にしました。「宣告を下したあなたの方が宣告を受ける私よりもおそれているのではないか?」このように述べてブルーノは中世的な世界観の犠牲となってしまうのですが、ここがルネサンスの終わりであると同時に近代への幕開けとなる瞬間でもありました。
ガリレオもまた裁判では有罪判決を受けることにもなりますが、有名な「それでも地球は動いている」と言ったエピソードが残っています。ガリレオは「自然という書物は数学の言葉で書かれている」と述べたように「慣性の法則」や「落体の法則」を発見したことで近代物理学を基礎づけました。
そして、アイザック・ニュートンが「万有引力の法則」を発見することになるのです。これによって、古典力学が完成されることになりました。
地動説の証明によって「人間は主役ではない」という大きな認識の変化が起こりました。天動説では地球こそが宇宙の中心で人間は神が創造した特別な存在だとされていましたが、地動説では王様も僧侶も誰もが同じ脇役に過ぎないということになったのです。20世紀の科学史家トマス・クーンは天動説という古い理論(パラダイム)から地動説という新しい理論へと転換(パラダイム・シフト)したと述べました。
このように、キリスト教の世界観を破壊した地動説の登場によって自由な思考によってものごとの真理を解明しようとする啓蒙の時代が幕を開けるのです。デカルト、ロック、ホッブズ、ルソー、モンテスキュー、カントなど、ここから、誰もが知っているあの哲学者たちがいよいよ登場することになります。
ただし、この後に登場する合理論や経験論の哲学者たちでさえも、「神の存在証明」をするなど神の思想からは完全に逃れることはできませんでした。ニュートンでさえも、神による世界創造を信じて錬金術に傾倒していたといわれています。これには、「神殺し」のあの男が登場するまであと数世紀の時間を要することになるのです。
まとめ
今回は「Re:ゼロから始める哲学生活」近代思想①ルネサンスと宗教改革編を解説しました。次回は近代思想の2大潮流である「イギリス経験論」「大陸合理論」を解説する予定です。
中世は暗黒時代であるという表現がされているのを耳にしたことがあるかと思います。14世紀の学者ペトラルカが古代ギリシアやローマの文化的な輝きに比べて古代文化が衰退したとされる時代のことを「暗黒」と表現したのが始まりのようです。
また、17世紀の啓蒙(理性という光で世界を理解する)時代に対して中世が神の絶対性を蒙昧していた「知的暗黒の時代」だとするような見方もありました。封建的な社会構造が百年戦争によって大きく変わる社会的な混乱期でもあり、黒死病(ペスト)の大流行によって多くの命が失われたことも関係あるかもしれません。
たしかに、そのような側面も否定できないわけではないと思いますが、だからこそこの時代に何が起こっていたのかを正しく見つめ直さなければいけないのです。実はボッカッチョの『デカメロン』はペストが猛威をふるったフィレンツェから10人の男女が郊外の別荘に隠れてステイホームをする物語なのです。彼らは面白おかしなことをするのですがこの思想がルネサンスにつながっていくのです。
また、ペストによって「メメント・モリ(死を忘れるなかれ)」という発想も生まれました。これが聖書をきちんと読んで神に祈ろうという宗教改革にもつながっていったのです。つまり、ペストがルネサンスと宗教改革という大きな運動へと発展するきっかけとなり、神の呪縛から人間を解放することによって歴史が進歩していったと考えることもできます。
奇しくも新型コロナというパンデミックが起きた現代もまた暗黒時代なのかもしれません。しかし、新型コロナが働き方改革を加速させ労働生産性の向上につながる予兆もあります。「哲学と宗教の補助線」を引いて歴史や世の中の流れを見ることで、これからの社会がどのようなものになるかを考えるヒントをえることができるのです。

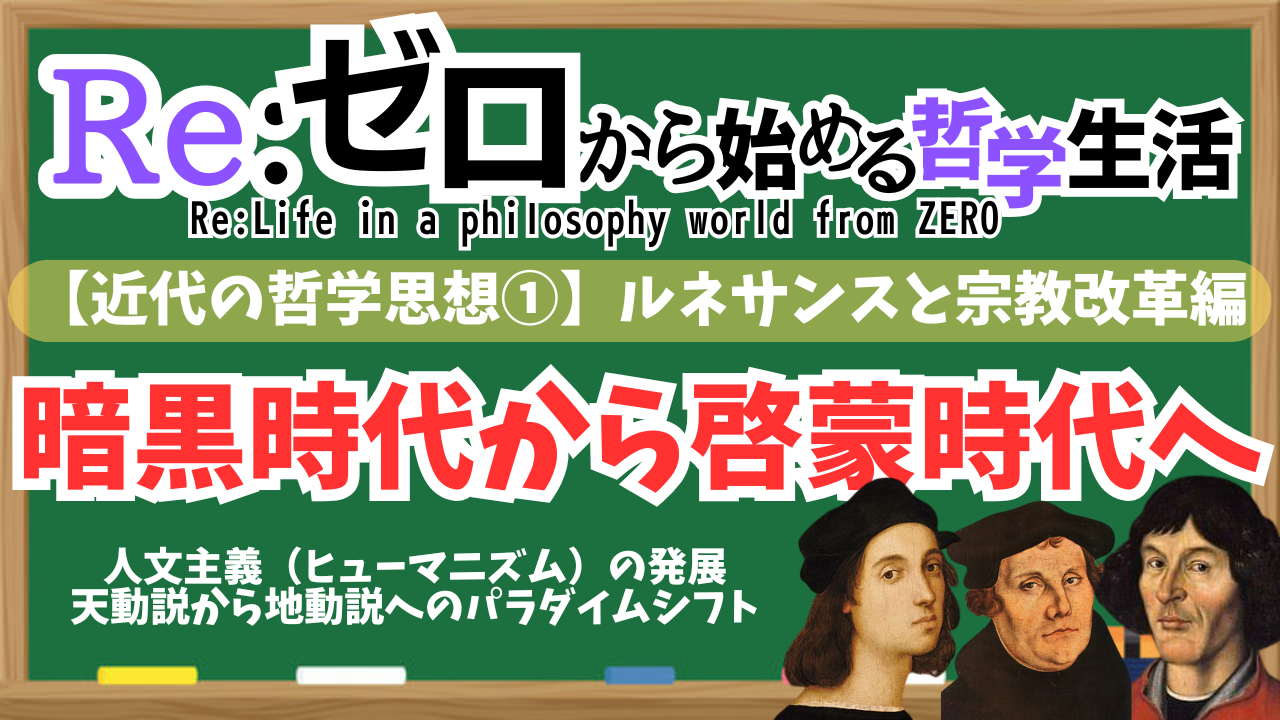

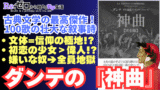

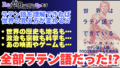

コメント