今回は『鬼滅の刃』について哲学の補助線を引いて考えてみたいと思います。参考文献は『鬼滅の刃』(著者:吾峠呼世晴)、「なぜ炭治郎は鬼の死を悼むのか」(著者:久保華誉)です。
『鬼滅の刃』は2016年から2020年にかけて週刊少年ジャンプに連載された漫画で、アニメ放送との相乗効果で単行本が売り切れるなど大きな社会現象にまで発展しました。(コロナ禍との関連もあってかその年のセンター試験の現代文では「妖怪」がテーマでした)。
2020年に公開された映画『無限列車編』は興行収入400億円を超える大ヒットであり、日本歴代興行収入でも『千と千尋の神隠し』を抜いて第1位となりました。また、最新作『無限城編-第一章 猗窩座再来-』は公開1か月で200億円を超えています。
なぜ、『鬼滅の刃』はこれほどまでに人気があるのでしょうか?まず、制作会社「ufotable」による美しい作画描写によるアニメが大きな要因でしょう。また、主人公たちが鬼を退治するという単純な勧善懲悪の物語ではなく、鬼の側にも感情移入できるような細かく丁寧な人物描写が多くの視聴者の涙を誘いました。
今回は『鬼滅の刃』に「哲学の補助線」を引いて少し高い視座から考えてみたいと思います。パワハラ上司に悩んでいるなら鬼舞辻無惨という不条理を哲学することで、嫉妬や欲望に負けそうになるなら日本固有の鬼という存在を哲学することで、絶望という暗闇の中で生きる意味を見出せないなら竈門炭治郎の生き方を哲学することできっとあなたの人生に希望の光を灯すことができることでしょう。 登場するのは実存主義の哲学者を中心にアルベール・カミュやフリードリヒ・ニーチェ、日本からも西田幾多郎などさまざまな角度から考察していますのでぜひ最後までじっくりとお楽しみください。
1 『鬼滅の刃』は癒しの物語
『鬼滅の刃』の概要を簡単に紹介したいと思います(知っている方はとばしてください)。主人公は山中で炭焼きを営む生活をしている竈門炭治郎です。ある日、鬼の頂点である鬼舞辻無惨に家族が襲われ、妹の禰豆子は人間の意識を残しながら鬼化することになってしまいました(人間は鬼にかまれることで鬼になってしまうのです)。
炭治郎は家族の仇をうち禰豆子を治療して元の人間に戻すために鬼殺隊に入隊します。そして、鍛錬を積んで仲間の剣士たちや半分は鬼でもある禰豆子と共に鬼と戦いながら、最終的に鬼殺隊の幹部(柱)たちと力を合わせて鬼舞辻無惨を消滅させる物語です。
以上がお話の簡単な概要なのですが、思想家の内田樹さんは次のように述べています。
「すぐれたマンガは世界の未来を予見するので、まるで世界がマンガを模倣しているように思えるということがそこでは起きる」
「鬼滅」がコロナ禍の時に社会現象にまでなった作品であることから、「鬼殺隊=医療者、鬼=コロナ(ウイルス)」のメタファーだと考えた人もいるでしょう。たしかに、鬼の特徴はウイルスの特徴とほとんど一致していると考えられます(生物ではないことや自己複製すること、弱点もあるが耐性をもつこともあるなど)。しかし、「鬼滅」の連載開始は2016年であることからこれは偶然の一致だといえます。つまり、「鬼滅」は人間と世界のあり方について深い洞察によって貫かれた作品であり、まるで今ここにいる自分のことを描いているような錯覚をもたらす作品だといえるのです。
この作品における「深い洞察」とはすなわち「境界線がない」ということです。舞台となった「大正時代」は近代と前近代がまだ明確に区別できないあいまいな時代です(鬼殺隊の多くは羽織に帯刀という恰好であり列車を見た伊之助は生き物と錯覚するなど)。
主人公の妹である禰豆子や珠世と愈史郎は味方であっても鬼となった者たちであり、鬼殺隊の剣士たちはほぼ全てが何らかのトラウマ的な経験を抱えている者たちなのです。いっぽう、鬼は「もう鬼になってもいい」と思うようなトラウマ的な経験をした元人間です。そして、鬼となって自分を失った鬼たちは死の間際にそのトラウマ的な経験を思い出して、それを語ることでつらい思い出と症状が劇的に寛解(消滅)するようになっているのです。
これはまさに精神分析の治療法を思い起こさせるような設定だといえるでしょう。以上のことから、「鬼滅」は病気と治癒をめぐる物語であると内田さんは語っています(それがたまたまコロナ禍というパンデミックの状況に当てはまってしまった)。
鬼だけでなく鬼殺隊の剣士たちでさえもそのほとんどはある意味で「病者」であり、そのほかの登場人物たちは「医療者」または「医療の支援者」となっています。だからこそ「鬼滅」の舞台のほとんどが戦場と病院で展開されることになっているのです。さまざまな思いを抱える剣士たちは戦場で傷つきながらも、病院で治療している時にお互いのことを許したり認めたりすることができる構成なのです。
このように、「鬼滅」は健常者と疾病者のことをデジタルな二項対立的に捉えるのではなく、そのあいまいな部分を生きているのが人間であることを示唆している作品なのです。ファスト教養や倍速映画などのようにわかりやすいことが求められる現代にあって、だれもが持っているであろうトラウマ的な経験をありのままに受け入れること―主人公の竈門炭治郎はそんな病者たちに寄りそう者の代表として描かれているのです。
2 「鬼舞辻無惨」×アルベール・カミュの哲学
「鬼滅」の物語では鬼によって大切な人を奪われた人々の姿が描かれています。また、その鬼でさえも鬼にならざるをえなかったさまざまな事情が描かれています。その根源にあるのはまちがいなく鬼舞辻無惨という「不条理」の存在ではないでしょうか?それが最もよく表現されているのが下弦の鬼たちを粛正する場面です。
「誰が喋ってよいと言った?貴様らの下らぬ意志で物を言うな!」
「お前は私が言うことを否定するのか?」
「全ての決定権は私にあり、私の言うことは絶対である」
「お前に拒否する権利はない、私が正しいと言ったことが正しいのだ」
これらはパワハラ上司ですらかわいく思えるような無惨の名言中の名言ですよね。個人的には逃げるのかと聞いたことに逃げませんと答えたら言われた②がとても怖いです(肯定しても否定しても怒られるならどうすればいいんでしょうか…?)。
何の落ち度もないにもかかわらず絶対的な力で人間も鬼も恐怖に陥れるという不条理―そんな鬼舞辻無惨のことを「不条理の哲学者」アルベール・カミュならどう見るでしょうか。
アルベール・カミュにとって「不条理」とは意味を求める人間の欲望と、それでも沈黙を守る世界との衝突から生じる感覚のことだとされています。私たちはついつい「なぜ生きるのか」という答えを求めますが、この世界は決してその答えを返してはくれません。そんなとき、私たちは生の無意味さに直面することで深い虚無感に包まれるのです。それこそが「不条理」の正体だと考えられます。
しかし、カミュは虚無に呑み込まれることも宗教に逃げることも拒否したうえで、答えのないまま意味を探し続ける反抗的な生き方をするべきであると考えました。これが『シーシュポスの神話』で描かれた「不条理への反抗」と呼ばれるものです。
鬼舞辻無惨は全てを支配する絶対的な力と永遠の命をもっているにもかかわらず、その本質は不安と恐怖に支配される存在だと考えられないでしょうか?無惨は死を徹底的に拒んで生き延びることだけを絶対的な目標にしていますよね。しかし、その生には目的などなく「なぜ生きるのか」という問いへの答えはありません。これはまさにカミュの考える「不条理」の典型だと考えられます。人間的な意味の探求はなく、ただ「生き延びたい」という衝動だけが存在している状態―無惨にとっての世界は探せば見つかる意味のある物語などではなく、捕食と支配の連鎖だけが繰り返される無目的な舞台でしかないのです。
カミュはこうした不条理な状況に対してシーシュポスの姿を通して「意味を与えられない世界でも、自ら意味を創造し続ける」ことを求めました。しかし、無惨は反抗ではなく死からの逃避を選びました。そして、支配と暴力によって恐怖を先送りにすることに腐心することになるのです。
無惨のこのような行為は、カミュが批判した「哲学的自殺」に近いものだといえるでしょう。答えのない不条理を直視せず、無限の延命という虚構に逃げ込んでいるにすぎないのです。いっぽう、鬼殺隊は死の不可避性を受け入れつつも限られた命に意味を込めようとします。それでもなお大切な人を守る姿や仲間を救う姿─それこそがカミュが考える「シーシュポスの反抗」だといえるのではないでしょうか?
鬼舞辻無惨の永遠の命は虚無を深め、鬼殺隊の有限の命は意味を輝かせるのです。この対比こそが「鬼滅の刃」における哲学的な核心の1つだと考えられます。アルベール・カミュの哲学について詳しく知りたい方にはこちらの動画がおすすめです。
3 「鬼」×西田幾多郎の哲学
「鬼滅の刃」では鬼殺隊と鬼との戦いが物語の主軸となっていますが、なぜ作者は「鬼」をモチーフに選んだのでしょうか?実は、日本固有の存在ともいえる「鬼」は単なる怪物や絶対的な悪ではなく、日本人の精神世界や価値観を映す鏡のような存在だと考えられるのです。
「鬼」という言葉はもともと中国の「隠(おぬ)」―すなわち、目に見えない霊的な存在を意味する語が変化したものだとされています。古代の日本では、疫病や災害など人智を超えた災厄を人格化した存在として登場しました。平安時代の『今昔物語集』『大江山絵巻』などでは、鬼は山中に棲む異形の者として描かれ、人里を脅かす存在であると同時に都の権力から疎外された者の象徴でもあったのです。
しかし、日本文化において、鬼は西洋の悪魔とちがって「絶対悪」ではありませんでした。仏教的視点での鬼は地獄で罪人を責める獄卒であり秩序を守る役割も担っています。民俗的視点での鬼は村の祭りなどで「鬼は外」と追い払われるような存在でありながらも、秋田の「なまはげ」のように鬼のことを神格化して祀る地域もあります。鬼とは破壊的であると同時に共同体を守る存在でもあるという二面性を持っているのです。
また、日本文学において、鬼はしばしば「人間が鬼になる」物語として描かれてきました。嫉妬や憎悪などの人間の感情が極限まで高まることで人は鬼へと変わってしまうのです。『源氏物語』の六条御息所は、嫉妬のあまり生霊からやがて鬼へとなって恐れられました。日本では鬼のことを「心の中に潜む影」というイメージで捉えられていたことがわかります。
しかし、鬼は恐怖の対象であると同時に、美的な存在としても扱われてきました。浮世絵や絵巻物に描かれる鬼は力強く、しばしば滑稽さや哀愁を帯びていますよね。これは、日本文化が「恐ろしいものを笑い飛ばす」あるいは「畏れを美に変える」という独特の態度を持っていることを示しているのです。
『鬼滅の刃』の鬼たちは、西洋的な「完全なる悪」とは異なり、かつての人間としての記憶や哀しみを抱えた存在として描かれています。これは古典文学以来の「鬼の人間性」を引き継いでおり、日本文化特有の倫理観─「悪にも理由や哀れみがある」という視点を現代に蘇らせていると考えられるのです。
西洋のキリスト教的な価値観では悪魔は絶対的な悪であると考えられていたことから、異端者や新大陸の人々を容赦なく凄惨な目にあわしていったという歴史があります。(十字軍で血にそまったエルサレムや奴隷制度など挙げればキリがありません)
このように、鬼であっても単純な悪として扱わないという態度は、日本における独特な倫理観の象徴でもあるのです。日本を代表する哲学者でもある西田幾多郎は「純粋経験」という概念を提唱しました。これは、自己と世界の区別が生まれる前の体験そのものの価値を重視するというものです。そして、自己とは世界から切り離すことができない経験そのものの中にある存在なのです。
西田幾多郎の哲学をもとに鬼の存在を考えてみれば、鬼であっても元は人間であり、その時の経験や感情の延長にいる存在だといえるでしょう。累という鬼は家族への強い愛情と執着が鬼になった後の言動にもあらわれており、妓夫太郎と堕姫という鬼たちは兄弟愛や貧困の記憶が鬼としての行動にあらわれています。だからこそ、炭治郎は鬼のことを単なる悪と断定して成敗するのではなく、鬼の過去や感情に寄り添って理解しようとすることができるのです。
このように、炭治郎が鬼のことをもともと人間であったと尊重する姿勢は、西田哲学的に「自己と世界の一体性を理解する行為」として読むこともできるのです。災厄の象徴でありながらも共同体を守る存在、恐れるものでありながらもそれはもともと人間の心の闇が生み出したもの―鬼のことをそのような存在として意識してきた日本人だからこそ、敵である鬼に対してもこれだけ多くの人が感情移入してしまうのかもしれません。日本人の精神性について解説しているこちらの動画もぜひご視聴ください。
4 「竈門炭治郎」×ニーチェの哲学
鬼は弱点をつかれない限り消滅することはありません。肉体は何度でも再生して無惨にいたっては首を切ってもすぐに回復してしまうのです。映画『無限列車編』では炎柱である煉獄杏寿郎に対して上限の鬼でもある猗窩座が「鬼になれ!」と迫るシーンが登場します。戦いで傷つき間もなく死ぬであろう煉獄に対して鬼になれば生きられると言うのです。
しかし、煉獄はそれを拒否しました。そして、「老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ」「老いるからこそ、死ぬからこそ堪らなく愛おしく尊いのだ」と言うのです。たしかに、鬼になれば永遠の時間を生切ることも可能になることでしょう。しかし、そこに蓄積されるものは虚無という終わりなき見えない苦しみにほかなりません。私たちの生は有限であるからこそ、自由や成長に意味や価値を見出すことができるのです。
実存主義の哲学者フリードリヒ・ニーチェは「運命愛」という概念を提唱しました。これは、自分に起こるすべての出来事を運命として受け入れ愛するという考え方です。人生の苦難や運命を拒む(無限を望む)のではなく、ありのままに受け入れる(有限の生を生きる)ことが力になるとニーチェは考えたのです。
煉獄さんを失った時に炭治郎はこうつぶやきます。「何か一つできるようになっても、またすぐ目の前に分厚い壁があるんだ」家族を鬼に殺されて妹を鬼にされるという絶望的な状況、上限の鬼という圧倒的な存在から身を挺して自分たちを守ってくれた師との別れ、炭治郎はそんな状況にあっても自分の運命を受け入れて強くなろうと立ち上がります。このような自己の可能性を最大限に引き出そうとする生命の根源的衝動のことをニーチェは「力への意志」と表現しました。
この後、炭治郎は仲間と共に鍛錬を積み、やがて上限の鬼たちを倒すまでに成長します。そして、映画『無限城編』において、いよいよ炭治郎は猗窩座に対して「弱い者は強くなり、また自分より弱い者を助け守る」と言うのです。かつて助けられる存在であった炭治郎が次は自分が守る番だと決意した瞬間です。大切な人を助けられなかった後悔が猗窩座を鬼に変えたのに対して、炭治郎は助けられたことを胸に鬼殺隊として成長していくことになりました。まさに、ニーチェが示した「超人思想」のように炭治郎は自らの価値観で倫理を創造しながら生きていくことを決意するのでした。
物語の中では炭治郎は決して最強の剣士ではありません。それでも最後には仲間たちと力を合わせて鬼舞辻無惨を消滅させることに成功しました。竈門炭治郎という人物をニーチェの視点から見てみることで運命を呪うのではなくそこに意味を創造すること、倒れても再び立ち上がる永劫回帰的な意志の強さ、外から与えられた価値ではなく自らの使命に従うこと、苦痛や喪失ですらも成長の糧に変えるという姿勢などを学ぶことができることでしょう。
5 まとめ
今回は『鬼滅の刃』について哲学の補助線を引いて考えてみました。社会現象を生み出すほどの芸術作品には必ず理由があるはずなのです。「哲学の補助線」を引くことで少し高い視座から鬼滅ブームを考えることができましたか。
埋めることのできない絶望的な格差、幸福になる希望をもつことさえも許されない社会情勢、さまざまな答えの出せない人生の問いと向き合わなければいけない時、哲学はきっとあなたの助けとなるヒントを与えてくれることでしょう。
今回はアルベール・カミュやフリードリヒ・ニーチェに登場してもらいましたが、我妻善逸とキルケゴールの哲学や嘴平伊之助とストア派の哲学なども面白そうですね。(ぜひコメント欄にあなたの考えを送ってください!)
「あてのない学堂」では「鬼滅の刃」のほかにも、マンガや映画に対して「哲学の補助線」を引いて考える企画を行っています。ぜひこれらの動画も合わせてチェックしてみてください。



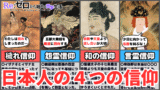
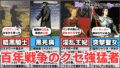
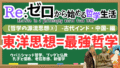
コメント