今回は2024年に発売された本の中でまちがいなくNo1のこの1冊をもとに、「労働と文化の両立」について「哲学の補助線」を引いて考えていきましょう。参考文献は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(著者:三宅香帆さん)です。
突然ですが、あなたは働くようになってから読書をする時間を確保できていますか?え、そもそも読書をする習慣がなかった…では読書のかわりに就職してから好きだった趣味の時間をもつことができていますか?多くの人が就職を機にあきらめなければいけないような状況なのではないでしょうか?なぜ昔と比べて社会はこんなにも豊かになっているのに、実感としてわたしたちはこんなにも苦しさを感じているのでしょうか?それは現在の社会では読書のできない働き方が当たり前と思われているからなのです。これはつまり「労働と文化的生活を両立させることのできない社会」ということです。
本書はこの問題を解決するためのヒントを思いもよらなかった視点、すなわち「労働」と「読書」の関係についての歴史という視点から教えてくれます。一見すると回り道のように思える本書の構成そのものが、実は「なぜ本を読めないのか」というタイトルの伏線回収になっているところも最高です。Youtubeでもさまざまな解説や著者の方のインタビューが出ていますので、今回はこのチャンネルらしく「哲学の補助線」をひいて本書を紹介してみました。哲学という教養があってこの本を読むのと読まないのでは印象も大きくかわるはずです。きっと明日からの人生に役立つヒントがつまっているのでぜひ最後までご視聴ください。
1 本書の概要 -労働と読書の歴史-
わたしたちの近代的な読書週間は明治時代に始まりました。明治から大正時代にかけては日本が近代化していく過程で、国家が青年たちに立身出世の大切さを説いたのです。そのため「修養」という名の自己啓発をすすめる書籍や雑誌が流行することになりました。読書は青年たちが立身出世するための手段として教養を重視する傾向が多かったようです。
戦前から戦後にかけてはサラリーマンという新中産階級が誕生しました。そのため「教養」を大衆に啓蒙していく円本や全集などが流行するようになりました。読書は娯楽化していきエリートだけでなく大衆にとっても教養をえるものとなりました。
高度経済成長期からバブルにかけては終身雇用のような日本的働き方が定着した時代です。読書は立身出世のための教養からメディアと連動した娯楽の1つとなったのです。
バブル崩壊から現代にかけては情報社会の到来とともに自己啓発書が流行しています。しかしこれはコスパやファスト教養などの言葉からもわかるとおり情報を重視して、自分の意図していない知識を不要(ノイズ)とするようになっていることを意味します。
本書では「情報」のことを「知りたいこと」としているのに対して、「知識」のことを「ノイズ+知りたいこと」と定義しているところが興味深いところです。つまり読書を通してえられる知識には「ノイズ(偶然性)」がふくまれるのです。教養としての古典や読者が想定していなかった偶然出会う展開こそが知識なのです。これまで日本において長時間労働が当たり前だったにもかかわらず読書ができていたのは、それが立身出世や社会的地位向上のための「知識」をえる媒体だったからなのです。しかし現代において労働に必要なものは自己啓発書に代表されるように、自分に関係のある「情報」のみをピックアップして行動する能力になっているのです。ノイズが除去された「情報」の価値があがることで必然的に読書の時間が減少したのです。
大きな転換点となったのはIT革命と新自由主義の波の到来でしょう。新自由主義とは個人の自由を最大限に尊重して政府による介入を少なくする思想です。そのためみんなで助け合おうという共同体論理よりも、自己責任の名のもと好きなように生きるという個人主義が重視されるようになるのです。
いつでもどこでも自分で情報をえることを可能にするインターネットの普及は新自由主義の思想と共鳴するかのように自己責任の論理を内面化するようにしました。人類は常に自分の外側にいるもの(他国との戦争や政府への反発など)と戦ってきました。しかし現代社会において敵は自分の内側にいるのです。なぜなら新自由主義では決してわたしたちのことを強制することはありません。その代わりわたしたちは競争心をあおられることによって、「自分から」その戦いに参加するようにさせられているのです。その結果わたしたちは自分で自分を追い込むことをよしとするようになってしまうのです。
ドイツの哲学者ビョンチョル・ハンは著書『疲労社会』において、「企業や政府から押し付けられた規律によって支配されてしまうこと」を問題としました。わたしたちは自分で自分のことを搾取してしまった末に鬱や燃え尽き症候群となるのです。「疲労社会」では仕事で自己実現できている人がキラキラ見えてしまいます。そのためそこに参加しようとすれば必然的に「全身」のコミットメントが必要となります。だからこそ本書の結論は「全身全霊を褒めるのやめませんか」で締めくくられているのです。そして「半身」のコミットメントこそがわたしたちの望む新しい社会、すなわち「働きながら本を読める社会」をつくることにつながるのです。「半身」とはいわゆる「にわか」のことです。「にわか」と聞くとどうしてもネガティブなイメージをもたれがちであるが、そのようなイメージをもつことこそが全身コミットメントをよしとする弊害ともいえます。労働に限らずどんなこと(それこそ読書でも)にわかでいいのです。
もちろん全身全霊を否定しているわけではありません。人生の中では何かに全身全霊で取り組むことがよい時期もきっとあることでしょう。しかしそれはあくまで一時期のことでありそれこそが至高のものである必要はないのです。『疲労社会』の中には以下のようなニーチェの言葉が引用されています。「もっと人生を信じているなら、瞬間に身をゆだねることが少なくなるだろう。だが君たちには中身がないので待つことができない ―怠けることさえできない!」全身のコミットメントは自我を消失させて没頭するということなのです。それが楽しいことにまちがいはなくわたしだってそう思うことが多々あります。それでもニーチェは「そんなのは人生を信じていないのだ」と首をふるのです。自分を忘れないために、他者を受け入れることができるように「半身」でいないさい…と。
まずはあなた自身が全身全霊を賞賛することをやめることから半身社会は始まります。半身社会は他者とのかかわりが不可欠な分だけ複雑で面倒な社会です。それでも自分や他者を忘れることなく誰も燃え尽きない社会を生きたいと著者は言います。「働きながら本を読める社会をつくるために半身で働こう」これが本書の結論です。以上ここまで簡単に本書の概要をまとめてみました。次章ではここに「哲学の補助線」をひいてよりわかりやすく紹介していきたいと思います。
2 新自由主義
本書でたびたび出てくる新自由主義についてもう少しくわしく紹介したいと思います。1928年の世界恐慌から1970年代に入るまではケインズ経済学が主流となっていました。経済学者のジョン・メイナード・ケインズは不況時には有効需要を生み出すために、政府が積極的に財政出動するべきであると提唱したのです(大きな政府)。しかしケインズ経済学では不況の克服には効果が大きかったいっぽうで、財政出動によるインフレや財政赤字によるスタグフレーションが問題となります。そこでミルトン・フリードマンやフリードリッヒ・ハイエクが提唱したのが個人の自由と市場原理を再評価して政府の介入を最低限にするという「新自由主義」です。このような考え方をもとにさまざまな政策を実行した代表的な政治家にはロナルド・レーガンやマーガレット・サッチャー、そして小泉純一郎などがいます。新自由主義的社会では、福祉・公共サービスを縮小したり規制緩和したりするとともに、市場原理を重要視(企業間の競争が激化)するような社会のことです。日本でも1990年代から2000年代にかけて民営化・金融自由化がすすめられました。その結果、新自由主義の自己決定・自己責任の論理を内面化する人々が増加したのです。
たしかにものごとを自己決定するという考え方そのものは悪いことではありません。しかし「自分で決めたことだから失敗も自己責任」という考え方に染まりすぎることは組織や政府にとってとても都合がいいことであることも事実なのです。何も疑わない人が増えれば為政者や管理者は都合のいいルールを制定しやすくなります。
また新自由主義的な政策(民営化など)は財政難に苦しむ政府にとって都合がよく、「人それぞれ」で連帯することなくバラバラでいてくれる方が支配もしやすいのです。その結果として貧富の差はますます拡大することになり社会は分断されていくのです。「新自由主義」の問題点などについてはぜひこちらの記事をごらんください。
新自由主義の中でもさらに個人主義に振り切った思想がリバタリアリズムです。リバタリアリズムとは個人の自由を最大限に尊重する自由主義のことです。ハーバード大学のロバート・ノージックの「最小国家論」では国家を廃止しないまでも、その役割は国防・裁判・治安維持といった最小限にとどめるべきであると指摘されました。またこのような考え方に対して共同体を重視する思想がコミュニタリアニズムです。もっとも有名なのはテレビ番組でも注目されたハーバード大学のマイケル・サンデルです。これらの思想はまとめて「政治哲学」のように分類されています。政治や経済についての知見も哲学的に考察されているところが現代思想の大きな特徴です。
3 構造主義とポスト構造主義
本書では新自由主義のような価値観は社会がつくり出したものであると述べられています。このように私たちがどのようにものごとを考えるかは、社会の構造に支配されているという哲学思想を「構造主義」といいます。
構造主義の祖といわれる哲学者クロード・レヴィ=ストロースは未開部族の調査を通して「野生の思考」の中にも真理が存在することを明らかにしました。近代文明からおくれていると思われていた未開部族の風習にも合理的なものを見出し、適当に作った「プリコラージュ」という工作群にも意味があることを指摘したのです。ポストモダンとよばれるこのような現代思想は「私」の意識を中心とした絶対的に正しいとされる唯一の答えに向かう近代の思想に対するアンチテーゼなのです。
構造主義を引き継ぐ形で登場したのがポスト構造主義であり、その代表的な哲学者にはミッシェル・フーコーやジル・ドゥルーズがいます。フーコーは「権力によってつくられた構造に人間社会は支配されている」として、「エピステーメー」こそが人類の構造であると考えました。これはそれぞれの時代において特有の形で存在する人間の思考形式のことです。私たちはそれぞれの時代におけるエピステーメーによってものごとを認識しています。これは無意識のうちに私たちの思考や感情がそれぞれの時代のエピステーメーによって支配されているということでもあります。フーコーは現代における私たちをしばる構造をパノプティコンにたとえています。功利主義者のベンサムによって考案されたパノプティコンは、一望監視装置という特性をもった円形の監獄のことで囚人が「監視されているかもしれない」と考えて自ら規範を守るようにするシステムです。現代の私たちも「同調圧力」という抽象化された権力によって社会という構造におさまるように監視されていると考えられるのではないでしょうか?そして無意識のうちに私たちを縛ることになるこの構造からはみ出すものを「狂気」として排除するシステムがつくられているとフーコーは指摘しました。
ドゥルーズは「ノマド」という生き方を提唱したフランスの哲学者です。ドゥルーズは「ものごとの関係には体系的な仕組みが存在する」という西洋思考を批判して、その体系から外れるものが排除されてしまう危険性について指摘しました。私たちも本来は欲望のままに生きていく存在であるはずなのですが、構造に抑圧されることで型(アイデンティティ)におしこめられていると指摘したのです。無意識に形作られたアイデンティティによって縛られながら生きることになっている、このような状態のことを「パラノイア(偏執症)」といいます。一方アイデンティティに縛られることなく、欲望のままに生きる存在のことを「スキゾフレニア(分裂症)」といいます。スキゾフレニアはリゾーム的な思考のもとで、自分の欲望のまま生きるだけではなく他者の価値観をも受け入れることができます。ドゥルーズはこのような生き方こそが大切であると考え、スキゾ的な生き方の理想形を「ノマド(遊牧民)」としました。本書の中で紹介されている『ノマドワーカーという生き方』という書籍もドゥルーズの哲学にその由来があることをぜひ覚えておいてください。
哲学の中でも特に構造主義のような現代思想について知っておくことは、「当たり前を疑う」という知的態度をもつことに大きく関わることでしょう。「働きながら本を読むことができない社会っておかしくない?」「なぜ社会はこんなにも豊かになっているのに私たちの心は貧しくなっているの?」「燃え尽きるまで全身全霊のコミットメントをすることが本当に正しいの?」私たちが当たり前と思っていることが実は社会の構造に支配されている結果だとしたら?
4 他者論 -エマニュエル・レヴィナス-
本書のもっともおもしろい主張が情報とはノイズが除去された知識であるという点です。新自由主義的社会で成功するためにはノイズの除去された「情報」にこそ価値があり、アンコントローラブルなノイズは労働するのに必要でなくなっていると書かれていました。『ファスト教養』が意味するものこそが「ノイズを除去した情報」としての教養なのです。現代社会では他人や社会といったアンコントローラブルなものは捨てて、自分の行動というコントローラブルなものを変革することを促すことが求められています。それはつまり自分に関係ないものをノイズとして除去する生き方をよしとしているのです。しかし私たちはノイズを完全に除去する人生を送ることなどできるのでしょうか?
そこでみなさんに知ってほしい哲学者が他者論で有名なエマニュエル・レヴィナスです。レヴィナスはユダヤ人の両親のもとリトアニアで生まれた哲学者です。レヴィナスは故郷の人々や近親者をナチスに虐殺されるという経験をもち、その非人道的な行為と親類を失ってもなお回り続ける世界に対して恐怖を感じるのです。そしてレヴィナスは「イリヤ」こそが人間の恐怖を生み出すものであると考えました。イリヤとは無の闇と沈黙の中にある自己を中心に築かれた世界のことであり、私という主体がないままにあるだけの永遠の暗闇が広がっているような状態のことです。レヴィナスはこれまでの哲学(主にカントの哲学)が、全て自己の中で完結することに終始してしまっていると指摘しました。そして自己の中で全てに意味付けを行う哲学を「全体性の形而上学」として批判して、このようなエゴイズムこそがイリヤを生み出す原因であると考えたのです。
ではどうすればこのイリヤから抜け出すことができるのでしょうか?第二次世界大戦をおえてあらゆるものを失ったレヴィナスはイリヤの中にいました。そんな彼をイリヤから救い出してくれたものこそが「他者」だったのです。「他者」とは私には理解できない何かのことでありそれは他人に限りません。そして「他者」とは自己の意識の外にいるため理解もコントロールもできない存在なのです。なぜなら自己の中でどれだけ論理的に他者を意味づけしたとしても、それを否定する別の他者が自己の意識の外側のどこかに必ず存在するからです。(この考え方を否定するということ自体が他者の存在を肯定しているとも言えます)。そのためレヴィナスは他者のことを「無限の存在」と表現しました。レヴィナスの「他者論」では否定することのできない絶対的な真理など存在しないのです。ということは「他者」とは真理への到達を阻む自分にとって不都合極まりない存在であり、ソクラテスが命をかけて探究した絶対的な真理への旅は他者の前に敗北をしたのです。
それなのになぜレヴィナスは迷惑な存在であるはずの他者こそがイリヤから私たちを救い出してくれるものと言ったのでしょうか?たしかに他者は私たちを悩ませることになる困った存在です。しかしこんなふうに他者のことを考えることもできるのです。「他者とは私という存在を自己完結のひとりぼっちから救い出してくれる唯一の希望であり無限の可能性である」とレヴィナスは言いました。あなたが他者の存在しない世界で絶対的な真理に到達できたと想像してみてください。全ての問題を即座に解決することができて、全ての反論を無効にする完璧な理論をもつことができたとします。それはあなたにとって理想の世界のように思えますが…本当にそうでしょうか?きっとそこにあるのはただの独りよがりな自己完結であり、何の楽しみもない永遠の虚無が続く退屈な世界のはずです。
しかし幸運なことに現実には必ずあなたの目の前には他者がいるのです。他者はあなたにとって理解もできなければあなたのことを否定してくる不愉快な存在です。でも他者がいるからこそあなたは対話すること問いかけ続けることができるのです。理解できないわからないものがあるからこそ「本当は?」と問いかけることができるのです。それゆえ私たちは他者を殺すことなく他者と向き合い続けなければいけないのです。他者の顔は常に「汝殺すなかれ」と訴えているとレヴィナスは言いました。これは物理的な殺害に限らず相手を無視することや排除することも含みます。だからこそ私たちは他者の顔と対話する時には倫理的な抵抗力によって、他者に対して無視するでも排除するでもない無限の責任をもつことになるのです。私たちは他者によって生かされており他者の存在こそが私を倫理的にしてくれるのです。それこそがイリヤという自己完結のエゴイズムから抜け出す唯一の方法なのです。
この世にたった1つ絶対的な真理があるとすればそれは「必ず私のことを否定する他者が存在する」ということなのかもしれません。そして他者とは私が理解することもコントロールすることもできない不愉快な存在です。しかしだからこそ「本当は?」と問いかけることができる唯一の存在でもあるのです。そうすることで他者の中に新しい価値観や無限の可能性を見出すことができるのです。私たちは無意識のうちにノイズを除去することが大切だと思わされているとしたら?しかしノイズ(他者)を完全に除去することなどできはしないのです。そんな視点をもってあらためて本書を読んでみれば、これまで気づけなかった新しい未来をきっと発見することができると思いますよ。
5 まとめ
今回は「労働と文化の両立」について考えてきました。動画の中では紹介することができなかったこともまだまだありますので、ぜひ本書を手に取って読書の歴史や労働とよりよい社会のあり方を考えてみてください。「哲学は何の役にも立たない」と思われがちですが、現代社会を生き抜くためのヒントが哲学の中にはたくさんあるのです。「人間は思考することをやめてしまえば誰もがナチスのような巨悪になりうる」公共哲学の哲学者ハンナ・アーレントはこのように言いました。これからも「哲学の補助線」を活かしていろいろな本を紹介していきますので、ぜひゼロから一緒に学んでいきましょう。本日の旅はここまでです、ありがとうございました。

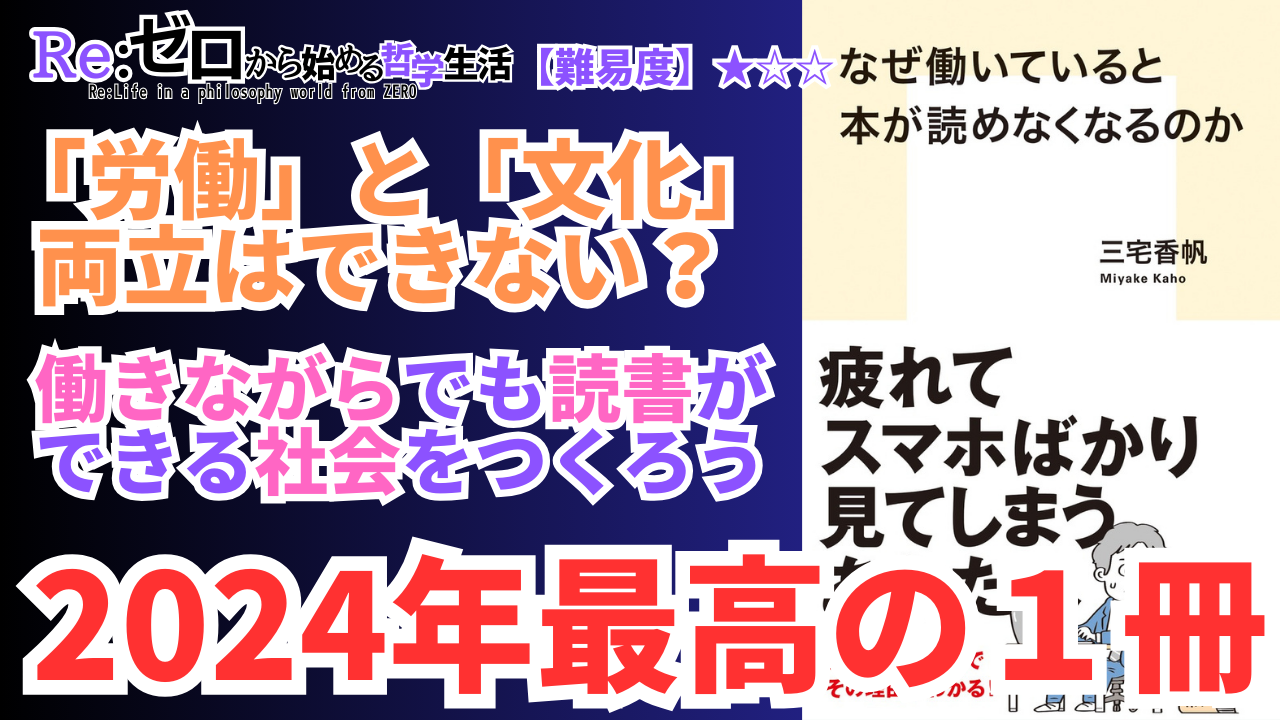








コメント