今回は「Re:ゼロから始める哲学生活」源流思想①ヘレニズム哲学編を解説します。参考文献は『哲学と宗教全史』(著者:出口治明さん)です。
ポール・ゴーギャンのこの長いタイトルの絵画―『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』をご存じでしょうか?「世界はどうしてできたのか?」「人間はどこから来てどこへ行くのか?」この最も根源的な問いについて考えてきたのが哲学と宗教なのです。 哲学という言葉の起源は「philosophy(愛知)」のことであり、「知(sophy)を愛する(philo)」という意味です。これを明治時代に西周が「賢哲を愛し希求する」という意味で希哲学―すなわち「哲らかにすることを希む学問」になったとされているようです。 つまり、哲学を一言で表すならば「真理を探究する知的営み」ということになります。「そもそも正義とは何か?」のように「そもそも」を哲かにする学問が哲学なのです。 最近、この哲学がいろいろな場面で注目されていることをご存じですか?実生活やビジネスには何の役にも立たないと思っている人もいるかもしれませんが、Googleやアップルでは専属の哲学者をフルタイムで雇用しているそうです。 私たちは哲学を学ぶことで固定観念を破るための方法を知ることができるようになります。固定観念とはその時代の人にとってあまりに常識的なものとなっているので、「そもそも」を疑うことができない人には何が固定観念なのかも自覚できないのです。 『暇と退屈の倫理学』の著者である國分功一郎さんは劇作家ブレヒトの言葉「英雄がいない時代は不幸だが、英雄を求める時代はもっと不幸だ」に対して、「哲学のない時代は不幸だが、哲学を必要とする時代はもっと不幸だ」と述べています。哲学が必要とされるこの時代に哲学の教養を欠いては幸福になることなどできないのです。 そこで、このシリーズでは「古代から現代までの哲学」を全て解説していく予定です。今回は西洋哲学の原点でもある古代ギリシア(ヘレニズム)の哲学を紹介します。哲学を継続して学ぶことができますのでぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 古代ギリシアの哲学
1-1 自然哲学者 -解説編-
古代ギリシアは哲学が生まれた地なのですがどのような経緯で誕生したのでしょうか。もともと、世界で起こることを体系的に説明していたものは「神話」でした。そして、あらゆる現象を神々の意志として説明するのが「神話的世界観」です。古代ギリシアでは多神教のギリシア神話(ミュトス)が信じられていたのです。もともと、口承で伝えられてきた神話でしたがしだいに文字化されていくのです。
まず、ホメロスの『イリアス』と『オデュッセイア』(いずれも叙事詩)があります。これは正義を求めるギリシアの英雄たちを理想の人間像として描いたものです。ただし、神の定める運命に逆らうとみな滅びることにもなっています。
つぎに、ヘシオドスの神々の系譜を描写した『神統記』があります。これはカオス(混沌)から万物が生まれ最高神ゼウスが神々を統括するという物語です。
ほかに、悲劇作家ソフォクレスの『オイディプス王』『アンティゴネー』などもあります。これらは神話をもとに人間の残酷な運命を見つめる作品となっています。心理学者フロイトのエディプス=コンプレックスという概念もここからきています。
しかし、このような神話による説明では正しいのかどうかを確かめることができません。そこで、自分たちの想像力による「神話(ミュトス)」ではなく、「論理(ロゴス)」によって確かめようとする人たちが登場するようになるのです。このような、世界のあり方を客観的に探究する人たちのことを「自然哲学」者といいます。
自然哲学者たちは自然を探究する中で世界のあらゆる現象を説明できる原理―つまり万物の根源(アルケー)を探究しました。タレスは「最初の哲学者」といわれるミレトス学派を形成した自然哲学者の1人です。万物の根源(アルケー)は「水」であると考えました。
ピタゴラスは宇宙と音階の中に調和と秩序を見出し万物の根源は「数」であると考えました。三平方の定理でおなじみのピタゴラスは宇宙のことをコスモスとよんだ最初の哲学者です。
ヘラクレイトスは「万物は流転する(パンタ・レイ)」と言いました。万物の根源は「火」であると考えて生成変化の象徴としての火をあげたのです。
デモクリトスは顕微鏡もないのに万物の根源は「アトム(原子)」であると考えました。さまざまなアトムが真空(ケノン)の中を運動していると考えたのです(驚異!)。この4人は「自然哲学」の四天王であり何度も出題されているので必ず覚えてください。
1-2 相対主義者とソクラテス -解説編-
古代ギリシアではポリス(都市国家)が発展して民主政治が行われていたことから、人々の関心は自然(ピュシス)から法や社会制度(ノモス)へと向かったのです。民主政治において最も大切なことは「弁論の技術」です(一般人の支持をえるため)。そのため、弁論術を教えるソフィスト(詭弁家)が登場するのです。有名なソフィストは「人間は万物の尺度である」と言ったプロタゴラスです。真理や正義などあらゆるものごとは人それぞれであるという「相対主義」の立場です。
このような時代背景のもと「絶対的な真理はある」と考えたのが哲学の祖ソクラテスです。ソクラテスは人間にとってのアレテ―(徳)とは魂を善いものにすること―つまり「魂への配慮」であり善く生きることが大切であると考えたのです。そして、善についての知を得られれば必ず善い行為ができる(知行合一)としました。
ある時ソクラテスの友人がデルフォイのアポロン神殿で「ソクラテスより賢いものはいない」という神託を受けたので伝えに行きました。そこで、ソクラテスは真偽を確かめるためにあらゆるソフィストたちと対話したのです。すると、ソフィストたちは賢いふりをした知ったかぶりだということがわかったのです。そのため、ソクラテスは自分も無知であることはまちがいないが、無知であると自覚しているだけまさっているということに気づきました。これが有名な「無知の知」です。
ソクラテスは相手の矛盾を指摘することによって相手に真理を発見させる最強の対話法―いわゆる「問答法」(産婆術)によって対話をしたとされています。しかし、ソクラテスはあらゆる知識人たちを論破してしまったので、「アテネの神々とは異なる神を信じて若者を堕落させた」という罪で死刑判決が出ました。ソクラテスはこの裁判で雄弁に自己の正当性を語るのですが、この時の様子を描いたのが弟子のプラトンによる『ソクラテスの弁明』です。
友人のクリトンはソクラテスに面会をした時に脱獄することをすすめました。しかし、ソクラテスは「不正(判決)に対する不正(脱獄)は許されない」と拒否するのです。そして、前述の「大切なのはただ生きるのではなく、善く生きることである」と言うのです。ソクラテスにとって哲学とは真の自己(永遠不滅の魂)を知ることにほかなりませんでした。だからこそ、死は悲しむべきではなく真の自己になることだと考えて毒杯を飲んだのです。
1-3 プラトンとアリストテレス -解説編-
ソクラテスの弟子プラトンは「観念論」とよばれる哲学の原型を構築した偉大な哲学者です。プラトンは「善とは?」「美とは?」のようなものごとの本質そのものについて考えました。そして、善そのものや美そのものは永遠不滅であり、感覚ではとらえることのできない永遠不変の真の実在のことを「イデア」とよんだのです。つまり、善そのものとは「善のイデア」、美そのものは「美のイデア」ということです。
たとえば、黒板に三角形が描かれていたとしても、それは三角形ではないのです。その三角形にはわずかな歪みがありそもそも線分に太さがあるので三角形とはいえません。そのため、目に見える三角形は「三角形のイデア」に似ているものでしかないのです。では、なぜ、目には見えない三角形というものを理解することができるのでしょうか?プラトンは「知性」によって本質(イデア)をとらえることができると考えたのです(「三角形とは3本の線分に囲まれた図形」というように…)。
いっぽう、プラトンは感覚によってとらえているのは現象にすぎないのであって、私たちがそれを見た時にそのもの(イデア)と勘違いしてしまうことを戒めているのです。これが有名な「洞窟の比喩」です。
プラトンは中でも「善のイデア」を太陽にたとえて特別なものであると考えていました。太陽は眩しいので直視することができないように善のイデアも直視することはできません。しかし、人間には真理や理想を追求しようとする本能的な欲求がある(理想主義)と考えて、この欲求のことをエロースと言いました(ソクラテスの「知を愛する」と同義)。
プラトンの哲学でもう1つ覚えておきたいのが「魂の三分説」と「四元徳」です。まず、プラトンは魂を「理性」「意志」「欲望」という3つの部分からなると考えました。これが「魂の三分説」です。そして、それぞれに対応する「知恵」「勇気」「節制」という徳(アレテ―)があり、これら3つがバランスよく調和することで「正義」が実現すると考えたのです。「知恵」「勇気」「節制」に「正義」を合わせて「四元徳」と言います。
さらに、魂についての考え方は国家(ポリス)にもそのまま当てはまるのです。つまり、国家は「統治者」「軍人」「生産者(庶民)」という3つの階級からなり、それぞれに対応する徳がそのまま「知恵」「勇気」「節制」ということなのです。プラトンは師ソクラテスを死刑に処した愚かな民主制のことを嫌悪していました。だからこそ、知恵をもつ哲学者が王として統治すること(哲人政治)でしか正義を実現することはできないと考えたのです。
アリストテレスはプラトンの弟子として学園アカデメイアで学び、論理学から天文学まであらゆる学問を体系化したことから「万学の祖」といわれます。しかし、プラトンが「理想主義」であったのに対してアリストテレスは「現実主義」です。
アリストテレスはイデア論を否定してものごとの本質は個物に内在していると考えました。まず、すべての事物はそれが何であるのかを表す「形相」に、それが何からできているのかを表す「質量」が結びつくことで成立すると考えたのです。「形相」のことはエイドス、「質量」のことはヒュレーともいいます。
プラトンは「机」と「机のイデア」は別のもの(二元論)として考えていましたが、アリストテレスは机の本質は机の中に内在するので現実と切り離せないと考えたのです。ただの木材は机になる可能性をもっていることから、「木材は机の可能態(デュナミス)」であると表現することができます。
いっぽう、机は木材の可能性が顕在化したものであることから、「机は木材の現実態(エネルゲイア)」であると表現することができるのです。アリストテレスは現実世界をこのような動的なもの(運動・変化)として捉えたのです。
現実世界がダイナミックに運動したり変化したりするのは以下の2つの理由があります。ひとつは、木材が机になるには誰かが運動を起こすことが必要になるので、この時の加工作業にあたるものを「始動因」であると表現できます。もうひとつは、机がつくられたのはものをのせるという目的のためなので、このような事物の目的のことを「目的因」であると表現できるのです。
また、アリストテレスは「倫理学」においても徳(アレテー)を「知性的徳(判断力)」と「習性的徳(人柄)」に分類して考えました。知性は学習によって習得できますが賢い人が善い人であるとは必ずしもいえません。そのため、人間には習性(倫理的な徳)も求められることから、過少と過剰を避けた中庸に適った善なる行為を習慣化することが必要であるとしたのです。
そんなアリストテレスの目的論の立場に立って人間の目的は何かと考えた時には、「幸福(エウダイモニア)」こそが人間の目的にあたるといえるのです。アリストテレスの有名な言葉には「人間はポリス的動物である」というものがあります。人間はポリスという共同社会で生きる存在であるのだけれども、そのためには共同体に結合させるための原理が必要であると考えました。それが「友愛」と「正義」の2つです。「友愛」とは相互に相手の徳を尊敬して相手の向上を願うような関係で成立する愛、「正義」とはさらに「全体的正義」と「部分的正義」に分けて考えられています。
「全体的正義」とはすべての市民が共同体の法を守ることであり、「部分的正義」とは状況に応じて公正さを保つための正義のことで以下の2つがあります。1つは「配分的正義」で個人の状況に応じて報酬や名誉を配分してもよいということ、もう1つは「調整的正義」で利害得失などの不均衡を調整してもよいという正義です。
こうして「友愛」と「正義」が実現すれば理想の国家ができあがるのですが、アリストテレスは現実主義者なので実際に可能かどうかまで検討しています。たしかに、理想的なのは「君主制」であっても堕落すればすぐに「独裁制」になります。そのため、堕落する可能性まで考慮するのであれば、現実的にリスクの少ない政治体制は「共和制(≒民主制)」であるといえるのです。民主制は時間も手間もかかるシステムではあるけれども中庸に適う方法であり、自国優先主義が台頭している現実社会の課題を考える上でも重要な議論だといえます。(そのため、試験問題として必ずといっていいほど出題される分野でもあるのです)
1-4 ヘレニズムの哲学 -解説編-
古代ギリシアのポリス社会はマケドニアによるギリシア統一によって終焉しました。アリストテレスが家庭教師を務めたこともあるマケドニアのアレクサンダー大王は、ペルシアやインドにまで東方遠征をして巨大な帝国を築き上げました。その結果ギリシアのポリス社会は破壊されてコスモポリタン思想が誕生するのです。
ギリシア人にとってギリシア語を話さない者はすべて野蛮人であると見なされていました。しかし、巨大帝国の誕生によって普遍的な人間観(コスモポリタニズム)が生まれたのです。また、ポリス社会という共同体を前提とする価値観が崩壊したことで、精神的な拠り所をなくして個人主義的な倫理が広がっていくことになるのです。ソクラテスたちが「公共の善」を探究したのに対して、この時代では個人的な「心のやすらぎ」が求められるようになっていったのです(人間関係が希薄な現代でもまたこの時代の哲学が再注目をあびているといえます)。
ヘレニズム時代(ヘレネス=ギリシア人)の哲学にはエピクロス派とストア派があります。まず、「エピクロス派」の思想はエピクロスが創始した哲学であり、肉体的な快楽ではなく心の平静(アタラクシア)を追求する哲学です。快楽主義ともいわれますが語感からとても誤解されがちな哲学でもあります。なぜなら、エピクロスは酒池肉林のような刹那的な快楽を退けようとしていたのです。ソクラテスのように街中で議論をするなどもってのほかであり、エピクロスは「隠れて生きよ」と言ってひっそりと隠棲することをすすめました。実際に「エピクロスの園」という学園をつくって仲間と静かに共同生活をしたのです。エピクロスはデモクリトスの原子論を信じていたことから、「死など誰も経験したことがないのだからおそれることはない」と説いてもいました。
いっぽう、「ストア派」の思想はゼノンが創始したといわれています。ストアはストイックの語源にもなっている通り禁欲主義ともいわれ、欲望に惑わされない不動心(アパテイア)を追求する哲学です。エピクロス派の「隠れて生きよ」に対して、前の問題にも出題されていたように、ストア派では自然の法則(ロゴス)―つまり「自然に従って生きよ」と考えたのです。ストア派の有名な哲学者には奴隷出身のエピクテトスやローマ帝国のセネカ、そして哲人皇帝マルクス・アウレリウスなどがいます。ストア派の哲学についてはぜひこちらの動画をご視聴ください。
まとめ
今回は「大学入試共通テスト講座③源流思想-ヘレニズム哲学編-」を解説しました。西洋哲学の二大潮流の1つである「ヘレニズムの哲学」の基礎をマスターできましたか?
「哲学は何の役にも立たない」「哲学は難しそうで興味がもてない」そんなふうに思われるかもしれませんが哲学って実はとても面白いんですよ。このチャンネルでは哲学の面白さを発信していますのでぜひ受験勉強のためだけと思わず、学生や社会人の方にも楽しみながら哲学のことを学んでほしいと思います。
これまで正しさをめぐる暴力によって数えきれない罪なき人々の血が流れてきました。大航海時代の植民地支配、アメリカ大陸の制服、ナチスによるホロコーストなどなど。いずれも「絶対に正しい」とされていることを盲信した結果が引き起こした悲劇です。私たちは「絶対的正義」を掲げた時に恐ろしいほど残虐なことを可能にしてしまうのです。ポピュリズム全盛ともいえる現代社会もまた倫理なき世界へと逆行している気がします。こんな時代だからこそ「倫理」が必要であり「哲学」が求められているのです。「私たちは迷うことでしか倫理を見つけることはできない」(『チ。』より)
ぜひその答えをこれからも一緒に探していきましょう。次回はもう1つの潮流「ヘブライズムの哲学」を解説する予定です。

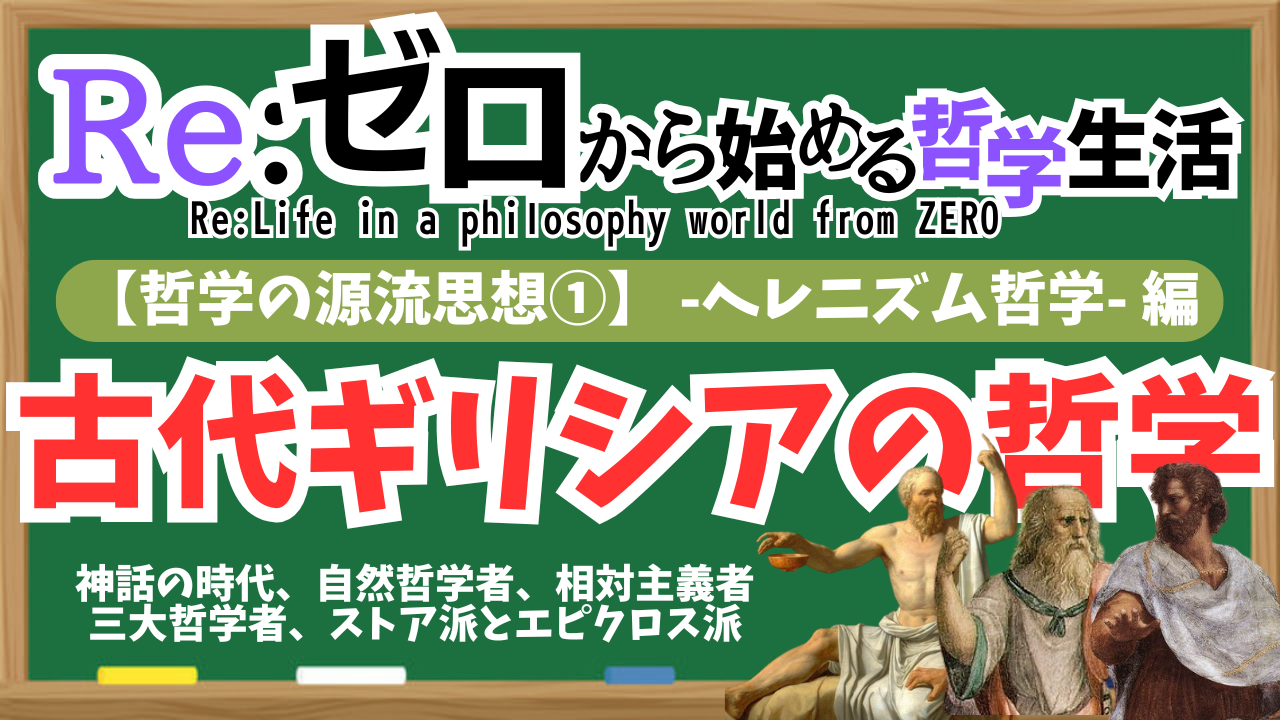
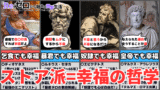
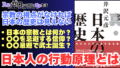

コメント