今回は「Re:ゼロから始める哲学生活」源流思想②ヘブライズムの哲学編を解説します。参考文献は『哲学と宗教全史』(著者:出口治明さん)です。
忙しくて読書をする時間がないという方はぜひAmazonのaudibleをご利用ください。
ポール・ゴーギャンのこの長いタイトルの絵画―『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』をご存じでしょうか?「世界はどうしてできたのか?」「人間はどこから来てどこへ行くのか?」この最も根源的な問いについて考えてきたのが哲学と宗教なのです。
宗教は英語で「religion」なのですがラテン語「 religio」から派生したといわれています。「re」は再びという意味の接頭語で「 ligare」は結びつけるという意味の言葉です。つまり「神と人とを再び結びつける」というような意味なのではないかと思われます。
人間は定住を始めたことがきっかけで世界を支配するようになっていくのです。地球上の全て―植物を支配する農耕、動物を支配する牧畜、そして金属を支配する冶金、これらを支配した人間はいよいよこの世界を動かす原理をも支配しようとしたのです。「太陽を動かしているのは誰か?」「誰が我々の生死を決めているのか?」そのような自然界のルールを定めているもの―それこそが「神」であると考えたのです。
最近、この宗教や哲学がいろいろな場面で注目されていることをご存じですか?実生活やビジネスには何の役にも立たないと思っている人もいるかもしれませんが、Googleやアップルでは専属の哲学者をフルタイムで雇用しているそうです。
私たちは哲学を学ぶことで固定観念を破るための方法を知ることができるようになります。固定観念とはその時代の人にとってあまりに常識的なものとなっているので、「そもそも」を疑うことができない人には何が固定観念なのかも自覚できないのです。『暇と退屈の倫理学』の著者である國分功一郎さんは劇作家ブレヒトの言葉、「英雄がいない時代は不幸だが、英雄を求める時代はもっと不幸だ」に対して「哲学のない時代は不幸だが、哲学を必要とする時代はもっと不幸だ」と述べています。哲学が必要とされるこの時代に哲学の教養を欠いては幸福になることなどできないのです。
そこで、このシリーズでは「古代から現代までの哲学」を全て解説していく予定です。今回は西洋哲学の原点でもある古代ギリシア(ヘブライズム)の哲学を紹介します 哲学を継続して学ぶことができますのでぜひ高評価&チャンネル登録をお願いします。
1 ヘブライズムの哲学(宗教)
1-1 ユダヤ教とキリスト教の成立
西洋思想の源流はヘレニズムの哲学とヘブライズムの哲学に大別されます。ヘレニズムの哲学は古代ギリシアが中心で理性(ロゴス)を頼りにする合理主義的な人間観をもとにした哲学でした。いっぽう、ヘブライズムの哲学はユダヤ教に始まりキリスト教へと発展していくように、人間の無力さへの自覚や神の前での平等をもとにした哲学となっています。
日本をはじめギリシアやインドなど世界中の多くの地域では多神教が信仰されていました。しかし、ヘブライズムは唯一神という絶対神をもつ一神教であることが特徴です。その始まりとなるのが「ユダヤ教」です(ユダヤ人とはユダヤ教を信仰する人の意味)。
ユダヤ教は『旧約聖書』を聖典とする特定の民族だけが信仰する民族宗教です。イスラエル民族の父であるアブラハムは神の声を聞いてカナンの地へと向かいました。カナンとは現在のパレスチナのことでありイスラエル民族にとっては約束の地なのです。後に飢饉から逃れるためにエジプトへ移住するのですが奴隷となってしまいます。そのため、約束の地カナンへもどろうと人々を導いたのが預言者モーセです。
モーセはエジプトを脱出してシナイ山で神から十戒を授けられます。これが「出エジプト」と「モーセの十戒」です。その後カナンの地でイスラエル王国を建国して栄華を誇るのですが、やがて王国は分裂して新バビロニア王国に滅ぼされて強制連行されることになるのです。この時バビロンへ連行されたことからこの事件を「バビロン捕囚」といいます。
このようにユダヤ人の歴史は苦難の連続なのですが、その中で信仰を深めていったことからユダヤ教は民族の心の拠り所となったのです。そして、イスラエル民族は神に選ばれたという「選民思想」をもつようになるのです。ユダヤ教では神への信仰を守って律法を遵守すれば神に救済されると考えられています。『旧約聖書』は39の文書から構成されているのですが、その中の冒頭5つを「モーセ五書」といいこれが守るべき「律法(トーラー)」なのです。
モーセの十戒には「唯一神の信仰」や「偶像崇拝の禁止」などの宗教的な戒めと「殺人や窃盗はいけない」などの道徳的な戒めが記されていました。これが唯一神YHWH(ヤハウェ)とイスラエル民族との契約であると考えるのが、ヘレニズムの哲学の大きな特徴です。
しかし、イスラエルの民は意外にこの契約を破りがちでその度に何度も神に激怒されます。有名な「ノアの方舟」や「バベルの塔」のエピソードも『旧約聖書』に出ているのです。ユダヤ教の神は人類に裁きを下すことから神への畏怖の気持ちも強くなっていきました。
また、神はイスラエルの民が苦難に耐えられなくなった時には預言者を遣わしました。予言(未来を予測)ではなく、預言(神の言葉を預かる)ですので注意してください。預言者は人々の堕落に対して警告をするだけでなく終末思想やメシア信仰も語りました。終末の日には神が正しい者とそうでない者を選別する「最後の審判」が行われて、そこに救世主(=メシア)が現れると信じられているのです。
そのような中で、「神の国は近づいた、悔い改めよ」と人々に説き、メシアであることを人々に予感させた人物こそがイエスなのです。イエスは紀元前4年ころにナザレの大工ヨセフとマリアのもとに生まれました。30歳のころ洗礼者ヨハネの洗礼を受けてユダヤ教の信仰のあり方を刷新していくのです。
ただし、イエスはユダヤ教の律法を否定したわけではありません。イエスは「わたしは律法を廃止するためではなく、完成させるために来た」と言い、『旧約聖書』の言葉は正しいとしてその解釈によって正しい信仰を示したのです。これが神と人間との新しい契約としてのちに『新約聖書』として編纂されるのです。
「旧約」とはキリストが示した「新しい契約」に対して「旧い契約」という意味です。そのため、キリスト教では『旧約聖書』と『新約聖書』をあわせて『聖書』としていますが、ユダヤ教ではいわゆる『旧約聖書』のみが『聖書』として認められているのです。
イエスはユダヤ教の律法を形式的・表面的に守ろうとする律法主義の態度を批判しました。なぜなら、当時のユダヤ教の指導者たち(特にパリサイ派)は信仰の正しさを誇ることで、律法を守ることのできない心の弱い者や異民族を蔑んでいたのです。しかし、イエスは「律法とは神の教えであり無差別で平等な絶対的な愛でる」と説きました。そして、誰もがみな罪人であり誰ひとりとして悔い改める必要のない人はいないとして、「わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためにいる」「罪を犯したことのない者だけが(姦淫した)この女に石を投げなさい」と言うのです。
ユダヤ教の神が「怒りの神」であるならばキリスト教の神は「愛の神」と表現できます。神は罪深い私たちに対して無限の愛を示してくださるのだから神を愛することと同時に、神と同様の愛を同胞たちにも差し向けなければならないという隣人愛が求められるのです。隣人とはつまりあらゆる人を意味するのでユダヤ教の選民思想を明確に否定したのです。
「右の頬を打たれたなら左の頬をも向けなさい」「敵を愛して自分を迫害する者のために祈りなさい」
このようなイエスの教えは貧しい人や女性、病人などの間で大きな支持を得ました。しかし、イエスのことをメシアだと思った人たちの期待はやがて失望に変わるのです。なぜなら、当時のユダヤ人たちはかつてのイスラエル王国のような現実の国家やダビデ王やソロモン王のような英雄的指導者をメシアであると考えていたのです。ローマ帝国の支配という現実の苦しみから脱することを切望していた民衆にとって、イエスの教えは革新的ではあるもののどこか物足りないものとなってしまったのです。
ユダヤ教の指導者たちはこれを機にイエスが神の子であると吹聴していると訴えて、ローマ帝国のユダヤ総督ピラトはイエスのことを十字架の刑に処するのでした。その後、イエスの教えは直弟子の十二使徒とパウロによって広がっていきます。
ちなみに、十二使徒と聞くと聖人たちのようなイメージをもつ方もいるかもしれませんが、イエスが十字架刑になる前の使徒たちは本当にどうしようもないクズ野郎たちでした…。一番弟子のペトロはイエスが逮捕されるとすぐに逃亡して関係者であることを否認します。ユダは裏切り者としても有名でほかの弟子もイエスが祈る時に居眠りして激怒されます。
しかし、イエスの死後に自分の行いを深く後悔した(まさに悔い改めた)ことによって、原始キリスト教会をつくって伝道活動を行っていくのです。ペトロはのちにローマ教会の初代教皇となりますが迫害にあって殉教したり、ほかの使徒たちもあちこちで迫害にあったりしてヨハネ以外はみな殉教するのです。
十二使徒とは別にキリスト教の伝道に最も貢献したのがパウロです。パウロはもともとイエスの弟子を迫害するパリサイ派のユダヤ教徒でしたが、イエスの声を聞いて回心するのです(「目からうろこが落ちる」の語源はここから)。パウロはイエスの死について「贖罪」という思想で宗教的な解明を行いました。神の子であるイエスが死んだのは人類の誰もが原罪を背負っているため、その罪をすべて引き受けて十字架の刑に処されたのだと説いたのです。こうして、イエスを神の子として信仰するべきであるというキリスト教が成立したのです。
パウロは「信仰義認説」という考え方を最初に示したことも重要です。ユダヤ教では律法の遵守が救済の条件であるとされていましたが、パウロは律法を守るという行為ではなく信仰することによって救済されると考えたのです。そして、「信仰」「希望」「愛」の3つをキリスト教における三元徳としたのです。このように、パウロはキリスト教への信仰をわかりやすく説きながら、ユダヤ人ではないローマ辺境の異邦人たちに伝道をするようにしたのです。今日、キリスト教が世界宗教といえるまでに発展したのはパウロの功績が大きいのです。
日本では「イエス・キリスト」という言い方が一般的ですが、キリストとはヘブライ語のメシア(救世主)に対するギリシア語訳クリストスのことです。そのため、これは救世主イエスという意味であるので1つの信仰告白ともいえるのです。
1-2 キリスト教の発展とイスラム教
紀元1世紀に『新約聖書』が編纂されてキリスト教はいよいよ急速に普及していきます。313年に出された「ミラノ勅令」によってローマ帝国におけるキリスト教の弾圧はおわり、392年にテオドシウス帝によってキリスト教はローマ帝国の国教になったのです。このような流れの中でキリスト教の教義を確立させるために異端信仰と論戦してキリスト教の正統教義の確立に尽力した教会指導者のことを「教父」といいます。そして、その代表といえるキリスト教の最大の教父がアウグスティヌスです。
アウグスティヌスは新プラトン主義などのギリシアの哲学にも造詣が深く、キリスト教の三元徳をプラトンの四元徳の上位概念に位置づけました。また、「父(神)と子(イエス)と精霊」が本質的には同一であるという考え―「父と子と精霊の御名において、アーメン」という三位一体説を確立しました。
まず、人間には原罪がある以上どうしても悪へと流されてしまうのは仕方ありません。そのため、たしかに自分の行為を自分で決めるという自由意志をもっているが、それは悪への自由でしかないため善をなす自由などないというのです。そして、このような人間が救われるためには神による「恩寵」しかないと説いたのです。こうして、教会は地上における神の代理として教会制度を確立することにもなるのです。この恩寵が与えられる人はあらかじめ決まっているという「予定説」という考え方は、のちに宗教改革の指導者カルヴァンにも大きな影響を与えるので覚えておきましょう。
それから約800年間後にスコラ哲学の大成者であるトマス・アクィナスが登場します。この時期には教会や修道院の学校で神学などのさまざまな学問が研究されていました。そのため、これをスコラ哲学といいます(スコラはスクールの語源です)。
アウグスティヌスはプラトン哲学に影響を受けていましたが、スコラ哲学はイスラム世界から逆輸入されたアリストテレス哲学の影響を受けました。なぜなら、この時期は教会の教えこそが絶対に正しいとされる時代だったのですが、アリストテレスの科学的な知見によって様々な現象が説明できるようになっていたのです。つまり、信仰よりも理性が優先されるようになりかねない状況でした。
そこで、トマス・アクィナスは信仰と理性は対象とする世界が異なると考えて、両者はけっして矛盾するのではなくむしろ相互補完的な関係にあるとしたのです。数学の計算は理性(哲学)によって答えられるが、イエスの復活にどのような意味があるのかを答えるのは信仰(神学)であるというのです。そのうえで、理性と信仰は対等ではなくあくまで信仰が上位の概念であるとしました。
「恩寵は自然を破壊せず、かえってそれを完成させる」と言って信仰が理性よりも高みにあることを示唆したのです。そのため、スコラ哲学では「哲学は神学のはしため」と表現されるのです。
余談ですが、スコラ哲学では「普遍論争」が大きなテーマの1つとなっています。普遍というのはミケやポチのような指定できる個別のネコに対して、思考でしかとらえることのできない「ネコ」という概念のことです。この「ネコ」という概念はただの名前でしかないとして、本当に存在するのは個別のミケやポチというネコであると考えるのが唯名論です。
しかし、唯名論の立場を認めると神という概念も存在しないことになってしまうので、実在論の立場に立って普遍概念は存在すると考えるようにしたのです。唯名論の代表者はウィリアム・オッカムで実在論の代表者はアンセルムスです。
トマス・アクィナスは普遍論争に対して、アリストテレスの立場から「普遍が個物に内在する」として両者を調停したのです。『チ。-地球の運動について-』でもこの2人は出てくるのでぜひ読んでみてください。
時代は少しもどって、アウグスティヌスから約200年後のアラビア半島では、ムハンマドがヘブライズムの系譜にあるもう1つの宗教であるイスラム教を創始しました。聖地は3つ―マッカ、マディーナ、そしてエルサレムです。聖典は『クルアーン』であり『旧約聖書』と『新約聖書』は啓典とされています。
キリスト教におけるイエスは神の子であり崇拝される対象であるのに対して、イスラム教におけるムハンマドはあくまで人間の預言者でしかありません。イスラム教では唯一神アッラーへの絶対服従を説く平等主義的な世界宗教です。キリスト教よりも神の絶対性を厳格に強調するので(イスラムとは「服従」の意味)、偶像崇拝はもちろん禁じられています(神やムハンマドを描くことも禁止)。しかし、ユダヤ教のような選民思想はなく信徒はだれもが神の前に平等であり、民族的な差別がないのはもちろん聖職者すら存在しないのです。
ムハンマドはある日、洞窟で神の啓示を聞き預言者としての活動をするようになります。そのため、ムハンマドは「最後の預言者」といわれているのですが、これはモーセやイエスに続く預言者の系譜の最後の1人という意味なのです。なぜなら、イスラムの世界ではユダヤ教徒もキリスト教徒も同じ啓典の民とみなされ、アッラーという絶対神も2つの宗教の神YHWHと同じであるとされているのです。
イスラム教徒になるためにはつぎの六信五行を覚えなければいけません。六信とは神・天使・啓典・預言者・来世・定命を信じることです。神はYHWH(アッラー)であり天使はムハンマドに預言を託したガブリエルのこと、啓展はクルアーンであり預言者はもちろんムハンマドのことです。そして、来世とは天国と地獄の存在を信じることであり定名は予定説のようなもの―人間が救われるのか滅びるのかはあらかじめ神が決めているということです。
五行とは信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼の5つの行動をすることです。信仰告白とは「アッラーが唯一神でありムハンマドが最後の預言者です」と宣言すること、礼拝は1日に5回マッカのカーバ神殿がある方向を向いて礼拝すること、喜捨はお金があるなら貧しい人たちにめぐみなさいという教えのことです。断食(ラマダン)はイスラム歴の9月に日の出から日没まで食事をとらないことであり、巡礼は一生の中で一度はマッカのカーバ神殿を訪れましょうということです。これまでの入試では「断食」に関する問題が多く出題されてきました。日の出から日没までの日中だけであり、1か月間のイベントであるところがポイントです。
イスラム教の信仰共同体のことを「ウンマ」といいます。その指導者はカリフ(ムハンマドの後継者)とされていましたが、のちに多数派の「スンナ派」と少数派の「シーア派」に分裂してしまいます。スンナ派はムハンマドの言行や慣行を重視する派閥で信徒の80%以上がこちらです。シーア派はムハンマドの血統を重視する派閥でイランなどの一部の地域がこちらです。
まとめ
「哲学は何の役にも立たない」「哲学は難しそうで興味がもてない」
そんなふうに思われるかもしれませんが哲学って実はとても面白いんですよ。このチャンネルでは哲学の面白さを発信していますのでぜひ受験勉強のためだけと思わず、学生や社会人の方にも楽しみながら哲学のことを学んでほしいと思います。
これまで正しさをめぐる暴力によって数えきれない罪なき人々の血が流れてきました。大航海時代の植民地支配、アメリカ大陸の制服、ナチスによるホロコーストなどなど。いずれも「絶対に正しい」とされていることを盲信した結果が引き起こした悲劇です。私たちは「絶対的正義」を掲げた時に恐ろしいほど残虐なことを可能にしてしまうのです。
ポピュリズム全盛ともいえる現代社会もまた倫理なき世界へと逆行している気がします。こんな時代だからこそ「倫理」が必要であり「哲学」が求められているのです。「私たちは迷うことでしか倫理を見つけることはできない」(『チ。』より)ぜひその答えをこれからも一緒に探していきましょう。

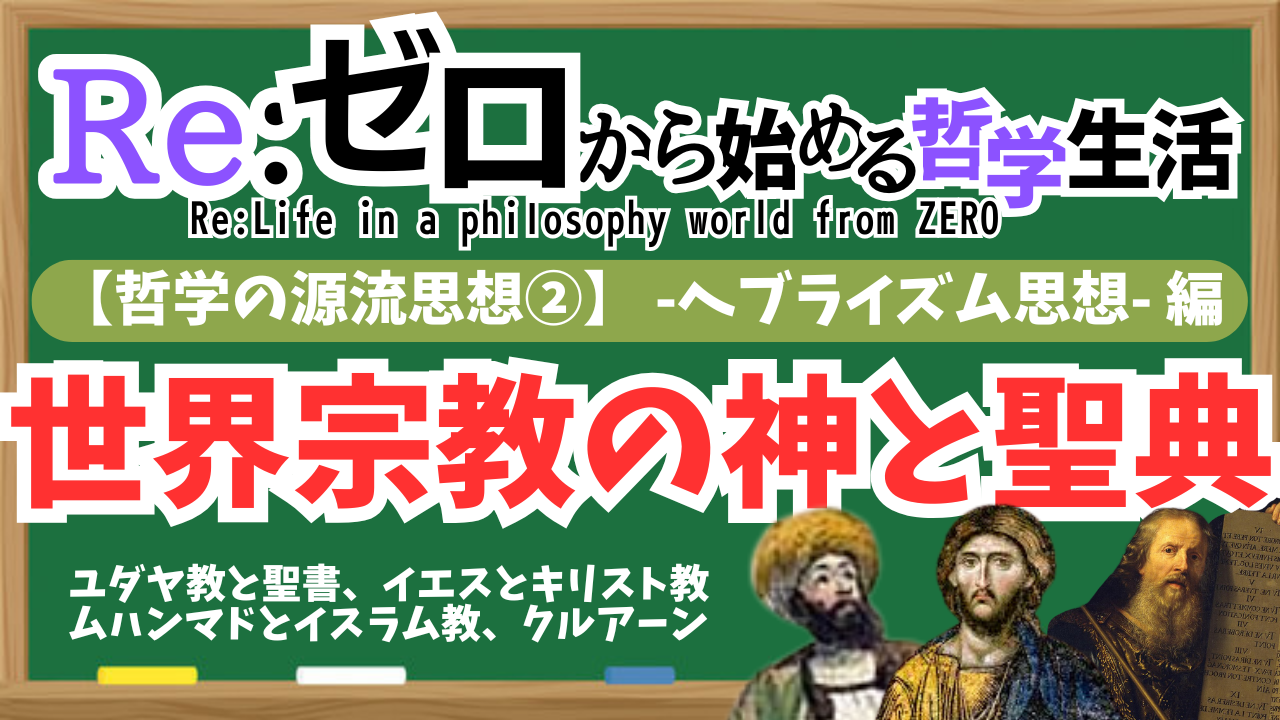
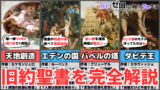
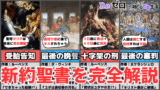

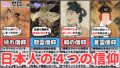
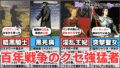
コメント