今回は、哲学初心者のわたしと一緒にドイツ観念論の哲学を探求する旅に出かけましょう。哲学って、少し難しそうに感じるかもしれませんが、実は日常生活の中にも深く関わっているのですよ。一緒に考え、問いに答え、新しい視点を見つけることで、哲学は驚くほど身近に感じられるようになるのです。この旅が終わる頃には、現代社会にはびこる生き辛さの正体を知るためのヒントをきっと見つけることができるでしょう。
1 イマヌエル・カント

カント(1724年~1804年)はイギリス経験論と大陸合理論を統合することを試みたドイツの哲学者です。「コペルニクス的転回」と呼ばれる認識論上の革命を起こした『純粋理性批判』普遍的な道徳の基準を理論立てた『実践理性批判』そして現在の国連のひな型となる国際機関創設を提案した『永遠平和のために』など様々な問題を普遍的な原理から考え直すという大事業を行ったことから「カント以前の哲学はすべてカントに流れ込み、カント以後の哲学はカントから流れ出る」といわれています。
カントの唱える「批判」というのは対象を否定するという意味ではなく吟味や熟考するという意味であり理性批判というのは理性について吟味するということです。カントはもともと大陸合理論を信仰する哲学者でした。しかしヒュームの哲学にふれて「独断のまどろみから目覚めた」ことをきっかけに
もう一度理性について考え直してみるという試みをスタートさせるのです。
まずカントは「たしかに人間は知覚の束かもしれないが、ではなぜちがう経験をしたはずの人間同士が共通の認識をもつことができるのか?」という疑問をもちます。そこで「たしかに人間の認識は知覚の束であるかもしれないが、その経験や知識を受け取る方法には先天的に共通のパターンがあるはずだ」と考えたのです。カントは経験や対象を認識する時には先天的な受け取り方をするため認識するべき「もの自体」を認識することはできないと考えました。なぜなら「もの自体」を認識した時にはすでに先天的な受け取り方というフィルターを通して認識しているからです。そこでカントは「もの自体」という真理を理性によって解明することはできないので人間が認識することのできる人間のための真理を解明するべきであると考えたのです。
さらにカントは二律背反(アンチノミー)の問題について言及します。二律背反とは相反する二つの命題が矛盾しながらもお互いに成立している状態のことです。つまり片方の命題が正しいとするともう片方の命題に矛盾が生じてしまう状態をあらわします。カントは提示した二律背反のうち最も有名なものが「時間・空間」の二律背反です。まず一方の命題を「世界は時間・空間的に有限である」としてもう一方の命題を「世界は時間・空間的に無限である」とします。ここで反対意見の矛盾を指摘する背理法によって命題の正当性を主張するのです。たとえば「世界は時間・空間的に無限である」であるならば
世界には始まりも終わりもないことになります。しかし私たちは過去から流れてきた時間の先端(今)を生きている以上時間の終わりが存在してしまうことになります。ということは世界が有限であると考えることができるはずです。
反対に「世界は時間・空間的に有限である」であるならば世界にはどこかに始まりと終わりがあるはずです。しかしもし始まりがあったとするならばその前には何があったのかということが説明できません。ということは世界が無限であると考えることができるはずです。このように背理法による証明ではお互いの命題が真であるということになってしまうのです。そこでカントは形而上学的な問いに理性のみで答えようとすると必ず二律背反に陥ってしまうと言ったのです。だからこそ人間の理性で認識できない真理については考えることはできないとして「もの自体」について考えるのではなく「もの自体」を認識する方法について考えることにしたのです。このような考え方を「認識のコペルニクス的転回」といいます。
これまでは対象を認識する時には対象が先に存在していてそれを見ることによって認識していると考えられてきました。これを「認識は対象に従う」と表現します。しかしカントは見る(感性)ことによって理性(悟性)が受け取った結果として対象が認識されると考えたのです。これを「対象は認識に従う」と表現します。このような対象を認識する力のことを「理論理性」といいます。それに対して意思決定する力のことを「実践理性」とカントはいいました。カントは理論理性で認識できる範囲を「現象界」といい「もの自体」が存在する範囲を「英知界」とよびました。しかし「もの自体」に到達することはできないので英知界のことを認識することができないことから人間としての行動の原則をもてなくなってしまいます。そこで「普遍的な道徳法則」によって実践理性が左右されると考えたのです。
カントは道徳法則について「定言命法」と「仮言命法」の2つの命令を考えました。「定言命法」とは「何々すべきである」という無条件の命令です。「仮言命法」とは「もし何々であるならば何々しなさい」という条件ありの命令のことです。たとえば困っている人がいたとして困っている人がいるなら助けるべきだと考えることが定言命法でありもし助けたらお礼をもらえるかもしれないから助けると考えることが仮言命法です。カントは道徳法則から出される定言命法に理性によって従うことが人間が善く生きるために必要なことであると言いました。これを「自律」とよび道徳法則にしたがおうとする意志を「善意志」とよびました。カントは著書『永遠平和のために』において理想国家の在り方について
①全ての国家が民主制を採用するべき
②軍隊を廃止するべき
③国家間のルールを定めた国際法を制定するべき
④国際的な平和機関をつくるべき
と提唱しました。これが現在の国際連合の基礎として受け継がれているのです。
2 ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ

フィヒテ(1762年~1814年)はベルリン大学の初代哲学教授となった主観的観念論を提唱したドイツの哲学者です。フィヒテはカントの理論理性(認識する力)と実践理性(意思決定する力)の2つを分ける二元論的な考え方を否定しました。そしてこれらをまとめて一元論的に世界を説明しようと試みたのです。
フィヒテは世界の根底にある一元的な要素のことを「自我」としました。「自我」とは
①根源的に自己自身の存在を定立する
②自我に対して非我が定立される
③自我は自我の内において可分的自我に対して可分的非我を定立するとしました
どういうことかというと①について自我がなぜ存在するのかといえばそれは「自我が自分自身を生み出すからである」と考えたのです。たとえば「父になる」という場合においてある男性に子どもが生まれて父になっていく過程において子育てをしていく中で自らの中に父としての役割をもつようになっていきます。このとき「父」という概念ははじめからあったわけではなく子育てをするという行動とセットになって同時に存在したと考えられるのです。このような理由から①について自我は自分を生み出すと同時に存在もしているといえるのです。
②について非我とは自我ではないものということです。そして③について自我は自分自身のことを非我によって制限されたものであると認識するためこの非我を乗り越えて元の自我で満たされた自我(=絶対我)を取り戻すように努力するのです。この時の自分自身の境界線を知った自我のことを「理論我」といい非我を乗り越えようとする自我のことを「実践我」といいます。これによってカントの理論理性と実践理性を自我の中に内包することができたのです。しかしフィヒテの理論は神の対する問題に直面することになるのです。つまり自我が世界をつくっているのであれば神もだれかがつくっているということになるのです。絶対者である神の存在がだれかの存在に影響されることがあるのですか?と。その結果フィヒテは無神論者のレッテルをはられてイエーナ大学を追放されることになるのですがベルリン大学が開校されたことで初代哲学教授に就任するのです。のちにベルリン大学で行われた講義『ドイツ国民に告ぐ』がドイツ帝国の建国に大きな影響を与えることになるのです。
3 フリードリヒ・シェリング

シェリング(1775年~1854年)はフィヒテの哲学を批判的に引き継いだ客観的観念論を提唱したドイツの哲学者です。フィヒテが『全知識学の基礎』を出版した翌年にシェリングは『哲学の原理としての自我について』を著しました。この時フィヒテはシェリングのことを「私のことを適切に理解している」と評価しました。しかしシェリングはフィヒテの「絶対我」に対して疑問をもつようになります。フィヒテの考える「絶対我」は自我の延長にあるものとして認識されていました。しかし絶対という以上それは絶対でなくてはならないはずなのです。つまり絶対であるならば非我が障壁となることはないはずなのです。
そこでシェリングは絶対我とは「絶対者」であると考えました。絶対者であるならば自我の根拠であるだけではなく非我の根拠にもなるべきであり自我である「精神」と非我である「自然」は両者ともに絶対者から展開されたものであるべきであるとしたのです。このように同じ1つの絶対者から精神と自然が生まれたとする考え方を「同一哲学」といいます。
では「なぜ同じ絶対者から精神と自然という異なるものが生まれたのか?」という疑問につてシェリングは「量の問題である」と考えました。同じ絶対者から生まれたのであれば質的なちがいがあるはずはないのでちがうとすれば量であるという考え方です。つまり精神の中にも自然の要素があり自然の中にも精神の要素があるということです。ということは精神の中にも精神の要素が多いものとそうでないものがあることになります。シェリングはそれを「芸術哲学(自分以上のものを表現しようとする)」「実践哲学(自由を実践する)」「理論哲学(必然的なものを追い求める)」に分類して芸術哲学こそがもっとも精神性が高いものであるとしました。芸術は絶対者そのものを直感して表現することだと考えたからです。理論哲学と実践哲学はそのままカントの哲学と同じものになります
4 ゲオルグ・W・F・ヘーゲル

ヘーゲル(1770年~1831年)はカントを批判したフィヒテとシェリングの哲学を批判的に統合してドイツ観念論を完成させたドイツの哲学者です。イエーナ大学の講師としてシェリングと共同でカントやフィヒテを批判する論文を執筆しました。しかしシェリングに対して批判的な意見をもつようになったのちに友好関係をも断絶するのです。そしてフィヒテのあとをついでベルリン大学の哲学教授に就任しました。ヘーゲルはフィヒテのことを尊敬していたので死後はフィヒテの墓の隣に埋葬されることを希望したほどでした。
ヘーゲルはこの世界は「絶対精神」によってつくられており我々そのものであると言いました。まさにスピノザの「神即自然」のことです。ヘーゲルは絶対精神に内包される有限者が変化を繰りかえしていくという営みこそが「世界」であり「歴史」であると考えたのです。絶対精神は全知であるけれど全能ではありません。そこで内包される有限者(人間)に変化することで自由や真理に到達しようとするのです。このような営みを「理性の狡知」といいます。つまり私たちが生きているこの「歴史」とは絶対精神が自由に到達するための過程でありいずれはカントの唱える「もの自体」にあたる真理にも到達できると考えました。
そしてヘーゲルは自由に到達するためのプロセスにはある法則があると考えたのです。それが「弁証法」です。たとえばAさんがある図形を見た時には「これは円です」と言いBさんがある図形を見た時には「これは四角形です」と言ったとします。このような対立を経て第三の新しい考え(実はこの図形は円柱だった)に至るプロセスこそが弁証法なのです。ある一つの立場「テーゼ(正)」に対して反対の立場「アンチテーゼ(反)」が存在します。そこでお互いの立場を考慮した上で新しい第三の立場へ向かうようにするのです。このような営みのことを「アウフヘーベン(止揚)」といい新しい第三の立場のことを「ジンテーゼ(合)」といいます。
ヘーゲルはこの弁証法のプロセスを限りなく繰り返していけば最終的に絶対精神にたどり着くことができると考えたのです。そして「歴史」もこの弁証法のプロセスそのものであるとしたのです。最初の国家は絶対王政であり王様のみが自由を手にしている状態でした。次に貴族制の国家が登場したことでそれまでよりも多くの人が自由を手にすることができるようになりました。そしてヘーゲルの時代にはフランス革命によって共和制が成立したことでさらに多くの自由をえることができるようになったと考えるのです。このように歴史も弁証法を繰り返すことによって人々はより多くの自由を手にしてきたと考えたのです。カントはよりよい世界をつくるためには実践理性によって意思決定すること(つまり道徳法則)が必要であると考えました。しかしヘーゲルは真の自由を手にするためには道徳性だけにたよるのではなく具体的な制度が必要であるといいました。この両者をアウフヘーベンすることで生まれる「人倫」こそが真の自由をもたらすと考えたのです。このように考えることによってヘーゲルはドイツ観念論を完成させたといわれるのです。
5 アルトゥール・ショーペンハウアー
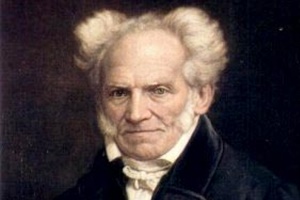
ショーペンハウアー(1788年~1860年)はカントとプラトンに影響を受けてヘーゲルの哲学を批判することになるドイツの哲学者です。ショーペンハウアーはヘーゲルと同時期にベルリン大学の哲学教授でしたがヘーゲルの講義が人気だったのに対してショーペンハウアーの講義は閑散としていたといわれています。そのためベルリン大学を辞職して生涯在野の哲学者として過ごすことになるのです。
25歳の時に著した『意志と表象としての世界』において世界は人間の意志と表象であるといいました。つまり私たちの世界は人間の表象でもあり意志でもあると考えたのです。“私たちの世界は人間の表象”であるというのはカントの「現象界」とほぼ同じことです。カントは「対象は認識に従う」と言って「もの自体」を認識することはできないとしました。そして人間が認識できる範囲の世界のことを「現象界」といいこれがそのまま“私たちの世界は人間の表象”ということになるのです。
ショーペンハウアーはこの表象を観察することによって「もの自体」に到達することができるのではないかと考えたのです。そして世界のあらゆる表象は生への絶え間ない努力をしていることに気づくのです。そこでショーペンハウアーは「もの自体」のことを「生への盲目的な意志」であると考えたのです。つまり「もの自体」というのは「意志」のことであり意志が表象としてあらわれたものを私たちは世界として認識していると考えたのです。人間そのものが「生への盲目的な意志」によって支配されていることによってショーペンハウアーは「生きるのは苦痛である」という結論を導き出すのです。「生への盲目的な意志」による生きたいという意志を満たせないことも苦痛でありその意志が満たされたことによる退屈も苦痛であるというのです。
ではどうすればいいのでしょうか?ショーペンハウアーは「芸術」や「愛」も意味があるとした上で最も重要なことは「禁欲」をするべきであると考えました。禁欲とは性的な行動を慎むことや節制をするということではなく「生への盲目的な意志」がもつ欲求を禁止するということです。つまり「意志が盲目的に自分を支配しようとしている」ということを認識することで意志(と同時にあらわれる表象)を消し去る(=世界への執着から脱却する)ことができるとしたのです。
このような思想は仏教における「一切皆苦」や般若心経における「色即是空空即是色」(この世のあらゆるものには実体がなく実体がないことがこの世のあらゆるものを形成している)と非常に似ており事実ショーペンハウアーの思想は東洋哲学からも大きな影響を受けているのです。ショーペンハウアーの哲学は「厭世主義(ペシミズム)」とよばれのちのニーチェなどの哲学者に大きな影響を与えることになります。
6 まとめ
イギリス経験論と大陸合理論を統合しようとカントが認識のコペルニクス的転回を起こしフィヒテ、シェリングと継承されながら最終的にヘーゲルによって完成されたドイツ観念論はその後の哲学にも大きな影響を与えていきます。
次回は「今ここにあるひとりの人間の現実存在(=実存)としての自分のあり方」を求める思想
実存主義について学んでいきましょう。ぜひご期待ください。本日の旅はここまでです。ありがとうございました。




コメント